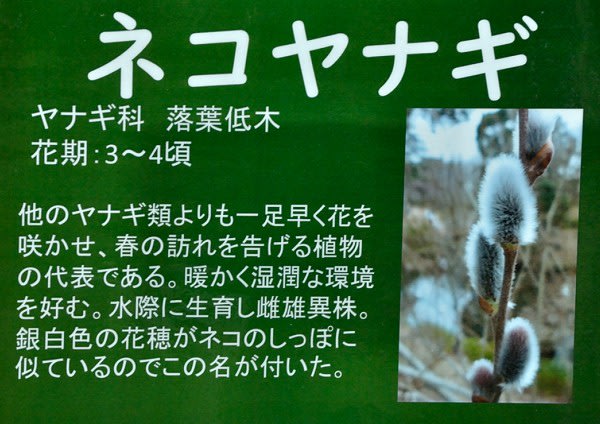「ムベ」の花 (*千葉市都市緑化植物園内で撮影)
「ムベ」:アケビ科ムベ属のつる性植物で日本原産。
*<「アケビ」との違い>*
①「実」:熟すとアケビは大きく裂けるがムベは裂けない。
②「花」:アケビの白い雄花は小さくて数が多いが、雌花は
濃い紫色で数が少なく、簡単に見分けることができる。
一方ムベの花は全部白っぽい色で見分けが難しい。
微妙だが雌花のほうがやや大きくて雄花は小さい。
③「アケビ」も「ムベ」も「雌雄同株で雌雄異花」の仲間。
*<「ムベ」の名の由来>*
その昔天智天皇がでかけた先のある老夫婦が
「ムベの実」を献上したところ、それを食した天皇は
「むべなるかな」と礼を言った。
*その言葉には「なるほどこのような良いものを食して
いるから、年老いても元気ではたらいているのだな。」
という意味が込められていたという言い伝えがある。
「フレンチラベンダー」の花
(*千葉市都市緑化植物園内で撮影)
とてもきれいでハーブとしても人気が高い薄紫色の花
開花時期は5~7月
無数にあるシソ科の植物で原産地は地中海沿岸
鎮痛・坑うつ・消炎・防腐・殺菌など多くの効能がある。
そのさわやかな香りは精神的なストレスも癒してくれる。
「ウラシマソウ」の花
新緑の頃山あいを歩いていると道端の草むらの中に
この一見不気味な植物を見かけることがよくある。
大きなマムシが鎌首をあげているかのようにも見える。
更に、鎌首からは長いひも状のものが上に伸びている!
この奇妙な植物の姿から浦島太郎の釣り竿の糸を連想し
「ウラシマソウ(浦島草)」と命名されたという。
(*DIC川村記念美術館庭園林間散策道で撮影)
*[参考]* 実はこれとよく似た植物が他にもある。
それは「マムシグサ(蝮草)」で、聞いただけでも怖い。
一つだけ記憶しておけば簡単に見分けることができる。
*「マムシグサ」には花序から上に延びる「ひも」がない。
「アツモリソウ」の花
この花もなんともいえない不思議な形をしている。
*<この花の名の由来>*
その昔の源平合戦で、平氏の武将「平敦盛」が
背後から弓で背中を射抜かれないように
大きく膨らませた防具を背負ったといわれる。
その武具の形とこの花の形がよく似ていることから
「アツモリソウ」の名がつけられたという。
(*千葉市都市緑化植物園内で撮影)
「ジュウニヒトエ」の花
(DIC川村記念美術館庭園で撮影)
林間散策道や奥の庭園散策道脇などに多く見られる。
「ジュウニヒトエ(十二単)」:シソ科キランソウ属の多年草
日本固有種で本州・四国に分布する。
開花期は4~5月で草丈は15~20cm
*<この花の名の由来>*
花の姿を宮中の女官などが着る十二単に見立てて
その名がつけられたという。