なんと、第一感通りでほぼ正解でした。買わない時に限って当たるんですよね、競馬は 来週の朝日杯はドリームジャーニーだと思います。
来週の朝日杯はドリームジャーニーだと思います。
将棋世界1月号が発売になりました。表紙からもわかる通り、名人戦問題についての特集号となっています。それについては説明するよりも読んでいただくとして、タイトル戦の記事について。
今回の竜王戦の場合、年末年始に発売される2月号に掲載されるのが第4.5局。この時点で竜王戦は終了しています。最終局が掲載されるのは2月発売の3月号です。就位式も終わっています。以前ならこれで問題ありませんが竜王戦はネット中継が充実しているので感想戦の内容までその日のうちに知ることができます。
皆がネット中継を見ているわけではないので将棋世界で初めて内容を知るという方もいるとは思いますが大半の方は主要変化が羅列されただけの記事では満足しないのではないでしょうか。
と偉そうに書いてみましたが、指し終わってから一ヶ月以上経過した将棋の記事にどうしたら新鮮味を出せるかというのは自分でも分かりません。ネット中継が充実し過ぎてるから仕方がない。ではなく、何か良い方法があるような気もします。これからの課題ですね。
明日は予防注射。「はぁ、嫌だなぁ」とため息をついていたら嫁さんに「柊でも泣かなかったんだからビクビクしないの 」と一喝されました
」と一喝されました
 来週の朝日杯はドリームジャーニーだと思います。
来週の朝日杯はドリームジャーニーだと思います。将棋世界1月号が発売になりました。表紙からもわかる通り、名人戦問題についての特集号となっています。それについては説明するよりも読んでいただくとして、タイトル戦の記事について。
今回の竜王戦の場合、年末年始に発売される2月号に掲載されるのが第4.5局。この時点で竜王戦は終了しています。最終局が掲載されるのは2月発売の3月号です。就位式も終わっています。以前ならこれで問題ありませんが竜王戦はネット中継が充実しているので感想戦の内容までその日のうちに知ることができます。
皆がネット中継を見ているわけではないので将棋世界で初めて内容を知るという方もいるとは思いますが大半の方は主要変化が羅列されただけの記事では満足しないのではないでしょうか。
と偉そうに書いてみましたが、指し終わってから一ヶ月以上経過した将棋の記事にどうしたら新鮮味を出せるかというのは自分でも分かりません。ネット中継が充実し過ぎてるから仕方がない。ではなく、何か良い方法があるような気もします。これからの課題ですね。
明日は予防注射。「はぁ、嫌だなぁ」とため息をついていたら嫁さんに「柊でも泣かなかったんだからビクビクしないの
 」と一喝されました
」と一喝されました




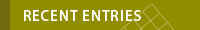
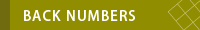
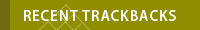


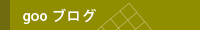
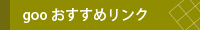




今、どうするのか・・・ 佳('_`)愚
って俚諺がありましたね・・・
名人戦問題の記事は、たぶん胸くそ悪くなるから読まないつもりです。ただ、一つだけ言いたいのは、なぜ今の時期にこの話題を出すかな~?、ということ。だって、まだなーんにも、正式に決まっていないんでしょ?両新聞社に対しても、失礼だと思わないのですかね?
とにかく、竜王戦七番勝負が終わるまでは、そんな話題はどうでもいいよ。次も、必勝!!
さて、対局時期と記事掲載のギャップの問題ですが、速報性だけでは補えない何かを価値として付加していくことが必要ではないかと思います。対局者自身による指し手、読み筋の詳細解説などは如何でしょうか? 対局後時間を経て初めて明らかになった筋なども含めて余計な文章なし、指し手の記号だけでトコトン解説するとか。
あるいはその正反対で、棋譜はさらっとオマケっぽく載せるだけで当代一流の作家の先生にちょっとした文学作品としてまとめてもらうというのはどうでしょう・・・。
難しい問題ですね。同じ素材で、どう調理の仕方を変えるか。
①解説者を付ける
羽生三冠による竜王戦第2局解説・・・・読みたいw
②読者の質問・コメントを竜王戦ブログで集めて掲載、解説
「ここでこう指してたら?」といった読者の生の声に答える。
コメントが本に掲載されればより嬉しいかも
③将棋世界のためにネタをいくつか温存
「勝負を決めた場面はなんと・・・ →続きは将棋世界○月号で。」
これぐらいネットと書籍が連動すれば販促にもなっていいかも。
かなりジレったいですがw
④1日目終了時点で封じ手と共に両対局者が作文を書く。
「なんであんな手指しちゃったんだ・・・あぁ苦しい。
2日目指したくないよぉ・・・もうダメぽ」
個人的にはめちゃくちゃ読みたいですが、対局者の負担は
半端ではありません。
周りの声にいろいろストレスの溜まる時期と思いますが、
どうか健康には気をつけて下さい(^ω^ )
「人間らしさ」を出せたら面白いと思います。
観戦記を別のプロ棋士が解説をする。
例えば、渡辺竜王vs佐藤棋聖の対局を立会人以外に観戦記を頼む。
トッププロの羽生三冠や谷川九段。または、若手の新四段。または、熟年の内藤九段や有吉九段など。または、アマトップの清水上アマ竜王や加藤アマ名人など。つまり、対局者と立会人以外の人に解説を頼む。
棋譜を見て何が楽しいか? それは、人によって読み方が違うこと。最善手は1つでも、たどり方や読み方が違うことを楽しみたいと思います。
今回の第4局でも、ゴキゲン中飛車なので、近藤五段に解説を頼むとか。 つまり、振り飛車のエキスパートでは、どのように手を読むか? また、純粋居飛車党のプロ棋士に解説を頼むとか? 居飛車党はどのように、手を読むのか?
プロの棋譜の「人間らしさ」があれば、読みたいと思います。
第5局が終わるまでこの話題はやめて、競馬一本でいきましょう。
あとマジック2ですね
ところで将棋世界の件でちょっと趣旨から外れるかもしれませんが、読みたいものがあります。それは「プロがどうやって強くなったのか」で、とくにアマ初段をクリアするまであたりが知りたいのです。
一般論(よくいう詰め将棋・得意戦法を磨く・実戦とか)ではなく、例えば渡辺竜王が最初に読んだ棋書とか、これとこれは必読とか。戦法講座とは別の、プロの上達法を直伝で。
具体案としては、誌上予備校みたいなヤツ。読者の実力に合わせたコース分けをして何人かの講師が、それぞれ誌上で仮想の弟子を育てるみたいな。1年(12回)で初段になるコースとか。大学受験している若手プロならノウハウもってると思うし、女流にも活躍してほしい。
具体的なことを書くとぼやけてきたのでまとめると、
1、プロの実体験によるアマ初段あたりまでの勉強法(これだと読みきりになりそう)
2、予備校みたいなヤツ(連載で固定読者をゲットだぜ)
3、それとは別に、矢倉の本書いてください(初段になったら読ませていただきます)
まあ個人的にも団体的にもお忙しいことは承知していますが、キボンヌしたいとおもいます
月曜日に受けるのは、見合わせたほうが良いと思います。
インフルエンザの予防接種は、弱いインフルエンザを体内に入れるわけですから、その日は風呂に入れませんし、微熱が出ますよ。
記事末尾に「注射・嫁・一喝」という爆笑をさそう内容あり、雑誌記事新方向への重要暗示になっている気がしました。
上の方と同じ意見です。
私も先日、インフルエンザの注射をしましたが、3日ほど
射した所が痛かゆいです。
できれば、注射をしてから日にちをあけて対局に臨まれた
方が良いと思います。
主治医と相談して!
棋士の癖(佐藤棋聖の咳など)が激しくなるのはどういう心境か?
といった棋譜から読み取れない部分を雑誌に期待します。
あとは最新の定跡手順とかですかね。
連盟の運営なんか興味持つ人は余程のマニアだけのような気がします。部数を落としたくなら、運営やネガティブな記事に偏らない方がいいと思います。ただでさえ将棋に暗いイメージありますから。趣味で気分転換したいのに、さらに暗くなりたい人なんていませんし。
毎年入浴していますが平気です。 ただ注射あとはニ三日
赤くはれていますので、無理はしないほうが良いのは勿論ですが。
2連勝して勢いは竜王にあります。 些細なこと(注射の影響←ありません!)など気にしないで防衛に王手をかけてください。
特にタイトル戦の感想戦や、他の手の手順をCD化して自分で駒を動かさずに解説文と一緒に体感です。
出来れば、棋戦を闘った両者の生の声の解説がうれしいです。
さらに、他の棋士からの変化の手順なども。
観戦ファンとしては、ポイントになる盤面と手順のテキストだけでは頭がついていけません。
もっと裾野を広げるには、ゲーム感覚での見せ方も必要ではないでしょうか。
同時にホームページで公開指定、今期の各棋士の成績などがデータ化され検索できれば面白いと思います。
CDやDVDを付録につけるようにしてください。
絶対に喜ばれますから!
大体、保存が厄介ですし、破損の危険性も高いのです。
JRAの「優駿」がレースDVDをつけ、100円値上げした際には、
「そんなものいらんから値上げするな」
こんな時代に月刊誌を読まれる方ですから、パソコンを使いこなせない方も、おられるのでは無いでしょうか。
いっそのこと、レビューに徹したほうがよいのではないでしょうか。できれば、複数の棋士による見解があれば面白いのですが。
渡辺竜王、森内名人ともに▲2八銀を知らなかったのは意外でした。どちらも歴史とか好きそうな顔されてるのに…
局面にヒネリ飛車とか後手から△3三桂△4五桂…戦法名忘れました。とかもやって欲しいな。
NHK杯もどんな長手数になっても編集して15~20分の感想戦を入れて欲しいなぁ~と思います。
竜王にはNHK杯で出来得るだけ感想戦を見れる戦い方をして欲しいなぁと思います。
たとえば、スポーツですと、「ナンバー」のような雑誌がそれなりの支持を得ているかと思われます。将棋でも、タイトル戦ごとに将棋世界別冊、もしくは主催紙による特集誌を出して欲しいです。
それには「記者」もしくは「編集者」の存在が大きいかと思われます。棋譜を、そして対局を、いかにおもしろおかしく(もちろん良い意味で)ふくらませられるか。
では具体的にはどうすればいいのか、まではさすがにちょっとアイデアは浮かびません。ただひとつ思うのは、タイトル戦(予選も含めて)を図面と棋譜と解説と観戦記で数ページで語るのは限界があると思います。対局を文章で「再現」するには、将棋世界や各新聞の観戦記では絶対的な文量が不足していると思います。個人的にはタイトル戦の年度ごとの特集を、「羽生vs佐藤全局集」並のヴォリュームでまとめて欲しいものですが。
ちょっと竜王の文章へのコメントとはややずれましたが、個人的な感想を書かせてもらいました。
ではでは
予選、本戦、タイトル戦の扱いにも不満があります。将棋世界や週刊将棋だと、予選は、特選譜の図面一、二面に解説、タイトル戦は図面五、六面に棋譜、解説。新聞観戦記だと予選は図面六面程度に解説、タイトル戦は二、三面図面と解説を増やす。そして、展望記事が少々。これが相場かと思われます。
ただタイトル戦の一年(一期)のストーリー性を表現するには、予選の記事にも相応の厚みが欲しいかと思われます。高校野球でもサッカーのW杯でも、決勝だけでなく予選、そして本戦のリーグ戦、トーナメント戦にもそれ相応の面白さがあるでしょう。将棋においても、記事の扱い次第では、その面白さは伝わりうるはずです。
将棋の「本」は決して需要がないとは思いません。
ではでは
観戦記事の内容が実際の言葉の解説がついての説明です。
NHKも解説があるので面白く分かりやすいです。それを動画で表現できればと思います。
記事は紙面の都合で掲載できない内容や細かい変化などが表現できません。
活字の限界があります。
それをビジュアルに表現するわけですから。
棋譜が将棋ゲームと連携して再現できたりすると、初心者には最適です。
もっと裾野を広げる意味でも色々なメディアを利用しては、いかがですか。
※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。