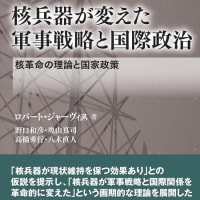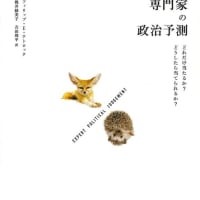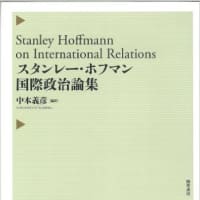近年の国際政治学において、数学を使った計量分析がどのように行われているかを分かりやすく解説した論文を紹介したいと思います。多湖淳「国際政治学における計量分析」『オペレーションズ・リサーチ』第56巻第4号(2011年4月)です。
数年前、私は国際関係の主要理論やアプローチを紹介したテキスト『国際関係理論』(勁草書房、2006年)を研究仲間とともに出版しました。同書は、お陰様で刷数を重ねておりますが、同時に、「国際関係の数理アプローチを軽視している」との批判も受けておりました。同書に、こうした物足りなさや不満を感じた方は、上記に紹介した多湖論文を読んで、国際政治学の計量分析へも視野を広げて頂ければ幸いです。
多湖論文が、国際政治学、とりわけ安全保障研究の計量アプローチの動向をうまくまとめていますので、私が、ここであまり余計なことを言う必要はありませんが、同学問の現状や計量分析の実証について、若干付記させていただければと思います。
1つは、現在の安全保障研究は、さまざまなアプローチから成り立っているということです。すなわち、「知的・方法論的多様性(the intellectual and methodological diversity)」(S. ウォルト氏)が維持されている、ということです。国際政治学の世界のトップジャーナルを見ると、傾向として、American Political Science Review誌、International Organization誌などは計量分析の論文をこぞって掲載する一方、International Security誌や Security Studies誌は、日常言語で書かれた理論や事例研究の論文を重視しています。こうした学問上の多様性は、国際政治学や安全保障研究にとって健全なことだと思います。
2つめは、数理理論の実証についてです。理論の経験的検証は、その妥当性を確かめるために必要不可欠です。その主なツールは、統計と事例研究です。合理的選択理論家がよく使う統計的検定は、検証の有力な方法である一方、事例研究による因果関係の過程追跡(出来事が理論通りに起こっているのかを歴史証拠などにより確認すること)も、理論の検証には、なくてはならないものです。前者については、多湖論文でもいくつか紹介されていますが、後者については、多湖論文が発表された後に大きな展開がありました。
計量分析での精緻化が進んだ「観衆コスト」モデルについて、ようやく本格的な事例研究が行われたということです。その1つが、Jack Snyder and Erica D. Borghard, "The Cost of Empty Threats: A Penny, Not a Pound," American Political Science Review, Vol. 105, No. 3 (August 2011), pp. 437-456 であり、もう1つが、Marc Trachtemberg, "Audience Costs: An Historical Analysis," Security Studies, Vol. 21, No. 3 (Jan-Feb 2012), pp. 3-42 です。
スナイダー・ボガード論文は主に第二次世界大戦後の事例、トラクテンバーグ論文は、第二次世界大戦前の事例から、観衆コストモデルを検証しています。両論文の結論は、理論の妥当性をかなり強く否定しています。この2つの刺激的な論文に対しては、おそらく、今後、数理理論家から反応があるでしょう。
これに関連して、イランの核開発危機は、観衆コストモデルの「実用性」を考える機会をわれわれに与えています。ダニエル・ドレズナー氏(タフツ大学)が『フォーリン・ポリシー』誌の「ブログ」で示唆するように、現在進行しているイランの核開発をめぐる「危機」は、観衆コスト仮説を試す、現在進行形の「テスト・ケース」を提供しています。この危機が、どのような帰結を迎えるのか(民主国イスラエルの脅しに、イランは屈するのか、など)、ということにも注目したいと思います。
数年前、私は国際関係の主要理論やアプローチを紹介したテキスト『国際関係理論』(勁草書房、2006年)を研究仲間とともに出版しました。同書は、お陰様で刷数を重ねておりますが、同時に、「国際関係の数理アプローチを軽視している」との批判も受けておりました。同書に、こうした物足りなさや不満を感じた方は、上記に紹介した多湖論文を読んで、国際政治学の計量分析へも視野を広げて頂ければ幸いです。
多湖論文が、国際政治学、とりわけ安全保障研究の計量アプローチの動向をうまくまとめていますので、私が、ここであまり余計なことを言う必要はありませんが、同学問の現状や計量分析の実証について、若干付記させていただければと思います。
1つは、現在の安全保障研究は、さまざまなアプローチから成り立っているということです。すなわち、「知的・方法論的多様性(the intellectual and methodological diversity)」(S. ウォルト氏)が維持されている、ということです。国際政治学の世界のトップジャーナルを見ると、傾向として、American Political Science Review誌、International Organization誌などは計量分析の論文をこぞって掲載する一方、International Security誌や Security Studies誌は、日常言語で書かれた理論や事例研究の論文を重視しています。こうした学問上の多様性は、国際政治学や安全保障研究にとって健全なことだと思います。
2つめは、数理理論の実証についてです。理論の経験的検証は、その妥当性を確かめるために必要不可欠です。その主なツールは、統計と事例研究です。合理的選択理論家がよく使う統計的検定は、検証の有力な方法である一方、事例研究による因果関係の過程追跡(出来事が理論通りに起こっているのかを歴史証拠などにより確認すること)も、理論の検証には、なくてはならないものです。前者については、多湖論文でもいくつか紹介されていますが、後者については、多湖論文が発表された後に大きな展開がありました。
計量分析での精緻化が進んだ「観衆コスト」モデルについて、ようやく本格的な事例研究が行われたということです。その1つが、Jack Snyder and Erica D. Borghard, "The Cost of Empty Threats: A Penny, Not a Pound," American Political Science Review, Vol. 105, No. 3 (August 2011), pp. 437-456 であり、もう1つが、Marc Trachtemberg, "Audience Costs: An Historical Analysis," Security Studies, Vol. 21, No. 3 (Jan-Feb 2012), pp. 3-42 です。
スナイダー・ボガード論文は主に第二次世界大戦後の事例、トラクテンバーグ論文は、第二次世界大戦前の事例から、観衆コストモデルを検証しています。両論文の結論は、理論の妥当性をかなり強く否定しています。この2つの刺激的な論文に対しては、おそらく、今後、数理理論家から反応があるでしょう。
これに関連して、イランの核開発危機は、観衆コストモデルの「実用性」を考える機会をわれわれに与えています。ダニエル・ドレズナー氏(タフツ大学)が『フォーリン・ポリシー』誌の「ブログ」で示唆するように、現在進行しているイランの核開発をめぐる「危機」は、観衆コスト仮説を試す、現在進行形の「テスト・ケース」を提供しています。この危機が、どのような帰結を迎えるのか(民主国イスラエルの脅しに、イランは屈するのか、など)、ということにも注目したいと思います。