「レッドテープ」は、「杓子定規ぶり」とか「わずらわしい煩雑なルールや規制」を意味する言葉です。このレッド・テープにイライラされた経験をお持ちの方は、さぞ多いことでしょう。
私が「レッド・テープ」から、真っ先に思い起こすエピソードは、真珠湾攻撃の際、日本海軍の航空機による攻撃に対して、P40戦闘機で果敢に反撃したウェルチ大尉の処遇です。この勇敢な行動が、軍からほめたたられるかと思いきや、彼を待っていたのは、「命令ナシの無断離陸」の罪状に関する取り調べだったそうです!(佐々淳行『危機管理のノウハウ(2)』PHP研究所、1980年、32-42ページ参照)。
この強烈な逸話は、私にとって、「レッド・テープ」を嫌悪させるに十分でした。佐々氏の同書を読んで、私と同じような感想を持った方も少なくないでしょう。他方、にもかかわらず「レッド・テープ」は、今も昔も、どの組織にも存在します。なぜなのでしょうか。
『官僚はなぜ規制したがるのか―レッド・テープの理由と実態―』(ハーバート・カウフマン、今村都南雄訳、勁草書房、2015年)は、この疑問に応える現代の古典です。本書に序文を寄せたフィリップ・ハワード氏の言葉を借りれば、多様性と不信と民主主義が存在する国家において、「レッド・テープ」は、「政府(行政)における最低水準の一貫性、公正性を確保する方途」であるということです。その副産物こそが、「レッド・テープ」に付随する煩雑さや非効率性、高コストということなのでしょう。「研究に費やした時間より研究費の申請書と報告書を作成するのに、多くの時間がかかった」という類のエピソードは、われわれの「業界」における「レッド・テープ」の典型例です。
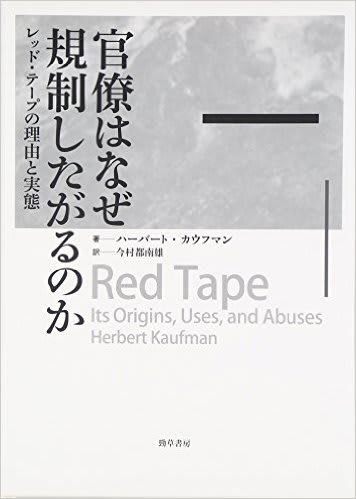
では、私たちは、「レッド・テープ」とどう付き合っていけばよいのか。私は本書を読んで、以下の一文にハッとさせられました。
「私たちは裁量と制約の間の適切なトレード・オフについて相反する感情を有し、誰もが自分自身に対しては前者を、隣人に対しては後者を欲する。こうした条件下において、それとともに生きることを学ぶこと、そのことしか(レッド・テープに対処するすべは)ないのである」(99ページ)。
こうした心理的属性を持っていることを自覚するだけでも、組織や社会における個人の行動は、より忍耐強いものになっていくでしょう。
他方、危機管理の際には、話は変わってきます。前出のハワード氏は「安全性にかかわる業務に対する政府監督となれば、おそらくはレッド・テープによってではなく、責任ある判断行使によってこそ果たすのが最善である」(序文、viiiページ)と指摘しています。佐々氏も「健全な『常識』と≪法三章≫の精神(肝賢な大綱のみを簡潔に定め、あとはそれを運用すること)によって、規則などの解釈による弾力的運用を図ることが大切である」(42ページ)と主張しています。

皆さんは、どう考えますか。
私が「レッド・テープ」から、真っ先に思い起こすエピソードは、真珠湾攻撃の際、日本海軍の航空機による攻撃に対して、P40戦闘機で果敢に反撃したウェルチ大尉の処遇です。この勇敢な行動が、軍からほめたたられるかと思いきや、彼を待っていたのは、「命令ナシの無断離陸」の罪状に関する取り調べだったそうです!(佐々淳行『危機管理のノウハウ(2)』PHP研究所、1980年、32-42ページ参照)。
この強烈な逸話は、私にとって、「レッド・テープ」を嫌悪させるに十分でした。佐々氏の同書を読んで、私と同じような感想を持った方も少なくないでしょう。他方、にもかかわらず「レッド・テープ」は、今も昔も、どの組織にも存在します。なぜなのでしょうか。
『官僚はなぜ規制したがるのか―レッド・テープの理由と実態―』(ハーバート・カウフマン、今村都南雄訳、勁草書房、2015年)は、この疑問に応える現代の古典です。本書に序文を寄せたフィリップ・ハワード氏の言葉を借りれば、多様性と不信と民主主義が存在する国家において、「レッド・テープ」は、「政府(行政)における最低水準の一貫性、公正性を確保する方途」であるということです。その副産物こそが、「レッド・テープ」に付随する煩雑さや非効率性、高コストということなのでしょう。「研究に費やした時間より研究費の申請書と報告書を作成するのに、多くの時間がかかった」という類のエピソードは、われわれの「業界」における「レッド・テープ」の典型例です。
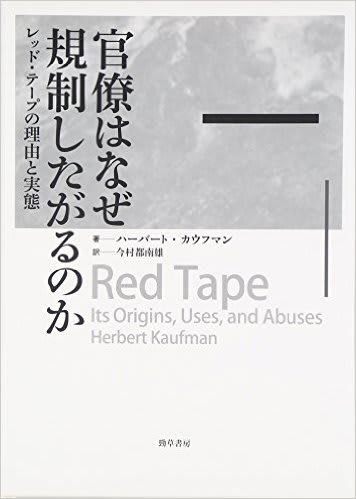
では、私たちは、「レッド・テープ」とどう付き合っていけばよいのか。私は本書を読んで、以下の一文にハッとさせられました。
「私たちは裁量と制約の間の適切なトレード・オフについて相反する感情を有し、誰もが自分自身に対しては前者を、隣人に対しては後者を欲する。こうした条件下において、それとともに生きることを学ぶこと、そのことしか(レッド・テープに対処するすべは)ないのである」(99ページ)。
こうした心理的属性を持っていることを自覚するだけでも、組織や社会における個人の行動は、より忍耐強いものになっていくでしょう。
他方、危機管理の際には、話は変わってきます。前出のハワード氏は「安全性にかかわる業務に対する政府監督となれば、おそらくはレッド・テープによってではなく、責任ある判断行使によってこそ果たすのが最善である」(序文、viiiページ)と指摘しています。佐々氏も「健全な『常識』と≪法三章≫の精神(肝賢な大綱のみを簡潔に定め、あとはそれを運用すること)によって、規則などの解釈による弾力的運用を図ることが大切である」(42ページ)と主張しています。

皆さんは、どう考えますか。
















