これから紹介する文章は、ある大学のある授業のシラバス(授業概要)の内容を記したものです。さて、どの大学で教えられている、何という講座でしょうか。
「このコースは、学問としての戦略研究の主要な特徴を総合的に扱うものである。その狙いは、学生が主な戦略的問題の強力な分析枠組みを身につけるとともに、それら数多くの問題を詳しく調べること手助けをすることである。具体的な内容は、戦略の性質や戦略と安全保障の関係、戦争の原因、大戦略、航空・陸上・海上戦略、武力行使に関する法的・倫理的問題、国際システムにおける暴力の役割、大量破壊兵器、テロ、国際的な平和維持・安定化の活動(作戦)、変容する軍事技術の影響になる」。
これが開講されているのは、どこかの士官学校や軍人のための大学ではありません。オーストリア国立大学における「戦略研究(Strategic Studies)」が、その答えです。
ちなみに、欧米の大学では、こうした戦略研究や戦争研究のコースが数多く設けられているます。イギリスのロンドン大学キングスカレッジには、「戦争研究学部」が設置されています。アメリカのエール大学で開講されている「大戦略(Grand strategy)研究」コースも有名です。言うまでもないことですが、これらの大学は、全て世界でトップクラスです(オーストラリア国立大学48位、キングスカレッジ36位、エール大学12位 Times Higher Educationによる2018年度のランキング)
もちろん、戦略研究を大学で教えることには、批判も寄せられています。以下は、世界で広く読まれている戦略論のテキストからの引用です。
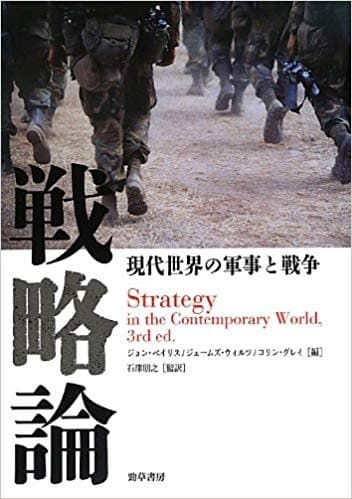
「戦略研究に寄せられた大きな批判には、『大学という場所の存在理由である、リベラルで人道的な(humane)学問の価値に対して根源的な挑戦』を挑んでいるというものである。つまり、戦略研究は学術的テーマではなく、大学で教えられるべきものではない」(15-16ページ、訳文の一部は引用者が改訂)
こうした批判には一理あります。大学は、人間性(humanity)を涵養するところです。この人間性とは、とらえどころがない概念ですが、とりあえず、ここでは知的理性や道徳的命令(人の道)に従う姿勢といったことを含意しているものとします。他方、ここでいう「戦略」は、人道にそぐわない内容を含んでいると言わざるを得ません。上記の『戦略論』には、この道の大家であるコリン・グレイ氏の戦略の次の定義が引用されています。「政治目的のために、組織化された力の行使あるいはその行使の威嚇をする際の理論と実践」。この定義を読んだ方からは、こう叱られそうです。「学問を政治に従属させるのか!」、「物理的暴力である軍事力の利用方法を研究するなど、人の道にもとる!(=道徳的・倫理的にけしからん)」と。
では、大学で戦略研究を無視しても構わないのでしょうか。そんなことはないという論者もいます。西原正氏は、今から30年前に出版された『戦略研究の視角』人間の科学社、1988年において、戦略研究の意義をこう主張しています。
「(戦略研究は)大学教育に馴染まない科目であるという意見は多い。…しかし…大学教育が…どんな政策を採ることが必要かという問題意識の高揚にも貢献することが、将来の指導者を培うことになる。大学はすでに経済政策、科学技術政策、環境政策、医学など多くの分野で政府の政策立案に貢献してきている。安全保障や戦略の分野でも、そうした政策指向の教授陣がいなければならない」(ivページ)
私は、この意見にも一理あると思います。国家戦略や安全保障政策が、国民生活の根幹を支えるものである以上、その立案や変更を研究することも大切だからです。残念ながら、「あなたは戦争に関心がないかもしれないが、戦争はあなたに関心を持っている」(トロツキー)のが、おそらく現実でしょう。だから、われわれはいやおうなく、戦争や軍事を考えざるを得ないのです。ここで注意していただきたいのは、戦略研究者は「御用学者」ではないことです(そういう人もいるでしょうが)。たとえば、米国では、多くの戦略研究者が、ブッシュ大統領のイラク侵攻やトランプ大統領の政策を公に批判しています。戦略研究は、大学教育の1つの根幹である「批判的思考」の育成と両立するのです。
さらに、欧米で戦略研究が「学問」として、大学で教えられている一方、日本の大半の大学おいて事実上、否定されている状態が続けば、この分野の欧米と日本の学問的ギャップが、広がるばかりです。これは、はたして学術的に健全なのでしょうか。上記のテキスト『戦略論』によれば、「戦略は依然として学術研究のなかで単独の価値を有する領域であり続けてい」(21ページ)ます。学問分野の構成を示せば、政治学⊃国際関係論(国際政治学)⊃安全保障研究⊃戦略研究となります。その国際政治学の1つの分野を構成する「戦略研究」が、一部の例外を除き、日本の学界、そして「大学のカリキュラムにおいてはタブー視され、意図的に排除されてきた」(西原、前掲書、ivページ)のであれば、今からでも遅くありません、「輸入学問」たる日本の国際政治学に「戦略研究」を取り入れるべきでしょう。
「このコースは、学問としての戦略研究の主要な特徴を総合的に扱うものである。その狙いは、学生が主な戦略的問題の強力な分析枠組みを身につけるとともに、それら数多くの問題を詳しく調べること手助けをすることである。具体的な内容は、戦略の性質や戦略と安全保障の関係、戦争の原因、大戦略、航空・陸上・海上戦略、武力行使に関する法的・倫理的問題、国際システムにおける暴力の役割、大量破壊兵器、テロ、国際的な平和維持・安定化の活動(作戦)、変容する軍事技術の影響になる」。
これが開講されているのは、どこかの士官学校や軍人のための大学ではありません。オーストリア国立大学における「戦略研究(Strategic Studies)」が、その答えです。
ちなみに、欧米の大学では、こうした戦略研究や戦争研究のコースが数多く設けられているます。イギリスのロンドン大学キングスカレッジには、「戦争研究学部」が設置されています。アメリカのエール大学で開講されている「大戦略(Grand strategy)研究」コースも有名です。言うまでもないことですが、これらの大学は、全て世界でトップクラスです(オーストラリア国立大学48位、キングスカレッジ36位、エール大学12位 Times Higher Educationによる2018年度のランキング)
もちろん、戦略研究を大学で教えることには、批判も寄せられています。以下は、世界で広く読まれている戦略論のテキストからの引用です。
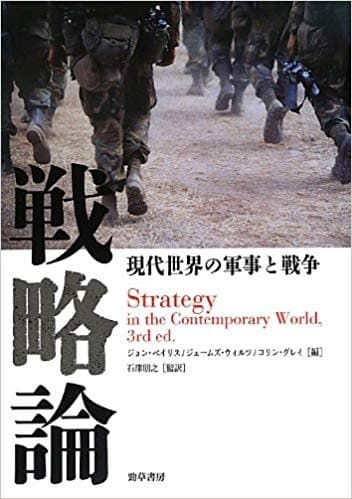
「戦略研究に寄せられた大きな批判には、『大学という場所の存在理由である、リベラルで人道的な(humane)学問の価値に対して根源的な挑戦』を挑んでいるというものである。つまり、戦略研究は学術的テーマではなく、大学で教えられるべきものではない」(15-16ページ、訳文の一部は引用者が改訂)
こうした批判には一理あります。大学は、人間性(humanity)を涵養するところです。この人間性とは、とらえどころがない概念ですが、とりあえず、ここでは知的理性や道徳的命令(人の道)に従う姿勢といったことを含意しているものとします。他方、ここでいう「戦略」は、人道にそぐわない内容を含んでいると言わざるを得ません。上記の『戦略論』には、この道の大家であるコリン・グレイ氏の戦略の次の定義が引用されています。「政治目的のために、組織化された力の行使あるいはその行使の威嚇をする際の理論と実践」。この定義を読んだ方からは、こう叱られそうです。「学問を政治に従属させるのか!」、「物理的暴力である軍事力の利用方法を研究するなど、人の道にもとる!(=道徳的・倫理的にけしからん)」と。
では、大学で戦略研究を無視しても構わないのでしょうか。そんなことはないという論者もいます。西原正氏は、今から30年前に出版された『戦略研究の視角』人間の科学社、1988年において、戦略研究の意義をこう主張しています。
「(戦略研究は)大学教育に馴染まない科目であるという意見は多い。…しかし…大学教育が…どんな政策を採ることが必要かという問題意識の高揚にも貢献することが、将来の指導者を培うことになる。大学はすでに経済政策、科学技術政策、環境政策、医学など多くの分野で政府の政策立案に貢献してきている。安全保障や戦略の分野でも、そうした政策指向の教授陣がいなければならない」(ivページ)
私は、この意見にも一理あると思います。国家戦略や安全保障政策が、国民生活の根幹を支えるものである以上、その立案や変更を研究することも大切だからです。残念ながら、「あなたは戦争に関心がないかもしれないが、戦争はあなたに関心を持っている」(トロツキー)のが、おそらく現実でしょう。だから、われわれはいやおうなく、戦争や軍事を考えざるを得ないのです。ここで注意していただきたいのは、戦略研究者は「御用学者」ではないことです(そういう人もいるでしょうが)。たとえば、米国では、多くの戦略研究者が、ブッシュ大統領のイラク侵攻やトランプ大統領の政策を公に批判しています。戦略研究は、大学教育の1つの根幹である「批判的思考」の育成と両立するのです。
さらに、欧米で戦略研究が「学問」として、大学で教えられている一方、日本の大半の大学おいて事実上、否定されている状態が続けば、この分野の欧米と日本の学問的ギャップが、広がるばかりです。これは、はたして学術的に健全なのでしょうか。上記のテキスト『戦略論』によれば、「戦略は依然として学術研究のなかで単独の価値を有する領域であり続けてい」(21ページ)ます。学問分野の構成を示せば、政治学⊃国際関係論(国際政治学)⊃安全保障研究⊃戦略研究となります。その国際政治学の1つの分野を構成する「戦略研究」が、一部の例外を除き、日本の学界、そして「大学のカリキュラムにおいてはタブー視され、意図的に排除されてきた」(西原、前掲書、ivページ)のであれば、今からでも遅くありません、「輸入学問」たる日本の国際政治学に「戦略研究」を取り入れるべきでしょう。


















