■笑う警官/M・シューヴァル & P・ヴァールー 2120.7.12
警察小説の代表的作品と言えば、『87分署』と『刑事マルティン・ベック』 でしょう。
先日は、 『87分署シリーズ/警官嫌い』 を読み直しました。
今日は、 『刑事マルティン・ベック/笑う警官』 を読みました。
『刑事マルティン・ベック』シリーズは、1965年から1975年までの10年の間に発表された作品です。
本書は、初版本ではなくスウェーデンで2012年に新装再出版されたミステリの新訳です。
そのあたりの事情を「訳者あとがき」から、抜き書きしてみました。
これは世界のミステリファンに警察小説の金字塔と目されている刑事マルティン・ベックシリーズの新訳第一作である。
スウェーデンの首都ストックホルムを背景として一九六五年から一九七五年までの十年間に発表された警察本庁殺人捜査課主任、刑事マルティン・ベックを主人公とする犯罪小説(Roman om ett brott)は、第一作の『ロセアンナ』(一九六五年)から四十八年経つたいまも、『87分署』シリーズのエド・マクベインとともに、世界の警察小説の二大双璧と認識され、後続のミステリ作家に多大な影響を与えたと評価されている。
二〇一二年の夏、本国スウェーデンでおよそ四十余年ぶりに全十作が新しい装いで賑々しく再出版された。
各作品には現在スウェーデンでもっとも力があると目される作家たちか賛辞を寄せている。
今年の二月に角川書店からマルティン・ベックシリーズ新訳のゴーサインが出たときは本当にうれしかった。世界中の読者に愛され続けてきた刑事マルティン・ベックシリーズを直接スウェーデン語から訳したいという思いは、翻訳を始めたころからわたしの中にあった。このシリーズは日本でも七十年代から八十年代にかけて全十作が英語から高見浩氏によって翻訳されている。軽妙洒脱な高見氏のスタイルは、長年読者を楽しませてきた。今回わたしは微力ながらマルティン・ベックシリーズを直接スウェーデン語から訳すことによって、原作のもつスウェーデン社会の雰囲気とそこに展開される人間模様を現代によみがえらせたいと願っている。
『笑う警官』はシリーズ四番目の作品だが、一九七一年にアメリカ探偵作家クラブのエドガー賞を受けている。十作品の中ではもっとも知られていることから、この作品が最初の訳出となった。今後は出版順に翻訳する予定である。従って次の作品は第一作の『ロセアンナ』となる。ご期待ください。
「巻末解説」で、杉江松恋氏は、本書の面白さを以下のように解説されています。
分かりやすくよくまとめられています。
ためいきが出るほどおもしろい。
読みながら、何度となくそんな言葉が漏れた。この小説を読むのはこれが何回目かわからない。間違いなく、この一年以内にも一回は読んでいる。しかし飽きるということがなかった。読むたびにおもしろく、読むたびに発見がある。
『笑う警官』とはそういう小説なのだ。
本書はストックホルムの刑事マルティン・ベックを主人公にしたシリーズの四作目にあたる。全十作に共通する形式として、一作が三十章に分割され、最初の数章で事件の発端が描かれ、それについてベックたちを含む刑事たちが手分けをして捜査に当たるさまが描かれる。最初は手がかりがほとんどなく、ベックたちは濃霧の中を手探りするような状態で進まなければならない。少しずつ情報が得られるにつれて光明が射し始め、ある瞬間に霧は一気に晴れて事件の全貌が明らかになる。名探偵が登場して神の如き叡智を披露するような作品とはまた違った、歩行の速度で進んでいく小説ならではの快感がこのシリーズにはあるのだ。一歩一歩踏みしめながら山を登り、来光を拝むような悦びにそれは似ている。
本作が発表された一九六八年は世界各国で反戦・平和を求める市民運動か巻き起こった年だった。当然スウェーデンも例外ではない。シューヴァル&ヴァールーは本シリーズを一年に一作ずつ書き、十年で完結させた。それは全十作で十年間のスウェーデンの社会変化を描くという年代記執筆の意図かあったからだ。したがって背景には毎回こうして、里程標となるべき政治経済や文化風俗の印象的な出来事が織り込まれているのである。
本書を読んで魅力に気づいてしまった方、このシリーズは十冊全部読破するとさらにまた別の味わいが出るのです。全十巻新訳が完成する日を心待ちにして下さい。
個性的で厳つい捜査官グンヴァルド・ラーソンは、当時のスウェーデン社会を次のように嘆いている。
「あいつは唾棄すべき男だ。おれがいちぱん嫌いなタイプだ」グンヴァルド・ラーソンが突然吐きすてるように言った。
「ん?」
「これからおれが言うことは、ほかのだれにも言ったことがない」グンヴァルド・ラーソンは言った。「おれは仕事上会うやつらのほとんどぜんぶを気の毒だと思っている。連中は本当にどうしようもない与太者で、生まれなければよかったようなやつらばかりだ。
だが、自分がなにをやっているのかわからない、なにをやってもうまくいかないのは彼らのせいじゃないんだ。いまの男みたいなやつがいるから、チンピラどもはみじめな生活に堕ちるんだ。自己中心のブタ野郎めが。自分の金と自分の家と自分の家族と自分の社会的地位しか考えないやつらだ。自分が優位にいるからと言って、ほかの人間に命令することができると思っていやがる。そんな連中がうんざりするほどいる。だが、そのほとんどはばかじゃない。じゃまだからといってポルトガルの娼婦を殺したりはしない。だからおれたちはめったにやつらと面と向かって会うことはない。今回は例外なんだ」
「そうさな。たぶんそうなんだろう」
『 笑う警官/マイ・シューヴァル&ペール・ヴァールー/柳沢由実子訳/角川文庫 』
警察小説の代表的作品と言えば、『87分署』と『刑事マルティン・ベック』 でしょう。
先日は、 『87分署シリーズ/警官嫌い』 を読み直しました。
今日は、 『刑事マルティン・ベック/笑う警官』 を読みました。
『刑事マルティン・ベック』シリーズは、1965年から1975年までの10年の間に発表された作品です。
本書は、初版本ではなくスウェーデンで2012年に新装再出版されたミステリの新訳です。
そのあたりの事情を「訳者あとがき」から、抜き書きしてみました。
これは世界のミステリファンに警察小説の金字塔と目されている刑事マルティン・ベックシリーズの新訳第一作である。
スウェーデンの首都ストックホルムを背景として一九六五年から一九七五年までの十年間に発表された警察本庁殺人捜査課主任、刑事マルティン・ベックを主人公とする犯罪小説(Roman om ett brott)は、第一作の『ロセアンナ』(一九六五年)から四十八年経つたいまも、『87分署』シリーズのエド・マクベインとともに、世界の警察小説の二大双璧と認識され、後続のミステリ作家に多大な影響を与えたと評価されている。
二〇一二年の夏、本国スウェーデンでおよそ四十余年ぶりに全十作が新しい装いで賑々しく再出版された。
各作品には現在スウェーデンでもっとも力があると目される作家たちか賛辞を寄せている。
今年の二月に角川書店からマルティン・ベックシリーズ新訳のゴーサインが出たときは本当にうれしかった。世界中の読者に愛され続けてきた刑事マルティン・ベックシリーズを直接スウェーデン語から訳したいという思いは、翻訳を始めたころからわたしの中にあった。このシリーズは日本でも七十年代から八十年代にかけて全十作が英語から高見浩氏によって翻訳されている。軽妙洒脱な高見氏のスタイルは、長年読者を楽しませてきた。今回わたしは微力ながらマルティン・ベックシリーズを直接スウェーデン語から訳すことによって、原作のもつスウェーデン社会の雰囲気とそこに展開される人間模様を現代によみがえらせたいと願っている。
『笑う警官』はシリーズ四番目の作品だが、一九七一年にアメリカ探偵作家クラブのエドガー賞を受けている。十作品の中ではもっとも知られていることから、この作品が最初の訳出となった。今後は出版順に翻訳する予定である。従って次の作品は第一作の『ロセアンナ』となる。ご期待ください。
「巻末解説」で、杉江松恋氏は、本書の面白さを以下のように解説されています。
分かりやすくよくまとめられています。
ためいきが出るほどおもしろい。
読みながら、何度となくそんな言葉が漏れた。この小説を読むのはこれが何回目かわからない。間違いなく、この一年以内にも一回は読んでいる。しかし飽きるということがなかった。読むたびにおもしろく、読むたびに発見がある。
『笑う警官』とはそういう小説なのだ。
本書はストックホルムの刑事マルティン・ベックを主人公にしたシリーズの四作目にあたる。全十作に共通する形式として、一作が三十章に分割され、最初の数章で事件の発端が描かれ、それについてベックたちを含む刑事たちが手分けをして捜査に当たるさまが描かれる。最初は手がかりがほとんどなく、ベックたちは濃霧の中を手探りするような状態で進まなければならない。少しずつ情報が得られるにつれて光明が射し始め、ある瞬間に霧は一気に晴れて事件の全貌が明らかになる。名探偵が登場して神の如き叡智を披露するような作品とはまた違った、歩行の速度で進んでいく小説ならではの快感がこのシリーズにはあるのだ。一歩一歩踏みしめながら山を登り、来光を拝むような悦びにそれは似ている。
本作が発表された一九六八年は世界各国で反戦・平和を求める市民運動か巻き起こった年だった。当然スウェーデンも例外ではない。シューヴァル&ヴァールーは本シリーズを一年に一作ずつ書き、十年で完結させた。それは全十作で十年間のスウェーデンの社会変化を描くという年代記執筆の意図かあったからだ。したがって背景には毎回こうして、里程標となるべき政治経済や文化風俗の印象的な出来事が織り込まれているのである。
本書を読んで魅力に気づいてしまった方、このシリーズは十冊全部読破するとさらにまた別の味わいが出るのです。全十巻新訳が完成する日を心待ちにして下さい。
個性的で厳つい捜査官グンヴァルド・ラーソンは、当時のスウェーデン社会を次のように嘆いている。
「あいつは唾棄すべき男だ。おれがいちぱん嫌いなタイプだ」グンヴァルド・ラーソンが突然吐きすてるように言った。
「ん?」
「これからおれが言うことは、ほかのだれにも言ったことがない」グンヴァルド・ラーソンは言った。「おれは仕事上会うやつらのほとんどぜんぶを気の毒だと思っている。連中は本当にどうしようもない与太者で、生まれなければよかったようなやつらばかりだ。
だが、自分がなにをやっているのかわからない、なにをやってもうまくいかないのは彼らのせいじゃないんだ。いまの男みたいなやつがいるから、チンピラどもはみじめな生活に堕ちるんだ。自己中心のブタ野郎めが。自分の金と自分の家と自分の家族と自分の社会的地位しか考えないやつらだ。自分が優位にいるからと言って、ほかの人間に命令することができると思っていやがる。そんな連中がうんざりするほどいる。だが、そのほとんどはばかじゃない。じゃまだからといってポルトガルの娼婦を殺したりはしない。だからおれたちはめったにやつらと面と向かって会うことはない。今回は例外なんだ」
「そうさな。たぶんそうなんだろう」
『 笑う警官/マイ・シューヴァル&ペール・ヴァールー/柳沢由実子訳/角川文庫 』
















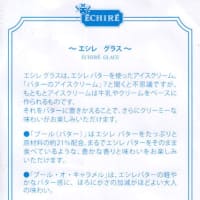








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます