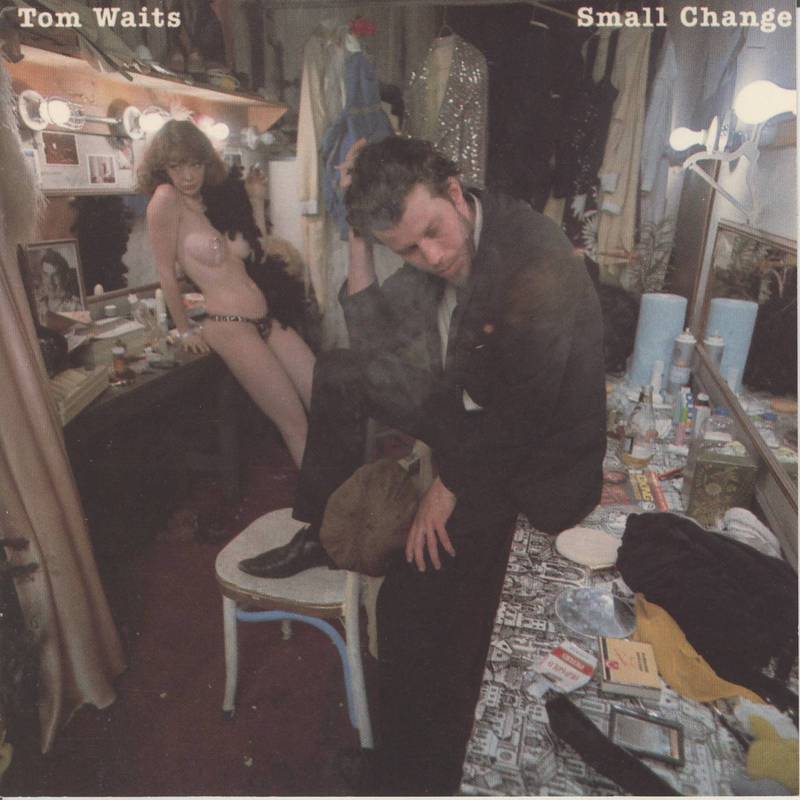1980年の作品だ。何かのコマーシャルで使われていたと思う。それまでの「ノスタルジー」を基調にした太田裕美から一転、明るく、溌剌とした太田裕美だ。ジャケットにもスポーティーな服装に身を包んだ太田裕美がいる。歌詞からも真夏のきらきらした風景と開放的なイメージが想起され、これまでと異なる路線を目指したことがわかる。爽快だ。
1980年の作品だ。何かのコマーシャルで使われていたと思う。それまでの「ノスタルジー」を基調にした太田裕美から一転、明るく、溌剌とした太田裕美だ。ジャケットにもスポーティーな服装に身を包んだ太田裕美がいる。歌詞からも真夏のきらきらした風景と開放的なイメージが想起され、これまでと異なる路線を目指したことがわかる。爽快だ。
以前にも書いたことがあるが、1980年代とはそういう時代なのだ。1970年代が自己に閉じこもる自閉と内省の時代であるとするなら、80年代はそれからの解放の時代だったのだ。70年代的な価値感は「暗い」「根暗」として糾弾され、「明るい」ことが善しとされるようになったのだ。しかし、その「明るさ」は、政治的文化的挫折に起因する70年代的「暗さ」の本質を解決・克服したものではなく、いくら内向・内省してもその先に本当に知りたいものや欲しいものが見出せないという焦燥とジレンマからくるものであった。以後、人々は自己の内部を掘り下げることなく、外部の世界の快楽に身をゆだねる生活を選んでいくことになる。
それは基本的に正しい選択であったろう。自己の内面にものごとの本質などはありはしないのだから……。例えば、『二十歳の原点』の高野悦子は80年代に青春をおくれば自殺などせずにすんだであろう。彼女は自己の内部になどありはしない人生や世界の本質を捜し求めてしまったのだ。
しかし、その明るさはやはり空虚だった。いくら明るく振舞っても心の空白は埋めることはできない。それが80~90年代の新興宗教ブームにつながっていくのであろうが、このシングル『南風』のB面に「想いでの赤毛のアン」と題する70年代的な曲が収録されているのは興味深い。このレコードが70年代的なものから80年代的なものへの過度期の作品であることをあらわすと同時に、80年代的な「明るさ」が埋めきれない70年代的「内向」を表現したものであると考えるのは、うがった見方であろうか。
ところで、「南風」のなかのオレンジ・ギャルという語が、小麦色に日焼けした女性を表すことにやっと最近気づいた。「ギャル」という語は、当時はもっと違った「さわやかな」語感があったはずだが、今となっては、怠惰でおちゃらけた女性たちをイメージしてしまい、わが太田裕美には、まったく合わない。