
GWも中盤に差し掛かった5月2日の土曜日、天理市豊田町で豊田トンド山古墳(仮称)の現地説明会が開催された。近鉄天理駅を下車、現地まで歩くこと20分。現地に行くには、豊田の旧村を抜けて、裏山に入っていく。竹林を登っていってしばらく歩くと平坦な地に出る。そこが古墳のある場所になるのだが、結構、この道の坂がきつかったので、登り切った時には汗だらだら。日差しもきつく初夏の風情であった。

👆この竹藪の中を入っていく。道案内の方が立っていなかったら絶対わからなかった。
現地に着くと、栗山の人だかり、多くの方がすでに来ていて、ビックリ。世に古墳ファン、古代史ファンという方々がたくさんいらっしゃるのだなあと実感。(僕もその一人ではあるのですが・・・。)

天理市の教育委員会の方の説明が始まる。一人女性の方が古墳の石室の中に立たれていたので改めて石室の大きさに目を見張る。

この豊田トンド山古墳については、都市計画道路建設に伴う調査により、新たに見つかった古墳である。もともと古墳があるだろうなとは思われていたのだが、まさか、こんな立派な横穴式石室のある古墳が出てくるとはという感じである。
天理市のこの豊田トンド山古墳のある地域というのは、近くに古墳時代の集落跡である布留遺跡があり、また、古墳のある丘陵地の北方には、古墳時代の後期の群集墳である石上、豊田古墳群がある。また、この古墳の東側の山には中世には、豊田山城が築かれている。

古墳自体は、中世にかなり改変を受けていて、石室の天井石等はすでになくなっている。また、それ以前の13~14世紀には盗掘にもあっているとのこと。そういえば、古墳の周辺に石材を割るための矢穴の開いた石が、見つかっている。

近くにあったという豊田山城を作る際に、再利用されたのかもしれない。
さて、豊田トンド山古墳であるが、現在は石室の一段目、あるいは奥壁の2段目が残っているに過ぎない。石室の大きさは、全長で9.4m、石室は、長さ4.9m、横2.0m、羨道は、長さ4.5m、横1.7mとなっている。石室に使われている石材で一番大きいものは、幅3mにも及ぶという。

古墳の墳丘の形は、すでに中世に改変されていてわからないが30mほどの円墳ではないかとのこと。古墳が作られた立地としては、終末期古墳の特徴である丘陵の南側を削って整地して築造しており、いわゆる「山寄せの古墳」となっている。
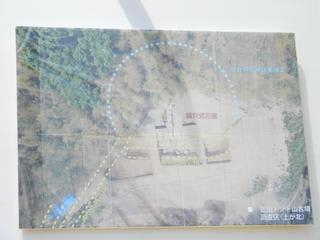
古墳の築造された年代としては、7世紀の前半を想定されている。日本書紀によると、587年丁未の乱により、物部氏の主流であった物部守屋が滅んでいるので、豊田トンド山古墳が作られた時期というのは、ヤマト王権内での物部氏の勢力は衰えている時期にある。そういった時期にありながらも、石上神宮や布留遺跡を望むような高所にこのような古墳を作ることができたというのは、丁未の乱後も、物部氏としては、隠然たる実力をこの地に持っていたということなのだろう。
壬申の乱後、天武天皇の時代に、物部氏は石上氏と改正し、奈良時代に渡って王朝貴族となって栄えることとなる。おそらくは、この古墳に埋葬された人物は、物部氏の冬の時代といったときを支えた人物であったのだろう。

👆写真は、豊田トンド山古墳から石上神宮の方を望む。
ちなみにこの古墳の埋葬者を直接示すような副葬品は残念ながら見つからなかった。凝灰岩で作られた石棺の破片と木棺に使用されたのではないかと思われる鉄釘が見つかっている。

今後、この古墳については、引き続き底面の排水溝等の確認調査を行うという。その後はどうするのかはこれから検討するのだとのこと。道路自体は、この古墳の前を走るみたいである。是非とも残してほしい古墳であると思う。


👆この竹藪の中を入っていく。道案内の方が立っていなかったら絶対わからなかった。
現地に着くと、栗山の人だかり、多くの方がすでに来ていて、ビックリ。世に古墳ファン、古代史ファンという方々がたくさんいらっしゃるのだなあと実感。(僕もその一人ではあるのですが・・・。)

天理市の教育委員会の方の説明が始まる。一人女性の方が古墳の石室の中に立たれていたので改めて石室の大きさに目を見張る。

この豊田トンド山古墳については、都市計画道路建設に伴う調査により、新たに見つかった古墳である。もともと古墳があるだろうなとは思われていたのだが、まさか、こんな立派な横穴式石室のある古墳が出てくるとはという感じである。
天理市のこの豊田トンド山古墳のある地域というのは、近くに古墳時代の集落跡である布留遺跡があり、また、古墳のある丘陵地の北方には、古墳時代の後期の群集墳である石上、豊田古墳群がある。また、この古墳の東側の山には中世には、豊田山城が築かれている。

古墳自体は、中世にかなり改変を受けていて、石室の天井石等はすでになくなっている。また、それ以前の13~14世紀には盗掘にもあっているとのこと。そういえば、古墳の周辺に石材を割るための矢穴の開いた石が、見つかっている。

近くにあったという豊田山城を作る際に、再利用されたのかもしれない。
さて、豊田トンド山古墳であるが、現在は石室の一段目、あるいは奥壁の2段目が残っているに過ぎない。石室の大きさは、全長で9.4m、石室は、長さ4.9m、横2.0m、羨道は、長さ4.5m、横1.7mとなっている。石室に使われている石材で一番大きいものは、幅3mにも及ぶという。

古墳の墳丘の形は、すでに中世に改変されていてわからないが30mほどの円墳ではないかとのこと。古墳が作られた立地としては、終末期古墳の特徴である丘陵の南側を削って整地して築造しており、いわゆる「山寄せの古墳」となっている。
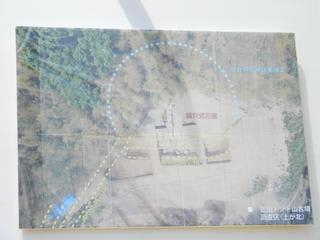
古墳の築造された年代としては、7世紀の前半を想定されている。日本書紀によると、587年丁未の乱により、物部氏の主流であった物部守屋が滅んでいるので、豊田トンド山古墳が作られた時期というのは、ヤマト王権内での物部氏の勢力は衰えている時期にある。そういった時期にありながらも、石上神宮や布留遺跡を望むような高所にこのような古墳を作ることができたというのは、丁未の乱後も、物部氏としては、隠然たる実力をこの地に持っていたということなのだろう。
壬申の乱後、天武天皇の時代に、物部氏は石上氏と改正し、奈良時代に渡って王朝貴族となって栄えることとなる。おそらくは、この古墳に埋葬された人物は、物部氏の冬の時代といったときを支えた人物であったのだろう。

👆写真は、豊田トンド山古墳から石上神宮の方を望む。
ちなみにこの古墳の埋葬者を直接示すような副葬品は残念ながら見つからなかった。凝灰岩で作られた石棺の破片と木棺に使用されたのではないかと思われる鉄釘が見つかっている。

今後、この古墳については、引き続き底面の排水溝等の確認調査を行うという。その後はどうするのかはこれから検討するのだとのこと。道路自体は、この古墳の前を走るみたいである。是非とも残してほしい古墳であると思う。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます