第6話 メタエンジニアリングによる文化の文明化のプロセスの確立(その2)
1970年代の文化と文明に関する著書
1970年代に発行された文化と文明に関する参考著書を6件列挙します。
20世紀文明の発達と、それをつくりだした科学と技術(エンジニアリング)の加速度についての幅広くかつ公正な見方がひろがり、その背景を探る議論が沸き起こった。そして、反面これで良いのだろうかとと云った疑問も出始めた期間だった。それが、有名な「成長の限界」に繋がってゆく。
また、文化と文明の観点から、それ以前とは異なり、異国の文化に対する研究も公平な視点から行われるようになり、その中で、日本人の考え方と文化についての考察も深まっていった。
1.伊藤俊太郎「文明における科学」勁草書房 (1976)KMB048彼は、「知のエートス」について、次のように述べている。

・科学の制度化やその専門職業化はどのように進行したか、科学的活動の中心がどの用に移動したか、-などを問題としてとりあげ、科学知識の内容そのものに関わる科学社会学的考察は断念され、・・・
・如何なる文化圏にも、その文化活動を支える基本的な「価値志向」というものがあり、これが他の文化的営為と同様に、科学的営為にも色濃く影響を与えているのだと思う。そしてこれをこそ先ず捉えてゆかなければならない。そこでこの知的営為に関わる「価値志向」をウエーバーの「経済倫理」(Wirtschaftsethik)になぞらえて、「知のエートス」(Wissensethons)となづけておきたい。
このような前置きの後で、古代のギリシャ、インド、中国の普遍的な思想を次のように網羅し、さらに知のエートスを表で表している。
求められる対象 知的営為の目的 世界に対する態度 方法
ギリシャ イデア 観照的認識 世界直視 理論的
インド 涅槃 宗教的解脱 世界超脱 思弁的
中国 道 倫理的実践 世界適合 直感的
この様にやや大胆に整理した後に、「知のエートス」については、次の表に纏めている。
知のエートス 科学の担い手 科学の支持者
ギリシャ meta-physics 哲学者 市民
インド meta-religiosa バラモン バラモン層
中国 meta-ethica 士大夫 為政者
アラビア meta-magica ハーキム 王侯
2.ノベルト・エリアス「文明化の過程」法政大学出版局(1997) KMB079

・科学・技術上の進歩の経験のみでは、進歩の理想化、人間状況のいっそうの改善に対する革新の契機となりえないことは、20世紀において明確に証明されている。今世紀における科学・技術上の実際上の規模と速度は、過去の数世紀における進歩の規模や速度を遥かに凌駕している。20世紀の一般住民の生活水準も、最初の工業化の波を受けた国々では、過去の数世紀に比して高い。健康状態は改善され、寿命は伸びた。しかし、「時代の大合唱」の中では、進歩を価値のあるものとして肯定し、人間状況の改善に社会的理想の核心を認め、確信をもって人類のより良き未来を信じる人の声は、過去数世紀に比して、著しく弱まっている。他方、これらすべての発展の価値を疑い、人類のより良き未来、もしくは自国の未来に対してさえ特別な期待も抱かず、かれらの主要な社会的信念がもっぱら眼前のこと、自国の保全・現存社会体制・過去・伝統・因習的秩序を最高の価値として、それらに集中しているような人々の声が20世紀において高まり、漸次優位を占めつつある。
・「文明化」と「文化」という対立概念の発展の過程について
3.ベン・ダヴィッド(1971)の邦訳本「社会における科学者の役割」「科学の社会学」潮木守一、天野郁夫訳、至誠堂(1974)
・この書物は近時の科学社会学の主要な動向を代表する好著と言ってよいが、この中で著者は科学社会学の方法として、(a)科学と社会制度の関係を論ずる制度論的アプローチと、(b)科学者相互の社会的関係を問題とする関係論的アプローチを区別し、さらに他方において、(a’)その社会的条件の影響が、専ら科学者の行動や科学活動だけに及ぶと考えるか、それとも(b’)さらに科学者自身の中味にまで、つまりその基礎概念や科学理論の内容にまで影響を与えるとするかという二つの立場を区別する。
4.角田忠信「日本人の脳」大修館書店 (1978)

・日本では認識過程をロゴスとパトスに分けるという考え方は、西欧文化に接するまでは遂に生じなかったし、また現在に至っても哲学・論理学は日本人一般には定着していないように思う。日本人にみられる脳の受容機構の特質は、日本人及び日本文化にみられる自然性、情緒性、論理のあいまいさ、また人間関係においてしばし義理人情が論理に優先することなどの特徴と合致する。西欧人は日本人に較べて論理的であり、感性よりも論理を重んじる態度や自然と対決する姿勢は脳の需要機構のパターンによって説明できそうである。西欧語パターンでは感性を含めて自然全般を対象とした科学的態度が生まれようが、日本語パターンからは人間や自然を対象とした学問は育ち難く、ものを扱う科学としての物理学・工学により大きな関心が向けられる傾向が生じるのではないだろうか?明治以来の日本の急速な近代化や戦後の物理・工学における輝かしい貢献に比べて、人間を対象とした科学が育ちにくい背景にはこの様な日本人の精神構造が大きく影響しているように思える。 (P85)
・左脳ばかりを使って論理のみをいじくりまわしていると、どうしても模倣になってしまい勝ちで、やはり何か新しいものを生みだすのは右の脳も使ってやらないといけない。(中略)それには西洋音楽を聴くことですよ。邦楽では語りが中心だし、自然に密着していますから、やはり充分な効果はない。全く異質という意味で、西洋楽器の音はよい刺激になります。 (副題「右の脳を活用しよう」(P22)
・西洋文明の危機が叫ばれているが、それは西洋人の窓枠を通しては、新しい時代に即した想像が生まれ得ない苦悩の表明ではあるまいか。数ある文明国の中で、異質の、しかもまだ充分に創造性の発揮されていない文化の枠組みを持つのは、実は日本以外にはないのである。
しかし、このことを日本と西洋の優劣というような価値観に結び付けて必要以上に劣等感に悩まされたり、逆に自信を持ちすぎることもない。必要なのはこの違いを如何に活かすかということである。著者は日本人が、日本人の窓枠の異質性にめざめて、借りものでない自分の頭で考え抜くときにはじめて日本人の独創性が発揮され、その所産は世界の文化に貢献できる可能性のあることを信じたい。 (P378)
5.芳賀綏「日本人の表現心理」中公叢書 (1979)
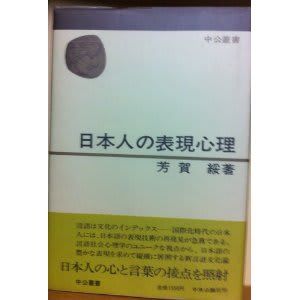
人文科学や社会科学を追求する上でも、「語らぬ」「わからせぬ」「いたわる」「ひかえる」「修める」「ささやかな」「流れる」「まかせる」というのが日本人のコミュニケーションの特徴であり、これに対する知見も持つことが大切であるなどと述べられている。
6.D.C.バーンランド「日本人の表現構造」サイマル出版会(1973)

人間の人格構造について、「未知なる自己」(U)、「私的自己」、「公的自己」という3重の同心円モデルを提唱し、それによって個人レベルの異文化コミュニケーションの摩擦のメカニズムを説明している。そして実験によって、日本人は比較的「私的自己」が厚く「公的自己」が薄く、逆にアメリカ人は比較的「私的自己」が薄く「公的自己」が厚い。そのためアメリカ人にとって快適な心的距離のコミュニケーションを行うと、日本人は自分の「公的自己」を突き破って「私的自己」の内までアメリカ人の自己が入ってくることになり、不愉快なコミュニケーションと感じるなどと説明されている。
次回の(その3)では、1980年代の8冊を紹介しようと思います。
1970年代の文化と文明に関する著書
1970年代に発行された文化と文明に関する参考著書を6件列挙します。
20世紀文明の発達と、それをつくりだした科学と技術(エンジニアリング)の加速度についての幅広くかつ公正な見方がひろがり、その背景を探る議論が沸き起こった。そして、反面これで良いのだろうかとと云った疑問も出始めた期間だった。それが、有名な「成長の限界」に繋がってゆく。
また、文化と文明の観点から、それ以前とは異なり、異国の文化に対する研究も公平な視点から行われるようになり、その中で、日本人の考え方と文化についての考察も深まっていった。
1.伊藤俊太郎「文明における科学」勁草書房 (1976)KMB048彼は、「知のエートス」について、次のように述べている。

・科学の制度化やその専門職業化はどのように進行したか、科学的活動の中心がどの用に移動したか、-などを問題としてとりあげ、科学知識の内容そのものに関わる科学社会学的考察は断念され、・・・
・如何なる文化圏にも、その文化活動を支える基本的な「価値志向」というものがあり、これが他の文化的営為と同様に、科学的営為にも色濃く影響を与えているのだと思う。そしてこれをこそ先ず捉えてゆかなければならない。そこでこの知的営為に関わる「価値志向」をウエーバーの「経済倫理」(Wirtschaftsethik)になぞらえて、「知のエートス」(Wissensethons)となづけておきたい。
このような前置きの後で、古代のギリシャ、インド、中国の普遍的な思想を次のように網羅し、さらに知のエートスを表で表している。
求められる対象 知的営為の目的 世界に対する態度 方法
ギリシャ イデア 観照的認識 世界直視 理論的
インド 涅槃 宗教的解脱 世界超脱 思弁的
中国 道 倫理的実践 世界適合 直感的
この様にやや大胆に整理した後に、「知のエートス」については、次の表に纏めている。
知のエートス 科学の担い手 科学の支持者
ギリシャ meta-physics 哲学者 市民
インド meta-religiosa バラモン バラモン層
中国 meta-ethica 士大夫 為政者
アラビア meta-magica ハーキム 王侯
2.ノベルト・エリアス「文明化の過程」法政大学出版局(1997) KMB079

・科学・技術上の進歩の経験のみでは、進歩の理想化、人間状況のいっそうの改善に対する革新の契機となりえないことは、20世紀において明確に証明されている。今世紀における科学・技術上の実際上の規模と速度は、過去の数世紀における進歩の規模や速度を遥かに凌駕している。20世紀の一般住民の生活水準も、最初の工業化の波を受けた国々では、過去の数世紀に比して高い。健康状態は改善され、寿命は伸びた。しかし、「時代の大合唱」の中では、進歩を価値のあるものとして肯定し、人間状況の改善に社会的理想の核心を認め、確信をもって人類のより良き未来を信じる人の声は、過去数世紀に比して、著しく弱まっている。他方、これらすべての発展の価値を疑い、人類のより良き未来、もしくは自国の未来に対してさえ特別な期待も抱かず、かれらの主要な社会的信念がもっぱら眼前のこと、自国の保全・現存社会体制・過去・伝統・因習的秩序を最高の価値として、それらに集中しているような人々の声が20世紀において高まり、漸次優位を占めつつある。
・「文明化」と「文化」という対立概念の発展の過程について
3.ベン・ダヴィッド(1971)の邦訳本「社会における科学者の役割」「科学の社会学」潮木守一、天野郁夫訳、至誠堂(1974)
・この書物は近時の科学社会学の主要な動向を代表する好著と言ってよいが、この中で著者は科学社会学の方法として、(a)科学と社会制度の関係を論ずる制度論的アプローチと、(b)科学者相互の社会的関係を問題とする関係論的アプローチを区別し、さらに他方において、(a’)その社会的条件の影響が、専ら科学者の行動や科学活動だけに及ぶと考えるか、それとも(b’)さらに科学者自身の中味にまで、つまりその基礎概念や科学理論の内容にまで影響を与えるとするかという二つの立場を区別する。
4.角田忠信「日本人の脳」大修館書店 (1978)

・日本では認識過程をロゴスとパトスに分けるという考え方は、西欧文化に接するまでは遂に生じなかったし、また現在に至っても哲学・論理学は日本人一般には定着していないように思う。日本人にみられる脳の受容機構の特質は、日本人及び日本文化にみられる自然性、情緒性、論理のあいまいさ、また人間関係においてしばし義理人情が論理に優先することなどの特徴と合致する。西欧人は日本人に較べて論理的であり、感性よりも論理を重んじる態度や自然と対決する姿勢は脳の需要機構のパターンによって説明できそうである。西欧語パターンでは感性を含めて自然全般を対象とした科学的態度が生まれようが、日本語パターンからは人間や自然を対象とした学問は育ち難く、ものを扱う科学としての物理学・工学により大きな関心が向けられる傾向が生じるのではないだろうか?明治以来の日本の急速な近代化や戦後の物理・工学における輝かしい貢献に比べて、人間を対象とした科学が育ちにくい背景にはこの様な日本人の精神構造が大きく影響しているように思える。 (P85)
・左脳ばかりを使って論理のみをいじくりまわしていると、どうしても模倣になってしまい勝ちで、やはり何か新しいものを生みだすのは右の脳も使ってやらないといけない。(中略)それには西洋音楽を聴くことですよ。邦楽では語りが中心だし、自然に密着していますから、やはり充分な効果はない。全く異質という意味で、西洋楽器の音はよい刺激になります。 (副題「右の脳を活用しよう」(P22)
・西洋文明の危機が叫ばれているが、それは西洋人の窓枠を通しては、新しい時代に即した想像が生まれ得ない苦悩の表明ではあるまいか。数ある文明国の中で、異質の、しかもまだ充分に創造性の発揮されていない文化の枠組みを持つのは、実は日本以外にはないのである。
しかし、このことを日本と西洋の優劣というような価値観に結び付けて必要以上に劣等感に悩まされたり、逆に自信を持ちすぎることもない。必要なのはこの違いを如何に活かすかということである。著者は日本人が、日本人の窓枠の異質性にめざめて、借りものでない自分の頭で考え抜くときにはじめて日本人の独創性が発揮され、その所産は世界の文化に貢献できる可能性のあることを信じたい。 (P378)
5.芳賀綏「日本人の表現心理」中公叢書 (1979)
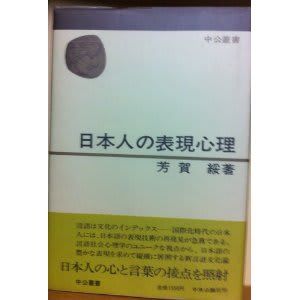
人文科学や社会科学を追求する上でも、「語らぬ」「わからせぬ」「いたわる」「ひかえる」「修める」「ささやかな」「流れる」「まかせる」というのが日本人のコミュニケーションの特徴であり、これに対する知見も持つことが大切であるなどと述べられている。
6.D.C.バーンランド「日本人の表現構造」サイマル出版会(1973)

人間の人格構造について、「未知なる自己」(U)、「私的自己」、「公的自己」という3重の同心円モデルを提唱し、それによって個人レベルの異文化コミュニケーションの摩擦のメカニズムを説明している。そして実験によって、日本人は比較的「私的自己」が厚く「公的自己」が薄く、逆にアメリカ人は比較的「私的自己」が薄く「公的自己」が厚い。そのためアメリカ人にとって快適な心的距離のコミュニケーションを行うと、日本人は自分の「公的自己」を突き破って「私的自己」の内までアメリカ人の自己が入ってくることになり、不愉快なコミュニケーションと感じるなどと説明されている。
次回の(その3)では、1980年代の8冊を紹介しようと思います。










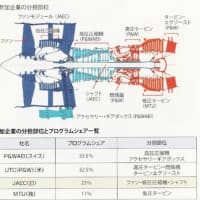
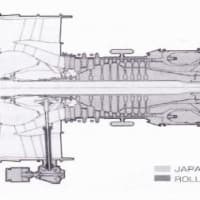



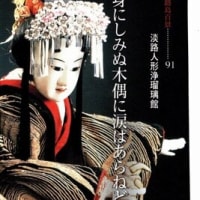
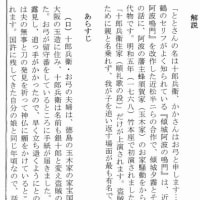


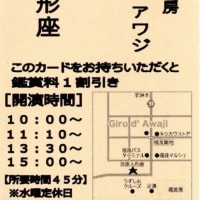
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます