その場考学とメタエンジニアリングの関係
ギリシャの哲学者アリストテレスは知識を3つに分類した。
① エピステーメー;科学知識
② テクネー;技術的知識
③ フロネーシス;良識、実践知、です。
西欧型科学技術文明の中で、科学的知識と技術的知識は大いに発展をして、現代社会を築きあげてきた。しかし、20世紀後半からその速度が加速されて、それによる弊害(負の価値)が目立つようになってしまった。このことは、社会への実践にあたって、①と②のスピードに③のフロネーシスが追いついていないことを示している。
つまり、実社会への適用にあたっての思慮の範囲が限定されてしまい、個別最適のままで世に現れて、全体最適が崩れてしまった、ということなのでしょう。
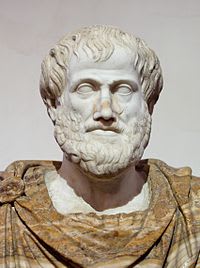
Ἀριστοτέλης、
前384年 - 前322年3月7日
(Wikipediaより)
実社会では、大なり小なりの問題が次々に現れます。情報過剰時代にあって、これらの問題解決の手段の決定を、すべての情報を集めて検討をしていたのでは、間合うはずがありません。そこで考えられたのが、「その場考学」です。一方で、「メタエンジニアリング」は、同様に実践に対して、広範囲な科学知識と技術知識の両方から必須事項のみを求めて、実践における全体最適を試みます。
つまり、この二つは、目的も方法も同じと言えるのです。
これからの諸検討では、この二つの言葉を頻繁に使いますが、同じ意味と考えていただければ幸いです。
「GEやRolls Royceとの長期共同開発の経験を通して得られた教訓 (その3)」
【Lesson3】製造技術だけなら勝つことができた(Howmet vs.小松製作所[1974])
1970年に通産省の大型プロジェクトとして始まったジェットエンジンFJR710の研究の当初から,私はシステム設計班長に加えて高圧タービン設計チームの班長も務めた。エンジンの性能達成のためには,タービン入り口温度を,従来の実績よりも100℃以上高めなければならない。
このことは英米でも同じで,米国内でも多くの大学でタービン翼の冷却法の基礎研究が行われ,交流も活発であった。年1回の学会の場に限らず,各大学主催のワークショップで研究者の最新情報が交換された。私は,ミネソタ大学とスタンフォード大学の常連となり,発表(1)を通じて多くの友人を得ることができた。
共通する最大の問題は,第1段タービン翼のリーディングエッジの冷却法で,インピンジメント冷却とフイルム冷却の併用が不可欠とされていた。
当時の技術では,双方の孔は表面からの放電加工で行われたが,それでは,インピンジメントの噴流力が,フイルム冷却孔に直接あたることになり,冷却効果は十分に発揮できない。そこで,インピンジメント冷却孔を鋳造で作ることが必要になる。
私は,この設計を大阪の小松製作所に持ち込んだ。彼らには,それまでにも何度も航空技術研究所(以後NAL)との共同で精密鋳造を依頼していた。彼らの判断は,「考えられるが実行は難しい。」であった。そこで,世界一の精密鋳造技術を持つ,米国のHowmet社にその設計図を持ちこみ議論を重ねることになった。彼らの回答は,「セラミックコアの製造は不可能で,鋳込み時にコアが折れてしまう。結論はImpossible」であった。
帰国した我々は,「世界一の会社ができないことにチャレンジしてみよう」であった。幸い,FJR710の予算には,その余力があった。最初の歩留まりは1%くらいであったが,それでもImpossibleではなかった。この冷却翼設計はFJR710/10と,それに続く/20の実機翼を用いた要素試験で続けられて,遂に鋳造品の歩留まりも実用レベルになり,FJR710/20の運転試験は目標値のタービン入り口温度を達成することに成功した。
産官学の協働が,米国の世界一の製造技術を追い越した瞬間であった。しかし,このような無謀とも思われるチャレンジ精神は,その後のプロジェクトでは次第に失われ,より堅実な方向に向かってしまったように感じられる。しかし,当時はこれだけでは終わらずに,次の特許論争にまで発展をした。
【この教訓の背景】
チャレンジをするということは、リスクをとるということとまったく同じ意味なのだが、そのことを認めないのが、日本的な考え方になってしまっている。私の経験では、「チャレンジをせよ!」という人に限って、「リスクは取りたくない」が本音のことが多い。
「チャレンジをせよ!」という人は、自分ではチャレンジをしない。その気ならば、「私がチャレンジする」というはずである。こんなことが明確になっていないのが、高度成長社会以後に実務に携わる人たちの中に多く見られる。リスクを採らずにチャレンジするという言葉は、欧米にはない。
「GEやRolls Royceとの長期共同開発の経験を通して得られた教訓 (その4)」
【Lesson4】特許論争でも勝つことができた(General Electricとの特許論争[1975])
FJR710/20が行われていた時代は,すでにBoeing747などのジャンボジェット機の最盛期で,オーバーホウルなどから,実機のタービン翼の冷却構造なども明らかになってきた。そのようなときに,事前に提出した前記の精密鋳造の冷却構造の特許が審査の時期を迎えた。
それ以前にも,いくつかの特許を提出していたが,特に問題はなかったが,これに関しては特許庁から「異議申し立てがありました。」との通知が来た。内容から異議の申し立てはGEからのものであることは明白だったが,私は,彼我の違いを説明する回答書を直ちに送った。しかし,再度の異議申し立て書が送られてきた。そのような往復が3回は繰り返されたと思う。そして,最終的には「冷却性能の飛躍的改善は伝熱工学的に明らかなので,その他の部分にGE社の特許と同じ構造が含まれていても,全体としては明らかに新発明である。」との意見が採用されたようであり,めでたく登録された。
この特許の冷却構造は,以降の多くのタービン翼応用されているだが,金銭的な収入には至らなかった。しかし,たとえGEが相手であろうとも,とことん議論を尽くすことは,この時の経験が以降の国際プロジェクトのV2500とGE90では大いに役立った。意見が対立するときには,先ずは反論をすること。それに対する反論にも,更に反論をすること。少なくとも3回はこれを繰り返さなければ,お互いの力を理解し合うことはできない。そして,国際共同開発プロジェクトにおいては,この「お互いの真の力を見極めること」が,真の協力体制を築くうえで最も重要なことの一つである。
ソクラテスが弟子のひとりとの会話の形で「正しいこと」を論じた内容がプラトン全集(3)に示されている。
ソクラテス「正しいことと不正なこととの場合はどうなんだろうね,いったい。答えてみたまえ。」
弟子「できません。」
ソクラテス「論ずることによってだ,といってくれたまえ。」
つまり,「正しいことは,知識の集積による議論により導き出されるもの」と明言している。この言葉は,「正しいこと」は普遍ではなく,時代とともに変わってゆくことも同時に示している。
【この教訓の背景】
ジェットエンジンの設計に関する特許は、ほかの製品とは大いに異なる。製造方法は別だが、設計は、まず要素試験が必要で、その確認に数年かかる。次に基本設計を行い、プロジェクトがスタートし、型式承認が取れて、機体に積み込まれ売り始めるには、5年はかかる。つまり、せっかく特許をとっても10年間は空回りで、製品の売上高には貢献しない。しかし、新発明の特許は、どんどん出した覚えがある。それは、防衛のための特許であった。つまり、一種の保険だった。
私の特許は高圧タービン翼の冷却法に関するもので、IHIが商品化するめどは、少なくとも、特許の有効期限内には全くないと確信をしていた。すでに40年前のことなのだが、唯一の製品化の可能性は、当時から独自の発電用GTの高温化の開発していた某社だった。ある時、ガスタービン学会で、後輩からこんな話があった。「あなたの特許を使わせてもらえませんか?」。
私は、その場で「特許についてとやかく言うことはないので、どうぞ好きなように利用していいよ」と、快諾した。未だ、大型プロジェクトが途中だったときだったと思う。
蛇足だが、私はメタエンジニアリングを考え始めてから俄かに、古代ギリシャと日本の縄文文化(正確には、土器文明)に興味を持つようになった。特に、プラトンからアリストテレスへの流れは、科学と技術と社会の関係について、現代文明が落ち込んだ様々な矛盾と解決困難な問題を解く鍵があるように感じている。
引用文献
(1)Katsumata,I, “Effect of Mach Number on Cooling Effectiveness of Film Cooled Turbine Blade”,The Film Cooling Work Shop, Univ. of Minnesota(1975)
(3)プラトン、プラトン全集 第10巻、(1975),pp. 269、角川書店
ギリシャの哲学者アリストテレスは知識を3つに分類した。
① エピステーメー;科学知識
② テクネー;技術的知識
③ フロネーシス;良識、実践知、です。
西欧型科学技術文明の中で、科学的知識と技術的知識は大いに発展をして、現代社会を築きあげてきた。しかし、20世紀後半からその速度が加速されて、それによる弊害(負の価値)が目立つようになってしまった。このことは、社会への実践にあたって、①と②のスピードに③のフロネーシスが追いついていないことを示している。
つまり、実社会への適用にあたっての思慮の範囲が限定されてしまい、個別最適のままで世に現れて、全体最適が崩れてしまった、ということなのでしょう。
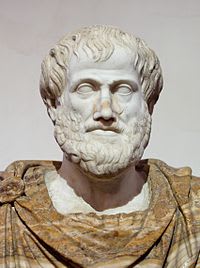
Ἀριστοτέλης、
前384年 - 前322年3月7日
(Wikipediaより)
実社会では、大なり小なりの問題が次々に現れます。情報過剰時代にあって、これらの問題解決の手段の決定を、すべての情報を集めて検討をしていたのでは、間合うはずがありません。そこで考えられたのが、「その場考学」です。一方で、「メタエンジニアリング」は、同様に実践に対して、広範囲な科学知識と技術知識の両方から必須事項のみを求めて、実践における全体最適を試みます。
つまり、この二つは、目的も方法も同じと言えるのです。
これからの諸検討では、この二つの言葉を頻繁に使いますが、同じ意味と考えていただければ幸いです。
「GEやRolls Royceとの長期共同開発の経験を通して得られた教訓 (その3)」
【Lesson3】製造技術だけなら勝つことができた(Howmet vs.小松製作所[1974])
1970年に通産省の大型プロジェクトとして始まったジェットエンジンFJR710の研究の当初から,私はシステム設計班長に加えて高圧タービン設計チームの班長も務めた。エンジンの性能達成のためには,タービン入り口温度を,従来の実績よりも100℃以上高めなければならない。
このことは英米でも同じで,米国内でも多くの大学でタービン翼の冷却法の基礎研究が行われ,交流も活発であった。年1回の学会の場に限らず,各大学主催のワークショップで研究者の最新情報が交換された。私は,ミネソタ大学とスタンフォード大学の常連となり,発表(1)を通じて多くの友人を得ることができた。
共通する最大の問題は,第1段タービン翼のリーディングエッジの冷却法で,インピンジメント冷却とフイルム冷却の併用が不可欠とされていた。
当時の技術では,双方の孔は表面からの放電加工で行われたが,それでは,インピンジメントの噴流力が,フイルム冷却孔に直接あたることになり,冷却効果は十分に発揮できない。そこで,インピンジメント冷却孔を鋳造で作ることが必要になる。
私は,この設計を大阪の小松製作所に持ち込んだ。彼らには,それまでにも何度も航空技術研究所(以後NAL)との共同で精密鋳造を依頼していた。彼らの判断は,「考えられるが実行は難しい。」であった。そこで,世界一の精密鋳造技術を持つ,米国のHowmet社にその設計図を持ちこみ議論を重ねることになった。彼らの回答は,「セラミックコアの製造は不可能で,鋳込み時にコアが折れてしまう。結論はImpossible」であった。
帰国した我々は,「世界一の会社ができないことにチャレンジしてみよう」であった。幸い,FJR710の予算には,その余力があった。最初の歩留まりは1%くらいであったが,それでもImpossibleではなかった。この冷却翼設計はFJR710/10と,それに続く/20の実機翼を用いた要素試験で続けられて,遂に鋳造品の歩留まりも実用レベルになり,FJR710/20の運転試験は目標値のタービン入り口温度を達成することに成功した。
産官学の協働が,米国の世界一の製造技術を追い越した瞬間であった。しかし,このような無謀とも思われるチャレンジ精神は,その後のプロジェクトでは次第に失われ,より堅実な方向に向かってしまったように感じられる。しかし,当時はこれだけでは終わらずに,次の特許論争にまで発展をした。
【この教訓の背景】
チャレンジをするということは、リスクをとるということとまったく同じ意味なのだが、そのことを認めないのが、日本的な考え方になってしまっている。私の経験では、「チャレンジをせよ!」という人に限って、「リスクは取りたくない」が本音のことが多い。
「チャレンジをせよ!」という人は、自分ではチャレンジをしない。その気ならば、「私がチャレンジする」というはずである。こんなことが明確になっていないのが、高度成長社会以後に実務に携わる人たちの中に多く見られる。リスクを採らずにチャレンジするという言葉は、欧米にはない。
「GEやRolls Royceとの長期共同開発の経験を通して得られた教訓 (その4)」
【Lesson4】特許論争でも勝つことができた(General Electricとの特許論争[1975])
FJR710/20が行われていた時代は,すでにBoeing747などのジャンボジェット機の最盛期で,オーバーホウルなどから,実機のタービン翼の冷却構造なども明らかになってきた。そのようなときに,事前に提出した前記の精密鋳造の冷却構造の特許が審査の時期を迎えた。
それ以前にも,いくつかの特許を提出していたが,特に問題はなかったが,これに関しては特許庁から「異議申し立てがありました。」との通知が来た。内容から異議の申し立てはGEからのものであることは明白だったが,私は,彼我の違いを説明する回答書を直ちに送った。しかし,再度の異議申し立て書が送られてきた。そのような往復が3回は繰り返されたと思う。そして,最終的には「冷却性能の飛躍的改善は伝熱工学的に明らかなので,その他の部分にGE社の特許と同じ構造が含まれていても,全体としては明らかに新発明である。」との意見が採用されたようであり,めでたく登録された。
この特許の冷却構造は,以降の多くのタービン翼応用されているだが,金銭的な収入には至らなかった。しかし,たとえGEが相手であろうとも,とことん議論を尽くすことは,この時の経験が以降の国際プロジェクトのV2500とGE90では大いに役立った。意見が対立するときには,先ずは反論をすること。それに対する反論にも,更に反論をすること。少なくとも3回はこれを繰り返さなければ,お互いの力を理解し合うことはできない。そして,国際共同開発プロジェクトにおいては,この「お互いの真の力を見極めること」が,真の協力体制を築くうえで最も重要なことの一つである。
ソクラテスが弟子のひとりとの会話の形で「正しいこと」を論じた内容がプラトン全集(3)に示されている。
ソクラテス「正しいことと不正なこととの場合はどうなんだろうね,いったい。答えてみたまえ。」
弟子「できません。」
ソクラテス「論ずることによってだ,といってくれたまえ。」
つまり,「正しいことは,知識の集積による議論により導き出されるもの」と明言している。この言葉は,「正しいこと」は普遍ではなく,時代とともに変わってゆくことも同時に示している。
【この教訓の背景】
ジェットエンジンの設計に関する特許は、ほかの製品とは大いに異なる。製造方法は別だが、設計は、まず要素試験が必要で、その確認に数年かかる。次に基本設計を行い、プロジェクトがスタートし、型式承認が取れて、機体に積み込まれ売り始めるには、5年はかかる。つまり、せっかく特許をとっても10年間は空回りで、製品の売上高には貢献しない。しかし、新発明の特許は、どんどん出した覚えがある。それは、防衛のための特許であった。つまり、一種の保険だった。
私の特許は高圧タービン翼の冷却法に関するもので、IHIが商品化するめどは、少なくとも、特許の有効期限内には全くないと確信をしていた。すでに40年前のことなのだが、唯一の製品化の可能性は、当時から独自の発電用GTの高温化の開発していた某社だった。ある時、ガスタービン学会で、後輩からこんな話があった。「あなたの特許を使わせてもらえませんか?」。
私は、その場で「特許についてとやかく言うことはないので、どうぞ好きなように利用していいよ」と、快諾した。未だ、大型プロジェクトが途中だったときだったと思う。
蛇足だが、私はメタエンジニアリングを考え始めてから俄かに、古代ギリシャと日本の縄文文化(正確には、土器文明)に興味を持つようになった。特に、プラトンからアリストテレスへの流れは、科学と技術と社会の関係について、現代文明が落ち込んだ様々な矛盾と解決困難な問題を解く鍵があるように感じている。
引用文献
(1)Katsumata,I, “Effect of Mach Number on Cooling Effectiveness of Film Cooled Turbine Blade”,The Film Cooling Work Shop, Univ. of Minnesota(1975)
(3)プラトン、プラトン全集 第10巻、(1975),pp. 269、角川書店









