
ジュウニヒトエ(十二単)
まだ一輪しか開いていなかったのは残念でしかが、
淡い紫色のは初めて♪ラッキーでした♪♪

キジムシロ(雉筵)
いつもミツバツチグリとの見分けで悩むのですが、
地面に葉を放射線状に広げるのがキジムシロで
ミツバツチグリは創出枝を出しません
でも、撮っているときは混同してしまいます(^^;
エイザンスミレ(叡山菫)
一株だけしか見つけられませんでしたが、濃い目のピンク色の花弁がで可愛いくて美しい

ノウルシ(野漆)
ちょっと見にはトウダイグサに似ています
葉は互生し先が尖った長楕円形です
茎から出る乳液を触るとかぶれるので、触るときは要注意です


ミツガシワ(三槲)
多年生の水草で、肥厚した地下茎を横に伸ばし増やしていきます
ジュウモンジソウ(十文字草)
散策路から離れた所にあったので、これ以上は大きく撮れませんでした


エゾエンゴサク(蝦夷延胡索)
裏高尾で見るヤマエンゴサクに比べ、逞しく、花色も鮮やか…
どちらかというと楚々としたヤマエンゴサクの方が好きですが、
北の大地に群生した風景は見てみたいとちょっと憧れます
ミヤマカタバミ(深山片喰)?
サクラソウの仲間だとは思うのですが、名札が無かったので…



シラネアオイ(白根葵)
花がアオイの花に似ていて、日光白根山で見つかったのでこの名がついたそうです
ヒラヒラのドレスに見えるのは花びらではなく、ガク片です
エゾノハナシノブ(蝦夷の花忍)
表現できない色合い…近い色は藍でしょうか
レブンキンバイソウ(礼文金梅草)
礼文島の固有種
ミチノクコザクラ(陸奥小桜)
青森県岩木山に特産する小型の多年草で、高山の湿った草原に生えるそうです
ユキワリコザクラ(雪割小桜)
北海道、本州北部の山地の岩場に生えるそうです
( 撮影日:2023年4月9・10日 )
先週の日・月(4/9,10)で箱根に行ってきました。
昨年11月の宿泊予約を私の急な入院手術で直前キャンセルをしたにも拘らず、
快く応じてくださった宿へのお礼と春の湿生花園での花撮影が目的♪♪
花撮影にはちょっと辛い強い日差しでしたが、
2日間湿生花園の花を楽しむことができました。
今日から数回に分けてご紹介したいと思いますので、
お付き合いいただければうれしいです(*^^*)
************
入口手前の駐車場から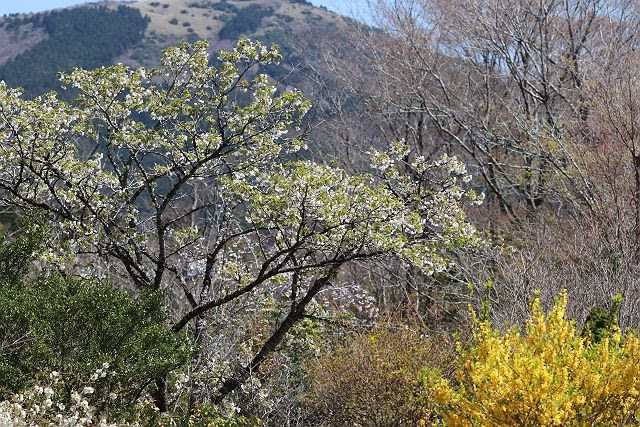
終盤でしたが、まだ桜が残っていました




ハルトラノオ(春虎の尾) タデ科
別名:イロハソウ
名の由来は、春早くトラの尾のような花穂を立てることからだそうです
花穂は長さ1.5~3.5cm、花は2~3㎜で白色で花弁に見えるのはガク片です
雌しべの根元と雄しべの葯が淡いピンクでとても可愛いです
以前、栃木県のイワウチワの群生を見に行った際に初めて見て以来、
もう一度見たいと思っていた花です


オオバナノエンレイソウ(大花の延齢草) シュロソウ科
ネットで検索をしてみると、
森の中で大きな白い花をつける、北海道の春を代表する花の一つで、
大きな花がドレスのようで気品が感じられる花であることから「森の貴婦人」といわれているそうです




シュジョウバカマ(猩々袴)
花色が淡紅色から濃紅色まで変化があり、白色のものもあるそうです
離れた所から見ると地味ですが、近くで見ると可愛くて美しいです
シダレザクラも少しだけ残っていました
シダの赤ちゃん?


イカリソウの仲間

ミズバショウ(水芭蕉)は茎や葉が伸びてしまっていて残念でした
ニリンソウ(二輪草)はここでも群生をしていました
イチリンソウ(一輪草)はこれからが見頃
仙石原湿原復元実験区
やっと冬眠から覚め、花はまだキジムシロくらいだったような…
マメザクラも終盤でしたが、離れて見るとピンクできれいでした
近くで見ると花色は白なんですけどねー

エンコウソウ(猿猴草) キンポウゲ科
茎が直立せず横に伸ばし増えていきます
長く伸びた花茎をテナガザルの手に見立てた名前だそうです
右奥はススキで知られている台ケ原です
( 撮影日:2023年4月9・10日 )
スミレの観察会があれば参加し、
様々なスミレを見て撮って、知りたいと思う今日この頃…
わからなければ「スミレ」で良いのかなぁと思いながらも、
やはり知りたい!!
ということで、今回わからなかった4つのスミレをアップ(^^;
露出や撮り方で分かりにくいとおもいますが、
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
**********
不明1


花色が白っぽいタチツボスミレでしょうか?
**********
不明2
バスの時間が迫っていて1枚しか撮れませんでした
**********
不明3

タチツボスミレにしては花の開き方が違うような気がして
******
不明4
何度も見ているうちにタチツボスミレじゃないかという気がしてます(*_*;
( 撮影日:2023年4月3日 )
今日も私でも同定ができた(たぶん(^^;)スミレをご紹介します。


マルバスミレ(丸葉菫)
別名:ケマルバスミレ
丸みのある葉とふっくらとした白い花ですぐに判別ができる可愛いスミレです
青森県から屋久島まで広く分布するそうで、
自宅からバスで行ける横浜市の舞岡公園でも見ることができます
日の当たる場所から半日陰の土手や落葉樹林下に生育し、
やわらかくて崩れやすい斜面に多いとのこと…
確かに日影沢沿いではそんな場所に生えていました
花が淡紅紫色のを以前見たことがあるのですが、今回は出会えませんでした
ヒナスミレ(雛菫)…だと思うのですが
図鑑によるとかなりの早咲きのため、
他のスミレと一緒に見ようとすると咲き終わりの状態でしか見つからないとあります
確かに花弁の先が少し傷んでいますが、
スミレのプリンセスと言われる魅力はまだまだ残っていました


ナガバノスミレサイシン(長葉の菫細辛)
花期は過ぎていたようで、この2株しか見つけることができませんでした
でも、残っていてくれてありがとうーです



タチツボスミレ(立坪菫)
いたるところで薄紫色の絨毯を作っていました
でも、岩や倒木の間から1株だけ咲いている姿は楚々として可愛い!!




エイザンスミレ(叡山菫)
別名:エゾスミレ


アカフタチツボスミレ(赤斑立坪菫)
初めて知ったスミレです
花はタチツボスミレなのに、
葉の基部から葉脈に添って紅紫色の斑が入っていて…
日焼けをしたのかと撮っているときは思っていました
きっと今までも見ていてもスルーをしていたのかもしれません
( 撮影日:2023年4月3日 )
裏高尾での楽しみはスミレに出会えることですが、
いつも同定に四苦八苦(^^;
山渓ハンディ図鑑『日本のスミレ』の中から、
撮ったスミレの名を探し出すのは私にとっては至難の業です。
今日は私でも同定ができるヒカゲスミレとタカオスミレをアップ♪
もし違っているのがあれば教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
**********







ヒカゲスミレ(日陰菫)
葉の色が緑からわずかにこげ茶色を帯びているもの、
また、花弁が細いものなど様々…
ヒカゲスミレと思ってセレクトしているときでも
本当に良いのかと迷ってしまいます




タカオスミレ(高尾菫)
高尾で発見命名されたスミレで、
葉の表面がこげ茶色から黒紫色になるものをタカオスミレとしているようです
基本種はヒカゲスミレ、
もしかすると3枚目はヒカゲスミレに分類をした方が良いのかもしれません
( 撮影日:2023年4月3日 )



フデリンドウ(筆竜胆)
去年見た場所ではまばらにしか出ておらず、
遊歩道からもう少し外側で咲けば踏まれずに済むのに…
蕾の状態でいくつかが踏まれていました


ミヤマカタバミ(深山片喰)
花弁の中にもうひとつ花弁があるかのような模様、
虫に受粉を助けてもらうための知恵でしょうか


ミヤマハコベ(深山繁縷)
花径が1~1.5センチほどある大きさなので、
私でも絶対間違えようがない花のひとつです



マルバコンロンソウ(広葉崑崙草)
ユリワサビと間違えてしまいそうな花ですが、
花期はユリワサビより少し遅れて咲くようです
( 撮影日:2023年4月3日 )
今日はキンポウゲ科の花を…







レンプクソウの次に見たかった花、トウゴクサバノオ(東国鯖の尾)です
ちょうど咲き始めたところのようで、
名前の由来の鯖の尾に似た果実はまだでした
でも、花径1センチに満たない小さな花の繊細な作りにまた感動でした





イチリンソウ(一輪草)
茎葉の間から1本の長い柄を出し、
先端に花径4センチほどの白い花をつけます
花弁は無く、白い花弁に見えるのはガク片で、薄紫を帯びることもあるそうです










ニリンソウ(二輪草)
茎葉の間から通常は2本の柄を出し(時には3本のこともありますが)、
先端に1.5~2.5cmの白い花をつけます
一輪草と同じく、白色の花弁に見えるのはガク片で普通5個ありますが、
今回撮影をした中には8個や9個のものがありました
( 撮影日:2023年4月3日 )
多摩森林科学園に行った翌日、咲いているのではないかと気になる花を撮りに
小仏川沿いから日影沢沿いに行ってきました。
もう一度見たい撮りたいと思っていたレンプクソウ、
2017年4月16日に初めて見たときは、花の様子をきちんと撮ることができませんでした。
今回ちょうど見頃で花もたくさん付いていました。
ただ、とにかく小さな花の集まり…
50枚以上撮ってもなかなか手ごわくまた宿題が残ったような気分です。
**********







先端は4花弁です

周りの4個は5花弁です


レンプクソウ(連福草)
別名:ゴリンバナ(五輪花)
図鑑によると北半球北部に分布する多年草で、
川沿いの竹やぶなどに群生するとのこと
茎の先に5個の花がかたまってつき、
先端の1個は4花弁、まわりの4個が5花弁という不思議な花です。
花径は5㎜あるかないかの小さな花です
( 撮影日:2023年4月3日 )
多摩森林科学園の桜や花のアップは今日で最後になります。
1日いても撮りきれないと思うほどの花に出会うことができ、
閉園時間を知らせる放送に急ぎ足になりながらも、傍らに咲いている花に気を取られ…
春に訪れたい場所がまた1か所増えてしまいました(^-^)
**********





ヤマルリソウ



ヤマブキ(山吹)

ヤブレガサ(破れ傘)

ムラサキケマン(紫華鬘)
ミヤマウグイスカグラ(深山鶯神楽)


ミミガタテンナンショウ
株が小さいと雄、大きくなると雌になるが、
果実が実った翌年は雄に戻ることが多い。
地下の鱗茎に蓄えた栄養の量で雌雄が決まることがわかっている
(説明板に書かれている中から、一部抜粋しました)
小さいのと大きいのがあるのは個体差なのかなぁと思いながら撮っていましたが、
説明板を読んでなるほど…と納得(^^;
植物の不思議をまたひとつ知ることができました

ミツバツチグリ(三葉土栗)


ヒメハギ(姫萩)
初めて見ることができた花、
想像していたよりも小さな花でした
桜の花に気を取られていたこともあり、とりあえず撮りました…状態。。
見たかった花だったのに、もっとしっかり撮ればよかったと反省と後悔

バイモ(貝母)


ネコノメソウ(猫の目草)
見慣れていたはずのネコノメソウですが、
このようなのは初めて!
ネコノメソウの仲間の別の種類かと調べてもイマイチ分からず、
いつもお世話になる花調べのサイトにSOS
雄しべが4個ということで「ネコノメソウ」だと教えていただきました
ニリンソウ(二輪草)


ジロボウエンゴサク(次郎坊延胡索)

クサイチゴ(草苺)
カキドオシ(垣通し)
木の土留めの隙間から生えていて、正に垣通し…です
( 撮影日:2023年4月2日 )

最後にもう一度『はるか』を・・・(*^^*)
多摩森林科学園はサクラ保存林のほかに第1~3樹木園が公開されています。
入園してからサクラ保存林に行く連絡経路になっている第2樹木林には様々な野草が咲いていました♪
もちろんサクラ保存林の散策路脇にも思いがけない花が咲いていました♪♪
その中から今日はスミレを…
エイザンスミレ(叡山菫)

タカオスミレ(高尾菫)
他のスミレとは葉がこげ茶色であることから区別は容易です
高尾で発見命名されたスミレということでも、良く知られています
翌日行った日影でも、数株見つけることができましたが、
小仏川沿いでは全く見つけることができませんでした

タチツボスミレ(立坪菫)
タチツボスミレ?

ナガバノスミレサイシン(長葉の菫細辛)

マルバスミレ(丸葉菫)
これは私でも容易に見分けることができる数少ないスミレです
丸みのある葉と純白の花、私の印象では花弁がほんの少し厚みがあるような…
裏高尾・日影では淡紅紫色を帯びた花を以前見たことがあります
初めて見るスミレだぁと大喜びしたのですが…
よくよく画像を見ると
斑入り葉のスミレの根元から他の品種のスミレが咲いているような(^^;
スミレは同定が本当に難しくて、
撮りたいけれど撮った後の作業がとっても悩ましいのです
スミレにお詳しいはなねこさんから
奥はタチツボスミレの花で、手前の斑入り葉はヒナスミレと教えていただきました(^-^)
( 撮影日:2023年4月2日 )















