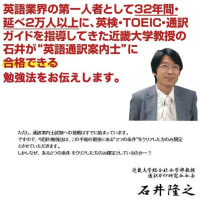2022年度<合格体験記>(13) 【16:30~17:30】(新型コロナウイルス)(英語)
●植山先生
お世話になっております。このたび通訳案内士試験(英語)に合格することができたことをご報告させていただきます。無料教材から<模擬面接特訓>まで何から何までサポートしていただき、とても感謝してます。以下は合格体験記になりますので、今後の学習者に何か参考になることがあれば幸いです。
●英語(メルマガ読者、無料動画利用者、無料教材利用者、<模擬面接特訓>受講者)
①受験の動機
もともと英語をライフワークのように考えて勉強を継続しており、TOEICを受験したり、実用英検1級、工業英検1級を取得していたのですが、コロナ禍で外出も自由にできないことが続いていたことから、この時期に英語力を集中的に高めたいと考え、資格受験を検討しました。まず国連英検特A級を取得し、次に最後の英語難関試験として昔から挑戦したいと考えていた通訳案内士の受験をすることとしました。旅行という分野も、英語の表現や趣味の幅を広げられる分野として最適だと思いました。
②第1次試験対策
<英語>(英検1級により免除)
<日本地理>(前年合格のため免除)
前年の結果(自己採点:84点)
地理は少し苦手意識があったため、マラソンセミナーの動画を受講し、テキストを繰り返し読み暗記しました。文字情報だけではイメージが湧きにくい部分もあるので、毎週図書館で各地域の「るるぶ」を借り、観光地などの情報をカラー写真でも確認しながら覚えていきました。また国立公園、重伝建などの最新の情報をアップデートするため、ネットで情報を補足しました。ですが、基本的にはマラソンセミナーの内容だけで十分だと思います。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
<日本地理>の傾向と対策<決定版資料>
<日本地理>の傾向と対策<音声ファイル>
<項目別地図帳>
<都道府県別地図帳>
<日本歴史>(前年合格のため免除)
前年の結果(自己採点:85点)
日本史はもともと好きですが、最近は難化しており、勉強量も多いため最も心配な科目でした。勉強方法は地理と同じく、マラソンセミナーの動画を受講し、テキストを繰り返し読み、「るるぶ」で寺院などの観光地の写真も確認しながら覚えていきました。また子供の学習用に買った日本史学習用まんがも繰り返し読みました。試験直前の対策としては植山先生の傾向と対策の資料を使用し、世界遺産の最新情報をアップデータしたり、出題頻度の多い項目で知識が足りない項目を確認していきました。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
<日本歴史>の傾向と対策<決定版資料>
<日本歴史>の傾向と対策<音声ファイル>
<マラソンセミナー>(日本歴史)(12講義24時間)
<一般常識>(前年合格のため免除)
前年の結果(自己採点:34点)
一般常識は過去問を見てもどのような対策をすべきか迷いました。
まずマラソンセミナーでは伝統文化のところだけはしっかりと受講しました。
政治・経済や時事問題は、普段新聞を読む程度で特に対策はしませんでしたが、個人的な予想として「SDGs」と「鬼滅の刃」は出そうな気がしたので対策をしました。あとは、しんどかったですが観光白書2年分を何回か読みました。統計もコロナ禍で連続性がなくなりましたが、一応は数字を覚えて臨みました。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
<一般常識>の傾向と対策<決定版資料>
<一般常識>の傾向と対策<音声ファイル>
<マラソンセミナー>(一般常識)(12講義24時間)
<令和3年版「観光白書」(完全版)>
<令和2年版「観光白書」(完全版)>
<通訳案内の実務>(前年合格のため免除)
前年の結果(自己採点:37点)
過去問は数年分しかなかったですが同じ傾向であったため、問題をそのまま暗記していきました。それ以外はハロー注解付き<観光庁研修テキスト>を読み込んで臨みました。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
<通訳案内の実務>の傾向と対策<決定版資料>
<通訳案内の実務>の傾向と対策<音声ファイル>
<観光庁研修テキスト>
③第2次試験対策
今年は全科目が免除になることから、早くから英語表現のインプットを重点的に行いました。
使用した教材は、ハローの「300選」<鉄板厳選128題>、「日本の観光名所300選」(植田一三)、図書館で借りた「中学英語で日本の〇〇が紹介できる」シリーズです。
前の2つの教材は完全に暗唱するのは無理でしたが、できるだけエッセンスは覚えて説明できるように心掛けました。最後の図書館の教材は日本の文化、伝統などについて理解を深めることができ、プレゼンで使えそうなネタで前の2つの教材にないような説明があった場合には、コピーして該当部に線を引き何回も読んで説明できるようにしていきました。実際に面接では、香川でなぜ良いうどんが作られるのかについてこの本の説明を使用しました。
面接の2か月前くらいから2次セミナーの過去問集を活用して実際の面接を意識した実践的な練習をしました。プレゼンは1つのテーマで3つの話題を考えそれぞれ30秒くらい話す練習をしました。
通訳問題は、過去問集に記載してある文章を読み上げソフトに貼り付けて、メモ取りと通訳の練習を繰り返しました。
シチュエーション問題は、主に2次セミナーの解説を理解して、自分で言えるように練習を繰り返しました。
試験の1か月前には、植山先生に<模擬面接特訓>をしていただきました。
実際に対人での面接を初めてしていただいて良い実践練習になっただけでなく、よく知らないようなことは話さないこと、大きな声で話すこと、笑顔で話すことなどのフィードバックをいただき、自分を客観的に見直して残り1か月で対策に努めることができました。
実際の本番の試験では、プレゼンテーマは「うどん」を選択し、通訳とシチュエーション問題は新型コロナウイルスに関する内容でした。沈黙することはなく話し続けることができましたが、内容が薄っぺらかったように感じ、ホスピタリティも見せることができなかった反省もあります。
しかし発表直前では、なんとなく合格しているかなという楽観的な気分になっていました。実際に官報で自分の番号と名前を見たときには安心し、ようやく肩の荷が下りた気がしました。
(下記を利用しました)
2次試験問題(2013年度~2022年度)
2次試験対策<特訓セミナー>
「日本的事象英文説明300選」<鉄板厳選128題>
2次試験対策<出題予想問題>(厳選125題)
④ハローのメルマガ、動画、教材、セミナーなどで役に立ったこと
一次試験の地理、歴史はハローのマラソンセミナーだけでほぼ十分ですし、
過去問をまとめられていたのも非常に助かりました。過去問がなければ2次試験の<外国語訳問題>を集中的に練習できていなかったかもしれません。また2次セミナーでプレゼンのテーマがトピック別に分けられていたので、連想ゲームで話題を作る練習に役立ちました。
⑤ハローに対するご意見、ご感想、ご希望
資格試験の勉強や趣味で何かを始める時は、達人の方や一般の経験者の意見を最初に読み込み、しっかりと計画を立ててから始めることが多いので、ハローのホームページ(公式ブログ)はその全てが盛り込まれており効率的に学習することができました。直前には<模擬面接特訓>までしていただき、とても感謝しています。
⑥今後の抱負
今回、通訳案内士試験の勉強に真剣に取り組み合格したことで、仕事の可能性を広げられただけでなく、日本文化の良さについて理解を深めることができたことで、今後の人生において趣味の幅も広げられて楽しく過ごせそうな気がします。実際には現在は副業はできないのですぐに仕事を始めるための行動は起こさないのですが、定年後は何か観光や旅行に関わる仕事をしてみたいという思いが強くなりましたので、今回の合格を活かしてさらに英語力向上や他の資格取得などにより、能力を磨いていきたいと思います。
⑦我、かく戦えり!
⑧<模擬面接特訓>の感想
本日は<模擬面接特訓>をしていただき有難うございました。これまではずっと一人で練習してきましたが、初めて対人で面接をしたということもありとても緊張しました。
プレゼンテーションでは、テーマとは直接関係のないことを時間を埋めるために話したことについてご指摘がありました。全てのテーマで更に詳しい説明をしたり体験談を交えるのは難しいですが、ある程度共通で使えるようなエピソードなどの準備が必要であると認識しました。
自分が確信を持っていることを話すようにとのご助言もいただきました。質問に対し、自分が知らないことを想像していい加減な内容で話してしまったこともあり、話せば話すほど危険だということを再認識させられました。
また基本的なことですが、大きな声で話すことと笑顔で話すことができていなかったので、緊張状態の中でもできるように意識的に練習を重ねて本番に臨みたいと思います。残りの約35日は通訳ガイドになったつもりで過ごし、本番で自然に態度に現れるようにしたいです。
反省ばかりの内容ですが、試験本番を前に失敗したことを前向きにとらえて最後の最後まで努力を続けて臨みたいと思います。このような機会をいただいたことを本当に感謝しています。(2022年度英語合格者)
・<模擬面接特訓>英語復習用資料
・<模擬面接特訓>英語復習用資料
以上