昨日取り上げたニューヨークの写真出版社Apertureだ
けど、サイトをみていると、Paris Photo と共同で写真
集へのアワードを2011年に創設しているのね。
Paris Photoと組むところが、ポイントかもしれない。
どちらが声がけしたのか。Apertureのパートナー企業
としてParis Photoとエルメスが名を連ねているけど。
「The 2013 Paris Photo-Aperture Foundation PhotoBook
Awards」と長い名前で、年間最優秀賞と新人賞の2
部門からなる。
☆
年間最優秀の写真集に選ばれたのが ブラジル人の
Rosângela Rennó さんが自費出版でだしはった
A01 [COD.19.1.1.43] ― A27 [S | COD.23]

どんな写真集かのさわりがvimeoに動画がある。ブラ
ジル語の説明などを自動翻訳してみると、リオ·デ·ジャ
ネイロ市にドキュメントアーカイブがあって、1903年
から1950年の間、公式カメラマン とその子供たちが
撮影した写真が盗難にあったらしい。
それをRosângela Rennó さんが何割か再構築していった、
写真集らしい。いつか出版されないかな。自費出版に賞を
あげるとは、渋い。例えていえば、芥川賞は自費出版の小
説にはいかないやろう。
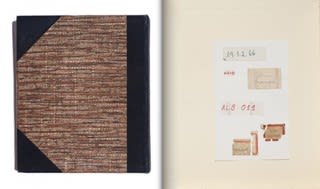
この賞のベスト10にノミネートされたうち2つの写真集が
日本人でAKAAKA舎のものだった。インパクト強烈な2冊;
・志賀理江子「螺旋海岸 album」
・大橋仁「そこにすわろうとおもう」
世界でも評価されてるんやなぁ。

新人賞の方は、自費出版が目白押し。大賞をとったのは、
ÓSCAR MONZÓNさんの『KARMA』。マドリードで、4
年間にわたり、車と人の関係を追ったもの。95ユーロで、
世界配送無料。
けど、サイトをみていると、Paris Photo と共同で写真
集へのアワードを2011年に創設しているのね。
Paris Photoと組むところが、ポイントかもしれない。
どちらが声がけしたのか。Apertureのパートナー企業
としてParis Photoとエルメスが名を連ねているけど。
「The 2013 Paris Photo-Aperture Foundation PhotoBook
Awards」と長い名前で、年間最優秀賞と新人賞の2
部門からなる。
☆
年間最優秀の写真集に選ばれたのが ブラジル人の
Rosângela Rennó さんが自費出版でだしはった
A01 [COD.19.1.1.43] ― A27 [S | COD.23]

どんな写真集かのさわりがvimeoに動画がある。ブラ
ジル語の説明などを自動翻訳してみると、リオ·デ·ジャ
ネイロ市にドキュメントアーカイブがあって、1903年
から1950年の間、公式カメラマン とその子供たちが
撮影した写真が盗難にあったらしい。
それをRosângela Rennó さんが何割か再構築していった、
写真集らしい。いつか出版されないかな。自費出版に賞を
あげるとは、渋い。例えていえば、芥川賞は自費出版の小
説にはいかないやろう。
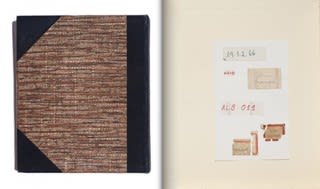
この賞のベスト10にノミネートされたうち2つの写真集が
日本人でAKAAKA舎のものだった。インパクト強烈な2冊;
・志賀理江子「螺旋海岸 album」
・大橋仁「そこにすわろうとおもう」
世界でも評価されてるんやなぁ。

新人賞の方は、自費出版が目白押し。大賞をとったのは、
ÓSCAR MONZÓNさんの『KARMA』。マドリードで、4
年間にわたり、車と人の関係を追ったもの。95ユーロで、
世界配送無料。









































