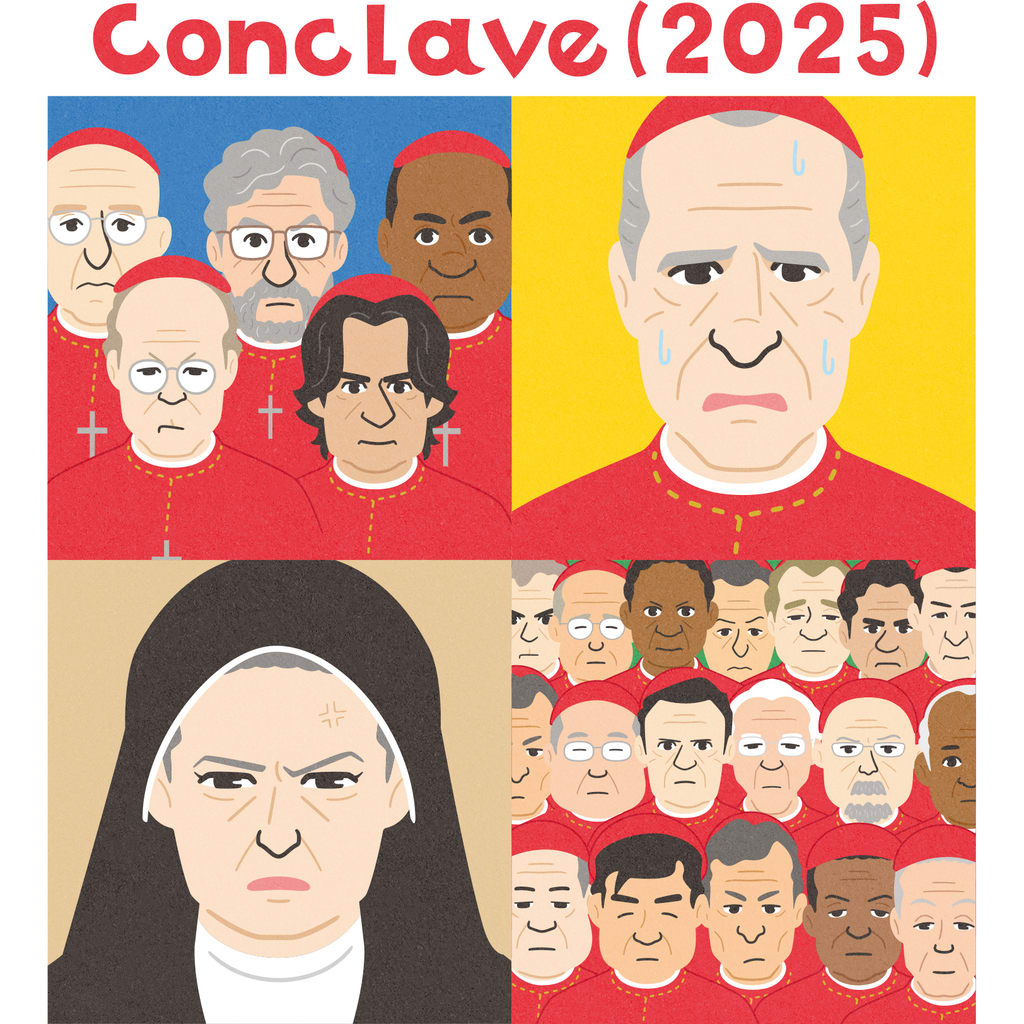質屋 The Pawnbroker (1964)
製作国:アメリカ
上映時間:116分
監督 シドニー・ルメット
脚本 デヴィッド・フリードキン
出演者 ロッド・スタイガー ジェラルディン・フィッツジェラルド
目次
- 残念ながら〝今〟の映画
- 3つの初めて
- 原作小説『質屋』
- ●ホロコーストを生存者の視点から描いたアメリカ合衆国で完全に制作された最初の作品
- ●ヘイズコード下で初めてヌードシーンが承認されたアメリカ映画
- ●ゲイのキャラクターが登場した初めてのアメリカ映画(演じたのはブロック・ピーターズ)
- 金しか信用できない難しい主人公像
- ラストネタバレ含むメモは以下に!
残念ながら〝今〟の映画
数十何前にあったこんな酷い虐殺(ジェノサイド)があったんだねえ二度としてはいけないねえではなく、今まさに人間がやってしまっていて止めることもできてない虐殺のトラウマを描いた映画。
虐殺はホロコースト以降も世界では起こってしまったけど、
まさに今!全世界がライブで見知っている虐殺が現在も続いている。
この映画は過去の映画ではなく、今の映画だし、
そのトラウマを抱えた人の苦悩を描いている点では〝未来〟の映画とも言える。
この主人公ソルのような人がたくさん生まれてしまっている。
この映画がまた作られてしまうし、ちゃんと作られなきゃいけない。歴史から消してはいけない。
3つの初めて
●ホロコーストを生存者の視点から描いたアメリカ合衆国で完全に制作された最初の作品
●ゲイのキャラクターが登場した初めてのアメリカ映画(演じたのはブロック・ピーターズ)
●ヘイズコード下で初めてヌードシーンが承認されたアメリカ映画
とのこと。
原作小説『質屋』
『質屋』(1961年)は、ユダヤ系アメリカ人の作家エドワード・ルイス・ウォラントが36歳の時に書いた同名小説。動脈瘤のため翌年死亡。
1960年の『人間の季節』は全米ユダヤ人図書賞を受賞している。
***
●ホロコーストを生存者の視点から描いたアメリカ合衆国で完全に制作された最初の作品
フランスのドキュメンタリー映画『夜と霧』(1956)などはあったが、ホロコーストのサバイバーでアメリカに移住したユダヤ人が当時を回顧するアメリカ映画は初とのこと。
この映画の冒頭では、
親戚が「ヨーロッパ旅行に行きましょうよ!」と誘うが
主人公のソルはヨーロッパに足を踏み入れることさえできない程のトラウマを抱えていることがわかる。
ホロコーストの情景はフラッシュバック形式で描かれている。
ソルの営む質屋に指輪を預けにきた女性の手の仕草を見て、絶滅収容所の前でユダヤ人たちが両手を頭の上に上げさせられて、ナチスの兵士たちに指輪が奪われるシーンがフラッシュバックする。
このようにフラッシュバックを重ねることで、セリフではなく主人公ソルにどんな過去があったのかがわかってくる。
***
●ヘイズコード下で初めてヌードシーンが承認されたアメリカ映画
ヘイズ・コード(アメリカ合衆国の映画界で導入されていた自主規制条項)が敷かれていた1930年から1968年までの期間で、
初めてヌードシーンが承認された映画。
ヘイズコードが敷かれる前はバンバンヌードシーンはあったんだけど、保守派の動きによってヘイズコードが敷かれ〝自主規制〟が行われた。
そもそも、2020年のドキュメンタリー映画『ヌードの映画史~黎明期から現代へ~』を見て、
この映画(『質屋』)に出てくるヌードシーン(黒人女優の胸)が性的搾取ではなく明らかに映画の文脈として必要だと決定できた理由が、
「主人公がホロコーストの生き残りであり、ナチス兵士らに強姦された妻を思い出してしまうので、女性の裸を見ることができない」という状況を描いているため、だとしている。
主人公ソルは性産業自体も憎んでいて、自分の生活費が性産業から生まれた金だと知って大きなショックを受けるシーンもあった。
****
●ゲイのキャラクターが登場した初めてのアメリカ映画(演じたのはブロック・ピーターズ)
〝バラエティ誌はブロック・ピーターズをアメリカ映画で同性愛者のキャラクターを演じた最初の俳優だとみなした。〟
Wikipwdiaには上記のように書かれていたけど、1964年以前にゲイキャラクターは出てなかった?ほんと?
しかもこの映画では特に自分で「俺はゲイだ」とも言ってないし、彼の持ち物の男性上半身ヌード雑誌が映るくらいしか彼がゲイであるという描写は見られない。
***
金しか信用できない難しい主人公像
映画のあらすじは以下の通り。
"ソル・ナザーマンは45歳の大柄な男で、
戦前はの教授を務めていた。
彼はトラウマに対処するため、意図的に感情を封じ込めてきた。
その結果、周囲の人々、特に店に来る絶望的な人々を「クズ」と見なすようになった。
戦時中の経験、妻が売春を強いられ、息子が強制収容所へ送られる途中の貨車の排泄物に溺死したことによる心身のトラウマから、ナザーマンは悪夢と頭痛に悩まされている。"
その結果、ソルは
「黒人も白人も黄色人種も皆クズだ
神など信じない
芸術も科学も新聞も政治も哲学もだ
信じられるのはカネだ
カネで買えるものは快適さ、贅沢、痛みからの解放。人生だ
カネが全てだ」
という状況になってしまった。
この映画の複雑で面白い点は、主人公はけして良きユダヤ人ではないんですよね。
金に執着していて人をクズだと思っていて実際周りの人に対して結構酷いことをする。。
これが主人公ってなかなか難しいんだけど、、
妻と息子の酷い最期がフラッシュバックによって描かれることによって、観客は主人公に寄り添うようになる。
これは主演のロッド・スタイガーの演技力が大変貢献している。
ベルリン映画祭で男優賞を受賞。映画自体もアメリカ国立フィルム登録簿に登録されている。
名作だと思いますので、ぜひ。
ラストネタバレ含むメモは以下に!
主人公ソル
「黒人も白人も黄色人種も皆クズだ
神など信じない
芸術も科学も新聞も政治も哲学もだ
信じられるのはカネだ
カネで買えるものは快適さ、贅沢、痛みからの解放
人生だ
カネが全てだ」
*****
知的な黒人男性。彼も大学教授だった?今は仕事を追われて?知的な会話をする相手はソルしかいなくて彼と会話するために質屋に来ているよう。ソルは彼にも冷たい。
*****
亡き親友の妻
「父が亡くなった どうすれば?」
「埋葬するしかないだろ」
「血が通ってないの?」
「店をやらなきゃ埋葬代も出せない」
「父が死んだのよ」
「それを望んでいただろ」
と電話を切る
*****
質屋の店員のヘズスの恋人の黒人女性
「私上手なの。本当よ。すごい経験をさせてあげる。
あと20ドルちょうだい。いい思いをさせてあげる」
女性、ヌードになる。
ソルはナチスの性の捌け口にされた妻のことを思い出して、彼女に服を着せて20ドルを渡す。
*****
ロドリゲス(貧民街のボス。ソルの質屋のスポンサー。質屋を資金洗浄に使ってる。ゲイ)
「あんなたの金がどこから出てるか知ってるか
テッシーに渡している生活費やロングアイランドの立派な家のローンもだ
全部知ってる
あんたの金の出所は俺だ
売春宿の収入は多い
ボウリング用、駐車場、貸家からもだ
知らなかったとは言わせない」
「知らなかった(ほんとに知らなかった?)」
「こんなにも愚かだったとは。あんたの金は売春宿から来てる。知らないわけがないだろ。目を瞑っているだけだ。それじゃクズ同然だ。価値のない人間だ。あんたは俺の隠れ蓑だ。2度と電話を切るな」
*****
ソル
「ここ数日なぜか突然怖くなったんだ
昔の記憶が突然よみがえって、もう忘れたと思っていた葬り去った思い出が突然雪崩れ込んできたんだ
聞くまいとしていた言葉が聞こえてきた
今はその言葉が頭にあふれてる
今日は記念日だ
私は死ななかった
愛するものがすべて、すべて奪われた
でも私は死ななかった
何もできなかった何ひとつ
何ひとつできることはなかった」
***
地下鉄に乗っても、絶滅収容所に連れて行かれる列車の中での出来事がフラッシュバックする。
息子を背負っていたソル。
ソルは眠ってしまい、息子のデイヴィッドを落としてしまう。
鮨詰めの車内の床は排泄物で埋まっていた。息子は排泄物の中で窒息して死んでしまった。
***
子供用の靴を質に入れにきた男。「10ドルはする」
50ドルを払うソル。
以降、客に大金を渡すようになるソル。
ヘズス「師匠、最近おかしいですよ」
ソル「お前はクズだ」
***
蝶の標本を預けにきた黒人男性。
その蝶を見て、妻子ともに幸せだった頃の風景を思い出してしまうソル。そこにナチスが3人を連行しにきた。
質屋に強盗が来た。
クズと言われて腹を立てた?ヘズスが悪友たちに質屋を強盗するように焚き付けていた。
「死にたいのか?カネより命が大事だろ 金庫の前からどけ」
銃声。
ソルを守ったヘズスが撃たれてしまう。
ソルはずっと目を瞑っている。
強盗団たちは逃げた。
ヘズスはなんとか表に出て警察に発見される。
野次馬。
目を開けるソル。
ヘズスがいない。
ソルがヘズスに駆け寄る。
ヘズス「俺は撃つなと言ったんです あなたを傷つけるなと あなたを傷つけちゃいけないんだ!」
ヘズス死亡。
関わってきた人の顔を次々と思い出しながら伝票差しで手のひらを串刺しにする。
そして、表に出て、嗚咽しながら画面奥の方へ去っていく。
(これゲリラ撮影かな?モブのリアクションが自然。)
終わり