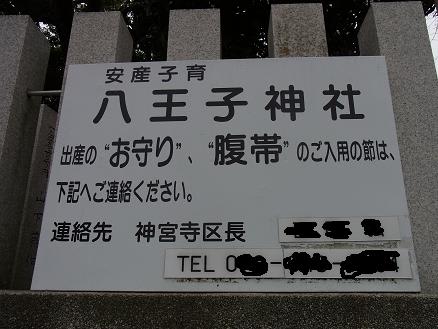★「光線と洞窟(1/2)」のつづき
黒崎神社は嘉祥年間(848~851)の創建と伝えられ、祭神は神功皇后である。古来より広田半島に住む漁民の信仰を集め、かつては沖を通る船は必ず帆を下げて航海の安全と大漁を祈願したという。こうした「礼帆」の習俗は、沿岸部で漁労航海神を祀った神社には全国的に見られ、かなり普遍的なものと言える。しかしそのいっぽうで黒崎神社の古い信仰には、海中にある神秘的な洞窟へのそれもあったらしい。当社の本宮(創建当時の黒崎神社があった場所)近くには海に面して亀裂のような断崖があり、その根元には雌沼雄沼という岩穴があって、次のような伝説が伝わっている。

黒崎神社本宮ふきんの断崖
雌沼雄沼はこの下にあるらしい
「黒崎仙峡は、陸中海岸国立公園の中で最も雄大な海蝕景観を誇っている。
この黒崎仙峡の岬の天狗の投げ石の下に一つの岩穴がある。この岩穴はいつもは海の中にあって見えないが、旧暦の3月3日だけは潮が引いて、よくその穴を見ることができる。この日にはまたこの穴から神楽のような音楽が聞こえてくるという噂を聞きつけて多くの村人たちが見物に来るようになった。
ある年のこと、この神楽のことを聞いた殿様が、なんとかして岩穴の秘密を知りたいと思い、調べに行くものはいないかと「お触れ」を出した。
このとき、与八と佐十という兄弟が名乗り出た。彼らは常日ごろ、仲が悪くお互いに意地を張り合っていた。
2人は準備をして岩穴探検にとりかかった。潮との長時間の戦いの後、狭い水路の所で、2人は船を捨てて海に飛び込んだ。
岩穴の前は深い淵になっており、潮の流れが激しくうず巻いていた。何度も押し流されたが、泳ぎ達者の2人はとうとうここを泳ぎ切った。
静かなよどみに出たとき、頭上から不思議ななんとも妙なる楽の音が聞こえてきた。与八と佐十はふと正面の岩壁の上を見上げた。突然2人の顔色が変った。岩の上に長い髪を腰まで伸ばして白衣の女が横たわっていたのである。音楽もやみ、ただならぬ妖気がただよってきた。
恐怖におののく2人は無我夢中で逃げ帰った。殿様の前で岩穴の秘密を話し終えると、2人はそのまま手を取り合って死んでいった。」
--- 「気仙の伝説」「陸中海岸の伝説」より」
・「黒崎仙峡温泉オフィシャルホームページ」からコピペさせていただきました。
当社は黒崎の突端部に鎮座しているが、同じような立地の神社に海中洞窟への信仰が見られるケースはまだ他にもある。
本州最南端の潮岬には、太陽信仰の磐座遺跡で名高い潮御崎神社が鎮座している。萩原法子の『熊野の太陽信仰と三本足の烏』によれば、当社のすぐ下には祭神である少彦名命を勧請した「静の窟」という洞窟があり、さらにその近くには「入陽のガバ」という洞窟があって、それは西向きで夕陽が射し込むという。
伊豆白浜に突き出た小さな岬には、式内明神大社の伊古奈姫命神社(「姫」は「比●(口に羊)」)が鎮座している。その突端部に近い駿河湾に面した崖下には、「御釜」と呼ばれるすり鉢状をした深い岩のくぼみがあり、その底は海とつながり、常時、潮が入ってきている。
「神職の原氏によれば、「御釜」のなかへは一年のうちでもごくわずかな機会、すなわち大潮の干潮時の、しかも砂が移動して歩ける状態のときのみ入ることができ、かつて先代の神職と土地の古老が入ったところ、その奥にさらに洞窟があり、本殿の真下に当たるかととおぼしき奥まった所に漆塗りの祠があって、つい数日前に塗られたばかりのように艶やかに光っていたという。(『日本の神々10東海』p293から引用)」

伊古奈姫命神社
伊豆国賀茂郡の式内明神大社

伊古奈姫命神社拝殿

御釜の外観(木の柵の向こう)

御釜の内部
海蝕洞を通じて入ってきた潮が白波を立てている
御釜は現在、近年の地震などで崩れ落ちた岩で埋まっており、
奥の洞窟へは進入できなくなっている

岬の突端にはいくつかの海蝕洞が口を開けている
御釜に入ってくる潮はここから流入しているものらしい
伊古奈姫命神社の祭神、伊古奈姫は伊豆諸島を造った三嶋大神の后神で、両神ははじめ三宅島にあったが、やがて当社のある白浜に移り、さらにその後、大神だけが現在の三島の地に遷祀されたという。本殿の鎮座する岬の上からは古代の祭祀遺物が多数、発見されており、そこからは伊豆の島々を望むことができる。当社の祭祀の源流は伊豆造島の神を来臨させて祀る祭祀にあったのだ。御釜の奥深く通じる秘密の洞窟は、こうして伊豆の島々から呼び寄せた造島の神が籠もる場所だったのだろう。

10月29日に行われる当社の大祭にあたって、
その前日に「火達ヒタチ祭」という神事が行われる
これは本殿の裏で焚き火をしながら伊豆諸島を遙拝するというもので、
かつては現社地に隣接する火達山で行われ、
そのいったいからは多くの祭祀遺物が出土している
文政十三年の縁起書によると神事の夜にかがり火を焚き、
これに呼応して島々でも焚き合わせたという
伊豆の島々から神を呼び寄せる神迎えの神事なのだろう
火達山は上の画像の左手に写っている小高く膨らんだ場所のことか

祭の翌日は「御弊オンベ流し」の神事が行われる
夕方になって拝殿裏の海岸に斎場を設け、
幣帛一本を立ててから神饌を供して伊豆諸島を遙拝し、
それから大明神岩という岩から島の数に相当する十本の幣帛と
供物を海中に投下する。この時はかならず西風が吹いて
幣帛を諸島へ送りと届けると信じられ、この風を「御弊オンベ西」と呼んだ
火達祭で呼び寄せた神々を伊豆の島々に送り返す神送りの儀式だろう
大明神岩は上の画像の右手にあるステージのような岩
伊豆諸島に向かって鳥居が立っている

以前、このブログでも紹介した子友町の蛇ケ崎神社(『太平洋が池のよう』の下のほう)がある蛇ケ崎は、黒崎神社から北に3kmほどしか離れていないが、当社が鎮座する崖の下にも「魔の瀬洞」と呼ばれる海蝕洞があり、「平家の落ち武者がそこに逃げ、只出のサユリという娘が朝夕、小舟でその洞に行き武者を世話していたら、そのうち源氏に知れてしまい、その洞に源氏が行ったとたん大波が来て、源氏の人達は波にさらわれ死んでしまったと言われる。現在でもサユリ波と畏れられている。(『岩手県神社名鑑』p273)」という伝承が伝わっている 。

蛇ケ崎神社

魔の瀬洞がある辺りの海蝕崖
これもまた伊古奈姫命神社と同じく、「海洋から来臨する神霊の籠もる洞窟」という基層信仰に、「外部からの来訪」という項を介して、後世になって平家の落ち武者伝説が上載されてできた伝承ではなかったか。
伊古奈姫命神社は社名通り女神を祀っているが、蛇ケ崎神社も豊玉姫命を祀っており、黒崎神社の祭神である神功皇后も女神の一種と考えられる。こうしてみると海中洞窟への信仰が見られる神社には女神が祀られている傾向が感じられる。これは洞窟地形が母胎を連想させることと無関係ではないだろう。
古代人にとって岬の突端は、海洋から神が来臨する聖なる場所であった。かつてはこのような場所にある洞窟に女神がいて、来訪した神と神婚し、威力ある新しい神霊が誕生するというような信仰があったのではないか。例えば岬の突端部にあり、古い信仰の見られる海蝕洞窟というと出雲にある加賀の潜戸が有名だが、『出雲国風土記』によれば、この洞窟は枳佐加比売命が佐太大神を生んだ場所とされているのである。

加賀の潜戸

黒崎神社の崖下にある洞窟で、岩の上に横たわっているのを泳ぎ達者の兄弟に目撃された長い髪を腰まで伸ばして白衣の女や、同じく蛇ケ崎神社の崖下にある洞窟に隠れた平家の落ち武者を庇ってやったサユリという娘も、あるいはこうした女神の零落した姿だったかもしれない。
黒崎神社

息気長帯姫命(神功皇后)を祀る旧村社で、風光明媚な景勝地、広田半島突端の黒崎に鎮座する。
『平成祭りデータ』にある由緒は以下の通り。
「黒崎神社は、広田の東端岬黒崎に鎮座し、初め黒崎明神と称され、巨岩怪石風光絶佳の所白浪渦巻き侵蝕した雌沼雄沼なる岩窟を眼下にする、仙境清浄の地に嘉祥年間西暦848年創建したと宮城縣史に伝えられ、又承安2年西暦1172年山伏の源真が息氣長帯姫命を勧請したとの記録あり、本宮としてその地に現在小祠がある海洋の民広田の漁民が、古来より祭神として萬里大海原を渡り、三韓に船出した神功皇后をこの地に移霊し、海上安全の豊漁を得んと信仰が深く、往時この沖を航行する船舶は必ず帆を下げ、海上安全と大漁を祈願したと伝えられている。中世社地狭くなり、元徳2年に現在の境内地に遷宮したと思われ、確実な記録としては、現存する宝物懸佛の銘文に明應5年広田城主大丹那源綱継願主賢春の2人が100日間社殿に参篭し、郷民に代わりて一郷安穏の為天長地久を祈り、現世安穏後世善處を勤行祈願すとあり、その時誦読の経文品目と共に広田を・田郷と記してある。明和6年には肝入及別当連名で願出し、京都神祇管令卜部家より大明神号を授けられる。明治5年、古社名黒崎大明神を改めて村社黒崎神社となった。3年毎に神輿渡御の大祭典が行なわれ、氏子総出で之を祭り、山車手踊り虎舞等の奉納余興を催し、神人共に賑わう。この社地は、国立公園陸中海岸中白眉の勝地として造化の妙と神威を併せ持ち、四近、景勝多く岩頭に立てば眼前に数万の鴎群れ飛ぶ椿島青松島南方遥に金華山を眺め北西に五葉連峰を一望する詩情豊かに又浩然の気充ち心身共に清爽を覚ゆる仙境である。祭日は旧3月10日と9月10日である。」
祭神の神功皇后について思いつきを一言。
神功皇后は神社の祭神として珍しいものではないが、周知の通り、普通は八幡神として応神天皇とセットで祀られていることが多い。神功皇后が単独で祀られている場合もあるが、そういう神社は神功皇后伝説が多く残された地域に鎮座しているもので、当社のように皇后の渡航ルートから大きく外れた地域で単独に祀っている例は珍しいのではないか。ところで、『太平洋が池のよう』で紹介した子友町の八幡神社は、当社から北に3km程度しか離れていないが、この神社は八幡神社であるにも関わらず応神天皇しか祀られていない。あるいは当社と八幡神社には信仰面でつながりがあり、両社は母子神としてセットだった、ということはなかろうか。