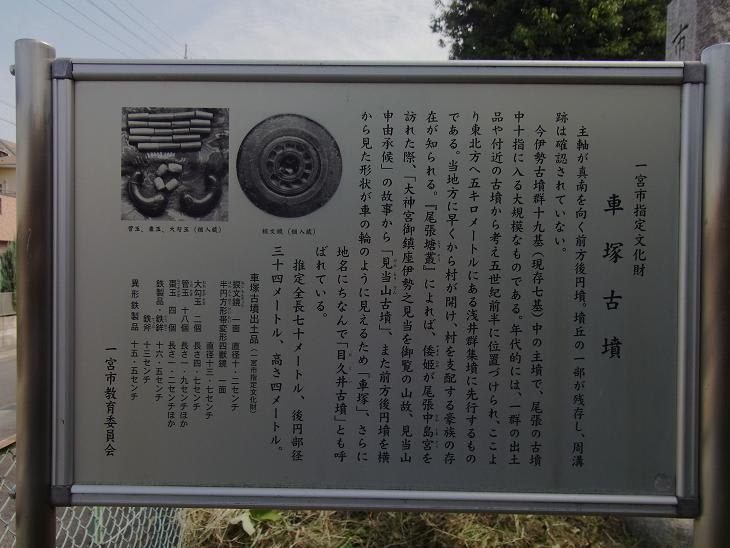将来、伊勢津彦捜しの歴史が書かれることがあったら、事忌神社をめぐる知の冒険のことも、奇妙な挿話として語られるかもしれない ── 。
伊勢国安芸郡に「事忌(こといみ)神社」という式内社がある。所在も祭神も由緒も祭祀氏族も不明だが、『神名帳傍注』は、「こといみ」の「こと」は「木霊(こたま)」の「こた」、「み」は「こたま」の「ま」とそれぞれ通音、ということで木霊を祀った神社であるとし、そこからその所在地を安芸郡林村とする説を立てた。
この説はその後の諸書において、だいたいに受け入れられた。
現在、津市芸濃町大字林(旧・安芸郡林村)に事忌神社という神社が鎮座しているのも、『神名帳傍注』の考証を受けて、林村に祀られていた何らかの神社が「事忌神社」に改称されたものだろう(ただし、当社の現祭神は木霊ではなく建早須佐之男命と菅原道真公)。
しかしながら、「こといみ」と「こたま」を通音とするのは無理があるし、さらに木霊を祀った神社だから所在地が「林」村というのも非常にコジツケっぽい。
はたして幕末から明治初期にかけて活躍した伊勢の国学者、御巫清直(みかんなぎ・きよなお)は『伊勢式内社検録』の中でこの説を批判して、「事忌を木霊に牽強する妄説」にすぎず、当社の所在地を林村のように木に関係する名前の村にするのだったら、高野尾村に樹神山長泉寺という寺院があるから、この村に配したって良いじゃないか、と一笑に付している。
そこまでは良かった。
が、清直は自らもこの失われた式内社の探索に乗り出したのである。
彼によれば、応永年中に書写された『日本書紀私見聞』所引の『伊勢国風土記』に、次のような条があると言う。
「伊勢と云ふは、伊賀の事忌社に坐す神、出雲の神の子、出雲建子命、またの名を伊勢津彦の神、またの名を天櫛玉命、この神、石城を造りその地に坐しき。ここに阿倍志彦の神、来り奪へど勝へずして還却りき。因りて以ちて名とせり。」
まず言っておかなければならないのは、現在、日本古典文学大系本をはじめとした諸書において、『日本書紀私見聞』にある『伊勢国風土記』逸文の赤字部分は、「伊賀の穴志社」となっていて、清直が言うように「伊賀の事忌社」とはなっていないということだ。が、それを言い出すと話が終わってしまうので、ここは彼の主張を黙認しよう。
清直は「伊賀事忌社」をとうがい式内・事忌神社に同定する。したがって、「伊賀」は国名の伊賀ではなく、伊勢国造安芸郡内にあった地名ということになる。だが、安芸郡内を捜しても「伊賀」という地名はなかった。その代わり彼は「赤部村」という地名を見つけた。
地名の「部」は訓んだり訓まなかったりすることがある。このため、古くは「部」を訓まず、「赤部」はたんに「あか」とだけ言われていたのだろう。そして、「伊賀(いか)」と「あか」は通音なので、清直は赤部村を「伊賀」の遺称地と結論した。
しかし、残念ながら赤部村には式内・事忌神社に当たるような神社がなかった。
その代わり、その隣に高佐村という村をみつけた。
そこで彼はひらめいた。
『天地麗気記』という書物に大略、「高佐山には十二個の石室があり、伊勢津彦の石窟、または春日戸神の霊窟である。」という記事がある。
ここで言う「高佐山」とは外宮の裏山に当たる高倉山の一名である。したがって高佐村のことを言ったものではない。しかし、伊勢津彦が石城に立てこもった伝承はもともと高佐村に伝わっていたものと考えたらどうだろうか。だとしたら、それが高倉山に訛伝したために、この山の異名が高佐山になったと考えられないか。
そう考えた彼は早速、現地を訪れた。すると高佐村は「石城を造るとあるに形勢相似たり」だった。またその地には産土神が三社あるが、そのうちの一社は「イソの神」と称しているのでこれを捉えて、「伊勢の神の転訛にて是即伊勢津彦神なるべし」と結論した、── 。w
「こといみ」と「こたま」を通音とした『神名帳傍注』の説もかなり強引だったが、ここに見られる清直の牽強付会もそうとうなものだ。『先代旧事本紀』の優れた考証を行うなど、国学史上の偉大な巨人と目される御巫清直、気でも狂ったか!、という無茶ぶりである。
短絡的に見ると、彼が『日本書紀私見聞』所引の『伊勢国風土記』にある「穴志社」を、「事忌社」と誤読したことが原因ではあったろう。しかし、勢津彦の伝承に強く惹きつける力がなければ、こうも清直が大風呂敷を広げることはなかったろう。

事忌神社には去年のまだ残暑が厳しい時期に訪れた。

事忌神社の社頭

事忌神社

同上
神社は簡素な施設の、つつましい佇まいだった。

事忌神社本殿

「村社事忌神社鎮座古跡」
当社は明治四十二年に一度、近隣にある黒田神社に合祀された。現在も社殿背後に建っている明治四十二年の「村社事忌神社鎮座地古跡」の石標はその時のものだろう。当社はその後、復祀し、現在に至っている。
清直が高佐村のことを「石城を造るとあるに形勢相似たり」と言っているので、神社の周囲を捜せば巨岩を祀った磐座に出会えるのではないか、と淡い期待を抱いていたのだが、そんなものはなかった。そもそもふきんいったいが、そんな地質の場所であるように見えなかった。
またさっきも言ったように、清直によれば高佐村には神社が三社あり、そのうちの一社が「イソの神」と呼ばれていて、彼はこの神社を式内・事忌神社に比定しているのだが、神社明細帳によれば、現・事忌神社はかつて宇気比神社という社名であったという。ぬう、よく分らん。
そんなこんなで、事忌神社のことを思い出すと、今でも狐につままれたような気分になる。