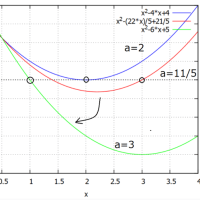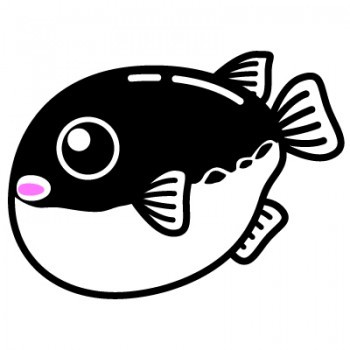1.まえがき
物理学では論理の組み立てが杜撰なまま議論され、可笑しな言明がなされることがある。
例えば、電磁気学をマクスウェルの方程式から構築すると称して、「ガウスの法則から
クーロンの法則が導かれる」というような言明である。
このことはニュートンに始まる物理の原初、力学からの悪しき伝統であるが、特殊相対性
理論における例を説明する。
2.光速度以上の速度は無い(光以外)
光速度以上の速度が無いことはローレンツ因子 γ=1/√(1-v²/c²) によって説明されて
いる。ところが、特殊相対性理論の仮定・原理には通常、挙げられる2つの他、どこにも
明らかにされていない重要な仮定
[仮定・原理] 慣性系間の相対速度は光速度より小さい。
がある。
何故この仮定が必要かというと、この理論の最初の結論はローレンツ変換であるが、これ
を見ると、慣性系Sから慣性系S'へ「必ず光が到達する」ことを使って、導出されている。
つまり、慣性系間の相対速度が光速度より小さくなければ、光は到達せず議論にならない。
そして、光速度以上の物体があったら、それを基準とする慣性系が設定でき、上の原理に
矛盾するからであ。
すなわち、この理論は初めから、光以外、光速度より小さい速度しか議論しておらず、こ
の理論を使って、タキオン云々は笑止なのである。
3.光速度不変は原理でなく電磁気学から導かれる定理である
この誤解は広く信じられている。しかし、この理論は慣性系間の時空の性質を規定するも
のである(ガリレイの相対性理論は、あまりに単純なためこの意義がはっきりしない)。
そして、この時空理論の上に力学や電磁気学が建設されている。したがって、電磁気学か
らローレンツ変換や光速度不変が導かれても当然であり、理論は矛盾していないというこ
とにすぎない。
なお、慣性系が異なると時間が異なり、空間と混じり合う理論のため、「時間」とは何か
ということをもう少し明確にする必要がある(巷に溢れる訳の分からない妄想哲学?論で
はなく物理で実際に使う時間)。
4.あとがき
上のような誤解が広がっている原因は、定義や法則・公理・仮定が不明確なまま議論され
てることにある。あまり厳密なことを言うと何も無くなるが要は程度問題であり現状は杜
撰すぎる。
なお、この理論は短縮や時間遅れなどの結論だけの議論がなされることが多いが、100年
前、物理の危機に対して偉大な先哲たちの苦悩や考察が忘れ去られてしまった。
たとえば、アインシュタインは何故、始めに「同時性の定義」を述べたか(ダンマリを決
め込んだようだが、本当はポアンカレの提言)、それは何処に使われているのかなど理解
されているのだろうか(昨今は、あまりに当たり前に見えるので、省かれたり、同時の相
対性と勘違いしている書籍もある?)。
以上