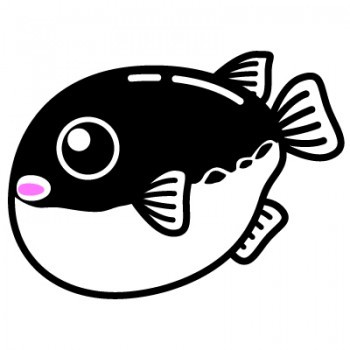平面上の曲線の捩れ率は0であるのは自明とも思えるがあえて証明してみる。
平面の式は 平面上の位置ベクトルをr、pを定ベクトルとして
r・p=定数・・・・・・①
となる。
この平面上の曲線を、弧長パラメータsを使って r(s) として、①を微分すれば、tを接線単位ベク
トルとして
t・p=0・・・・②
もう一度微分して、nを主法線単位ベクトル、κ(≠0 とする)を曲率として
κn・p=0 → n・p=0・・・・③
となる。
ここで、従法線単位ベクトルを b (=t×n) とすると、公式と②③から
p×b=p×(t×n)=(p・n)t-(p・t)n=0
となる。
つまり、pとbは平行。つまり、bの方向はpと同じで一定。さらにbは単位ベクトルだから、bは
定ベクトルとなる。すると捩れ率τは
τ=-db/ds・n=0
となる。
以上
1. まえがき
前に、ex 上の任意の2つの点の法線の交点の作る集合を求める問題を考えた。ここでは x2 につい
て計算する。
2. 計算
(1) 交点の計算
法線の傾きは -1/2x だから、x=a,b (≠0) での法線は
y=-(1/2a)(x-a)+a2 , y=-(1/2b)(x-b)+b2 ・・・・・①
その交点は、a≠b だから
x=-2ab(a+b)=-2a{ (b+a/2)2-a2/4 } ・・・・・②
y=b(a+b)+1/2+a2 =(b+a/2)2+(3/4)a2+1/2 ( > 0 ) ・・・・③
この x,y の領域を調べればよい。aを固定して、bを変化させたときを考える。すると、x,y の範
囲は次のようになる。
y≧(3/4)a2+1/2 で、b=-a/2 のとき、最小の y=(3/4)a2+1/2
a > 0 のとき、x≦ a3/2 ( > 0) 、さらに、 b=-a/2 のとき、最大の x=a3/2 ( > 0)
a < 0 のとき、x≧a3/2 ( < 0)、さらに、b=-a/2 のとき、最小の x=a3/2 ( < 0)
は②③から明らか。
(2) 交点の最下端の軌跡
すると、法線の下部端の軌跡は b=-a/2 のときで
x=a3/2 , y=(3/4)a2+1/2
となり、
y=(3/4)(2x)2/3+1/2 = 3(x/4)2/3 +1/2・・・・・・⑥
となる。
(3) 法線の包絡線
別の観点から、法線①の前者の包絡線を考える。①をaで微分した式は
0=-x/2a+2a → x=4a3
これを①に入れると
y=2a2+1/2+a2=3a2+1/2=3(x/4)2/3+1/2
つまり、この包絡線は⑥と一致する。
これらの曲線は図のように特異点で左右に分かれている。この特異点は
x=0 , y=1/2
となる。
この図で青が x2 で、赤が⑥の包絡線かつ、交点の最下部の軌跡、そして、緑とピンクが x=a=1
における、法線と最下部の交点を作る x=-1/2a=1/2 の法線である。
(4) 求める交点の範囲
以上のことと包絡線と法線の関係から、求める領域は緑の法線の太い部分がなぞる部分、つまり
赤の線の上の黄の部分となる(境界の部分も含むが、下記の理由により特異点は除かれる)。
また、議論で除いた a=0 の場合は②③から x=0 , y≧1/2 の半直線になるが、最下部は a=b/2=0
なので、交点を作る法線は同一になり、この特異点は除かれる。
以上
1. まえがき
ex 上の異なる任意の2つの点の法線の交点の作る集合を求める問題があった。はじめは検討の余
地もないほど面倒だと思った。
2. 計算
(1) 交点の計算
法線の傾きは -e-x だから、x=a,b での法線は
y=-e-a(x-a)+ea , y=-e-b(x-b)+eb ・・・・・①
その交点は
x=(ae-a-be-b)/(e-a-e-b)+(ea-eb)/(e-a-e-b)
=a+(a-b)e-b/(e-a-e-b)-ea+b ・・・・・②
y=-e-a { (a-b)e-b/(e-a-e-b)-ea+b }+ea
=-(a-b)e-a-b/(e-a-e-b)+ea+eb ・・・・③
この x,yの領域を調べればよい。aを固定して、bを変化させたときを考える。すると
x → -∞、y → +∞ (b → ±∞)
となり、x,y とも極値を持つ。そして、この領域は ex の上側にあり、法線の傾きは負だから、
法線の下側で端点がある。それは、xの極大、yの極小になるから、②③を微分して
dx/db=(-1)e-b/(e-a-e-b)+(a-b) { (-1)e-b/(e-a-e-b)+e-b(-1)e-b/(e-a-e-b)2 }-ea+b=0
両辺を -e-b/(e-a-e-b) で割って
1+(a-b){ 1+e-b/(e-a-e-b) }-(e-a-e-b)ea+2b=0・・・・・④
dy/db=e-a-b/(e-a-e-b)-(a-b){ -e-a-b/(e-a-e-b)+e-a-b(-1)e-b/(e-a-e-b)2 }+eb=0
両辺を e-a-b/(e-a-e-b) で割って
1+(a-b){ 1+e-b/(e-a-e-b) }+(e-a-e-b)ea+2b=0・・・・・⑤
④⑤から
2(e-a-e-b)ea+2b=0 → a=b
を得る。しかし、相異なる法線の交点なので、このとき、交点が存在するわけではない。
(2) 交点の最下端の軌跡
すると②③から、法線の下部端はロピタルによって
(a-b)/(e-a-e-b) → -1/e-b=-ea ( b → a)
を使うと
x=a-1-e2a ( < 0)
y=e-a+2ea ( > 0)・・・・・・⑥
となる。この曲線は交点の最下部の aのパラメータ表示で、図1,2 となる(図1,2の交点の詳
細が不明なので拡大したものが図3)。

(3) 法線の包絡線
別の観点から、法線①の前者の包絡線を考える。①をaで微分した式は
0=e-a(x-a)+e-a+ea → x=a-1-e2a
これを①に入れると
y=-a-a(-1-e2a)+ea=e-a+2ea
つまり、この包絡線は⑥と一致する。
これらの曲線は右下の特異点で上下に分かれている。この特異点は x=a-1-e2a の極値
となるから
dx/da=0 → a=-(log2)/2=-0.346
x=-log2/2-1-1/2=-1.846 , y=√2+2/√2=2.828 (⑥に代入して)
となる。
すると、この曲線の上側、図1は a < -0.346 、下側が a > -0.346 の範囲となるから、包絡線
に接する法線は包絡線の接点で最下部となり、図3のようになる。
(4) 求める交点の範囲
以上のことから、求める領域は上下の曲線に囲まれた部分になるといいたいが、a=b の場合
の⑥の交点は極限であり、実際は存在しないから、この領域から淵(境界)を取り除いたものに
なる。
以上
1. まえがき
関数表記 f(x) には、不明確さに起因する不具合が発生する。この要因は f(x)が関数を
指すか値を指すかの区別ができないことにある。その例を示す。
2. 微分の不具合
関数 f(x,y) としたとき、f(x²y, x+2y) の偏微分を
(∂/∂x)f(x²y, x+2y)=fx(x²y, x+2y)2xy , (∂/∂y)f(x²y, x+2y)=fy(x²y, x+2y)2
と書いたりする。しかし、正確には
u=x²y , v=x+2y
と変数変換したとして、連鎖律から
(∂/∂x)f(x²y, x+2y)=fu(u, v)2xy={ fu(u, v)(u=x²y, v=x+2y) }2xy
(∂/∂y)f(x²y, x+2y)=fv(u, v)2={ fv(u, v)(u=x²y, v=x+2y) }2
のことである。
昔、関数表記として
f(▢₁, ▢₂)
という表現を見たことがある。これを使えば
(∂/∂x)f(x²y, x+2y)=f₁(▢₁, ▢₂)(▢₁=x²y, ▢₂=x+2y)2xy
(∂/∂y)f(x²y, x+2y)=f₂(▢₁, ▢₂)(▢₁=x²y, ▢₂=x+2y)2
として、u,vを使わなくても良い。
ただ、こんなことをしていたら、面倒なだけでなので、結局、注意しながら、使う
しかない。
3. あとがき
ミクシンスキーの演算子法ではこのような不明確さのため関数を {f(x)}で表し、値と
区別していた。
以上
1.まえがき
あるサイトに次の問題があった。∂f/∂x=∂xf=fx , g'(u)=dg(u)/du などと書く。
[問題]ともにC∞級の関数f(x,y)とg(u)に対して
h(x,y)=g(f(x,y))
と定める。このとき
f(x,y)=y+xh(x,y)
となる関係を満たすとき、次の関係を証明せよ。
(1) (∂f/∂x)(x,y)=h(x,y)(∂f/∂y)(x,y) が成り立つ。
(2) ∀n∈N に対して (∂ⁿf/∂xⁿ)(x,y)=(∂ⁿ⁻¹/∂yⁿ⁻¹)(hⁿ∂f/∂y)(x,y)
2.証明
(1) まず、
f=y+xg(f)・・・・・①
の両辺をxで偏微分すると
fx=g+xg'fx ⇒ fx=g/(1-xg')・・・・②
①の両辺をyで偏微分すると
fy=1+xg'fy ⇒ fy=1/(1-xg')
ゆえに、fx=gfy (もとい、∂f/∂x=h∂f/∂y)・・・・③
を得る。
(2) ③を使って
∂yⁿ(gⁿfx)
=∂yⁿ⁻¹(ngⁿ⁻¹g'fyfx+gⁿfxy)=∂yⁿ⁻¹{ngⁿ⁻¹g'(fx/g)fx+gⁿ∂x(fy)}
=∂yⁿ⁻¹{ngⁿ⁻²g'fx²+gⁿ∂x(fx/g)}=∂yⁿ⁻¹{ngⁿ⁻²g'fx²+gⁿ(fxxg-fxg'fx)/g²}
=∂yⁿ⁻¹{(n-1)gⁿ⁻²g'fx²+gⁿ⁻¹fxx}=∂yⁿ⁻¹{∂x(gⁿ⁻¹fx)}
=∂x{∂yⁿ⁻¹(gⁿ⁻¹fx)}・・・④
③④を使って
∂yⁿ⁻¹(gⁿfy)=∂yⁿ⁻¹(gⁿ⁻¹fx)=∂x{∂yⁿ⁻²(gⁿ⁻²fx)}
以降を帰納的に{}内のnを下げていけば
∂yⁿ⁻¹(gⁿfy)=∂xⁿ⁻¹{fx}=∂xⁿf
を得る。これは求める式になる。
3.あとがき
どうしてこのような関係を見つけるのか驚きである。何か役に立つのだろうか?
以上