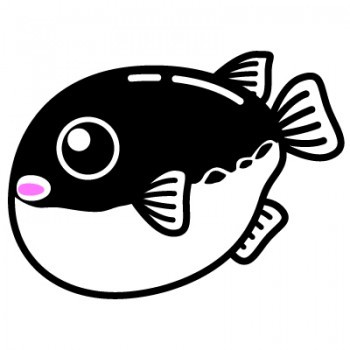1. まえがき
無限平面導体上に半球の突起部があるときの電界を問う問題があった。調べると下記の
書籍に解報が載っており、巧妙で面白いので紹介する。
2. 問題
図のように無限平面導体面の上に半径aの半球の突起部がある。導体は接地されている。
半球の中心Oを原点とする。Oから平面に対して垂直な距離dの位置に電荷qがあるとき
の電界を求める。このときは単純に鏡像法が使えない。
3. 計算
P点の球の鏡像点をP₁、電荷をq' とする。すると、
OP₁=a²/d , q'=-aq/d
となる。そして、P,P₁の鏡像をP', P₁' とすると
OP₁'=-a²/d , OP'=-d (電荷はそれぞれ、-q₁=+aq/d , -q)
となる。
このとき、P, P', P₁, P₁' の電荷にによ導体平面の電位が0になることはすぐわかる。問
題は半球面の電位がどうなるかである。ここで、PとP₁ の電荷による電位を考えると、
半球面で0になる。つぎに、P'とP₁' の電荷による半球面の電位も0になるから、これ等
を重ね合わせた電位も0になり、境界条件を満たし、これらの鏡像による電界が解とな
ることがわかる。
Qの座標(r,θ)の電界は、図のようにP, P', P₁, P₁' からの距離と角度をそれぞれ、s, s', s₁,s₁',
φ, φ', φ₁, φ₁' とすると
Ex=(q/4πε₀)[cosφ/s²-cosφ'/s'²-(a/d){cosφ₁/s₁²-cosφ₁'/s₁'²}]
Ey=(q/4πε₀)[sinφ/s²-sinφ'/s'²-(a/d){sinφ₁/s₁²-sinφ₁'/s₁'²}]
と書ける。このとき
s²=r²+d²-2drcosθ , rsinθ=s sinφ , s₁²=r²+(a²/d)²-2(a²/d)rcosθ , rsinθ=s₁sinφ₁
s'²=r²+d²+2drcosθ , rsinθ=s'sinφ' , s₁'²=r²+(a²/d)²+2(a²/d)rcosθ , rsinθ=s₁'sinφ₁'
となるが、これ以上は面倒なのでやめる。
4. 平面上の電界
例題にあるように、平面上の電界 Exを求めてみる。θ=±π/2(a≦r)なので
s=√(r²+d²) , cosφ=-d/s , s'=s , cosφ'=d/s
s₁=√(r²+(a²/d)²)=√(r²+(a⁴/d²)) , cosφ₁=-(a²/d)/s₁ , s₁'=s₁ , cosφ₁'=(a²/d)/s₁
なので
Ex=(q/4πε₀)[-d/s³-d/s³-(a/d)(a²/d){-1/s₁³-1/s₁³}]=-(q/2πε₀)[d/s³-(a³/d²)/s₁³]
=-(q/2πε₀)[d/(r²+d²)3/2-(a³/d²)/{r²+(a⁴/d²)}3/2] (a≦r)
となる。
5. 球面上の電界
面倒なので、球面の先端、r=a, θ=0 の場合のみ。すると
s=d-a , cosφ=-1 , s'=d+a , cosφ'=1
s₁=a-(a²/d)=(a/d)(d-a) , cosφ₁=1 , s₁'=a+a²/d=(a/d)(d+a) , cosφ₁'=1
なので
Ex=(q/4πε₀)[-1/s²-1/s'²-(a/d){1/s₁²-1/s₁'²}]
=(q/4πε₀)[-1/(d-a)²-1/(d+a)²-(a/d)(d/a)²{1/(d-a)²-1/(d+a)²}]
=-(q/4πε₀)[ { 2(d²+a²)+(d/a)4ad }/(d²-a²)² ]
=-(q/4πε₀)[ { 2(d²+a²)+4d² }/(d²-a²)² ]
=-(q/2πε₀)[ (3d²+a²)/(d²-a²)² ]
となる。
なお、上式で、a=0 と置くと、設定が特異的になり、平面の結果と合わない。
[参考書籍]
詳解 電磁気学演習 後藤憲一他 共立出版㈱ P117
以上
1 まえがき
あるサイトにつぎの問題が載っていた。計算がちょっと変わっていたのが面白かった。
問 図のような半径Rの半球面殻に一様な面電荷σが分布しているときの、Z軸上の電界および
無限遠に対するポテンシャルを求めよ。
2 電界の計算
半球面の点PをX-Y平面からの角度θで表す。Pからzまでの距離をrとする。X-Y平面に平行な微小
長さをdlとすると、P点の微小面Rdθdlの電荷はdq=σRdθdlとなる。この電荷によるZ軸上の電
界とZ軸とのなす角をφとする。すると、この電界のZ成分は(dq/(4πεr²))cosφとなる。この
電界はX-Y平面に平行な円周を考えると当然、X,Y方向はキャンセルして、Z成分のみとなる。
この電界のZ成分は、この円周上では一定なので、X-Y平面に平行な微小リングの長さを掛ける、
つまり dl→(2πRcosθ)として
dEz=(σ/(2εr²))R²cosφcosθdθとなる。
ここで、余弦定理より上の図のように
r²=R²+z²-2zRcos(π/2+θ)=R²+z²+2zRsinθ、cosφ=(z+Rsinθ)/r (z≧0)
r²=R²+z²-2(-z)Rcos(π/2-θ)=R²+z²+2zRsinθ、cosφ=(z+Rsinθ)/r(z<0)
となる(cosφにより、z<0の場合もうまく、Ezの方向を現している)。これらより、
dEz=(σ/2ε) R²((z+Rsinθ)/r³)cosθdθ となり、これをθ=0~π/2で積分すればよい。
つぎに、r=√(R²+z²+2zRsinθ)と変数変換する。θ=0,π/2に対して、r=√(R²+z²)=a,
r=|R+z|=bとおく。rdr=zRcosθdθ、(r²-R²-z²)/(2z)=Rsinθだから
Ez=∫dEz=(σ/2ε)R∫[a,b]{1-(R²-z²)/r²}dr/(2z²)
=(σ/2ε)R/(2z²) [r+(R²-z²)/r][r=a,b]=(σ/2ε)R/(2z²){b-a+(R²-z²)(1/b-1/a)}
=(σ/2ε)R/(2z²){(b²+(R²-z²))/b –(a²+(R²-z²))/a}
=(σ/2ε)(R/z)²{(R+z)/|R+z|-R/√(R²+z²)}
となる。この式は、z=-R以外の実数で成立する。これをまとめると
Ez=(σ/2ε)(R/z)²{1-R/√(R²+z²)} (z>-R)・・・・(1)
Ez=(σ/2ε)(R/z)²{-1-R/√(R²+z²)} (z<-R)・・・・(2)
ただし、z=0のときはロピタルの定理で極限を取らねばならないが、z=0として積分しても求められ
Ez=σ/(4ε) (z=0)・・・・(3)
をえる。以下に、R=1としたときの電界と電位を図示した。
3 ポテンシャルの計算
3.1 z>0のとき
(1)式から u=R/zと変数変換して
V=-∫[+∞,z]Ezdz=-(σ/2ε)∫[+∞,z](R/z)²{1-R/√(R²+z²)}dz・・・・(4)
=-(σ/2ε)∫[+0,R/z] u²{1-|u|/√(1+u²)}(-Rdu/u²)
=(σ/2ε)R∫[+0,R/z] (1-u/√(1+u²))du (z>0からu>0なので |u|=u)
=(σ/2ε)R [u-√(1+u²)][u=+0,R/z]・・・・・・(5)
=(σ/2ε)R{R/z - √(1+(R/z)²) +1} ({}内は正)
となる。z=0のとき発散するが極限をとると{}内は1となり
V=(σ/2ε)R (z=+0)・・・・・(6)
となる。
3.2 0>z>-Rのとき
積分区間をz=+∞~+0とz=-0~zにわける。始めの区間の積分は(6)式であり、次の区間では
|u|=-uだから(5)式を調整して
V=(σ/2ε)R + (σ/2ε)R [u+√(1+u²)][u=-∞,R/z]・・・・(7)
=(σ/2ε)R + (σ/2ε)R{R/z+√(1+(R/z)²)}
=(σ/2ε)R{1 + R/z + √(1+(R/z)²)}
ここで、 lim[u→ -∞](u+√(1+u²))={-u²+(1+u²)}/{-u+√(1+u²)}=0 を使用した。
同様に、z=-0の極限では(6)式と同じ
V=(σ/2ε)R (z=-0)
となる。z=-R+0のときは
V=(σ/2ε)R√2 (z=-R+0)
3.3 z<-Rのとき
このときは(2)式を(-∞,z)で積分する。(2)式と(7)式の後半を調整して
V=(σ/2ε)R [-u+√(1+u²)][u=-0,R/z]
=(σ/2ε)R{-R/z+√(1+(R/z)²) - 1} ({}内は正)
z=-R-0では
V=(σ/2ε)R√2 (z=-R-0)
となる。
以上