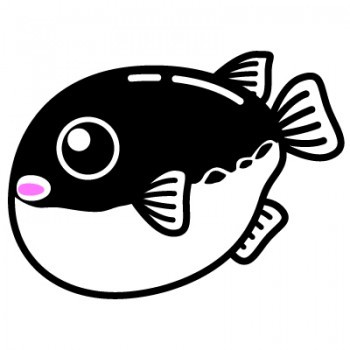1.まえがき
円弧の台を滑る物体に働く抗力を求める問題があった。一般に台の形状の微分を使
った複雑な式を計算するが、円弧なので法線方向の運動方程式が使えて簡単になる
ことに気が付いた。
台は固定されており、形状は図のように2つの半径 rの円弧に接する直線でつなげ
た。滑る物体の質量は mで大きさは無視できるとし、台との摩擦は無い。抗力をS、
mの速さを vとする。
物体mは初速度0で高さhから放たれ斜面を滑り降り、A-B-C-D-E-F-G と移動する。
2.計算
(1) 抗力の最大値とその位置を求めよ
左の円弧の中心からの垂線と円弧の中心とmの位置を結んだ線のなす角を
θ(α~-α)とする。この曲線の法線ベクトルは上向きなので、始めの円弧についての
法線方向の運動方程式は
mv²/r=S-mgcosθ → S=mv²/r+mgcosθ・・・・・①
また、この円弧の水平面からの高さは rcosθ だから、円弧のある位置での速さは
v²=2g(h+rcosθ)
①に入れて
S=mg(2h/r+3cosθ)
したがって、Sが最大になるのは θ=0 の時なのは自明。つまり
Smax=mg(2h/r+3)
ちなみに、この式から始めの直線部では r=∞であり、①から S=mgcosα となり、
Smaxが大きい。また、θ=0以降は①から
S≦mv²/r+mg
であり、高さが小さくなり、vも小さくなるので、やはりSmax以上にはならない。
(2) 高さhをある値以上にするとmは台から離れる。この時のhと位置を求めよ
離れるとすれば、右の円弧の部分となる。同様に、この円弧の中心と垂線とのなす
角をθ(α~-α)とする。法線の方向は下向きとなり運動方程式は
mv²/r=-S+mgcosθ → S=mgcosθ-mv²/r・・・・・②
この円弧上の水平線からの高さは
r(cosθ-cosα)
したがって、mの速度は
v²=2g(h-r(cosθ-cosα))
となり、②に入れると
S=mg(-2h/r+3cosθ-2cosα)
となる。S<0 のとき、離れるから
h>(r/2)(3cosθ-2cosα)・・・・③
を満たせばよい。
ここで、1≧cosα だから、θ=αのとき、hは最も小さく
h>(r/2)(3cosα-2cosα)=(r/2)cosα
であれば離れる(θ=αの位置)。
なお、③はθ(α~-α)に対して対称だから、θ=0までに離れなければ、それ以降も離
れない。
以上
1. まえがき
図のような円筒側面を転がり落ちる円板が側面を離れる位置を求める問題があった。
これを求めてみる。
2. 条件
半径aの円筒の中心軸が水平に置かれている。この上を半径b、質量mの円板が円筒の
頂点から滑りが無く転がり落ちるとき、円筒の側面から離れる位置を求める。
鉛直からの円板重心までの角度をθ、鉛直から円板の回転角度をφとし、円板にかかる
摩擦力をF、円筒からの抗力をRとする。円板の重心周りの慣性モーメントは mb²/2
である。重力の加速度をgとする。
3. 計算
3.1 円筒が回転しない時
円板重心のθ方向の運動方程式は m(a+b)θ''=mgsinθ-F・・・・・①
円板重心の半径方向の運動方程式は m(a+b)θ'²=mgcosθ-R・・・・②
円板の重心を中心とする回転の運動方程式は (mb²/2)φ''=bF・・・・・・・③
となる。
また、円板の回転弧長CBD=弧CB+弧BD=bφ は、滑りが無いので 弧BD=弧AB=aθ
であり、弧CBの角度はθだから、弧CB=bθ となり
bφ=aθ+bθ=(a+b)θ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④
となる。④➂から F={m(a+b)/2}θ'' となり、これを①に入れると
(3/2)m(a+b)θ''=mgsinθ
この両辺にθ' を掛けて、積分し、θ(0)=θ'(0)=0 を使うと
(3/4)m(a+b)θ'²=mg(1-cosθ)
これを②に入れると
R=mgcosθ-(4/3)mg(1-cosθ)=(mg/3)(7cosθ-4)
を得る。円筒から離れるときは抗力が無くなる時なので、R=0 つまり
cosθ=4/7
となるときである。
3.2 円筒が回転する時
円筒が摩擦の無い中心軸によって回転するときは、円筒の慣性モーメントと回転角
を ma²、αとすると、円板の回転弧長は 円筒の回転分 aαだけ少なくなるから
bφ=aθ+bθ-aα=(a+b)θ-aα・・・・・・・・・・⑤
となる。また、円筒の回転の運動方程式は
ma²α''=aF・・・・・・・・・・・・・・・・・⑥
となる。その他の運動方程式①~➂はそのまま成り立つ。
➂⑥から aα''=F/m=(b/2)φ'' となる。これを⑤を2回微分したものにこれを入れて、
αを消すと
bφ''=(a+b)θ''-(b/2)φ'' → bφ''=(2/3)(a+b)θ''
となり、➂に入れると
F=(m/3)(a+b)θ''
となる。これを①に入れると
m(a+b)θ''=mgsinθ-(m/3)(a+b)θ'' → (4/3)m(a+b)θ''=mgsinθ
この両辺にθ' を掛けて、積分し、θ(0)=θ'(0)=0 を使うと
(2/3)m(a+b)θ'²=mg(1-cosθ)
これを②に入れると
R=mgcosθ-(3/2)mg(1-cosθ)=(mg/2)(5cosθ-3)
を得る。円筒から離れるときは抗力が無くなる時なので、R=0 つまり
cosθ=3/5
となるときである。
以上
1. まえがき
ランダウの力学に次の記述があり、その意味が不明という疑問が載っていた。
2. 疑問
P6、「しかしながら、その系に関しては空間が一様かつ等方的であり、時間も一様で
あるというような基準系をつねに見出すことができるということがわかる。このよう
な系を慣性系という。その特別な場合として、この系てば、ある時刻に静止していた
自由な物体は、いつまでも静止し続ける。
ここで、自由に運動している質点の慣性基準系においてラグラジアンから二、三の
結論を出すことができる。空間と時間の一様性は、この関数が質点の位置ベクトル r、
時間 tをあらわには含まないということを意味する。すなわち、Lは v だけの関数であ
る。空間の等方性のため、ラグラジアンはベクトル v の方向に依存してはならない。
したがって、ラグラジアンは v の絶対値、すなわち、その2乗 v²=v² だけの関数とな
る:
L=L(v²) (3.1)
ラグラジアンが r によらないから ∂L/∂r=0. したがって、ラグランジュ方程式により
(d/dt)(∂L/∂v)=0
すなわち、∂L/∂v=const.一方、∂L/∂v は速度だけの関数であることから、また
v=const. (3.2)
でなければならない。」
と書かれているが、この記述から(3.2)が導かれる最後の理屈がわからないというので
あるが当然の疑問であり、この根拠を考えてみた。
3. 説明
要は
(d/dt)(∂L(v²)/∂v)=0・・・・・・・・・・①
から(3.2)を導けばよい。
はじめに、特殊な記法の注意として
∂L/∂v=Const. ⇒ <∂L/∂vx , ∂L/∂vy , ∂L/∂vz>=Const. ・・・・・②
のことである。ここで、<・>はベクトルを意味する。
すると L=L(v²), v=√(vx²+vy²+vz²) なので、
∂(v²)/∂vx=2v(vx/v)=2vx
となるから、
∂L(v²)/∂vx=(dL(v²)/d(v²)){∂(v²)/∂vx}=2(dL(v²)/d(v²))vx
となる。vy ,vz についても同様で
(∂L/∂v)=2(dL(v²)/d(v²))v
を得る。これを②に入れると
(dL(v²)/d(v²))v=Const.
を得る。ここで、 f(v²)=dL(v²)/d(v²) とおくと
f(v²)v=Const. ・・・・・・・・・・・③
となる。この両辺で自身の内積を取ると
f(v²)²v²=Const.
となる。左辺は v²のみの関数だから、v²=Const. を得る。これを➂に入れると
f(v²)≠0 ならば
v=Const.
を得る。
4. あとがき
簡単な記述なので、ランダウにとっては自明なことなのだろうか?
文献
力学 ランダウ、リフシッツ 理論物理学教程 東京図書㈱
以上
1. まえがき
あるサイトで以下の問題があった。とても難しかったが計算してみた。
2. 問題
図のように、水平な床の上に直方体の物体(台)aが載っている。台aの上面に小物体
bが載っており、小物体cと伸び縮みしない紐でつながっている。小物体cは台の角
にある滑車を通して、台の側面に垂らされている。
物体a,b,cの質量をそれぞれ、Ma, Mb, Mc とし、床と台や各物体間、滑車には摩擦
は無いとし、重力の加速度をgとする。このとき
(1) 台aを固定する。物体b,cがcの落下に対応して、運動しているとき、台が床から
受ける抗力を求めよ。
(2) 台aに力Fを加えて、一定加速度Aの運動をさせた。このとき、物体b,cがCの落下
に対応して、運動しているとき、物体cの落下の加速度を求めよ。
3. 計算
(1) 糸の張力をT、床の垂直抗力をNとすると、床の垂直方向の釣合は
N=Mag+Mbg+T=(Ma+Mb)g+T・・・・・(3.1)
なお、Tは滑車を通してMaに加わる。
b,cの加速度の大きさは同じなので、Bとすると、b,cの運動方程式
MbB=T , McB=Mcg-T・・・・・・・(3.2)
からTを消して、
B=Mc g/(Mb+Mc)・・・・・・・(3.3)
これを前者に入れて、
T=MbMc g/(Mb+Mc)
(3.1) にいれて、
N=(Ma+Mb)g+MbMc g/(Mb+Mc)={Ma+Mb+MbMc/(Mb+Mc)}g・・・(3.4)
となる。
(2) 加速度Aの座標系でbの運動方程式は、慣性力は -MbA なので
MbB=T-MbA
となる。b,cの加速度の大きさは同じなので、cの運動方程式は
McB=Mc g-T・・・・・・(3.5)
となる。これらを加えて、Tを消すと、
(Mb+Mc)B=Mc g-MbA → B=(Mc g-MbA)/(Mb+Mc)・・・・・(3.6)
となる。
加速度系でのMbの加速度Bは、Mcの加速度としては、静止系の垂直方向の加速度
と同じとなる。
例として、Ma=10M[kg], Mb=3M[kg], Mc=2M[kg], A=0.1g[m/s²] のとき、(3.4)(3.6)
から
N=(71/5)Mg , B=(17/50)g
となる。
4. その他の計算
(1) aが静止している場合、aとcの抗力をSとすると、aの運動方程式は
MaA=F-S-T , McA=S
となるが、a,cは水平方向で静止しているから、A=0 となり
S=0 , F=S+T=T
となる。また、(3.2)の前者と(3.3)から T=MbMc g/(Mb+Mc) なので
S=0 , F=T=MbMc g/(Mb+Mc)
となる。
(2) aが加速度Aで運動する場合、aとcの抗力をSとすると、aの運動方程式は
MaA=F-S-T , McA=S・・・・・(3.7)
となる。(3.5)(3.6)から、
T=Mc g-McB=Mc(g-B)=Mc{g-(Mc g-MbA)/(Mb+Mc)}
=MbMc(g+A)/(Mb+Mc)
となるから、これを(3.7)に入れて
S=McA
F=MaA+S+T=MaA+McA+MbMc(g+A)/(Mb+Mc)
=(Ma+Mc)A+MbMc(g+A)/(Mb+Mc)
となる。
4. あとがき
2項の(2)の問題は、始め静止系で考えたが困難だった。
以上
1. まえがき
図のように、壁と楔の釣合の問題があった。
2. 問題
図のように壁に接した質量Mの物体に向かって、床に置かれた質量mの楔を押し込む場合を考える。
この場合の最小の力Fを求める。
図ように、M,mの重力 Mg,mg、押込む力F、各面の抗力N₁,N₂.N₃、各面の摩擦S₁,S₂,S₃だけの
水平と垂直成分のつり合いだけを考えればよい。ここで
S₁=μ₁N₁, S₂=μ₂N₂, S₃=μ₃N₃
である。
1.1 mのつり合い
水平 F=S₁+N₂sinθ+S₂cosθ=μ₁N₁+N₂sinθ+μ₂N₂cosθ=μ₁N₁+(sinθ+μ₂cosθ)N₂
垂直 mg=N₁-N₂cosθ+S₂sinθ=N₁-N₂cosθ+μ₂N₂sinθ=N₁-(cosθ-μ₂sinθ)N₂
これから、N₁を消して
F=μ₁{mg+(cosθ-μ₂sinθ)N₂}+(sinθ+μ₂cosθ)N₂
=μ₁mg+{μ₁(cosθ-μ₂sinθ)+(sinθ+μ₂cosθ)}N₂
=μ₁mg+{(μ₁+μ₂)cosθ+(1-μ₂)sinθ}N₂ ・・・・①
1.2 Mのつり合い
Mが上に動くためには
水平 N₃=N₂sinθ+S₂cosθ=N₂sinθ+μ₂N₂cosθ=(sinθ+μ₂cosθ)N₂
垂直 Mg<N₂cosθ-S₂sinθ-S₃=N₂cosθ-μ₂N₂sinθ-μ₃N₃=(cosθ-μ₂sinθ)N₂-μ₃N₃
これからN₃を消してN₂を求めると
N₂>Mg/{cosθ-μ₂sinθ-μ₃(sinθ+μ₂cosθ)}
=Mg/{(1-μ₂μ₃)cosθ-(μ₂+μ₃)sinθ}・・・・・②
①②から
F>μ₁mg+{(μ₁+μ₂)cosθ+(1-μ₂)sinθ}Mg/{(1-μ₂μ₃)cosθ-(μ₂+μ₃)sinθ}・・・・③
となる。ここで、③の分母は
(1-μ₂μ₃)cosθ-(μ₂+μ₃)sinθ>0 ・・・・④
の必要がある。つまり、
tanθ<(1-μ₂μ₃) /(μ₂+μ₃) ・・・・・⑤
となる。もしこれを満たさなければ、いかなるFでも、Mを上に押し上げる力は発生せずMは固
定されたままとなる(概略、S₂の垂直成分がN₂のものより大きくなる)。
1.3 摩擦が無いとき(μ₁=μ₂=μ₃=0)
F>tanθMg
となる。このとき、⑤は無意味だが、元の➃が常に成り立っている。
1.4 θ=0゜のとき
③からF>μ₁mg+{(μ₁+μ₂)/(1-μ₂μ₃)}Mg となるが、これは間違いである。つまり、M,mの接
触面は水平なので、上下方向の移動は無い。つまり、S₃=0となり、②は
Mg=N₂cosθ-S₂sinθ+0=N₂
となる。①にいれると
F>μ₁mg+(μ₁+μ₂)Mg
となる。
なお、各面での静止摩擦条件は一部が破壊されてもすべての面で破壊されなければ静止しているの
で静止摩擦係数を使ってよい。
以上