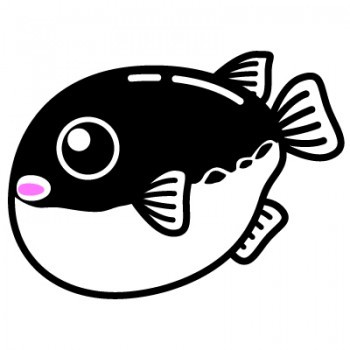1. まえがき
次のような特殊相対論の面白い問題があった。
慣性系Sの原点に静止したAがいる。BはS系で+x方向に速度 v=0.8c で運動するロケットに
乗っている。Bが x=0 を通過したとき、共に20才であることを確認した。
つぎに、Aが1年後、21才になった時、この歳 A1=21 をBに向かって光通信した。Bはこ
の信号を受けると当時に、自分の歳 A2 をAに向かって光通信した。Bはこの信号を受け
ると同時に、自分の歳 A3 をBに向かって、光通信した。
以上の手順を繰り返したときの一般項 An (n=1,2,…) を求めよ。
2. 計算
慣性系S'はS系に対して、+x方向に速度 vを持つとし、BはS'系の原点にいるとする。そし
て
β=v/c、γ=1/√(1-v2/c2)=1/√(1-β2)
とする。
S,S'系の時空をそれぞれ (x, t), (x',t') とする。nを奇数として、S系の時刻 tn にAからBに向
けて光を発射して、S系の時刻 tn+1 にBに到達したとする。
このとき、BのS系での座標を xn+1 とする。すると
xn+1=vtn+1
tn+1=tn+xn+1/c=tn+βtn+1 → tn+1=tn/(1-β)
すると
xn+1=(v/(1-β))tn
この時、S'系の時刻は(返信してくるBの年齢)
t'n+1=γ{ tn+1-(β/c)xn+1 }=γ{ tn/(1-β)-(β/c)(v/(1-β))tn }
=γ{ tn/(1-β)}{1-(β/c)v }=γ(1+β)tn =( √{(1+β)/(1-β)} )tn
=ktn
ここで
k=√{(1+β)/(1-β)}=√(1.8/0.2)=3
と置いた。
Bは信号を受けると同時に(S系で時刻 tn+1)、Aに向けて、返信するので、これが Aに届く、
S系の時刻 tn+2 は
tn+2=tn+1+xn+1/c=tn/(1-β)+(v/(1-β))tn/c={(1+β)/(1-β)}tn=k2tn
まとめると
n:奇数
t'n+1=ktn
tn+2=k2tn
ここで、t1=1 (1年後なので、原点合わせから)となる。
この数列 tn は簡単に解けて
n:奇数
tn=(k2)(n-1)/2 t1=k(n-1)=3(n-1)
t'n+1=(k2)n/2=3n
により、順次時刻が決定される。
これを An にすると、原点合わせの時、共に20歳だったから
n:奇数
An=tn+20=3(n-1)+20
An+1=t'n+1+20=3n+20
となるが、偶奇で分けずとも
An=tn+20=3(n-1)+20 (n=1,2,…)
となる。
実際の数値は
A1 A2 A3 A4 A5 A6
A 21 29 101
B 23 47 263
以上