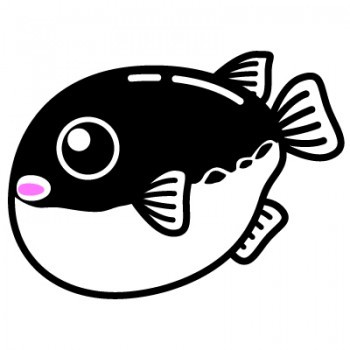1.問題
(1) 関数 g(t) (t∈R)を
g(t)=∫01 |x-t|n dx
と定義する。このとき、g(t)の最小値とその時の tを求めよ。
(2) f(x) (x∈[0,1]) を連続関数とする。このとき
∫01 xk f(x) dx=0 (k=0,1,・・・,n-1)・・・・・①
を満たすとき、
∫01 (x-t)n f(x)dx=∫01 xn f(x)dx・・・・・・②
が成立することを示せ。
(3) ①の条件のもと、f(x) (x∈[0,1]) の最大値をMとすれば
|∫01 xn f(x)dx| ≦ M/{ (n+1)2n }
が成立する。
2.証明
(1)
(a) x∈[0,1], t<0 とすると、
0≦xn<|x-t|n
なので、g(t)≧g(0) (t<0) となる。
(b) t>1 → t-x>1-x、ここで、0≦x≦1 なので t-x>0, 1-x≧0 だから
→ |t-x|>|1-x| → |x-t|>|x-1| → |x-t|n>|x-1|n
積分して
∫01 |x-t|ndx >∫01 |x-1|ndx → g(t)>g(1) (t>1)
(c) 上の(a)(b)から、g(t)の最小値は 0≦t≦1の間にある。0≦t≦1 とする。
g(t)=∫01 |x-t|ndx=∫0t |x-t|ndx +∫t1 |x-t|ndx
=∫0t (t-x)ndx +∫t1 (x-t)ndx
(0≦x≦t → |x-t|=t-x , t≦x≦1 → |x-t|=x-t なので)
=(1/(n+1)){ [-(t-x)n+1]t0 + [(x-t)n+1]1t
=(1/(n+1)){ tn+1 + (1-t)n+1 }
g'(t)=tn - (1-t)n=0 → t=1-t → t=1/2
g''(t)=n{tn-1 + (1-t)n-1}≧0
したがって、g(t) は t=1/2で最小となり
g(1/2)=(1/(n+1)){ (1/2)n+1 + (1/2)n+1 }=1/{(n+1)2n} ・・・・・・③
となる。
(2)
①が成り立つから (x-t)n を展開すれば②のせいりつは自明。
(3)
A=|∫01 xn f(x)dx|=|∫01 (x-t)n f(x)dx|
≦∫01 |x-t|n |f(x)|dx ≦ M∫01 |x-t|n dx = Mg(t)
上の不等式は 任意のtについて成り立つから、①によりg(t)の最小、g(1/2)を取れ
ばよい。つまり
A≦Mg(1/2)=M/{(n+1)2n}
となる。
以上