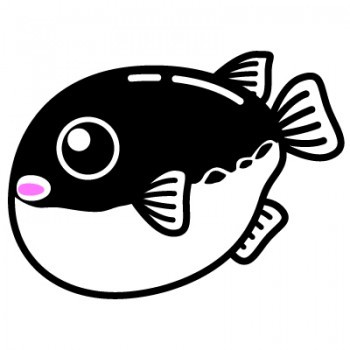1. まえがき
G(x,y)=x²+y²-12≦0 のもとで、F(x,y)=x³-y³+3(x-y)² の最大最小を求む、という問題があっ
た。計算がとても面倒だった。
2. 計算
極値の判定は面倒なので、有界閉領域には必ず最大・最小が存在し、微分可能な関数では、最大・
最小は極値にもなるから、求めた停留点の候補から、F(x,y)の最大・最小を選べばよい。
まず、G(x,y)=x²+y²≦12 の内部と境界で別々に検討する。
2.1 内部、G(x,y)<0
内部の停留点はF(x,y)を微分して
Fx=3x²+6(x-y)=0, Fy=-3y²-6(x-y)=0 から 6(x-y) を消して、x²=y² → y=±x をえる。
これを再度 Fx=0 に入れると、x=0 or x(x+4)=0 → x=0 or x=-4 をえる。さらに、Fx=0
にいれると、x=y=0 or x=-4, y=4 を得る。
後者の候補は、G(x,y)<0 を満たさず、領域外なので、内部の候補は
F(0,0)=0・・・・・・・・①
のみとなる。
2.2 境界、G(x,y)=0
境界の停留点はラグランジュの乗数法を使う。
Fx-λGx=3x²+6(x-y)-λ2x=0, Fy-λGy=-3y²-6λ(x-y)-λ2y=0・・・・・②
2つの式を加えて 6λ(x-y) を消すと 3x²-3y²-2λ(x+y)=0 → (x+y)(3(x-y)-2λ)=0 →
y=-x or 2λ=3(x-y)・・・・・・・③
を得る。前者は G(x,y)=0 に入れて
x=±√6 , y=∓√6 (複合同順)
を得る。このとき、
F(±√6,∓√6)=±6³/²-(∓6³/²)+3(±√6-(∓√6))²=±2・6³/²+12・6
=±12√6+72・・・・・・④
③の後者は➁の前者に入れてλを消すと
2(x-y)+xy=0 → x=2y/(y+2)
となる。これを G(x,y)=0 に入れて、xを消すと
y⁴+4y³-4y²-48y-48=0 → (y²-2y-4)(y²+6y+12)=0
となるが、y²+6y+12=(y+3)²+3>0 なので、解は y²-2y-4=0 となる。これは
y=1±√(1+4)=1±√5
をえる。G(x,y)=0 に入れると
x²=6∓2√5=1∓2√5+5=(1∓√5)² → x=±(1∓√5)
をえる。まとめると
x=±(1∓√5) , y=1±√(1+4)=1±√5 (複合同順)
である。このとき、
(1±√5)³=1+3(±√5)²+3(±√5)+(±√5)³=1+15±3√5±5√5=16±8√5
なので、
F((1∓√5),1±√5)=60∓16√5・・・・・・⑤
F(-(1∓√5),1±√5)=F(-1±√5,1±√5)=-20・・・・⑥
となる。
以上の、①➃⑤⑥の中から最大・最小を選ぶと
最大・・・・F(√6,-√6)=12√6+72 (>60+16√5)
最小・・・・F(-1±√5,1±√5)=-20 (複合同順)
となる。
以上
つぎの自作問題というものがあった。
[問題]x+y+z=1、x,y,z≧0 と実数の定数Nに対し、実関数f(x,y,z)=xy+yz+zx+Nxyz のとりう
る値の範囲を求めよ。
[解]fは有界閉集合上の連続関数だから、最大最小が必ず存在する。したがって連続関数fの範囲は
その最大最小の範囲なので、これ等を求めればよい。ラグランジュの未定乗数法を使う。
これによって求めた、停留点は上の閉集合の内部であるから、まず、境界の最大最小を求めて
おき、ラグランジュの結果と比較して、最大最小を求める。
1. 境界の評価。
x+y=1 , z=0 の境界を考えると f=x(1-x) なので
0≦f≦1/4・・・・①
となる。 対称性から、他の境界も同じとなる。
2. ラグランジュの結果(領域の内部の評価)
λを消してまとめると (x-y)(1+Nz)=(y-z)(1+Nx)=(z-x)(1+Ny)=0
を得る。すなわち、(x-y)=(y-z)=(z-x)=0 を選ぶと
x=y=z(=1/3)・・・・②
となる。他の選び方により
x=y かつ 1+Nx=1+Ny=0・・・・③
または
y=z かつ 1+Ny=1+Nz=0 ・・・・④
または
z=x かつ 1+Nz=1+Nx=0・・・・⑤
がある。
2.1 N≧0 のとき
N≧0 のときは x,y,z≧0 のため、1+Nx などは正となり、③➃⑤がなりたたず、条件は②
のみになり、
x=y=z=1/3
となる。
f≧0 は明らか。 f(1,0,0)=0 なので、f=0が最小値。
f(1/3,1/3,1/3)=3/9+N/27=1/3+N/27
すると①と比較して
(1/3+N/27)-1/4=1/12+N/27>0
なので、
0≦f≦1/3+N/27
2.2 N<0 のとき
③の条件、x=y かつ 1+Nx=1+Ny=0 のとき、x=y=-1/N, z=1-2x=1+2/N となる。
すると
f=1/N²+2(-1/N)(1+2/N)+N(1/N²)(1+2/N)=-(1/N+1/N²)
対称性から、➃⑤の時も同様。
以上から
a=min{0,1/3+N/27,-(1/N+1/N²)}
b=max{1/4,1/3+N/27,-(1/N+1/N²)}
とおくと
a≦f≦b
となる。
以上
問:a,b,cを正の実数とし、a≠bとする。点(c,0)と楕円(x/a)²+(y/b)²=1
上の点の距離の最大値を求めよ。
解:楕円上の点(x,y)と点(c,0)との距離は L=√{(x-c)²+y²}
g=(x/a)²+(y/b)²-1 ・・・・①
とする。
x-c=λx/a² → x=ca²/(a²-λ)・・・・➁
かつ
y=λy/b² → y(1-λ/b²) → y=0 or λ=b² ・・・③
である。場合分けすると
1.
③の y=0 のとき、➁は無関係で①から x=±a
2.
③のλ=b²のときは②から x=ca²/(a²-b²) ・・・・④
➀から y=±b√(1-x²/a²) となる。ただし、このときは、|x|≦a であり、④から
c≦|a²-b²|/a・・・・・⑤
の範囲となる。計算を続けると
y=±b√{1-c²a²/(a²-b²)²)}・・・・⑥
3.
以上で最大値の候補が4つ見つかったので、それぞれの値を計算して最大のものを選べば
よい。
1.の場合
L=√{(±a-c)²+0}=|a∓c| なので、
大きい方は L₁=(a+c) (x=-aのとき)・・・・⑦
2.の場合
L₂=√[ {ca²/(a²-b²)-c}²+b²{1-c²a²/(a²-b²)²} ]
=b√[ {c²b²+(a²-b²)²-c²a²}/(a²-b²)² ] = b√[ {-c²(a²-b²)+(a²-b²)²}/(a²-b²)² ]
=b√[ {-c²+(a²-b²)}/(a²-b²) ]=b√{1-c²/(a²-b²)}・・・・⑧
結局、⑦⑧の内、最大のものを選べばよい。この計算のため、a,bの大小の場合分けを
して考察する。
4. a>b の場合
L₂が存在すると仮定すると⑤を満たすから、c²/(a²-b²)≦(a²-b²)/a² となり⑧のルート
内は 1-c²/(a²-b²)≧1-(a²-b²)/a²=b²/a²>0 となり、L₂は存在する。そして
c²/(a²-b²)>0 であるから、⑧は
L₂<b(√1)<a<a+c=L₁
となって、最大値は⑦から1点
L₁=a+c , (x=-a,y=0)・・・・・⑨
となる。
5. a<b の場合
L₂のルート内は常に正でL₂は⑤を満たせば、存在する。そこで、A=L₁²-L₂² を考えると
A=(a+c)²-b²{1-c²/(a²-b²)}={1+b²/(a²-b²)}c²+2ac+(a²-b²)
ここで、B={1+b²/(a²-b²)}=a²/(a²-b²)<0 とおくと
A=B(c-a/B)²
となる。ここで、c-a/B>0、つまり、c-a/B≠0 だから
A=B(c-a/B)²<0
となる。
結局、A<0 , L₁<L₂となり、最大は⑧から L₂=b√{1-c²/(a²-b²)} となる。このとき、
④⑥から、Lの最大値は2点
x=ca²/(a²-b²) 、y=±b√{1-c²a²/(a²-b²)²)}
となる。
ただし、⑤を満たさないとき、L₂は存在しないので、最大値は L₁、つまり、⑨となる。
以上
1. はじめに
f(x,y)=sin(x)+sin(y)+sin(x+y) (0≦x,y<2π・・・・①)
の極値を求める問題があった。この場合、鞍点や変曲点の判定が難しかったので考察した。
最大最小値の問題は以前にあったが、有界閉集合上の連続関数は必ず、最大最小が存在し、
微分可能関数なら、極値でもあるので、停留点の候補を比較すればよく簡単だった。
2. 計算
まず、停留点は
fx=cos(x)+cos(x+y)=0、fy=cos(y)+cos(x+y)=0・・・②
であり、
fxx=-sin(x)-sin(x+y)、fyy=-sin(y)-sin(x+y)
fxy=-sin(x+y)
である。
まず、②の2式は和積の公式から
cos(x+(y/2))cos(y/2)=cos(x/2+y)cos(x/2)=0
これを解くと
x+(y/2)=π/2+mπ または、y/2=π/2+nπ・・・・④
かつ
x/2+y=π/2+kπ または、x/2=π/2+pπ ・・・・⑤
を得る(m,n,k,p は整数)。
つまり、これを分解整理すると、つぎの4種類になる。
x+(y/2)=π/2+mπ かつ x/2+y=π/2+kπ・・・⑥
または
x+(y/2)=π/2+mπ かつ x/2=π/2+pπ ・・・⑦
または
y/2=π/2+nπ かつ x/2+y=π/2+kπ・・・⑧
または
y/2=π/2+nπ かつ x/2=π/2+pπ ・・・⑨
の場合を解けばよい。
2.1 ⑥を整理すると
x=π/3+(2m-k)2π/3、y=π/3+(2k-m)2π/3
となる。このとき、①の条件から、x の (2m-k) は 0,1,2 しか無い。
(a) 2m-k=0 のとき
x=π/3, y=π/3+(3m)2π/3=π/3+2πm=π/3 (①からm=0のみ)
fxx=fyy=-√3、 fxy=-(√3)/2 , fxx
なので、f(π/3,π/3)=(3√3)/2 で極大。
(b) 2m-k=1 のとき
x=π、y=y=π/3+(3m-2)2π/3=-π+2πm=π (①からm=1のみ)
fxx=fyy=fxy=0 なので判別式は使えない。そこで、x=y の方向のf の変化を考える。
f(x,x)=2sin(x)+sin(2x)=2sin(x)(1+cos(x))=sin(x)cos²(x/2)
なので(ここで、倍角・半角の公式を使用した)、x=πの前後で sin(x) によって、f()の
符号が変化する。つまり、この場合は極値ではない。
なお、変化方向として、y=π, x=π, y=2π-x のいずれも f=0 となるので、簡単なものは
上の場合しかない。
(c) 2m-k=2 のとき
x=5π/3, y=π/3+(3m-2)2π/3=-7π/3+2πm=5π/3 (①からm=2のみ)
fxx=fyy=√3、 fxy=(√3)/2 , fxx>0, fxxfyy-fxy²=3-3/4>0
なので、f(5π/3,5π/3)= -(3√3)/2 で極小。
2.2 ⑦を整理すると
x=(2p+1)π, y=-π+(m-2p)2π となり、➀の条件を満たすものは p=0 のみ。つまり、
x=π、y=-π+2mπ=π (①からm=1のみ)
したがって、この条件は x=y=πで、2.1項の(b)と同じとなる。
⑧の場合は、⑦でx,yを変更しただけの式であるが、⑦の結論は x=y=π だから、ここの結
論と同じになる。
2.3 ⑨を整理すると
y=π(1+2n) かつ x=π(1+2p)
となり、いずれも、①を満たすのは n=p=1 の場合のみで、x=y=π となり、2.2項と同じ
結論となる。
結局、極値は 2.1項の(a)(c)のみとなる。そして、これが最大最小値でもある。
以上