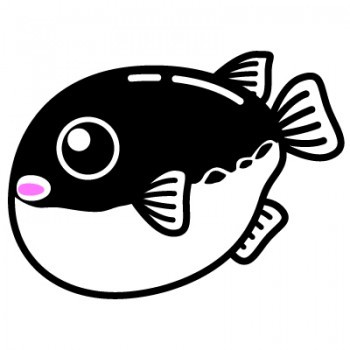1.まえがき
座標系の原点をOとする。直線l: y=3x/4 上の点A(4,3)で、lに接する円をC₁とする。
C₁は +x軸とも接する。円C₂は直線lについて円C₁と線対象である。円C₁上の点Pが点A
について点対称のC₂上の点をQとする。
このとき、円C₁の式と、三角形OPQの面積が 25/3 となるとき、直線 PQの傾きを求め
よ。
2.計算
(1) C₁の式
円C₁の中心を(a,b)とする。つまり
C₁: (x-a)²+(y-b)²=b²・・・・・①
となる。これをxで微分して、この円の接線の傾きy'は
x-a+(y-b)y'=0 → y'=-(x-a)/(y-b)
となる。
これが、A(4,3)でlと接すると傾きは 3/4になるから
y'=-(x-a)/(y-b)=-(4-a)/(3-b)=3/4 → 4a+3b=25・・・・②
また、AはC₁上にもあるから、①により
(4-a)²+(3-b)²=b²
となり、②を入れてbを消すと
a²=25 → a=5 (>0)
を得る。②から
b=5/3
ゆえに
C₁: (x-5)²+(y-5/3)²=(5/3)²・・・・・③
(2) 直線PQの傾き
点対称だから、長さ QA=AP であり、3角形 OAQとOAP の面積は等しい。だから
求める3角形OPQの面積Sは、ベクトルOP=<x,y> と OA=<4,3> の外積で表される
平行四辺形の面積だから
S=|<x,y>×<4,3>|=|3x-4y|=3x-4y=25/3
となる(この順のベクトル積は+z方向となり、3x-4y≧0)。これに、④を入れると
y=3x/4-25/12・・・・・⑤
これを③に入れてまとめると
x²-10x+25+(3x/4-25/12-5/3)²=25/9 → x²-10x+25+(3x/4-15/4)²=25/9
→ (1+9/16)x²-(10+45/8)x+25+(15/4)²-25/9=0
→ 25x²-250x+16・25+15²-16・25/9=0 → x²-10x+16+15²/25-16/9=0
→ x²-10x+209/9=0 → x=5±4/3=11/3, 19/3
⑤にいれて
(x,y)=(11/3,2/3), (19/3,8/3)
PQの傾きmは
(11/3,2/3)のとき m=(3-y)/(4-x)=7
(19/3,8/3)のとき m=(3-y)/(4-x)=-1/7
3.あとがき
上のように、2つの傾きは直行している。AP、AQが円の直径と一致するとき、3角
形OPQの面積は最大
OA・AP=5・(5/3)・2=50/3
となる。PQの角度が時計・反時計回りの2方向に変化していくとき3角系の面積は
0になっていく。
以上
1.まえがき
円錐をある位置から見たときの円錐のシルエットとしての母線の位置を求める問題が
あった。ある視点を定め、ここから線を引いた時、円錐の側面に接する点の軌跡とす
る。
2.設定
円錐の高さを h、底面の半径を a、視点の座標を (x,0,z) (z≧0)とする。円錐の接平面上
の母線が底面において、x軸とのなす角をθとする。
3.計算
この軌跡は、次の考察から円錐の母線(直線)となる。図において y=0 の位置から、
左右に対象の位置で円錐の側面に平面を張付けたとすると、これは円錐の接平面とな
る。この2つの接平面の交線は直線となる。その交線上の1点を通る、接平面上の直
線は円錐に接し母線を形成する。つまり、母線は直線となる。
x-z平面での接平面の式は
z=-(h/a)x+h (y=0)・・・・①
となる。x軸から角度をθとするとxy平面の回転によって、θの位置の切平面の式は
z=-(h/a)(xcosθ-ysinθ)+h・・・・②
となる。
この平面の ±θの位置の2つは②を整理して
xcosθ-ysinθ+(a/h)z-1/a=0
xcosθ+ysinθ+(a/h)z-1/a=0
となり、この2つの平面の交線の方向比 (l,m,n) は公式から
l=-sinθ a/h-(a/h)sinθ = -2(a/h)sinθ
m=-{cosθ a/h-(a/h)cosθ} = 0
n=cosθsinθ+sinθcosθ = 2sinθcosθ
となる。
またこの直線は必ず、円錐の頂点 (0,0,h) を通るのでこの接線の式は
x/{-2(a/h)sinθ} = y/0 = (z-h)/2sinθcosθ
→ z=-(h/a)cosθ x+h (y=0)
となる(この直線上のどの位置から見ても母線は同じ)。
したがって、(x,0,z) の位置から見た、θは
cosθ=(a/x)(1-z/h)
となる。
この式から、z>h のときは、θ>π/2、つまり、円錐の裏
側に回り込む。
4.検討
なお、z>h(1+x/a) のとき、cosθ<-1となり、解は無いが、このとき視点から見える
のは、円錐の底面なので、楕円が見える。また、a/x≦1 なので、z の下限に制限は
無い。
以上
N個の各質点の位置ベクトルと質量をri, mi とすると重心R は
R=Σi=1N mi ri/M (M=Σi=1N mi )
となる。この重心から見たと各点の距離ベクトルは
ri -R={ Σj=1N mj (ri -rj) }/M
となる。各点間の距離
|ri -rj|=ℓij 、(当然、ℓij =ℓji 、ℓii =0 )・・・・・・・①
とすると、重心からの各点までの距離 |ri -R| が、mi と ℓij によって表されることを示す。
2. 計算
(1) 一般の場合
|ri -R|²=(ri -R)・(ri -R)=(1/M²) { Σj=1N mj (ri -rj) }・{ Σk=1N mk (ri -rk) }
=(1/M²) Σj=1N Σk=1N mj mk (ri -rj)・(ri -rk)
=(1/M²) Σj=1N Σk=1N mj mk ( ri²- ri ・rk -rj・ri+rj・rk )・・・・②
ここで、
ℓij²=(ri -rj)・(ri -rj)=ri²+rj²-2ri・rj → ri・rj=( ri²+rj²-ℓij² )/2
これを②に入れると
|ri -R|²=(1/M²) Σj=1N Σk=1N mj mk
{ri²- ( ri²+rk²-ℓik² )/2 - ( ri²+rj²-ℓij² )/2+ ( rj²+rk²-ℓjk² )/2 }
=(1/M²) Σj=1N Σk=1N mj mk (ℓik² + ℓij² - ℓjk²)/2
となる。つまり
|ri -R|=(1/M) √ { Σj=1N Σk=1N mj mk (ℓik² + ℓij² - ℓjk²)/2 }・・・・・③
(2) mi =m のときは
|ri -R|=(1/N) √ { Σj=1N Σk=1N (ℓik² + ℓij² - ℓjk²)/2 }
=(1/N) √ { (NΣj=1N 2ℓik² - Σj=1N Σk=1N ℓjk²)/2 }
=(1/N) √ { NΣj=1N ℓik² - (Σj=1N Σk=1N ℓjk²)/2 }・・・・・④
となる。ここで、
Σj=1N Σk=1N ℓik² =Σj=1N Σk=1N ℓij² =NΣj=1 ℓij²
となることを使った。
3. 検証
(1) N=2 のときは
|ri -R|=(1/M)√{m1²ℓi1²+m1m2(ℓi1²+ℓi2²)+m2²ℓi2²-m1m2ℓ12²}
ここで、①から、
m1m2(ℓi1²+ℓi2²)-m1m2ℓ12²=0、m1²ℓi1²+m2²ℓi2²=m(3-i)²ℓ12²
となるから、
|ri -R|=(1/M)m(3-i)ℓ12 (i=1,2 のとき、(3-i)=2,1 となる)
(2) N=6、mi =m かつ 各質点が正6角形の配置の時
反時計回りに、質点の番号を順にとる。ℓ12 =ℓi(i±1) =ℓ とする。
④から
|ri -R|=(1/6)√{ 6(2ℓ²+2(√3ℓ)²+(2ℓ)²) - 6(2ℓ²+3(2√3ℓ)²+(2ℓ)²)/2 }
=(1/6)√{ 3(12ℓ²) } =ℓ
以上
1. まえがき
2つの平面から等距離にある点の集合を求める問題があった。
2. 計算
a,b,x,x₀をベクトルとし、c,dを定数とする。(x|y) を内積とすると、平面 (a|x)=c, (b|x)=d
と点x₀との距離は公式より
|(a|x₀)-c|/|a|, |(b|x₀)-d|/|b|
となる。したがって、
|(a|x₀)-c|/|a|=|(b|x₀)-d|/|b|
がなりたつ。これは
{(a|x₀)-c}/|a|=±{(b|x₀)-d}/|b| → (a/|a|∓b/|b||x₀)=c/|a|∓d/|b|
となるから、x₀ → x として、つぎの平面となる。
(a/|a|∓b/|b||x)=c/|a|∓d/|b| (複合同順)・・・・①
2.1 a/|a|=b/|b| かつ c/|a|=d/|b| のとき(同一平面のとき)
(a|x)=c に平行な平面であればよいから
(a|x)=e (∀e) の平面
2.2 a/|a|=b/|b| かつ c/|a|≠d/|b| のとき(平面が平行のとき)
①のマイナスは 0=c/|a|-d/|b| となって、成り立たないのでプラス符号の
2(a/|a||x)=c/|a|+d/|b| → (a|x)=(c+d|a|/|b|)/2
の平面。これは、2つの平面の間の中間にある。
2.3 a/|a|≠b/|b| かつ c/|a|≠d/|b| のとき(平面が交差するとき)
①の2つの平面となる。
この2つの平面の法線ベクトルはそれぞれ
a/|a|+b/|b| , a/|a|-b/|b|
だから、この内積を取ると
(a/|a|+b/|b| | a/|a|-b/|b|)=(a|a)/|a|²-(b|b)/|b|²=1-1=0
となり、この平面は直交している。
以上
1. まえがき
ベクトル空間にN個の点 {ri} があったとき、
R=(Σi=1N ri )/N ・・・・・・・・①
ri* =ri-R ・・・・・・・・・・・②
とおくとき、
|ri-rj|=C (>0 の定数、i≠j) ・・・・③
を満たすとき
ri*=rj* (ri*=|ri*|)・・・・・・・・・・・④
が成立つことを示す問題があった。
これは、正多面体(?)の重心 R から各頂点 ri への距離 ri* が等しいことを示すもの
となる。
2. 計算
➁から簡単に
ri*-rj* =ri-rj
とわかるから、➂を使って
C²=|ri-rj|²=(ri-rj)・(ri-rj)=(ri*-rj*)・(ri*-rj*) = ri*²+rj*²-2ri*・rj* (i≠j)
→ ri*・rj* = (1/2)( ri*²+rj*²- C² ) (i≠j) ・・・・・⑤
また①②から
Σi=1N ri* = Σi=1N ri-Σi=1N R=NR-RN=0
すると
ri*= -Σk=1N[k≠i] rk*
となる。
ri*²=ri*・ri* =(Σk=1N[k≠i] rk*)・(Σl=1N[l≠i] rl*) = Σk=1N[k≠i] Σl=1N[l≠i] rk*・rl*
=Σk=1N[k≠i] rk*² + ( Σk=1N[k≠i] Σl=1N[l≠i] )[k≠l] rk*・rl*
このとき、右辺第2項で k≠l だから⑤により
=Σk=1N[k≠i] rk*² + (1/2){ ( Σk=1N[k≠i]Σk=1N[l≠i] )[k≠l] (rk*²+rl*²-C²) }
=Σk=1N[k≠i] |rk*|² + (1/2){ Σk=1N[k≠i](Σk=1N[l≠i,k≠l] rk*²)
+Σk=1N[l≠i](Σ[k≠i,k≠l] rl*²) - Σk=1N[k≠i](Σ[l≠i,k≠l] C² }
=Σk=1N[k≠i] rk*² + (1/2){ (N-2)Σk=1N[k≠i] rk*²)
+(N-2) Σk=1N[l≠i] rl*² - (N-1)(N-2)C² }
=Σk=1N[k≠i] rk*² + (N-2)Σk=1N[k≠i] rk*² - (N-1)(N-2)C²/2
=(N-1)Σk=1N[k≠i] rk*² - (N-1)(N-2)C²/2
= -(N-1)ri*² + (N-1)Σk=1N[k] rk*² - (N-1)(N-2)C²/2
となり、ri*² をまとめると
N ri*²=(N-1)Σk=1N rk*² - (N-1)(N-2)C²/2
となり、結局
ri*²={ (N-1)/N }{ Σk=1N rk*² - (N-2)C²/2 } ・・・・・・・・⑥
となる。この右辺は i に無関係なので、左辺を i→j とすると
ri*²=rj*²={ (N-1)/N }{ Σk=1N rk*² - (N-2)C²/2 }
→ ri*=rj*
となり、➃を得る。
3. あとがき
なお、1、2、3次元のときは N=2,3,4 となり、⑥を用いると重心からの頂点への半径
ri* を求めることができる。ri* は等しいから、r* とすると
r*²={ (N-1)/N }{ Nr*² - (N-2)C²/2 } = (N-1)r*² - {(N-1)(N-2)/N}C²/2
→ r*=( √{(N-1)/2N} )C
したがって、N=2,3,4 のとき、r*=C/2, C/√3, (√(3/8))C となり、N → ∞ のとき、C/√2
となる。
以上