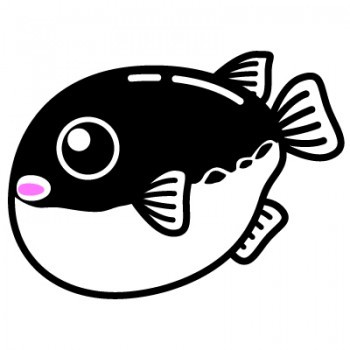1.まえがき
複素平面において、点A:(1,0)と複素数 zと z² の点をB,Cとする。3角形ABCが直角3角形の
時、点Bの軌跡を求む。また、3角形ABCに外接する円の中心の軌跡を求む。
2.z、点Bの軌跡
A,B 点の座標は
z=(x, y) → z²=(x²-y², 2xy)
である。
2.1 ∠B=90゜のとき
ベクトル AB=(x-1, y)と BC=(x²-y²⁻x, 2xy-y) は直交だから「・」を内積として
(x-1,y)・(x²-y²⁻x,2xy-y)=0 → x( y²+(x-1)² )=0
したがって
x=0 or y²+(x-1)²=0 → x=0 or (y=0かつx=1)
ところが、後者はA点なので
x=0
の直線のみ。つまり、y軸となる。そして
B: z=(0, y), C: z²=(-y², 0)
となる。ただし、y=0 のときは3角形を作らないので除外。
2.2 ∠A=90゜のとき
同様に、ベクトル AB=(x-1, y) と AC=(x²-y²-1, 2xy) は直交だから
(x-1, y)・(x²-y²-1, 2xy)=0 → (x+1)(y²+(x-1)²)=0
となり、上と同様3角形を作るには後者は除外し
x=-1
の直線のみとなる。そして
B: z=(-1, y) , C: z²=(1-y², -2y)
となる。ただし、y=0 のときは3角形を作らないので除外。
2.3 ∠C=90゜のとき
同様に、ベクトル BC=(x²-y²-x, 2xy-y)と AC=(x²-y²-1, 2xy) は直交するから
(x²-y²-x, 2xy-y)・(x²-y²-1, 2xy)=0 → (y²+x²-2x+1)(y²+x²+x)=0
→ (y²+(x-1)²)(y²+(x+1/2)²-1/4)=0
同様に、前者は3角形を作らないので除外できる。したがって
y²+(x+1/2)²=1/4
となり、(0, -1/2)を中心とする半径1/2の円となる。ただし、これも3角形を作るという
条件から、y=0 の2点は除外される。
2.4 まとめ
以上をまとめるとBつまり、zは図のような軌跡となる。円と2直線から2点を除いた
もの。

3.三角形ABCの外接円の中心の軌跡
A:(1,0)である。
3.1 ∠B=90゜のとき
x=0なので、
B:(0,y), C:(-y²,0)
このとき、直角3角形ABCに外接する円の直径はACとなるから、円の中心はACの中点
となる。素の座標を (X, Y) とすると
(X, Y)=( (1+y²)/2, 0 )
となる。この軌跡は yをパラメータとすると
X=(1+y²)/2, Y=0
つまり、yは実数の範囲で y≠0 だから
-∞<X<1/2
の直線となる。
3.2 ∠A=90゜のとき
x=-1 なので、
B:(-1,y), C:(1-y², -2y)
同様に、円の直径はBCとなるから、円の中心はBCの中点となる。その座標を (X, Y)
とすると
(X, Y)=(-y²/2, -y/2)
となる。この軌跡は yをパラメータとすると
X=-y²/2, Y=-y/2 → X=-2Y²
つまり、yは実数の範囲で y≠0 だから (0,0)を除いた放物線になる。
3.3 ∠C=90゜のとき
同様にABの中心の座標を (X, Y) とすると
(X, Y)=( (x+1)/2, y/2 )
となる。このとき、y²+(x+1/2)²=1/4 なので
Y=y/2 → Y²=(1/4-(x+1/2)²)/4
つまり
Y²=(1/4-(2X-1+1/2)²)/4=1/16-(X-1/4)² → (X-1/4)²+Y²=1/16
となり、これは円となる。同様に y≠0 から
(0, 0) , (1/2, 0)
は除かれる。
以上