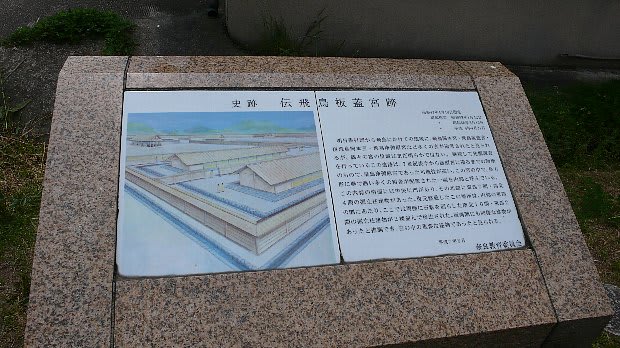施福寺を出て、次に向かうのは西国第五番の葛井寺です。国道170号線を北進していると「喜志」という
地名の表示板が見えてきました。喜志・・・喜志・・・、ん~何か聞き覚えのある地名やな~・・・と
考えていると、思い出しました。喜志は聖徳太子御廟のある叡福寺への最寄り駅の名前!・・・ということは
叡福寺はこの近くか? それでナビで調べてみると、その地点からわずか5kmほどの距離。これは参詣しなきゃ!
ということで急遽予定を追加して叡福寺に向かいました。では参拝記を。前回の参拝記はこちらで。
叡福寺の最寄り駅である近鉄喜志駅の周辺は一般的な商店街で人や車の往来が多い街である。以前訪れた
時にはだんじり祭の最中で勇壮なだんじりが駅前に繰り出していた。だんじりは岸和田のが有名であるが、
その周辺地域でも同様の山車が出る祭りが多くあるみたいだ。駅前には「聖徳太子磯長御廟」と刻まれた
立派な石柱が建っている。斑鳩のJR法隆寺駅前にも同様に「聖徳太子御旧蹟」と刻まれた石柱があるが、
どちらも聖徳太子ゆかりの地であることへの誇りがあらわれている。
喜志駅からは巡回バスが出ていて、これまでの参詣ではこのバスに乗車して叡福寺に向かったのだが
今回は自家用車。喜志駅あたりから数分して太子町内へと入りやがて叡福寺の多宝塔(重文)の相輪が見えてくる。
自家用車は門前脇駐車場が無料で利用できる。駐車場のみならず境内も開放されている。

南大門をくぐると広い境内一面に白砂がきれいに敷き詰められていて、いささか遠慮気味にその上を歩き
境内を進んで、まずは太子の本地仏である如意輪観音を本尊とする金堂や太子を本尊とする聖霊殿にお参り、
最後に正面奥の御廟所を参拝した。境内では植木職人さんが剪定をしていて、敷き詰められた白砂は
掃き清められている。美しく整えられた境内は聖徳太子御廟を守護するという叡福寺の務めの気持ちが現われて
いるようで、参詣する者にとってもある種の心地よい緊張感をもたらすのである。

叡福寺と道を挟んで正面の向かい合わせに新西国霊場札所である西方院がある。太子遷化の後に
3人の乳母たちがこの地で太子の菩提を弔ったという。

叡福寺のある太子町の東方は奈良県との県境で斑鳩とは直線距離にして10km超ほどである。
また北方には羽曳野・藤井寺・八尾があり旧国名では河内国だが、かつて蘇我氏と敵対した物部氏の
本領地があったため、両者の戦場ともなり、その由縁から太子ゆかりの寺院も多く点在する。
上之太子の叡福寺、中之太子の野中寺、下之太子の大聖勝軍寺をはじめ、蘇我稲目が建立したと
伝えられる西淋寺や菅公との縁もある道明寺などもこの地域にある。太子との結びつきが強い地域である。
参拝日時:平成21年11月28日(土)午前10時半~午前11時
「黒駒思いのままの記」←こちらも見てやってください。
 ←ポチッとお願いします。
←ポチッとお願いします。
地名の表示板が見えてきました。喜志・・・喜志・・・、ん~何か聞き覚えのある地名やな~・・・と
考えていると、思い出しました。喜志は聖徳太子御廟のある叡福寺への最寄り駅の名前!・・・ということは
叡福寺はこの近くか? それでナビで調べてみると、その地点からわずか5kmほどの距離。これは参詣しなきゃ!
ということで急遽予定を追加して叡福寺に向かいました。では参拝記を。前回の参拝記はこちらで。
叡福寺の最寄り駅である近鉄喜志駅の周辺は一般的な商店街で人や車の往来が多い街である。以前訪れた
時にはだんじり祭の最中で勇壮なだんじりが駅前に繰り出していた。だんじりは岸和田のが有名であるが、
その周辺地域でも同様の山車が出る祭りが多くあるみたいだ。駅前には「聖徳太子磯長御廟」と刻まれた
立派な石柱が建っている。斑鳩のJR法隆寺駅前にも同様に「聖徳太子御旧蹟」と刻まれた石柱があるが、
どちらも聖徳太子ゆかりの地であることへの誇りがあらわれている。
喜志駅からは巡回バスが出ていて、これまでの参詣ではこのバスに乗車して叡福寺に向かったのだが
今回は自家用車。喜志駅あたりから数分して太子町内へと入りやがて叡福寺の多宝塔(重文)の相輪が見えてくる。
自家用車は門前脇駐車場が無料で利用できる。駐車場のみならず境内も開放されている。

南大門をくぐると広い境内一面に白砂がきれいに敷き詰められていて、いささか遠慮気味にその上を歩き
境内を進んで、まずは太子の本地仏である如意輪観音を本尊とする金堂や太子を本尊とする聖霊殿にお参り、
最後に正面奥の御廟所を参拝した。境内では植木職人さんが剪定をしていて、敷き詰められた白砂は
掃き清められている。美しく整えられた境内は聖徳太子御廟を守護するという叡福寺の務めの気持ちが現われて
いるようで、参詣する者にとってもある種の心地よい緊張感をもたらすのである。

叡福寺と道を挟んで正面の向かい合わせに新西国霊場札所である西方院がある。太子遷化の後に
3人の乳母たちがこの地で太子の菩提を弔ったという。

叡福寺のある太子町の東方は奈良県との県境で斑鳩とは直線距離にして10km超ほどである。
また北方には羽曳野・藤井寺・八尾があり旧国名では河内国だが、かつて蘇我氏と敵対した物部氏の
本領地があったため、両者の戦場ともなり、その由縁から太子ゆかりの寺院も多く点在する。
上之太子の叡福寺、中之太子の野中寺、下之太子の大聖勝軍寺をはじめ、蘇我稲目が建立したと
伝えられる西淋寺や菅公との縁もある道明寺などもこの地域にある。太子との結びつきが強い地域である。
参拝日時:平成21年11月28日(土)午前10時半~午前11時
「黒駒思いのままの記」←こちらも見てやってください。