執事・メイド・従僕・使用人について。あらゆる作品が対象。出版元の詳細は記事中の作品名をクリック。amazonに行けます。
執事たちの足音
「MANOR HOUSE (マナー・ハウス)」の面白さ① 「エドワード朝」

「MANOR HOUSE 英國発 貴族とメイドの90日」
まずは、執事役のエドガー氏(上掲写真の男性)について一言いわせてください。
オノ・ナツメ氏描く「眼鏡の老紳士」にそっくりだ。(老境の色気)
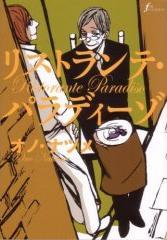 こちらがオノ・ナツメ氏の眼鏡の老紳士。
こちらがオノ・ナツメ氏の眼鏡の老紳士。『リストランテ・パラディーゾ』
や、先走ってしまった。
何のこっちゃ分らない方、わたくしがここ一ヶ月あまりどっぷり浸かっていたドキュメント・ドラマの話なんです。前のブログで「購入予約した!」と力んでいたあのDVD、「MANOR HOUSE 英國発 貴族とメイドの90日」です。
| 「MANOR HOUSE 英國発 貴族とメイドの90日」とは― 約8,000人のオーディションから選ばれた現代のイギリス人20名が、マナー・ハウス(領主の住む大邸宅)に集い、貴族と使用人に分かれて百年前の“エドワード朝時代”の階級社会を再現し、90日間を過ごす歴史再現ドキュメンタリー・ドラマ。イギリス・チャンネル4制作、2002年本国で放送。2007年5月25日、日本初DVD販売。 「MANOR HOUSE 英國発 貴族とメイドの90日」公式HP http://www.manorhouse.jp/ |
番組の原題はずばり、
“THE EDWARDIAN COUNTRY HOUSE”
華麗なエドワーディアンがどのような暮らしをしていたのか? またそのエドワーディアンの豪奢な暮らしぶりを支えるために、使用人たちがどのように働いていたのか? 当時の生活を21世紀の現代人がシミュレーション、疑似体験するのが目的の番組です。
このDVDを予約した当初は、
「メイドのコスプレした人たちが『エドワード朝時代の人たちって、こんなにタイヘンだったのねウフフ』なぁんて笑顔で感想言い合うような、創りの浅い体験ドラマだったら、ヤだなぁ~」と思っていたのです。じつは。
失礼しました。いや、侮ってました。
とことん当時を再現し尽くした、とんでもない歴史ドキュメンタリーでした。
だってあなた、当時の召使いたちに倣って、本当に一週間に一度しかお風呂に入らない(入れない)のですよっ! 生理用品(ナプキン)は布切れを細長く束ねてヒモを付けた、手作りの「ふんどし」みたいなモノですし。(←これは現代の女性にとって本当に辛いと思う)
汗ぺっとり、臭いわ、汚いわ。うら若きメイドの乙女たちが身体中ドロドロの状態で、疲れきった青白い顔して、這いつくばって床を磨いている。
「容赦ないな…」ここまでやるのか、と観てるこちらの胸が痛くなるほど。
これは「頭でエドワード朝を知る」ではなく「肌でエドワード朝を感じる」ドラマです。すごい。素晴らしい。購入した価値ありました。十二分に。
さて、次にわたくしなりの『マナー・ハウス』の面白さを、今回、次回と2回にわたって述べようと思います。
まずは、とっても根本的な事なんですが、
21世紀人がタイムスリップする時代が「エドワード朝」である、ということ。
「中流階級」がもっとも輝いていた時代です。
 エドワード朝という時代―礼儀作法(マナー)と規則(ルール)
エドワード朝という時代―礼儀作法(マナー)と規則(ルール)第一話で語られるナレーションの言葉、
「使用人は規則に、主人は礼儀作法に縛られます」いみじくもエドワード朝をよく表している言葉だと思います。
エドワード朝は「中流階級」が自信に満ちていた時代です。
「中流階級」はヴィクトリア朝時代に生れました。
かつて、社会的階級は「富める者」と「貧しき者」とに二分されていました。しかし産業革命により、商売で莫大な財を築いたブルジョワジーが登場したのです。
産業革命以後のブルジョワジーの財力はとんでもないものでした。
例えば、植民地から仕入れた材料を本国の大工場で生産し、出来上がった製品を植民地に原価の40倍ほどの値段で売っていました。商品一個の原価が1円がなら、一個につきおよそ4千円の売り上げです。こりゃ儲からないはずがありません。
莫大な財力を得たおかげで、ブルジョワジーは今まで交流し得なかった上流階級とのつながりを持てるようになりました。ギャンブルなどで手元が不如意になった上流階級が、ブルジョワジーに借金を申し入れるようになったのです。
(ギャンブルは上流階級の一大レジャーであり“遊びに賭けられるだけの余裕がある”という意味で、ギャンブルでの借金は恥ではなかった。)
上流階級とつながるブルジョワを単なる「商人」(下層階級に属する)とは呼びづらくなり「中流階級(ミドル・クラス)」または「上中流階級(アッパー・ミドル・クラス)」と呼ばれる階級が誕生したのです。
上昇志向の強い中流階級の人々は、そこで満足せず、さらに上を目指しました。たとえ金はうなるほどあっても、称号(タイトル)を持っていないのです。何だかんだ言っても称号による階級がものを言うのがイギリス社会。中流階級の人々は称号の獲得を夢見て、“立派なイギリス紳士” と自他ともに認められるように、余りあるお金を自分自身への投資に当てました。
名の通ったクラブ会員になる。チャリティーを行う。召使いを最低でも二人は雇う。そのために大きな屋敷に引っ越す―これら体面を保つための努力は“スノビズム(紳士気取り)”と揶揄されました。
それでもスノッブだちは上流階級に倣って「紳士・貴婦人にふさわしい振舞い」を身につけようと躍起になりました。そう、中流階級がそもそも礼儀作法(マナー)にこだわる理由がここにあります。
マナーを身につけることは、下の階級(労働者階級、つまり召使いたち)との差別化を図るのにも役立ちました。フォークとナイフの使い方ひとつで「私たちとあなた方は違うのよ」と示すことが出来るのです。
同時に召使いたちへは、厳しく、こと細かい規則(ルール)を設けました。
中流階級も労働者階級も、「働いてお金を得る」という点では同じなので、階級が召使いたちより上位であることを示すためにも、「命令」ともいうべき厳しい規則(ルール)が必要だったのです。
さて、そんなスノビズムの時代を経てエドワード朝時代に入ると、中流階級は上流階級が無視できないほどの政治経済力を持つまでになりました。いっぽう上流階級は財政難に陥ったり、没落してゆく貴族が多くいた。中流階級はそんな貴族から称号を買取ることで、比較的容易にあこがれの「イギリス貴族」になることが出来たのです。
中流階級と上流階級の違いは、中流階級は努力し、ひたすら働いて高い地位を得たという点です。ですからエドワード朝は「努力の報われた中流階級が、もっとも自身の階級を謳歌した時代」だといえます。
そう考えると、番組製作者がなぜ「エドワード朝時代」(1901~10)を選んだのか、その意図が見えてくるような気がします。
オーディションで選ばれた素人さんたちは、主人側も召使い側の人々も、
「最低でも週に一度は休みを取る」のは働く者の当然の権利であり、「人にものを頼むときはプリーズをつける」のを 当然のことと思っている、常識ある21世紀のイギリス人です。
そんな現代の常識人が主人は階級差を楽しみ、召使いは階級差に苦しむ時代に放り込まれるのです。
主人側の人たちは―不本意ながらも―マナーに沿ってつねに自身の権威を損なわぬよう、召使い側の人たちに偉そうな態度を見せつけなくてはならないし(最後のほうは慣れたのか、自然に尊大な態度をとれるようになって、それはそれで召使い役の人たちに嫌われていた)、召使い側の人たちは文字通り「奴隷のように」扱われながらも、ルールに準じた「召使いの本分」を強いられる。
マナー(Manner)とルール(Rule)。
主人も、召使いも、同じように、
「~してはいけない」
「~すべきである」
こまかな約束事に縛られていたエドワード朝時代。
『マナー・ハウス』のプロジェクトに参加した素人さんたちが、90日のあいだ一貫して苦労し、泣き、怒り、疲労困憊させられたのが、このマナーとルールだったように思います。そしてマナーとルールに対する困惑ぶりそのものが、『マナー・ハウス』全体を通しての面白みだと思うのです。(申し訳ないけど)
次回は、冒頭で触れた執事役のエドガー氏にスポットを当てます。
いやさ、これがまた雰囲気のある、い~いカンジの、おじ(おじい)さんなんだわ。(つづく)
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
| « 執事って、就... | 「MANOR HOUSE... » |







MANOR HOUSEのMANORなんですが、マナーと訳されていますが、「荘園」とか「領地」という意味ではないでしょうか。いわゆるマナーはMannerだと思うのですが。
興味深い記事がたくさんあるので、引き続き読ませていただきたく思っています。これからもよろしくお願いします。
>MANOR HOUSEのMANORなんですが、マナーと訳されていますが、「荘園」とか「領地」という意味ではないでしょうか。いわゆるマナーはMannerだと思うのですが。
「マナー(Manor)とルール(Rule)」
→記事本文中の、ここの部分ですね。
あー、やっちゃった!はい、スペル間違いです。
ご指摘のとおりMannerが正解です。
訂正の上、再度記事をupしました。ありがとうございます。
ここでちょっと、「マナー・ハウス」の呼び名について。
meewさんの仰る通り、マナー・ハウスは「荘園主が住む家」を意味します。荘園制度が始まったのはノルマンディ王朝時代です。ですから「マナー・ハウス」といえば「古い血筋を持つ、由緒ある館」なんですね。
記事でも触れましたが、このイギリスTV番組の原題は、
“THE EDWARDIAN COUNTRY HOUSE”
「カントリー・ハウス」となっています。
カントリー・ハウスは、簡単に言うと「イギリスの地方にある貴族所有の屋敷」の総称です。
マナー(Manor)を含めて、アビー(Abbey)、カースル(Castle)、ハウス(House)、ホール(Hall)…etc. さまざまな歴史や様式をもつ貴族の館をひっくるめて「カントリー・ハウス」と、一般的に呼ばれているようです。ものの本によりますと。
それを限定して、舞台を由緒ある「マナー・ハウス」としてしまうと、にわか成金のエドワーディアンにはそぐわない…なので、イギリス番組制作は「カントリー・ハウス」の総称を題名に使ったのではないか、と思います。
ところが日本でDVD発売されるにあたって、原題にある「カントリー・ハウス」が、わざわざ馴染みのない「マナー・ハウス」へと変わっている。
はて、何故に?
やっぱり日本だと「カントリー・ハウス」と聞くと、アメリカにある田舎の家(ターシャ・テューダーのような?)がイメージされるからでしょうかね?