大伴夫人の墓 大原の里 高市郡明日香村小原1字寺西34
(おおともぶにんのはか)藤原鎌足の母、大伴夫人の墓といわれている。 東西11m、南北12m、高さ2.4mの円墳。
大伴夫人とは、大伴咋(くい)の娘・智仙娘のことで、 中臣御食子(なかとみのみけこ)の妻となって鎌足を生んだとされています。ちなみに、大伴咋は任那問題で失脚した大連・大伴金村の子で、崇峻天皇から推古天皇の時代にかけて活躍し、崇峻天皇4年には、任那再興のため大将軍となって筑紫まで出陣している。





大織冠とは、天智天皇8年(669)10月、天智天皇が死の床にある中臣鎌足の家に弟の大海人皇子を遣わして、藤原の姓とともに授けた大臣の位であり、 正一位に相当するという。これ以後、中臣鎌足は大織冠・藤原鎌足と呼ばれるようになる 藤原鎌足は、「大織冠伝」(760年頃成立)によると、614年)、大倭国高市郡の人として、藤原の第(邸宅)に生まれたと記されている。藤原は、現在のここ明日香村小原の地である

大友夫人の墓



狛犬とお社。大原神社の御祭神は、品陀別命と大織冠鎌足

天武天皇と鎌足の娘の藤原夫人との間に交わされた、万葉集の歌二首を刻んだ石碑
天皇の藤原夫人(ふじはらのきさき)に賜へる御歌(おほみうた)一首
巻02-0103
我が里に大雪降れり大原の古りにし里に降らまくは後(のち)
※わがこの里に雪が降ったぞ。そなたが住む大原の古ぼけた里に降るのは、ずっとのちのことだろう。
藤原夫人の和へ奉れる歌一首
巻02-0104
我が岡のおかみに乞ひて降らしめし雪の砕けしそこに散りけむ
※私が住むこの岡の水神に言いつけて降らせた雪の、そのかけらがそちらの里に散ったのでございましょう。


井戸への道


「志貴皇子」の万葉歌碑

大意










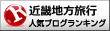















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます