鳥住山地蔵峠の「地蔵堂」
また山を下り、地蔵峠まで戻ると、トンネルの入口の近くに「地蔵堂」が建っています。809年(大同4年)空海が求聞勤行(ぐもんごんぎょう)で大峯山修行の砌、この辺り(黒滝村鳥住)を巡錫し、日印唐三国の土で地蔵尊を造り奉祀したら、安産、母乳、眼病治癒等に霊験あらたかで、その後、895年(寛平7年)大峯中興の聖宝(理源大師)が鳥住鳳閣寺を開いた時、この地蔵尊のご利益は益々盛んでしたが、今の地蔵尊は1742年(寛保2年)奉祀され、高さ三尺八寸の松香石造、「鳥住山」の刻銘があり、大峯先達・内海道助三郎の寄進、細工人西川伊兵衛、厨子は1778年(安永7年)山石惣講の寄進です。




鳳閣寺(TEL 0747-62-2522)吉野郡黒滝村大字鳥住90
飛鳥時代の白鳳6年(678年)に天皇の命令によって役小角が開き、寛平7年(895年)に聖宝が中興したとされる。江戸時代の元禄13年(1700年)、醍醐寺三宝院に属して修験道当山派を支配する「諸国総袈裟頭」の寺として、明治5年(1872年)の修験道廃止令までおおいに栄えた。



庫裡の裏にある宝塔のレプリカ

本堂

理源大師廟塔
鳳閣寺から「理源大師廟塔」(重文)までの距離は600mほど。百貝岳への登山道の途中にある 宝塔は理源大師聖宝の廟塔で、南北朝時代 伊派石大工 井行長の作、精密な作品は我国石塔中一番といわれる 重文 花崗岩造りの極めて精巧な宝塔形の石塔




五輪塔・箱屋勘兵衛供養塔 重文
箱屋勘兵衛が奈良から鳳閣寺の理源大師を訪ねる度に、大師好物の餅飯等を持参したので、大師は勘兵衛を『餅飯殿』(もちいひどの)と呼ばれ、勘兵衛の居住地の奈良の餅飯殿町はそこから付けられたと言われている




















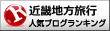















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます