先日、NHK<チコちゃんに叱られる>において「おすし屋さんで粉末状のお茶が出されるのはなぜ?」という話題がありました。
答えは「お寿司をおいしく食べてもらいたいから」という結論でした。
( ,,`・ω・´)ンンン?
なんかハッキリしない答えですね

 。教えてくれた先生は、中村順行先生。
。教えてくれた先生は、中村順行先生。
我々茶業者は、この先生のお名前を良く拝見しますし、現在は静岡県立大学茶学総合研究センターのセンター長でいらっしゃいます。
私も、中村先生の書籍を勉強で拝見することがありますが、こんなモヤっとした結論を言われる先生ではありません。
内容も、NHKにしては奥歯にものが挟まったような言い回しの展開でした



ですので、私の見立てでは、この回は紆余曲折で製作が進んだのだろうと考えました。あくまで主観です。
と言っても、はじめは丁寧に取材をされたのだと思いますが、お寿司に対する「殺菌」という点で、
コンプライアンス的にNGだったのではないでしょうか?このご時世、「○○に効く!」「○○に効果!」とはあまり言えません。
ましてや薬ではない「茶」の効果効能は、突かれると面倒です。もちろん効果は期待できますが、では「何杯飲めばいい?」とか、
「どのタイミングで?」「○○寿司の粉末は効果があるの?」など使用する茶の種類や品質によっても正確には異なる嗜好品の為、
これを言い始めたら「バラエティー」にはならないのでしょう

では、なぜ粉末茶なのか?
お茶屋の私個人としての主観は、ズバリ「便利だから」だと思います。


昔は、お寿司屋さんでは「粉茶」が使われていました。これは、テレビでも紹介されていた「本茶」を製造するときにより分けられた、

つまり、ふるいでふって落ちた、お茶の葉がくずれた茶葉です。

ふるい・・・網目の細かさは何種類かあります。それを何回も通してお茶を仕上げていきます。
これは、急須でいれます。ですので、お茶をいれるたびに「茶殻」が出ます。そのごみの量、急須を洗う手間、お茶をいれる手間を考えたら、結構大変です。

(↑お茶殻)
しかも、大型回転ずしで毎回これをやるとそれだけで大仕事です。一昔前は、ティーパックをおいてある回転寿司もありましたが、これもゴミになります。
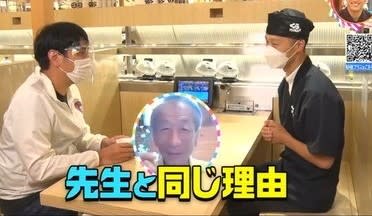
しかし、粉末はどうでしょう。飲みたい量を好きなだけ飲めますし、ゴミも出ません。お茶にかかる人件費、コストが相当抑えられます。これが一番の理由でしょう。
次に、玉露と粉末茶を比べていましたが、これはミスリード、誤った比較です。

粉末茶とは、「どのように加工したか?」という物であって、お茶の種類は関係ありません。玉露でも、玄米茶でも、ほうじ茶でも、すり潰して粉末にすれば粉末状、溶けるように加工すれば粉末茶です。
高級すし店では「煎茶の粉茶」を出されているとのことでしたが、想像するにたぶん、番茶に近い煎茶だと思います。

番茶とは、お茶の葉を大きく成長させ、繊維質の多いお茶です。煎茶に比べ味に深み、甘味、うま味はありませんが、爽やかな渋みがあります。
渋み≒カテキンです。番組でも取り上げられておりましたが、お寿司に合わせるのに一番重要なのは、この渋みだと思います。
これにより、お口の中をさっぱりさせることが出来、生モノ・魚を食べたあとに、カテキンで殺菌する効果もあるのだと思いますが、たぶんここがエビデンスとして言い切れないのでしょう。研究結果がないので・・・
もちろん、カテキンの研究では証明されていますが、人での試験、どれくらい飲めばどれくらいというデータは残念ながらありません。(私が見たことないだけかも知れませんが、研究会などで質問しても大概「データはない」と言われるので。)
渋みが重要なのは、番組の通りですが、お茶のうま味と渋みは反比例の関係にあります。そして、うま味のあるお茶は総じて高級茶、値段が高いです。
ですので、玉露、煎茶などうま味を楽しむ茶種よりは、番茶など爽やかな渋みを楽しむ茶種の方が、味としても、身体にも、経済的にも良いということが言えます。
またそのあたりも今後、いろいろと試してみたいと思いますが、差し当って、【煎茶】において、どこの産地のお茶がお寿司に合うのか動画で実験してみました。
またご覧いただければ幸いです。 茶の君野園Youtube「お寿司(納豆巻)に合わせる煎茶5産地飲み比べ」
(本ページ内番組画像は、インターネット画像欄より拝借させて頂きました)















