白馬スネルゴイキャンプ2日目に
『第9回白馬クリスチャンフイルムフェステバル』
が行われますが、その作品がYouTubeから順次アップされています。👇
http://atv.antioch.jp/hcff2019/

是非ご覧になってください。
💮ドキュメンタリー
💮 ドラマ
💮 ミュージックビデオ
💮 CM
4部門にさまざまな作品が応募されてます。

このなかで、どの作品がノミネートされ、28日に発表されて、どの作品が賞を取るのかしらと、私は今見始めました。皆様も是非ご覧ください。
ドルカス
白馬スネルゴイキャンプ2日目に
『第9回白馬クリスチャンフイルムフェステバル』
が行われますが、その作品がYouTubeから順次アップされています。👇
http://atv.antioch.jp/hcff2019/

是非ご覧になってください。
💮ドキュメンタリー
💮 ドラマ
💮 ミュージックビデオ
💮 CM
4部門にさまざまな作品が応募されてます。

このなかで、どの作品がノミネートされ、28日に発表されて、どの作品が賞を取るのかしらと、私は今見始めました。皆様も是非ご覧ください。
ドルカス















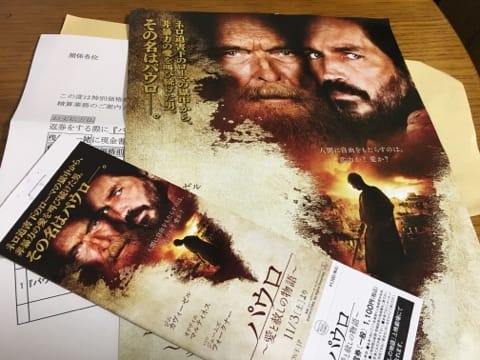




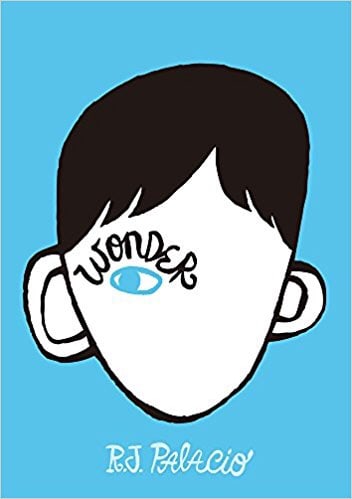
カンヌ映画祭で、最高のパルムドール賞を受賞した是枝監督の「万引き家族」を観に行った。
映画に関心のある方は、ぜひ映画館で観ておくべき作品だろうと思う。一言では言えない、いろいろ考えさせられる映画であり、問題を投げかける映画でもある。
この映画を観て、直後は「良い映画」と思ったが、一日経ってもうちょっと思い出すとまた考えが変わって来た。最初に感じたのは人間と人間の関係が濃縮する家族、それは血縁の絆が中心に考えられているが、そうではないことを提起している。互いが受け入れ合い、支え合って、必要として正直に生きれば血縁にまさる家族なんだと・・・・。

だから映画では、実の両親から虐待され、冬の寒いベランダに出されている「じゅり」を救出するシーンから始まる。「じゅり」は次第に柴田家の同情と愛を得て、かけがえのない一員として暮らすようになる。祖母の年金だけでは足りない父と息子は、息の合った万引きを繰り返す。孫の「亜紀」はマジックミラー越しの風俗店で働いている。唯一妻だけがまともにクリーニング店で働くが、それも「じゅり」を露見させないために人減らしの憂き目にあってしまう。
この家族は犯罪を重ねていても、おばあちゃんの家で暮らす全員には、家族としての愛が溢れている。そのピークが半年たった夏の海水浴を家族で楽しむシーンだ。しかしそれも、おばあちゃんの死と、息子の万引き失敗から崩れていく。そして次々に明るみに出る家族の秘密。
私は是枝監督をけなしたいとは思わないが、海外には受けても、これは日本では基本的に受け入れられない部分がある映画だと思う。「じゅり」を虐待する夫婦、娘亜紀の失踪を偽り取り繕う家族。血縁家族のおどろおどろしさを目一杯見せつける。加えて正当防衛とされたが前夫を殺した妻、その妻と正式に結婚していなかった前科のある万引き夫の組み合わせだ。最後に分かる息子の翔太すら、松戸のパチンコ店から連れ出した子という設定なのである。偏見、と言われるかも知れないが、これは通常は有り得ない異常な設定だ。この彼らが傷を舐め合うように、仲良く幸せに暮らしている・・・なんてことは、普通に考えるならあり得ないでしょう。
だから私は、本当の家族とは、と問題提起したように見えるが、実は実際にはあり得ない、非常に作為的な家族で提起している、と感じてしまう。 その日暮らしで、過去に大きな傷を持っている者同士が、しかも万引きという犯罪を重ねる家族なのに、果たしてあんな風に思いやり合え、優しく睦みあえるものだろうか。それはちょっとしたブラック・ジョークである。または、いつか壊れることが分かっている、その直前の全員による思い出作り家族ごっこなのかも知れない。これは映画でしかつくれない、超ユートピア物語に見える。
真の家族って何だろう?を描こうとした是枝監督の意図はわかるものの、どうしても世の中のあらゆる悲惨なパターン、それあぶり出したような無理の作り過ぎ、その不自然さが拭いきれない。
 ただし秀逸な場面がある。発覚後、この家族の虚構が警察の取り調べによって、一枚一枚剥がされていく。誘拐、殺人、死体遺棄・・・が、主演の妻役の安藤さくらが、刑事に問いかけられて答えに詰まって泣くシーンがある。台本にない、意図的なぶっつけ撮影らしい。これに見事に対応しての演技力に感嘆した。この安藤のシーンだけでも、この映画を観る価値があると思った。
ただし秀逸な場面がある。発覚後、この家族の虚構が警察の取り調べによって、一枚一枚剥がされていく。誘拐、殺人、死体遺棄・・・が、主演の妻役の安藤さくらが、刑事に問いかけられて答えに詰まって泣くシーンがある。台本にない、意図的なぶっつけ撮影らしい。これに見事に対応しての演技力に感嘆した。この安藤のシーンだけでも、この映画を観る価値があると思った。
ケパ



 しかしいくら何でも、うさぎ退治にダイナマイトみたいな爆弾を投げまくるとか、最後にはピーターが起爆装置を押してピーターたちの家のある大木を爆発で倒壊させる・・・など、これはちょっとあり得なさ過ぎ、やり過ぎの感がした。「あり得ない」シーンを連発して笑いを取ればいいって言うものではないような。この映画は、作者のビアトリクスらしさ、愛らしい動物物語とは異なる世界だ。
しかしいくら何でも、うさぎ退治にダイナマイトみたいな爆弾を投げまくるとか、最後にはピーターが起爆装置を押してピーターたちの家のある大木を爆発で倒壊させる・・・など、これはちょっとあり得なさ過ぎ、やり過ぎの感がした。「あり得ない」シーンを連発して笑いを取ればいいって言うものではないような。この映画は、作者のビアトリクスらしさ、愛らしい動物物語とは異なる世界だ。


