「ばくおん‼」1~10借りて読みました。
自分で買わないで済みそうです。
バイクネタがよくわかりました。
スズキオチ、スズ菌がうつるとか笑えました。
今のところ、私のバイク熱は平熱となっております。
レガシィ熱がバイク熱を冷ましてしまいました。
バイクはホンダ以外乗ったことがないので、スズ菌にも感染しておりません。
カプチーノ系スズ菌には侵されっぱなしです。
横溝正史全集2に収録。
「仮面劇場」を読み終わった後、残りの収録作品を読みました。
その中で「夜光虫」がおもしろかったです。
人面瘡を持つ美少年白魚鱗次郎、しゃべることができない美少女志摩琴絵。
二人が両国の川開きの花火大会が開かれる中、納涼船で出逢います。
鱗次郎は警察に追われる身、琴絵はさらわれて座敷牢にとじ込められます。
で、由利先生と三津木俊助が出てきます。
でも、推理小説ではありません。冒険小説と言った方が近いです。
サーカスのライオンが逃げ出して、ピストルを手に由利先生と三津木がライオンを追いかけるシーンなんて、どこの国のお話でしょう。
昭和11年のお話なので探偵や新聞記者がピストルを持つのは普通なのかな?
とにかく場面展開が早くて、あれよあれよと話が進んでいきます。
隠された財宝をねらっていた悪人は時計塔の仕掛けによって殺されてしまうし、まるで「カリオストロの城」みたいなお話です。
現在、金田一耕助事件ファイル8巻目「迷路荘の惨劇」を読んでいます。
たしかに文庫本は読みやすいです。
最近の出版物なので活字は大きいし、難しい漢字は使っていません。
まだまだ、読む本が残っていると思うとわくわくするような儲かったような気分です。
もっと前に読んでおきたかったという気持ちと今日まで取っておいてよかったという気持ちが半々です。
本はおもしろければ読み進み、つまらなければ投げ出すでいいのです。
横溝正史著。横溝正史全集7。1970。
ドラマも、出だしは原作どおりだったのだとわかりました。
おかげてすんなりこの小説の世界が頭に入ってきました。
映像ではかわいい系の女優さんが演じる椿美彌子が「容貌はお世辞にも美人とはいいにくい。かなりのおでこである。…」というのはおもしろいです。
今までの横溝作品と同じように、どれだけドロドロな話なんだろうと読んでいくと、まったく予想とは違ってすっきりしていて読みやすいです。
読みやすさはすっかり横溝ワールドに、はまったせいなのか、私が大人になったからなのか、もともとそうだったのか、わかりません。
オチも犯人もわかっているので、二度読みみたいな感じで読んでいました。
横溝ワールドでは美しく生まれたことは決して人生のしあわせを約束していません。かえって不幸の種となります。
美彌子が活き活きとしているのは、ドロドロ世界と無縁でいられた容姿のおかげなのだと言えるでしょう。
東太郎は悪魔の子でありながら美彌子と一彦の兄でもあるいうことは、孤独だった東太郎の唯一の希望だったのかもしれません。
全集7収録作品「黒猫亭事件」Y先生と金田一耕助の出会いのエピソードが入っていて、金田一ファンにはたまらない作品でしょう。金田一の友人風間俊六も出てきて、風間さんってそういう人かと納得しました。推理にもキレがあります。
「車井戸はなぜ軋る」「犬神家の一族」に出てきた傷を負った瓜二つの復員兵、奉納絵馬の手形での本人確認というエピソードが出てきました。
ヒロイン鶴代の手紙という形式で書かれた小説は、鶴代の死を告げてさらっと終わります。
鶴代は心臓弁膜症で「八つ墓村」の田治見春代を連想させます。
短編小説として実によくできています。
読者が鶴代に感情移入したところで、鶴代が死ぬのは読者を驚かし、衝撃を与えるちょっとしたトリックだと思います。
横溝正史著。角川書店。1980。
「あいつは平家蟹だ…鵼(ぬえ)のなく夜に気をつけろ…」ってなんのこっちゃとずーっと思っていました。
それはこの本が出版された時だったでしょうか。映画封切前のCMコピーだったでしょうか。
38年後の今日ようやく意味が分かりました。
横溝先生77歳の作品ですが、みずみずしい作品です。
瀬戸内海の島、双子の姉妹、洞窟探検、まさに横溝ワールドの集大成です。
公害問題、過疎の島と当時の問題も描かれています。
録画していた映画「悪霊島」を見始めましたが、もう少し読んでおいたらもっと面白く見られるかもと映画を途中で止めて、読みかけの原作を読んだら終わりまで読んでしまいました。
おもしろく読めました。
ただ、おっさんとなってしまった金田一耕助が、物語の中であまり女性と絡まなかったのがさびしいところです。
三島由紀夫著「豊饒の海」第三部
タイから帰ってきて「暁の寺」が気になって読んでみました。
「豊饒の海」の第三部から読んでも、なんのこっちゃなのに、三島作品もいままで読んだことがない。
なので、厳しい読み始めでした。
三島の圧倒的な文章力、ちりばめられた言葉、自分の語彙のなさ、漢字が読めない。
戦争前のシャム王国、バンコクの風景。その果てのインド。
私もバンコクに行き、この先行きつくところはインドだなーと考えていたのでおやっと思いました。
そして、舞台が戦後になると急に読みやすくなって、内容が初老の男の傍観者としての恋愛感情を描いていました。
これは「男はつらいよ」の三島版じゃないの?なんて思いながら読み終わりました。
とりあえず、ごちそうさま。
第一部「春の雪」から読み直すのはそのうちに…。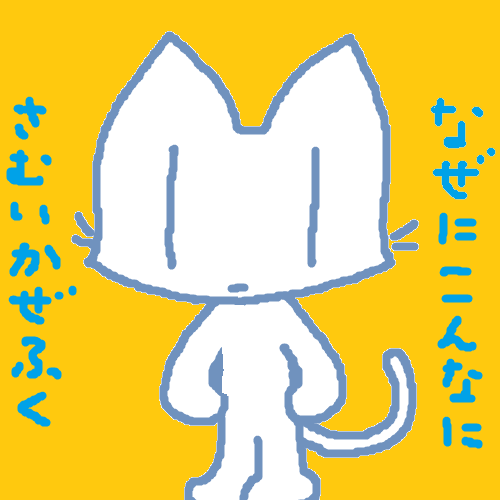
『病院坂の首縊りの家』読み終わりました。
きのう、本のページがあともう少し残ったところで、ふとんの外に出していた腕が冷えてきて寝ることにしましたが、なかなか寝付かれず、結局、夜中に最後まで読みました。
やっぱり、映画より深く、重く、長い時間を描いた内容でした。映画を先に見ていてよかったです。
本を先に読んでいたら、映画を見て違和感だらけだったでしょう。
映画を先に見ていたので、重要なシーンでは、その光景を思い浮かべるのが楽でした。
小説はどう考えても、2時間ちょっとでまとまる内容ではありません。
犯人も映画とは違っていましたし…。
なぜ、生首を風鈴のようにつるしたかは、死んだ本人の希望だったとして、体をどこかへ運んだ理由が映画ではわかりませんでしたが、小説ではわかりました。
また、由香利と敏男の遺体は決して、映画のように一緒に埋葬されることはありえないということも小説を読むとわかります。
そして、敏男が映画のように自殺することも小説を読めばありえないことと感じます。
でも、映画化するにあたり、桜田淳子さんが小説の由香利のような死に方はできないこともわかります。
映画では冬子が弥生の娘であるが故に、由香利と小雪がそっくりだったという設定にしていましたが、小説では由香利と小雪がそっくりだったことで、弥生は由香利が法眼琢也の孫であることを知るという設定でした。
小説の方がよくできているなーと感心しました。
それでも、横溝先生も出演させて、よく映画をまとめました。やっぱり市川監督さすがです。
そのうち、映画と小説が私の頭の中でごちゃごちゃになって、勝手に独自の映画を作ってしまいそうです。
おもしろいです。
なんで、こんなに読みやすいんでしょう。
本を読んでいくとこの物語と映画が重なっていきます。
映画のシーンが物語にぴったりはまっているのです。
市川監督恐るべし。
物語は今いいところです。
二人目の犠牲者が出たところです。
謎の殺人鬼の偽おりん婆さんの存在がクローズアップされてきます。
そして、意外だったのは、磯川警部と立花警部補の二人が原作にも出てきたことです。
映画化するのに際して、常連の加藤武を出したいために立花警部を追加したのかとばかり思っていました。
映画を見る前に読みました。
横溝正史全集。
その前に古谷一行主演の2時間ドラマ「女王蜂」を見たんですがこれが無茶苦茶な展開でびっくり。
いったい原作はどうなっているの?と読んでみたら納得。
いろんな登場人物、舞台も何か所もあり、とても2時間ドラマにならないのがわかりました。
しかも、原作はラスト、ヒロイン智子の未来に明るさがあるのです。
ドラマはラストに自殺しちゃったので、あまりのちがいにびっくりしました。
密室トリックが心理的だったところがうまいなーと感じました。
残念なところは感情移入できる登場人物がいなかったこと。
応援したくなるような人がいませんでした。
さて、映画はどうなっているのでしょう。おたのしみ。
毎晩、ふとんに入って「ツバメ号」を読む。
何度も読んでいて、読みやすい。
1章あまりを読んで寝る。
実にしあわせな時間です。
もしかして、こういう時間を作るために、かつて「ツバメ号」に出会ったのかもしれません。









