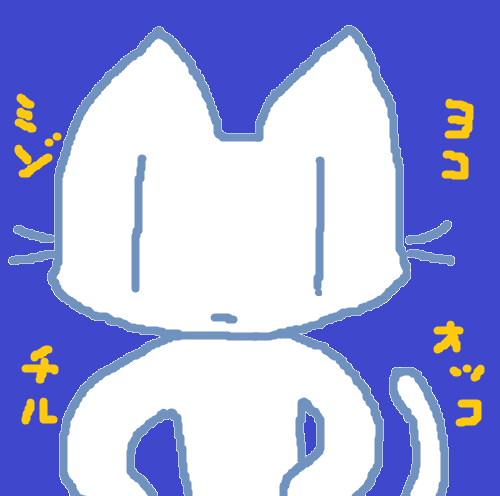石田ゆうすけ著 幻冬舎 2009
YouTubeのGhibli Ojisanの北海道自転車旅に出てきた石田ゆうすけさんの本を読んでみました。
自転車旅って、考えたことなかったです。
どうしても自転車というとパンクが連想されてしまいます。バイクだとそんなことはあまり考えないのに。
輪行という、自転車をバッグに入れて鉄道で目的地付近に行って、駅で自転車を組み立てて走り出すという旅のスタイル、いいもんですね。
ジブリオジサンの動画を見て、この本を読んで、つい軽量な折りたたみ自転車でも買ってしまおうかと思いました。
鉄道が好きで、自転車が好きだったら輪行ありです。
でも我に返って考えると、雨が降ったり、列車が来なかったり、荷物をあまり運べなかったり、苦労は多そうです。
家にはステップコンポという折りたたみ自転車もあるし、とりあえずこれで輪行体験してみたらよさそうです。
でこの本は自転車で世界一周をした石田さんが国内を旅した記録を基に書かれたものでした。
今回、石田さんの本を初めて読みましたが、するする読めました。
石田さんは感情の起伏が激しくて、涙がよく出てきます。
人に話しかけられやすくて、人と触れ合うのに自転車は最適だと言うのがよくわかりました。
しばらく石田さんの本を追っかけてみたいと思います。
妹尾河童さんの「河童が覗いた」シリーズを読んできました。
50人の仕事場は昭和も終わりに近づいたころの日本を代表する仕事師の仕事場をイラストにまとめたものでした。
平成も終わった今となっては物故者となった方が多いのではないでしょうか。
そして同時代を生きていた私ですが、まったく知らなかった人、今となってはまったく消息が分からない人が出てきます。
当時のアナログな仕事場がなつかしく、そんな職場こそ働き甲斐があったのかもしれないなと思うのでした。
ドローンや超広角レンズ、360度カメラができた今ではこの空から仕事場を見るイラストは簡単に映像化できそうです。
しかし、アナログな仕事道具がなくなってしまって、映ったものはパソコンだけなんてことになりそうです。
『深夜特急』もいつか読もう本でした。
読み始めてびっくり、なんて軽いノリの本なんでしょう。
もっと深刻な内容で読むとこっちまでへこむような本だと勝手に思い込んでいました。
ドラマの宣伝で(ドラマは見ませんでした)「カジノにハマって抜け出られない」みたいな表現があって、そんなギャンブル廃人の旅物語なのかと思い込んでいたんです。
たとえれば「麻雀放浪記」が世界を舞台にしたようなもの。
しかし、読んでみれば、本の中の私は傷つくこともなく深みにはまる前に次の国に飛び立ってしまうのです。
気に入らない、肌が合わない国には文句をつけて、次の国に行くのは気楽だろうなー。
そして、この本を26歳までに読んでいたら、つられて世界に旅に出ていたかもしれません。
文庫本には沢木氏の対談がおまけについています。
2巻では高倉健さんが饒舌に沢木氏と語っているのが驚きです。
この対談だけでも読む価値があります。
『河童が覗いたインド』の後『河童が覗いたヨーロッパ』を読みました。
EU統合前のヨーロッパのホテルの間取りがイラストで現わされています。
この頃のヨーロッパに行ってみたかったという気にさせてくれます。
で次に『河童が覗いたニッポン』を読みました。
この本もあの頃のニッポンが描かれていました。
あの頃は何か希望らしきものが、世の中はみんなの力で変わるんだみたいなものが確かにありました。
どうして、ニッポンはこんなに冷めてしまったんでしょう。
おもしろかったのは「盲導犬ロボット」と「点字本の印刷機」の研究について書かれたエピソードです。
この研究が進んでいたら今頃街には「盲導犬ロボット」があふれていたはずなのに…、そうなっていてもおかしくないのにまったくそうなっていません。
未だに盲導犬を酷使しています。この本にもストレスで盲導犬は長生きできないことが載っています。
でも、そんなこと今では誰も言っていません。ただ盲導犬を美談にして語るだけです。
そして盲導犬を持てない人は白杖を持って事故に遭うのです。
ソニーのアイボは盲導犬として発展させるとかそんな考えはなかったのでしょうか。
「点字本の印刷機」の方は時代が進み、パソコンで印刷ができるようになっています。
こちらは技術の進歩によってまったく当時の予想と違って達成してしまいました。
と同時に音声読み上げ装置、録音図書の発展もあり、点字を使える人が減ってしまうというのが皮肉です。
いつか読もうと思っている本があります。
「イツカハコナイ」でも来ましたよ。
前に紹介したYouTubeの宮脇俊三さんのNHK講座にこんなエピソードが紹介されていました。
宮脇さんの娘さんがインドに行くにあたって何の本を読んだらいいか?との問いに宮脇さんは『河童が覗いたインド』と『深夜特急』と自著の『インド鉄道紀行』を挙げたそうです。
この時、イツカが来ました。さっそく図書館で取り寄せました。
『河童が覗いたインド』と『深夜特急』の文庫本第1巻。
『河童が覗いたインド』はおもしろかった。夜更かしして読んでしまいました。
インドの地図が頭になくて地名が出てもなんのこっちゃですが、こんなところが世界にはあるのねと思うばかりです。
河童さんの俯瞰図、イラスト、手書き文字…まさに河童ワールドの本なのです。
ちょっぴり宮脇さんの本と重なった場所も出てきてなつかしい感じもします。
この前タイに行った時、薄まったインドの香りを感じ、このまま西に行くとどんどんインドが濃くなっていくんだろうなーと感じたのを思い出しました。
いきなりインドに行ったらやっぱりやられてしまいそうです。
夜中、本を読んでいました。
『鴨川食堂』ドラマを見て、小説を読みたくなりました。
ドラマで食堂の奥に探偵事務所があるなんてやりすぎだなーと思いましたが、小説だったら不自然じゃないのかもと読んでみましたが、やっぱりありえない。
でも、おもしろいじゃない。
ついつい読み進んでしまいました。
ただし、京料理の記述はちんぷんかんぷん、理解はおろか、頭にも入ってきません。
こんなに自分が日本料理の世界を知らなかったことにあきれてしまいました。
京都のこともちんぷんかんぷんです。
でも書きたかったのは本のことでありません。
ふと気づくと足がかゆい。
何か所も蚊に喰われていました。
そして、目の前を飛ぶ蚊が…。
蚊というのはなんでこんなにかしこいのだろうと思うことがあります。
ほどほどに血を吸うと後はじっとしている。
暗くなるのを待って飛ぶ。明るくなると飛ぶのをやめる。
とてもかないません。
ところがたまに本能のまま、血を吸いまくる奴がいます。
そいつはもう血の飲みすぎでゆっくりしか飛べません。
「ぱちん」手のひらにA型の血液がびっちょり。
なんで、こんなに気持ちいいの。スッキリ。でもかゆーい。蚊にナムー。成仏してね。
「孤独のグルメ」にハマって何年になるでしょう。
シーズン1は放送当初は見ていなくて、再放送から見始めました。
それから、ずーっと見ています。
日曜の6時20分からBSテレ東の「孤独のグルメ」の再放送を見るようになって「サザエさん」をまったく見なくなったほどです。
それでいて原作マンガに手を出さなかったのは、本屋さんで出逢わなかったこともありますし、それほど必要性を感じなかったこともあります。
ようやく原作マンガを手に入れて読んでみると、残念ながら想定範囲内でした。
あーこのシーンがドラマに使われたんだーという感慨はありましたけれど。
一番見たかった五郎が従業員に怒鳴るコックさんに怒る『東京都板橋区大山町のハンバーグ・ランチ』は期待しすぎだったなという感想です。
どうみても五郎の方がやりすぎのように見えてしまいます。
このマンガが描かれた1995年だったらやったぜ五郎なんでしょうが、2019年に見るとただの暴力的クレーマーです。
このマンガをとてもうまくドラマ化し、松重さんは五郎をうまく作り上げたんだなとわかりました。
内田百閒は学生時代に講談社の全集をすべて読みました。
「百鬼園先生言行録」も読んでいます。
本をリピートして読むとおもしろくてしょうがありません。
昔の友人に会って話し込んでしまうような感覚です。
自分が若い頃は内田百閒はなんて大人でおじいさんなんだと思っていましたが、今ではただのへんなおじさんとして見ることができます。
「百鬼園先生言行録」の頃はもちろん今の私より年下の内田さんでした。
内田百閒は家族だったら困ってしまう人ですが、先生だったら慕われる人だったんだろうなと思います。
他人だったら実におもしろいおじさんなのです。
生活力がまるでなくて借金だらけ、高利貸しにお金を借り、出版社に原稿料を前借して生活していました。
とにかく、お金がないのにお金を使います。
そして、文章を書かせたら天下一品なのです。
日本語ってこんなにすばらしいのかと思わせてくれます。
宮脇淳子著 扶桑社新書 2014
韓国ドラマ「朱蒙」、「太王四神記」、「善徳女王」、「龍の涙」、「宮廷女官チャングムの誓い」、「ファン・ジニ」、「イ・サン」がいかに歪曲されているかを書いた本です。
私は「太王四神記」以外は全部見ました。あーあの頃はおもしろかったなー。
「太王四神記」だけは見始めて止めてしまいました。あまりにリアリティがなく、見続けるのがつらくなったから。
当時、朝鮮史なんてまったく知らなかったから、おもいっきり知識として吸収してしまいました。
もちろん、すべて真実なんて思っていないのですが、ある程度は信じてしまったかもしれません。
結局、なんて救いのない国なんだろう、彼の国に生まれなくてよかったなーと思うのでしたけれど。
救いがないからこそ、ドラマの中では歴史をバラ色にしたい気持ちもわかります。
でも、ドラマやスマホの世界では韓国が日本に圧勝していることは明らかなんですが、それはなぜなんでしょう。
日本が韓国や中国をなめていたからとしか思えません。
だから、この本が正しいことを言っているとしても、それをもって韓国を全否定するより、日本より優れているところは認めて取り入れることが必要なのだと思います。
横溝正史の短編。
従兄弟の相克の物語。
人間関係が希薄になった現在では絶対ありえない物語だけど、横溝ワールドにはまってしまった私にはおもしろくってしょうがなかったです。
犬神佐清みたいなゴムマスク男が出てきて、やっぱり入れ替わりトリックがあります。
舞台が諏訪湖畔なんですが、豊田村なんて地名が出てきて、それって「たんけんぼくのまち」の舞台だったところなんじゃない?
こんなところでシンクロニシティが発生するなんておもしろい。
もう一度、諏訪湖に行って「鬼火」の舞台として眺めてみると、今までと違って見えるような気がします。