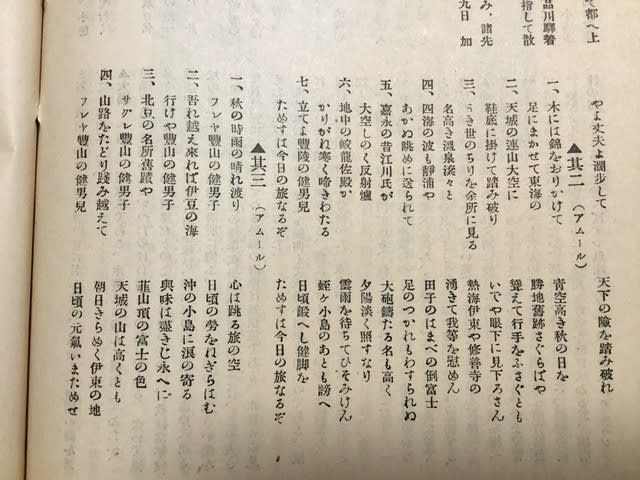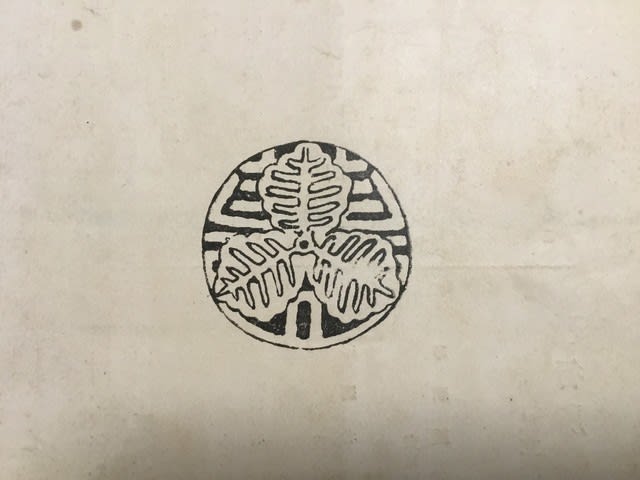練習の成果を高めて大会で結果を出すためには、心身ともに最も良い状態に整える必要があります。
コンディションを崩す要因は次のようなものがあげられます。
①トレーニングの量と質があわない
②故障や病気による体調不良
③人間関係や緊張からくる精神的ストレス
④日常生活の乱れ
選手を続けている限りコンディショニングは必要であり、一流選手になれるかどうかは、「自己管理」ができるかどうかにかかっているともいえます。
大切なことは厳しい練習に耐えられるために規則正しい生活を送り、栄養補給とストレッチング、休養をしっかり摂ることです。
もし気になる部分があれば練習後にアイシングを行って、ひどくなる前にかかりつけの医師や治療家による専門的なアドバイスを受ける必要があります。
故障をする前の予防が何より重要であって、競泳選手は肩や腰を痛めやすいので、練習前にチューブトレーニングや補強をしっかりと行うことで故障を防ぐことができます。
選手はある程度は筋肉の種類について知っておくことも必要だと考えています。
自分が鍛えたり、ストレッチしている筋肉、痛みを感じている部分をある程度知っていれば練習や治療の効果もよりあがります。
私の今までの経験からいうと、選手の練習への取り組みや体調が100%の状態だとしても大会で思うような結果が出ることはあまりありません。
120%の状態でそれなりの結果につながり、150%間違いないといえるぐらいの状態になってはじめて満足する結果が出るような気がしています。
それぐらい満足したベストタイムを出して活躍するというのは難しいものだと感じています。
スポーツを続けている間は「選手としての自覚」を常に持ち続けていることが大切な条件になるのは間違いありません。
約1か月間にわたって私が学んできたトレーニングの理論を紹介してきました。
当然のことながら、知識は実践によってはじめて生かすことができます。
競泳選手として必要な知識を得たうえで、それを実践して経験を積むことが何より重要です。
私は競泳選手として大学時代まで練習し、その後指導者として25年近くの経験を積んで合計すると40年もの間競泳に関わってきましたが、今だにわからないことだらけです。
常に悩みながら練習を作っていて、これが絶対だという答えはありません。
これはおそらく競泳に携わっている間はずっと続くことでしょう。
理論は時代とともに変わっていくものです。
スポーツに関わっている間は常に学び続けて、現場で実践することが続いていくのだと考えています。

竹村知洋