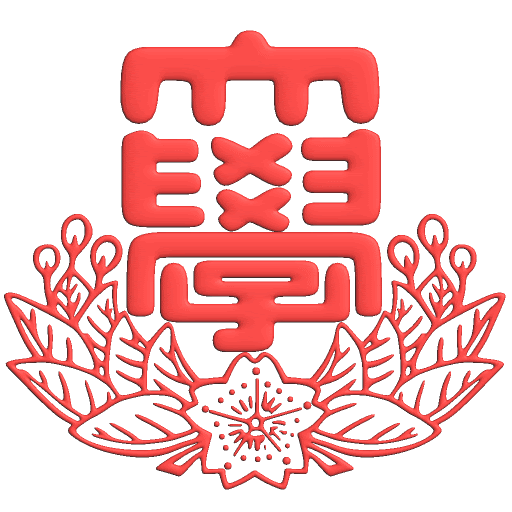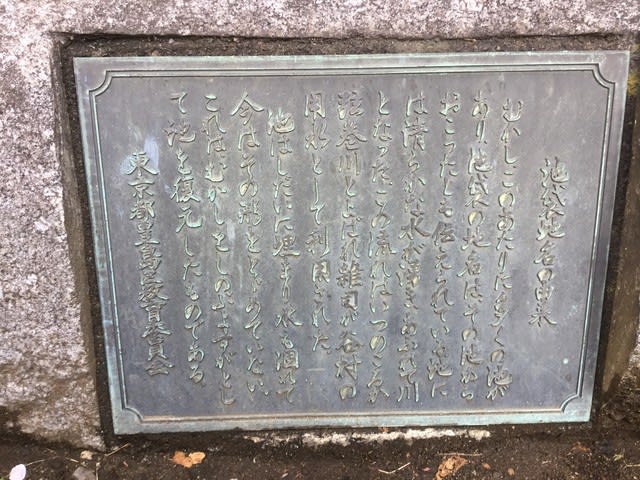サプリメントを摂取するとしたら1番目に「タンパク質」、2番目に「鉄」を勧めます。
食品では牛や豚などレバーやひじき、あさり、ほうれん草などに多く含まれています。
主な働きです。
①赤血球中のヘモグロビンをつくる
②有酸素運動の基礎となる
③成長促進や免疫の働きを助ける
ヘモグロビンは鉄とタンパク質でできており、身体の組織に酸素を運搬しますので、競泳など持久系の運動選手にはとても重要な栄養素です。
骨の鉄骨にあたるコラーゲンもつくりますので、中高生の成長期にある選手は特に意識して摂取する必要があります。
また生理的な働きにより女性は鉄不足に気を付けなければなりません。
鉄が不足すると鉄欠乏性の貧血になり、疲労感・無力感が増したり、身体が冷えやすくなります。
鉄は動物性の食品(牛・豚など)に含まれている「ヘム鉄」の方が吸収がよいです。
植物性の鉄分は「非ヘム鉄」といって吸収されにくいです。
動物性の方が植物性よりも10倍は吸収が優れているということです。
血液検査をすると分かりますが、身体には血液中に流れている鉄分と体内に貯蔵されている鉄分があります。
体内(肝臓や脾臓)に貯蔵されている鉄分を「フェリチン」といって、この値を高めることが大切です。
鉄分が食品に含まれている量は少ないため、サプリメントで補給する必要があります。
サプリメントを選ぶ場合は「ヘム鉄」の鉄剤を選択してください。
鉄はビタミンCと一緒に摂るとさらに吸収がよくなります。
栄養を考える時は栄養素が含まれている量だけでなく、吸収を考えて摂取することでより効率的になります。

竹村知洋