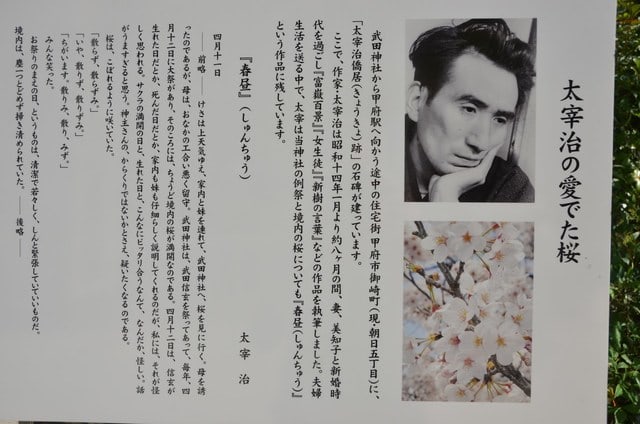静岡
9月初め、静岡を訪ねました。
室町時代以来、駿河国は今川氏の領国
でした。
今川氏全盛期の義元の時代、1549年
徳川家康(幼名 松平竹千代)は人質と
して19歳までの12年間、駿府で生活
しています。

(東御門)
臨済寺の住職太原雪斎などから、種々の
教えを受け、人間形成の上で重要な時期
を駿府で過ごしました。
1560年今川義元が桶狭間で織田信長
に討たれると、今川氏は衰退し1568
年、武田氏により駿府を追われました。
家康は駿府の武田氏を追放(1582年
)。この戦功により駿河国を与えられ、
駿府において信長を接待しています。
この接待のために街道を整備し宿館を造
営しました。
駿府城の築城を開始し、浜松城から移り
ます。(1586年)

(紅葉山庭園)
しかし秀吉が家康を関東に移封すると
(1590年)、豊臣系が城主となり
ます。
家康は関ヶ原の戦いに勝利すると、16
03年江戸幕府を開きます。
1605年将軍職を息子秀忠に譲り、大
御所として三たび駿府に入りました。
「江戸の将軍」に対して「駿府の大御所
」として実権を掌握し続けました。

(家康公の像)
駿府の町を大改造し、大々的な土木工事
が実施され、「駿府城と駿府城下町」が
誕生しました。
江戸時代最初の城下町です。
1607年7月に新装された城が完成す
ると、家康はすぐ入城します。
ところが12月大火災により御殿や天守
など本丸の全てを焼失してしまいます。

(天守台発掘調査現場)
家康は江戸城で使用予定であった材木を
駿府に運ばせ、再建工事を命じます。
江戸より駿府城の再建を優先させたとい
われます。
1615年豊臣氏を滅亡させた後、翌
1616年家康は75才で死去します。
生涯のおよそ3分の1を駿府城で過ごし
たことになります。
辞世は次の2首。
「嬉やと再び覚めて一眠り
浮世の夢は暁の空」
「先にゆき跡に残るも同じ事
つれて行ぬを別とぞ思ふ」

(坤櫓内部)
家康没後の1635年、再び火災により
豪華絢爛たる天守や御殿をほとんど失い
ました。
駿府城がどんな城だったかを知るために
は、二条城を参考にするのが良いそうで
す。
二条城も駿府城も大工の棟梁が同一人物
であり、内部の意匠その他が酷似してい
たそうです。

(巽櫓)