【社説②・11.28】:在職老齢年金 働く意欲をそがぬよう
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説②・11.28】:在職老齢年金 働く意欲をそがぬよう
もっと働きたいという高齢者の意欲をそぐことなく、共に社会を支える環境づくりを進めたい。
厚生労働省は、働いて一定の収入がある高齢者の年金支給額を減らす「在職老齢年金制度」を見直す。適用する基準額(賃金と年金の合計)を現在の月50万円から62万円へ引き上げる方向で、満額支給となる対象を広げる。
減額されない枠内に就労を抑える年金世代の「50万円の壁」を取り除き、人手不足の緩和につなげる狙いだ。「働き損」を改めつつ、年金財政や現役世代らへの影響なども包括した改革の議論が求められよう。
制度は1965年に導入。高齢者にも年金制度を支えてもらう目的で2000年の改正以降、賃金と厚生年金(基礎部分除く)の合計が基準額を上回った分の半額を減らす仕組みとされた。
働き続ける高齢者が増え、賃金と年金の両方を受ける65歳以上は22年度末で約308万人に上る。基準超えは約50万人で、年金支給は年4500億円抑えられた。
今回の見直し案で、基準額を62万円に引き上げると満額支給は約20万人増えると見込まれる。
現状では「年金が減らないよう調整して働く」高齢者が4割超という国の調査もあり、本人の受給増と企業の人手確保を後押しすると期待の声が上がる。欧米などでは減額の仕組みがなく、制度自体の廃止を求める意見も根強い。
ただ、減額対象を縮小して支給総額が増えると年金財政の悪化は避けられず、将来的な給付水準を低下させかねない。
これを補うため、厚労省は高所得の会社員が払う厚生年金保険料の上限を引き上げる案も複数示した。納める保険料が増えると、本人が老後に受け取る年金額は増えるが、現役世代の負担感が増すことには抵抗もあるだろう。
政府は9月改定の高齢社会対策大綱で、希望に応じた就労や社会参加を進め、60代後半の就業率を現行52%から57%へ引き上げるとした。法改正で70歳までの就業機会確保は企業の努力義務とされており、働きやすい環境や多様な選択肢の整備も重要である。
年金改革では、財政検証で明らかになった基礎年金の目減りへの対策も不可欠だ。厚労省は、底上げには厚生年金の積立金や巨額の税の投入が必要とするが、確保のめどは立っていない。
老後の安心を社会全体で支える持続的な年金制度に向け、丁寧な説明と合意形成が欠かせない。
元稿:京都新聞社 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2024年11月28日 16:05:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
















 </picture>
</picture>

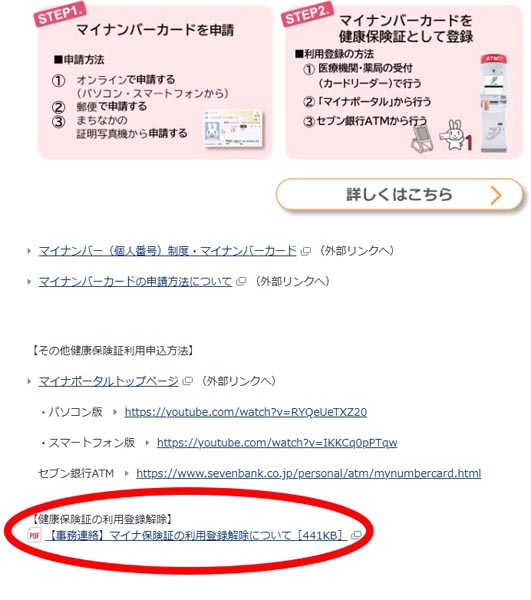 </picture>
</picture>





