◎母は、私を憎むようにさえなってきた
中野清見『新しい村つくり』(新評論社、一九五五)を紹介している。本日は、その二十九回目で、第二部「農地改革」の8「母の悲しみ―逆襲」を紹介している。同章の紹介としては二回目。
私が村の憎まれ者になるにつれて、母や私たちの立場も悪くなった。母にとっては岩泉家は本家であり、私にとってもその家族は恩ある人々である。それが今や仇敵となって争っている。母は最初困惑し、次第に私を憎むようにさえなって来た。初めのころ私に意見をした。「村長というものは、役場に行って新聞を読んでいればよいのだ。大学まで出ながら、こんなところに来て村中から悪くいわれて……」というのであったが、私は「新聞を読むためにこんなところに来ているのではない、大学出でなければやれない仕事をするんだから、黙っていて貰いたい」と強く言い返した。それ以後口には出さなかったが、家の中にいることは私にも辛かった。母に弟夫婦にも、この勝負で私が勝つとは思えなかったに違いない。私は負けてしまえば再び東京に去るだろう。そうすれば、息子が笑い者にされるばかりでなく、後に残った自分たちへの迫害がひどいだろう……。そういうふうに考えるのは当然のことであった。
それに母にとっては、そもそも大学を出た息子が、こんなところの村長などになり下がったことが気に入らなかったに違いない。こうした空気の中ては、家に帰って飯を食うことも気がひけた。私の家族はすでに八戸市に引き上げて、この村にはいなかった。私は朝起きると、たいていはすぐに役場に来て、一日に一度ぐらいしか飯を食わなかった。集会でもあって、他所でありつけば二度も食ったりした。夜は、役場のストーヴの廻りに川原〔徳一郎〕や助役〔川戸与四郎〕たちと集まって、二時、三時まで起きていた。家に帰ると敷き放しの寝床はあるけれども、部屋には火の気もなく、零下十五度もあるような夜半には、まともに寝られたものではない。オーバーを着たまま、靴下をはいたまま、床にもぐり込むのが毎夜のことであった。
いよいよ疲れて来れば、機を見て八戸に帰り、一晩夜も眠りつづけたりした。自宅へ帰ると、炬燵〈コタツ〉に向って坐ってもいられなかった。横になればすぐ眠った。しかしこうした休息も容易に許されなかった。ちょっと村を空けると、助役から電話がかかって来る。敵の動きがあわただしく、何事か企らんでいるようだから帰ってくれという。急遽帰ってみると、それほどたいしたことでもなさそうだ。数日してまた盛岡にでも出ると、また電話だ。こんなことがくり返された。助役たちも私がいないと心細かったに違いない。【以下、次回】


















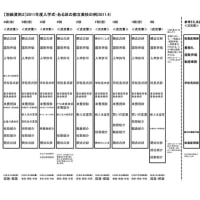
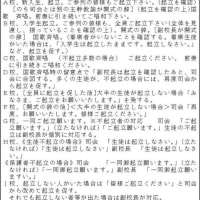








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます