◎郭沫若の「日本人の支那人に対する態度」を読む
昨日は、信濃憂人(魚返善雄)訳編『支那人の見た日本人』(青年書房、一九三七)から、傅仲濤という人の「日本民族の二三の特性」(原題・日本民族的二三特性)という文章を紹介した。
本日は、同書の冒頭に置かれている、郭沫若〈カク・マツジャク〉の「日本人の支那人に対する態度」(原題・関于日本人対于中国人的態度)という文章を紹介しよう。出典は、陶亢徳編『日本管窺』(宇宙風社、一九三六)と思われが、この本が初出かどうかは確認していない。
それほど長い文章ではないが、その前半部分を紹介する。
日本人は「中国」のことを「支那」と称する。本来「支那」といふのには何等〈ナンラ〉悪い意味はなく、これはもと「秦」の字の晋が変化したのだと言ふ人も居る。しかし、これが日本人の口から出る場合には、欧州人が猶太〈ユダヤ〉人をデュー〔Jew〕と呼ぶのよりももつと下等になる。この態度が最も露骨に現れてゐるのは、彼等が国際関係を表示する文字の慣例だ。例へば、中国と日本とを併記する様な場合には「日支」と称するのが例になつてゐるが、これはもともと「内では魯、外では中夏」式のやり方で、恰も〈アタカモ〉支那人が「中日」と称する如く、謂はばお互様であり、土地が変れば呼び方も変るといふわけである。然るに〈シカルニ〉、この本国に対する場合の慣例は別として、その外にも大いに差別が有るのである。「支那」は其他の一個又は一個以上の国家と並列される場合にも常に下位に置かれてゐる。「英支」「仏支」「独支」「米支」「白支」「伊支」「露支」の如きその例である。甚しきに至つては暹羅〈シャム〉と並列する場合の「暹支〈センシ〉」、フイリツピンと並列する場合の「菲支〈ヒシ〉」、朝鮮と並列する場合の「鮮支」、近年はまた満洲と並列して「満支」と称し、これに日本を加へて「日満支」と称するなど、彼の『春秋』に於て蛮夷を盟約国の最下位に列したのと一様で、支那は常に最も劣等の地位に置かれてゐるのである。かういふ現象は、多少注意して日本の新聞紙を見ればすぐ解る。就中〈ナカンズク〉感心させられるのは、それが画一的に行はれてゐることだ。これらの表現法に関しては、もともと国法とか文法とかの規定が有るわけのものではないが、幾千の新聞幾万の記者が皆申し合はせた様にかういふ表示法を取つてゐるのであるから、かうした所からでも彼等の国是は窺はれるのである。
主張は明白である。「支那」という言葉自体に悪い意味はないが、その言葉が日本人の口から出るときには差別がある、と郭沫若は言う。また、日本人の「支那」に対する評価は、シャム(タイの古名)、フィリピン、朝鮮、満洲以下だという指摘も鋭いところを衝いている。
今日でも、中国のことを「シナ」と呼んでいる識者、中国のことは「シナ」と呼ぶべきだと主張している論者がいる。そうした識者、論者が中国に対して差別感情を抱いているのか否かはしばらく措く。しかし、戦前・戦中においては、この支那=シナという言葉に、中国に対する差別感情が含まれていた。今日の日本人は、少なくともこの事実だけは、認識しておく必要があるだろう。
ちなみに、郭沫若(一八九二~一九七八)は、中華民国、中華人民共和国の政治家・文学者・歴史家である。一九一四年(大正三)に来日し、一九一六年(大正五)に日本人の佐藤をとみと結婚した。一九二三年(大正一二)、九州帝国大学医科大学を卒業して、中国に帰るが、一九二八(昭和三)年に日本に亡命。日中戦争が始まった一九三七年(昭和一二)に、妻子を残して中国に帰り、国民党に参加した。
今日の名言 2012・10・27
◎今の自民党はそんなに評価できない
石原慎太郎東京都知事の言葉。今月25日の「国政復帰」記者会見の席上での発言。本日の東京新聞「こちら特報部」欄は、石原流レトリックを詳細に分析していて興味深い(構成は、佐藤圭・中山洋子)。同欄によれば、政治アナリストの伊藤惇夫氏は、石原氏の「今の自民党はそんなに評価できない」などの言葉について、自民党と決別するとは言っていないことに注目している。


















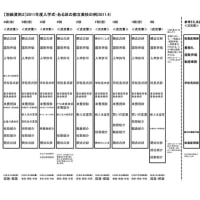
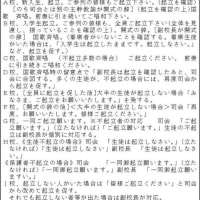








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます