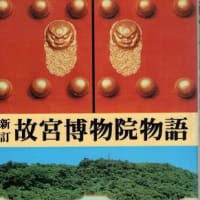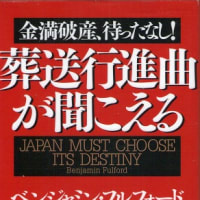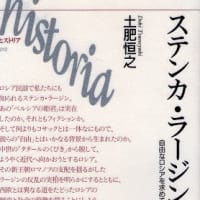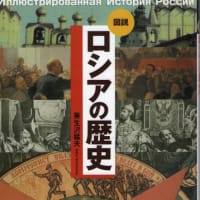例によって図書館から借りてきた本で、「泰平のしくみ」という本を読んだ。
サブタイトルには「江戸の行政と社会」となっていた。
出版社は岩波書店であった。
著者は藤田覚と言う人で、東京大学の日本近世史の教授ということであるが、とにかく読みにくい本であった。
史料の引用がふんだんにあることが良い事なのか悪い事なのかさっぱりわからない。
読む側、この場合は私自身であるが、古文の解読には馴染みがないという意味で、引用された史料が素直に読めないので、本全体が読みにくくて仕方がなかった。
凡人のやっかみとして、大学の先生たるものが、素人向けにこんなに読みにくい本を出版していいものだろうか。
学術誌や学会誌ならばともかくとして、素人向けに書いた本と思われるものがこんなに読みにくいようでは、学問が学問足り得ないのではないかと思う。
学識経験豊富な大学の先生が、素人向けに本を書くのであれば、判りやすさに重点を置いてモノを考えるべきではないかと思う。
江戸時代の約270年にわたる太平の世というのは、平和で、文化が爛熟した時期ということは十分に理解できる。
270年間も平和な時期が続いたという点では、何がそうさせたか、というその根源的なものを考えることが現代人の思いとして当然のような気がする。
私の浅薄な知識では、江戸時代イコール封建主義の時代イコール抑圧と搾取という図式でしかモノを見られないが、この本を拾い読みする限り、そうでもなさそうである。
この地球上に生れ出てきた人間は、自己の生存を維持するために必然的に群れを成して生きざるを得なかった。
ロビンソン・クルーソーのように、たった一人では生きておれないので、群れをなさなければ種の保存さえ不可能なわけで、群れを成すとなると必然的にリーダーの輩出という問題に直面する。
群れの中で、誰が一番それにふさわしいかということは、群れの構成員一人一人の思いが違っているため、かならずしも一人の人間に集約されることはないだろうが、大体は人望のある人に限定されることは間違いないだろうと思う。
だがこのケースは統治の局面であって、富の集積とはまた別の課題であることは論を待たない。
自分の仲間としての群れ、言い換えれば地域社会において、統治上の人望と富の集積の上手下手は両立しないようにみえるが、頭の良い人というのは、何ごとにも如才がないわけで、その両方を兼ね備えた人がいても不思議ではないし、現実にはそうなっている。
人の群れ、いわゆる民族にもその大きさの大小があるわけで、大きくて広範な地域に広がって生きているグループと、小さなグループで狭い地域にまとまって生きているグループがある。
これらには当然のこと各々のグループに適した生き方の相違がある。
その相違こそが文化というものであるが、そういう意味では統治の手法も、文化の一側面をなしているといえるが、統治という作為は、安全保障も民心の安定ということも、合わせ持っている。
江戸時代、約270年の太平の世というのは、この両方が見事にバランスよく機能した時期と言える。
それは我々の民族の置かれた環境が、四周を海で囲まれた特異な状況であったということも大きく影響していることは言うまでもない。
とはいうものの、その中で生きていた民族が優れていたから270年も安泰の世が続いたということもいえる。普通の自然の成り行きを素朴に考えれば、原始人の集落の中においても、富を集積できる人とそうでない人は、必然的に分かれてくると思う。
富を集積できる人は、周りの人より何処か優れた点があったからこそ富を集積できたので、それは同時に人を統率する才にも長けていたに違いないと思われる。
封建領主が人々を抑圧し搾取し続けたというイメージは、共産主義者に依って歪められたイメージであって、封建時代だからと言って、全部が全部、悪代官ばかりであっというのは間違った認識だと思う。
この本に描かれた江戸時代の人々は、決して搾取されるばかりの人々ではなく、今の日本社会と極めてよく似た社会状況であったみたいだ。
そのことは言い方を変えれば極めて民主的な社会ができていたということが言える。
と言うよりも、当時の武士階級というのは、今の社会に置き換えれば、各省庁の官僚の立場に酷似しているが、この官僚が案外下々のことを念頭に置いて行政を司どっていたように見える。
決して、上から下への一方通行ではなくて、相互に意見を交換し合って、落としどころを探り合っていたように思える。
そして、統治する側としては、社会的インフラ整備を実施するについて、誰に何をどうさせればいいか、という問題は極めて難しい問題で、入札という方法に落ち着くのだが、これはこれで談合という不明朗な仕組みを誘発してしまうので、統治する側としては頭の痛い事であったに違いない。
しかし、「入札や談合が不明朗だからいけない」、というのは現在の価値観であって、社会システムが複雑化してきて、利害得失が輻輳する中においては、こういう手法の意義も大いにあったと考えるべきだ。
談合などは「業者側が不当に儲けるからいけない」という論理であるが、確かに適正価格を大幅に逸脱すれば不整合を指摘されても仕方がないが、業者側は業者側として、従業員を養っていかねばならないので赤字を承知で請けることも叶わないであろうと思う。
江戸時代においては、今の日本のように民主主義が確定していたわけでもないのに、案外民主的な手法で統治、行政が執り行われていたようである。
テレビの時代劇で見るように、悪代官が全国で跋扈していた風にも見えない。
案外、民主的な手法が広まっていたように見えるが、それは同時にその時代の人々の発想が民主的な思考に極めて近い事を指し示していると思う。
江戸時代と今日では、同じ日本人でもその数に大きな開きがあると思う。
江戸時代は今よりもうんと日本人の数がすくなかったに違いない。
しかし、我々の民族としてのモノ考え方は、あまり大きく変化することなく今日まで来ていると思う。
ところがここで江戸時代が終わって、新しい明治という時代を迎えると、我々の古来のモノの考え方は、新しい西洋の潮流に席巻されて、その基底にぐらつきが生じてきた。
明治維新を経て、新しい西洋の考え方を目の当たりにしたとき、自分たちの古来の考え方が間違っていたのではないか、という不信感に苛まれてしまった。
結果として、それがその後の革新的な思考として確立されて、日本の大学の先生方が、それに権威付けを行ってしまった。
我々は四周を海という外壁で囲まれていたので、その中である意味で純粋培養されたようなもので、日本流の民主主義がその中では醸成されていた。
ところが、この日本流の民主主義というのは、キリスト教文化圏で言うところの民主主義とは一味も二味も違っていたが、その微妙なニュアンスの違いを表現する適当な言葉がなかったので同じ民主主義という言葉で間に合わせしまった。
だから、その本質のところで大きな相違を内在しているにもかかわらず、今の我々が民主主義という場合、キリスト教文化圏のイメージでそれを理解しているので、どうしても細部に齟齬が生じている。
例えば、「多数決で事を決める」という時、我々の学識経験豊富な人々は、全員一致でなければ多数決と認めない。
これでは絶対主義そのものであるにも関わらず、日本の学者先生方は「少数意見をどうするのだ?」という原理原則を踏みにじってまで綺麗ごとを並べ、良い子ぶるが、民主主義にも多数決にも、負の側面を併せ持っていることを無視して、良い面のみを汲み取ろうとするから、こういう不合理が罷り通るのである。
キリスト教文化圏でいう民主的な多数決原理に則れば、51:49で事が決しても、それはそれで認めなければならないが、我々の学者先生の発想では、「その49の意見は全く無視して良いのか」ということになる。
キリスト教文化圏では、この部分はいた仕方ないという認識で、素直に敗北を認める思考であろうけれども、我々の学者先生の思考は、そう単純に諦め切れずにしこりが残る。
だから我々の場合は、こういうケースでは示談ということが行われて、限りなく絶対主義に近いが、決定は密室で行われ、単純明快に結論を導き出すのではなく、粘り強い交渉で、大方の総意をとりつけて、違う意見の人をできるだけ納得させるべく知恵を出し合う努力をするのである。
ところがこういうケースでも、西洋の新しい思想、特に共産主義というような極めて人間の理想の実現にエネルギーを傾注しようとする新思考に、人々は感化しやすいわけで、それに真っ先に感化したのが皮肉なことに大学をはじめとする智識階層であった。
これは、かっては仏教に帰依し、後にはキリスト教に帰依し、その後では共産主義に身も心も捧げた構図であって、我々の民族の歴史的軌跡であるといってもいいと思う。
そしてこういう誘惑に一番弱い人々は、知的に優れた人たちで、高学歴で、体制に不満を持つ日和見な人々である。
共産主義の理念というのは、非の打ちようのない人間の理想社会を描き出しているわけで、純粋で心に穢れのない人間ほど、その理想の虜になり、現実の社会を直視することを忌避して、絵に描いた餅を追いかけることになるのである。
こういう絵に描いた餅を追い求める無知蒙昧な大衆に対して、「そういう無為な行為に現を抜かしていてはいけませんよ」と、現実を直視すべく若者をリードすべきが本来の大学の先生方の使命ではなかろうか。
こういう理想の実現には、今、目の前にある現実の秩序を御破算にしないことには次なる新しい社会の建設には進めないので、とにもかくにも、現行の秩序破壊に血道を開けているのである。
その結果として、統治者、為政者、お上、権力者等々の提示する新しい建設的な意見には、すべて反対意見を投じ、統治、あるいは行政の施策が滞るように仕向けるのである。
彼らの行動の原理としては、自らの責任とか成果が、為政者のする施策を邪魔するだけなので、民族だとか国家だとか同胞のためにするという認識はいささかもない。
そういう思考を、戦後の大学と称する高等教育の場で若者に教えていたわけで、公立の高等教育の機関で、こういう教育を受けた次世代が、古い価値観の国家意識を醸成するわけがない。
江戸時代でも、持ち場立場で利害得失が異なっているのは当然で、為政者としては何らかの裁定を下さねばならない場合も多々あったにちがいない。
こういう場合に公平という価値観も当然存在していたに違いないと思うが、その裁定は多数決で決められたとも思えない。
今まで述べた様に、示談とか、談合とか、入札という手段で裁定がなされたと思うが、この事実を今の日本の学識経験者の感覚で言えば、「古い封建主義的な問題解決の手法」ということになるのであろう。
我々日本民族は、古来からこういう問題解決の知恵を持っていたにもかかわらず、明治維新で西洋のキリスト教的な新思考に接すると、旧来の自分たちの知恵に自信を無くして、自分たちは古い人間だと勘違いしてしまった。
この間違った認識が、我々、日本民族の上に暗雲のごとく覆いかぶさって、我々は古い思考を捨てて、新しい思考に一刻も早く乗り換えなければ時流に乗り遅れると勘違いしてしまった。
いわゆる昭和時代の初期に流行った「バスに乗り遅れるな」という思考と同じであって、西洋のものなら何でもかんでも憧憬の眼差しで見入るという風潮におちいってしまったのである。
その最も顕著な例は、為政者の指示に従わないということで、お上の言うことには何でもかんでも反対するという風潮である。
この本の中でも頻繁に述べられているが、江戸時代の幕府も、案外、下々の生活には気を配っていたようだが、こういう事はどういうものか歴史として表面に出ることがなく、歴史と言えば為政者の歴史しか歴史として認識されない。
だから江戸時代の物語で注目を集めるのは悪代官のような体制側の悪人しか話題に上らないのである。
いつの世でも、善政を敷いた為政者は、それが統治として極めてスタンダードな有体であるが故に、話題性に乏しく、悪い為政者こそが後世の語り草としては価値が大きいということになる。
サブタイトルには「江戸の行政と社会」となっていた。
出版社は岩波書店であった。
著者は藤田覚と言う人で、東京大学の日本近世史の教授ということであるが、とにかく読みにくい本であった。
史料の引用がふんだんにあることが良い事なのか悪い事なのかさっぱりわからない。
読む側、この場合は私自身であるが、古文の解読には馴染みがないという意味で、引用された史料が素直に読めないので、本全体が読みにくくて仕方がなかった。
凡人のやっかみとして、大学の先生たるものが、素人向けにこんなに読みにくい本を出版していいものだろうか。
学術誌や学会誌ならばともかくとして、素人向けに書いた本と思われるものがこんなに読みにくいようでは、学問が学問足り得ないのではないかと思う。
学識経験豊富な大学の先生が、素人向けに本を書くのであれば、判りやすさに重点を置いてモノを考えるべきではないかと思う。
江戸時代の約270年にわたる太平の世というのは、平和で、文化が爛熟した時期ということは十分に理解できる。
270年間も平和な時期が続いたという点では、何がそうさせたか、というその根源的なものを考えることが現代人の思いとして当然のような気がする。
私の浅薄な知識では、江戸時代イコール封建主義の時代イコール抑圧と搾取という図式でしかモノを見られないが、この本を拾い読みする限り、そうでもなさそうである。
この地球上に生れ出てきた人間は、自己の生存を維持するために必然的に群れを成して生きざるを得なかった。
ロビンソン・クルーソーのように、たった一人では生きておれないので、群れをなさなければ種の保存さえ不可能なわけで、群れを成すとなると必然的にリーダーの輩出という問題に直面する。
群れの中で、誰が一番それにふさわしいかということは、群れの構成員一人一人の思いが違っているため、かならずしも一人の人間に集約されることはないだろうが、大体は人望のある人に限定されることは間違いないだろうと思う。
だがこのケースは統治の局面であって、富の集積とはまた別の課題であることは論を待たない。
自分の仲間としての群れ、言い換えれば地域社会において、統治上の人望と富の集積の上手下手は両立しないようにみえるが、頭の良い人というのは、何ごとにも如才がないわけで、その両方を兼ね備えた人がいても不思議ではないし、現実にはそうなっている。
人の群れ、いわゆる民族にもその大きさの大小があるわけで、大きくて広範な地域に広がって生きているグループと、小さなグループで狭い地域にまとまって生きているグループがある。
これらには当然のこと各々のグループに適した生き方の相違がある。
その相違こそが文化というものであるが、そういう意味では統治の手法も、文化の一側面をなしているといえるが、統治という作為は、安全保障も民心の安定ということも、合わせ持っている。
江戸時代、約270年の太平の世というのは、この両方が見事にバランスよく機能した時期と言える。
それは我々の民族の置かれた環境が、四周を海で囲まれた特異な状況であったということも大きく影響していることは言うまでもない。
とはいうものの、その中で生きていた民族が優れていたから270年も安泰の世が続いたということもいえる。普通の自然の成り行きを素朴に考えれば、原始人の集落の中においても、富を集積できる人とそうでない人は、必然的に分かれてくると思う。
富を集積できる人は、周りの人より何処か優れた点があったからこそ富を集積できたので、それは同時に人を統率する才にも長けていたに違いないと思われる。
封建領主が人々を抑圧し搾取し続けたというイメージは、共産主義者に依って歪められたイメージであって、封建時代だからと言って、全部が全部、悪代官ばかりであっというのは間違った認識だと思う。
この本に描かれた江戸時代の人々は、決して搾取されるばかりの人々ではなく、今の日本社会と極めてよく似た社会状況であったみたいだ。
そのことは言い方を変えれば極めて民主的な社会ができていたということが言える。
と言うよりも、当時の武士階級というのは、今の社会に置き換えれば、各省庁の官僚の立場に酷似しているが、この官僚が案外下々のことを念頭に置いて行政を司どっていたように見える。
決して、上から下への一方通行ではなくて、相互に意見を交換し合って、落としどころを探り合っていたように思える。
そして、統治する側としては、社会的インフラ整備を実施するについて、誰に何をどうさせればいいか、という問題は極めて難しい問題で、入札という方法に落ち着くのだが、これはこれで談合という不明朗な仕組みを誘発してしまうので、統治する側としては頭の痛い事であったに違いない。
しかし、「入札や談合が不明朗だからいけない」、というのは現在の価値観であって、社会システムが複雑化してきて、利害得失が輻輳する中においては、こういう手法の意義も大いにあったと考えるべきだ。
談合などは「業者側が不当に儲けるからいけない」という論理であるが、確かに適正価格を大幅に逸脱すれば不整合を指摘されても仕方がないが、業者側は業者側として、従業員を養っていかねばならないので赤字を承知で請けることも叶わないであろうと思う。
江戸時代においては、今の日本のように民主主義が確定していたわけでもないのに、案外民主的な手法で統治、行政が執り行われていたようである。
テレビの時代劇で見るように、悪代官が全国で跋扈していた風にも見えない。
案外、民主的な手法が広まっていたように見えるが、それは同時にその時代の人々の発想が民主的な思考に極めて近い事を指し示していると思う。
江戸時代と今日では、同じ日本人でもその数に大きな開きがあると思う。
江戸時代は今よりもうんと日本人の数がすくなかったに違いない。
しかし、我々の民族としてのモノ考え方は、あまり大きく変化することなく今日まで来ていると思う。
ところがここで江戸時代が終わって、新しい明治という時代を迎えると、我々の古来のモノの考え方は、新しい西洋の潮流に席巻されて、その基底にぐらつきが生じてきた。
明治維新を経て、新しい西洋の考え方を目の当たりにしたとき、自分たちの古来の考え方が間違っていたのではないか、という不信感に苛まれてしまった。
結果として、それがその後の革新的な思考として確立されて、日本の大学の先生方が、それに権威付けを行ってしまった。
我々は四周を海という外壁で囲まれていたので、その中である意味で純粋培養されたようなもので、日本流の民主主義がその中では醸成されていた。
ところが、この日本流の民主主義というのは、キリスト教文化圏で言うところの民主主義とは一味も二味も違っていたが、その微妙なニュアンスの違いを表現する適当な言葉がなかったので同じ民主主義という言葉で間に合わせしまった。
だから、その本質のところで大きな相違を内在しているにもかかわらず、今の我々が民主主義という場合、キリスト教文化圏のイメージでそれを理解しているので、どうしても細部に齟齬が生じている。
例えば、「多数決で事を決める」という時、我々の学識経験豊富な人々は、全員一致でなければ多数決と認めない。
これでは絶対主義そのものであるにも関わらず、日本の学者先生方は「少数意見をどうするのだ?」という原理原則を踏みにじってまで綺麗ごとを並べ、良い子ぶるが、民主主義にも多数決にも、負の側面を併せ持っていることを無視して、良い面のみを汲み取ろうとするから、こういう不合理が罷り通るのである。
キリスト教文化圏でいう民主的な多数決原理に則れば、51:49で事が決しても、それはそれで認めなければならないが、我々の学者先生の発想では、「その49の意見は全く無視して良いのか」ということになる。
キリスト教文化圏では、この部分はいた仕方ないという認識で、素直に敗北を認める思考であろうけれども、我々の学者先生の思考は、そう単純に諦め切れずにしこりが残る。
だから我々の場合は、こういうケースでは示談ということが行われて、限りなく絶対主義に近いが、決定は密室で行われ、単純明快に結論を導き出すのではなく、粘り強い交渉で、大方の総意をとりつけて、違う意見の人をできるだけ納得させるべく知恵を出し合う努力をするのである。
ところがこういうケースでも、西洋の新しい思想、特に共産主義というような極めて人間の理想の実現にエネルギーを傾注しようとする新思考に、人々は感化しやすいわけで、それに真っ先に感化したのが皮肉なことに大学をはじめとする智識階層であった。
これは、かっては仏教に帰依し、後にはキリスト教に帰依し、その後では共産主義に身も心も捧げた構図であって、我々の民族の歴史的軌跡であるといってもいいと思う。
そしてこういう誘惑に一番弱い人々は、知的に優れた人たちで、高学歴で、体制に不満を持つ日和見な人々である。
共産主義の理念というのは、非の打ちようのない人間の理想社会を描き出しているわけで、純粋で心に穢れのない人間ほど、その理想の虜になり、現実の社会を直視することを忌避して、絵に描いた餅を追いかけることになるのである。
こういう絵に描いた餅を追い求める無知蒙昧な大衆に対して、「そういう無為な行為に現を抜かしていてはいけませんよ」と、現実を直視すべく若者をリードすべきが本来の大学の先生方の使命ではなかろうか。
こういう理想の実現には、今、目の前にある現実の秩序を御破算にしないことには次なる新しい社会の建設には進めないので、とにもかくにも、現行の秩序破壊に血道を開けているのである。
その結果として、統治者、為政者、お上、権力者等々の提示する新しい建設的な意見には、すべて反対意見を投じ、統治、あるいは行政の施策が滞るように仕向けるのである。
彼らの行動の原理としては、自らの責任とか成果が、為政者のする施策を邪魔するだけなので、民族だとか国家だとか同胞のためにするという認識はいささかもない。
そういう思考を、戦後の大学と称する高等教育の場で若者に教えていたわけで、公立の高等教育の機関で、こういう教育を受けた次世代が、古い価値観の国家意識を醸成するわけがない。
江戸時代でも、持ち場立場で利害得失が異なっているのは当然で、為政者としては何らかの裁定を下さねばならない場合も多々あったにちがいない。
こういう場合に公平という価値観も当然存在していたに違いないと思うが、その裁定は多数決で決められたとも思えない。
今まで述べた様に、示談とか、談合とか、入札という手段で裁定がなされたと思うが、この事実を今の日本の学識経験者の感覚で言えば、「古い封建主義的な問題解決の手法」ということになるのであろう。
我々日本民族は、古来からこういう問題解決の知恵を持っていたにもかかわらず、明治維新で西洋のキリスト教的な新思考に接すると、旧来の自分たちの知恵に自信を無くして、自分たちは古い人間だと勘違いしてしまった。
この間違った認識が、我々、日本民族の上に暗雲のごとく覆いかぶさって、我々は古い思考を捨てて、新しい思考に一刻も早く乗り換えなければ時流に乗り遅れると勘違いしてしまった。
いわゆる昭和時代の初期に流行った「バスに乗り遅れるな」という思考と同じであって、西洋のものなら何でもかんでも憧憬の眼差しで見入るという風潮におちいってしまったのである。
その最も顕著な例は、為政者の指示に従わないということで、お上の言うことには何でもかんでも反対するという風潮である。
この本の中でも頻繁に述べられているが、江戸時代の幕府も、案外、下々の生活には気を配っていたようだが、こういう事はどういうものか歴史として表面に出ることがなく、歴史と言えば為政者の歴史しか歴史として認識されない。
だから江戸時代の物語で注目を集めるのは悪代官のような体制側の悪人しか話題に上らないのである。
いつの世でも、善政を敷いた為政者は、それが統治として極めてスタンダードな有体であるが故に、話題性に乏しく、悪い為政者こそが後世の語り草としては価値が大きいということになる。