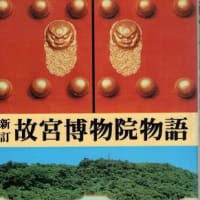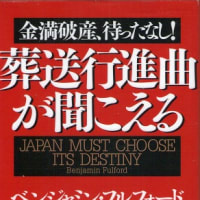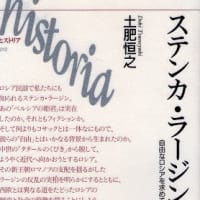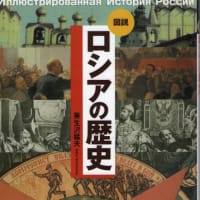例によって図書館から借りてきた本で、「無一文の億万長者」という本を読んだ。
ツアーで海外旅行に出掛けると、おそらくDFSの店に案内された経験は一度や二度ではないと思う。
このDFSを立ち上げた人物のサクセス・ストーリであった。
生い立ちから始まって、如何に苦労してのし上がったかというストーリーであるが、それはそれなりに興味深い読み物でもある。
ところが、このDFSの創業者のチャールズ・フィーニーという人物は、成功した後の考え方が、並みの人物ではないところがより興味深い。
ビジネス界である程度の成功を納めるというのは、この世に数えきれないほどの企業が存在している限り、その数と同じだけ成功者がいるということだと思う。
並みの経営者がビル・ゲイツやチャールズ・フィーニーと違うところは、その規模の大きさのみで、企業主の全てが、最初はゼロから企業を立ち上げて、無から有を築きあげたものだと私は思う。
人それぞれに苦労して現在の地位を得たに違いないものと思う。
今、日本の政治は転換期を迎えて、自民党が没落して民主党が旭日の勢いであるが、この騒動の中で「格差の是正」ということが双方で声高に叫ばれている。
これって本当はおかしなことではなかろうか。
人が複数集まった社会の中で、皆が一律に均一ということはあり得ないわけで、それを理想に掲げた共産主義というものは、すでに崩壊して久しいわけで、人の集団から「格差をなくす」などということはあり得ないことである。
共産主義の理念だって、この世から貧富の格差をなくすことにあったわけで、その為には金持ちを殺してバカな大衆に統治を任せよう、という発想であったわけである。
今の政治家は共産主義を振り回すような愚は犯していないが、基本的に「格差の是正」といえば、行く着く先は同一労働同一賃金に行きつかなければならないわけで、こういう矛盾を知ってか知らずか、綺麗事で能書きを並べているとしたら、政治を弄んでいるに等しい行為だと思う。
DFSの創業者、チャールズ・フィーニーという人のサクセス・ストーリーは、極めつけの資本主義社会の中で自分の富を得る創意工夫に徹した結果として、成功を収めた例であろう。
人が金儲けのためだけに生きるとするならば、もっともっと殺伐とした世の中になっていると思う。
この世には、金儲けよりも人助け、子供の教育、物作り、芸術に自分の力を注いでみたい、という名もなき大勢の人がいると思う。
メデイアに一度も取り上げられることもなく、誰からも称賛されることもなく、それこそ名もなく金も名誉も得ることなく生涯を閉じる人も大勢いると思う。
世の中というのは突き詰めればそういう人たちで成り立っているわけで、成功してメデイアに大々的に取り上げられる人の方が少ない筈である。
大部分の庶民と呼ばれる人たちは、基本的に、名もなく貧しく美しく生涯を生き抜いていると思うが、問題は「貧しく」の内容と質が問われているわけである。
激動の連続であった昭和の時代には、日本でも数多くのサクセス・ストーリーが生まれた。
松下幸之助、本田宗一郎、盛田昭夫等々、立派な起業家もこの時代には数多く輩出しているが、日本人の起業家の場合、それが物作りの方に偏在してしまって、純粋に商業の部分、いわゆるマーチャンダイズの面では、物作りに比べると人々の意識がいささか後ろ向きの感がしないでもない。
我々は、長い江戸時代の庶民感覚をそうそう綺麗さっぱりと払しょくしきれず、士農工商の秩序が潜在意識の中に澱となって残っているのであろう。
成功した人の生き方というのは、それこそ努力の上に努力を重ねて、アイデアを絞りだし、それを果敢に実践した結果として成功という果実が実るわけで、私が今年金だけの汲々した生活を余儀なく強いられているのは、そういう努力を怠ったからに他ならない。
私の個人的な例でいえば、私は金儲けという行為に対してあまり関心がなかった。
食うに足るだけの実入りがあればそれで十分だと思い、それ以上の金を得るということについては、考えたこともなかった。
今の生活が維持できていればそれで十分で、ほんの少し欲を言えば、本を自由に買う金があればいいなあと思うこともあるが、これも図書館を利用すればことは足りるわけで、その為に体を酷使して金を稼ぐということはご免こうむりたい。
今、巷に氾濫している若者、ニートだとか、フリーターだとか、派遣社員というのは、この私の思考と全く同じ考え方の若者ではないかと思う。
私を含めて、今の我々の生きている空間というのは、完全に満ち足りた空間なわけで、基本的に何もしなくても生きていける世の中に身を置いているのである。
派遣切りで仕事がないといっても、生きるだけならばなんとでもなるわけで、そういう状況に甘え切っているから社会問題と化しているのである。
終戦直後のように食うもの自体がない時代ならば、いかなる手段を講じようとも、まず自分が生き切ることが先決問題であったわけで、仕事が厭だとか、きついなどという不平不満は言っておれなかった。
人が事業に成功するということは、こういうハングリー精神を常に維持していないことには、成功という果実は採れないのではなかろうか。
それを人々は、夢とか希望とか表現しているが、「若者ならば夢をもて」だとか、「希望を捨てるな」とか言って、若者のやる気を煽りがちであるが、こういう若者を扇動するような綺麗事の言葉は罪つくりだと思う。
若者に「自分の好きなことを続けよ」とか、「自分に納得の出来る仕事を探せ」だとか、若者の理想を煽る言葉を安易に使っているが、若者には現実の惨さをもっともっと知らしめるべきだと思う。
この本を読んで、企業家の心の在り方にやはりノブレス・オブリージというものがあるように思えた。
このDFSを立ち上げたチャールズ・フィーニーという人は、わずか50歳代で、億万長者になったわけだが、億万長者になってしまうと今度は慈善事業家になってしまって、匿名で寄付することを生きがいにするようになったということだ。
成功した人の、その後の在り方というのは、こうでなければならないと思う。
ビル・ゲイツも大規模な寄付をしたという話を聞いた覚えがあるし、有名な話としては鉄鋼王のカーネ-ギーも、大口の寄付をしたことは既存の事実であるが、アメリカ人が儲けた金を社会に還元する発想は実に素晴らしいことだと思う。
功成り名を成した人が死んだ後でどのように検証されるかということは、貧乏人の僻み根性として極めて興味あるところであるが、アメリカの元大統領のジョン・F・ケネデイーとその弟のロバート・ケネデイーの墓は、実に質素そのものである。
緩やかな丘の上に永遠の火こそ絶えることなく燃えているが、墓標らしきものはなく、火の前の銘盤がそれを示すだけの実に簡素なものである。
そこにいくと日本の経営者の墓というのは実に立派なものが多く、生前の偉業を誇示せんばかりのこけおどしの体を成したものがあまりにも多い。
日本の経営者の中にも、儲けた金を社会に還元しなければ、と考える人は大勢いるわけで、基金を作ったり、美術館のようなものを作って一般公開する会社もたくさんある。
それはそれで一つの企業としてのノブレス・オブリージだと私は考える。
ただこの本に描かれているDFSを立ち上げたチャールズ・フィーニーの特異なところは、それを完全に匿名で行うという点にある。
ひところ、メセナという言葉が飛び交い、企業の文化活動が声高に叫ばれた時期があったが、このメセナにしろ、基金や美術館の建築というような動きにしても、企業の儲けを社会に還元するということは、仮にその企業の宣伝や広報に利用されたとしても、それはそれでいいと思う。
冠つきのイベント、冠つきの施設など、いくら冠がついていようとも、利用者がそれを享受出来れば、それに越したことはないわけで、堂々と企業名を入れたイベントや施設でも、無いよりはましだ。
ところが、このチャールズ・フィーニーは、匿名に徹底的にこだわったわけで、その部分が実に特異だと思う。
企業名や奇贈者の名前があろうが無かろうが、受け取る側の有り難さはそれによって変わるものではない筈で、それはただただ贈る側の自意識の問題でしかない。
人にものを贈るということは、まさしく贈る本人の心まで心地よい気分にさせ、何か良い事をした気分に浸ることになり、心が軽やかになるものと考える。
人に恵むという行為は、そういう要素を秘めた行為のように思える。
如何なる宗教でも、寄付を否定する宗教はないわけで、全てが貧しきものに寄付をすることを善と見なしているわけで、その意味からすれば、寄付をするということは人間の深層心理の善の欲求を満たす行為ということになりうる。
我々、凡庸な人間は、今あるものをもっと大きく、もっと沢山、より多く手に持ちたいという欲望にかられるが、これこそ人間の煩悩というものであろう。
しかし、この世に生を受けたいかなる人間でも、三途の川を渡るときにはなにも持っていけないわけで、生まれた時に裸であったように、彼岸に行く時も身一つの裸で行くしかない。
しかし、それが解っていながら、死ぬまで富を手にしたいという人間の心は全く私には理解しかねる。
死んだ後のことまで悩みながら死んでいく人の心がわからない。
この本の主人公、チャールズ・フィーニーという人は、ビジネスをゲームと認識していたのではないかと思う。
こういう風に考えれば、人生もかなり気楽に生きれると思うが、こうなるまでにはかなりの原資を用意する必要があるわけで、私ごときが、「人生はゲームだ」などと言いだせば、その日から家族が路頭に迷うことになる。
今はやりの蟹工船ではないが、いくら虐げられても、おおんぼろ船から逃げ出すわけにはいかない。
今の若者は、この部分で、極めつけの極楽トンボを決め込んでいるので、派遣切りだとか、仕事が無いとか、仕事が気に入らないから辞めるなどという贅沢が許されているのだと思う。
如何なる社会でも同じだと思うが、報われる人というのは、それだけの努力をしているわけで、この本の主人公も、ごくごく小さい時から自分の才覚で金を稼ぐということをしているわけで、今の日本の若者は、その部分が全く未成熟だと思う。
これは今の若者だけが悪いのではなく、彼らの親、彼らの祖父母までが、代々自分の子供を甘えさせて育ててきたわけで、言い換えれば民族の潜在意識として、自分の才覚で稼ぐということを忌避してきた結果だと思う。
日本でも昭和の初期までは、家族の中の子供は小さいながらも労働力であった。
ところが日本の近代化が進むに従い、子供の扱い方が変わってきて、子供には学歴を付けて立身出世をしてもらうことが親としての喜びとなった。
いわゆる親離れ子離れが未成熟で、自分の子供が可愛いから自分と同じ苦労をさせたくない、良い学校に行って、良い大学に入って、良い会社に就職することが、本人を含めた家族の願いとなったわけである。
だから子供が日銭稼ぎの仕事に精を出すよりも、机に向かって勉強してもらった方が親としては喜ばしいという思考に至った。
この思考が3代続いた結果として今の若者は働くということを安易に考え、働かなくても食うだけはできるので、飢えを知らないが故に甘えているのである。
そこに以ってきて、物わかりの良い知識人というというな人達が、「そういう若者を救済しなければならない」などと綺麗事のご都合主義の言辞を並べるから、彼らはますますハングリー精神を喪失してしまうのである。
ツアーで海外旅行に出掛けると、おそらくDFSの店に案内された経験は一度や二度ではないと思う。
このDFSを立ち上げた人物のサクセス・ストーリであった。
生い立ちから始まって、如何に苦労してのし上がったかというストーリーであるが、それはそれなりに興味深い読み物でもある。
ところが、このDFSの創業者のチャールズ・フィーニーという人物は、成功した後の考え方が、並みの人物ではないところがより興味深い。
ビジネス界である程度の成功を納めるというのは、この世に数えきれないほどの企業が存在している限り、その数と同じだけ成功者がいるということだと思う。
並みの経営者がビル・ゲイツやチャールズ・フィーニーと違うところは、その規模の大きさのみで、企業主の全てが、最初はゼロから企業を立ち上げて、無から有を築きあげたものだと私は思う。
人それぞれに苦労して現在の地位を得たに違いないものと思う。
今、日本の政治は転換期を迎えて、自民党が没落して民主党が旭日の勢いであるが、この騒動の中で「格差の是正」ということが双方で声高に叫ばれている。
これって本当はおかしなことではなかろうか。
人が複数集まった社会の中で、皆が一律に均一ということはあり得ないわけで、それを理想に掲げた共産主義というものは、すでに崩壊して久しいわけで、人の集団から「格差をなくす」などということはあり得ないことである。
共産主義の理念だって、この世から貧富の格差をなくすことにあったわけで、その為には金持ちを殺してバカな大衆に統治を任せよう、という発想であったわけである。
今の政治家は共産主義を振り回すような愚は犯していないが、基本的に「格差の是正」といえば、行く着く先は同一労働同一賃金に行きつかなければならないわけで、こういう矛盾を知ってか知らずか、綺麗事で能書きを並べているとしたら、政治を弄んでいるに等しい行為だと思う。
DFSの創業者、チャールズ・フィーニーという人のサクセス・ストーリーは、極めつけの資本主義社会の中で自分の富を得る創意工夫に徹した結果として、成功を収めた例であろう。
人が金儲けのためだけに生きるとするならば、もっともっと殺伐とした世の中になっていると思う。
この世には、金儲けよりも人助け、子供の教育、物作り、芸術に自分の力を注いでみたい、という名もなき大勢の人がいると思う。
メデイアに一度も取り上げられることもなく、誰からも称賛されることもなく、それこそ名もなく金も名誉も得ることなく生涯を閉じる人も大勢いると思う。
世の中というのは突き詰めればそういう人たちで成り立っているわけで、成功してメデイアに大々的に取り上げられる人の方が少ない筈である。
大部分の庶民と呼ばれる人たちは、基本的に、名もなく貧しく美しく生涯を生き抜いていると思うが、問題は「貧しく」の内容と質が問われているわけである。
激動の連続であった昭和の時代には、日本でも数多くのサクセス・ストーリーが生まれた。
松下幸之助、本田宗一郎、盛田昭夫等々、立派な起業家もこの時代には数多く輩出しているが、日本人の起業家の場合、それが物作りの方に偏在してしまって、純粋に商業の部分、いわゆるマーチャンダイズの面では、物作りに比べると人々の意識がいささか後ろ向きの感がしないでもない。
我々は、長い江戸時代の庶民感覚をそうそう綺麗さっぱりと払しょくしきれず、士農工商の秩序が潜在意識の中に澱となって残っているのであろう。
成功した人の生き方というのは、それこそ努力の上に努力を重ねて、アイデアを絞りだし、それを果敢に実践した結果として成功という果実が実るわけで、私が今年金だけの汲々した生活を余儀なく強いられているのは、そういう努力を怠ったからに他ならない。
私の個人的な例でいえば、私は金儲けという行為に対してあまり関心がなかった。
食うに足るだけの実入りがあればそれで十分だと思い、それ以上の金を得るということについては、考えたこともなかった。
今の生活が維持できていればそれで十分で、ほんの少し欲を言えば、本を自由に買う金があればいいなあと思うこともあるが、これも図書館を利用すればことは足りるわけで、その為に体を酷使して金を稼ぐということはご免こうむりたい。
今、巷に氾濫している若者、ニートだとか、フリーターだとか、派遣社員というのは、この私の思考と全く同じ考え方の若者ではないかと思う。
私を含めて、今の我々の生きている空間というのは、完全に満ち足りた空間なわけで、基本的に何もしなくても生きていける世の中に身を置いているのである。
派遣切りで仕事がないといっても、生きるだけならばなんとでもなるわけで、そういう状況に甘え切っているから社会問題と化しているのである。
終戦直後のように食うもの自体がない時代ならば、いかなる手段を講じようとも、まず自分が生き切ることが先決問題であったわけで、仕事が厭だとか、きついなどという不平不満は言っておれなかった。
人が事業に成功するということは、こういうハングリー精神を常に維持していないことには、成功という果実は採れないのではなかろうか。
それを人々は、夢とか希望とか表現しているが、「若者ならば夢をもて」だとか、「希望を捨てるな」とか言って、若者のやる気を煽りがちであるが、こういう若者を扇動するような綺麗事の言葉は罪つくりだと思う。
若者に「自分の好きなことを続けよ」とか、「自分に納得の出来る仕事を探せ」だとか、若者の理想を煽る言葉を安易に使っているが、若者には現実の惨さをもっともっと知らしめるべきだと思う。
この本を読んで、企業家の心の在り方にやはりノブレス・オブリージというものがあるように思えた。
このDFSを立ち上げたチャールズ・フィーニーという人は、わずか50歳代で、億万長者になったわけだが、億万長者になってしまうと今度は慈善事業家になってしまって、匿名で寄付することを生きがいにするようになったということだ。
成功した人の、その後の在り方というのは、こうでなければならないと思う。
ビル・ゲイツも大規模な寄付をしたという話を聞いた覚えがあるし、有名な話としては鉄鋼王のカーネ-ギーも、大口の寄付をしたことは既存の事実であるが、アメリカ人が儲けた金を社会に還元する発想は実に素晴らしいことだと思う。
功成り名を成した人が死んだ後でどのように検証されるかということは、貧乏人の僻み根性として極めて興味あるところであるが、アメリカの元大統領のジョン・F・ケネデイーとその弟のロバート・ケネデイーの墓は、実に質素そのものである。
緩やかな丘の上に永遠の火こそ絶えることなく燃えているが、墓標らしきものはなく、火の前の銘盤がそれを示すだけの実に簡素なものである。
そこにいくと日本の経営者の墓というのは実に立派なものが多く、生前の偉業を誇示せんばかりのこけおどしの体を成したものがあまりにも多い。
日本の経営者の中にも、儲けた金を社会に還元しなければ、と考える人は大勢いるわけで、基金を作ったり、美術館のようなものを作って一般公開する会社もたくさんある。
それはそれで一つの企業としてのノブレス・オブリージだと私は考える。
ただこの本に描かれているDFSを立ち上げたチャールズ・フィーニーの特異なところは、それを完全に匿名で行うという点にある。
ひところ、メセナという言葉が飛び交い、企業の文化活動が声高に叫ばれた時期があったが、このメセナにしろ、基金や美術館の建築というような動きにしても、企業の儲けを社会に還元するということは、仮にその企業の宣伝や広報に利用されたとしても、それはそれでいいと思う。
冠つきのイベント、冠つきの施設など、いくら冠がついていようとも、利用者がそれを享受出来れば、それに越したことはないわけで、堂々と企業名を入れたイベントや施設でも、無いよりはましだ。
ところが、このチャールズ・フィーニーは、匿名に徹底的にこだわったわけで、その部分が実に特異だと思う。
企業名や奇贈者の名前があろうが無かろうが、受け取る側の有り難さはそれによって変わるものではない筈で、それはただただ贈る側の自意識の問題でしかない。
人にものを贈るということは、まさしく贈る本人の心まで心地よい気分にさせ、何か良い事をした気分に浸ることになり、心が軽やかになるものと考える。
人に恵むという行為は、そういう要素を秘めた行為のように思える。
如何なる宗教でも、寄付を否定する宗教はないわけで、全てが貧しきものに寄付をすることを善と見なしているわけで、その意味からすれば、寄付をするということは人間の深層心理の善の欲求を満たす行為ということになりうる。
我々、凡庸な人間は、今あるものをもっと大きく、もっと沢山、より多く手に持ちたいという欲望にかられるが、これこそ人間の煩悩というものであろう。
しかし、この世に生を受けたいかなる人間でも、三途の川を渡るときにはなにも持っていけないわけで、生まれた時に裸であったように、彼岸に行く時も身一つの裸で行くしかない。
しかし、それが解っていながら、死ぬまで富を手にしたいという人間の心は全く私には理解しかねる。
死んだ後のことまで悩みながら死んでいく人の心がわからない。
この本の主人公、チャールズ・フィーニーという人は、ビジネスをゲームと認識していたのではないかと思う。
こういう風に考えれば、人生もかなり気楽に生きれると思うが、こうなるまでにはかなりの原資を用意する必要があるわけで、私ごときが、「人生はゲームだ」などと言いだせば、その日から家族が路頭に迷うことになる。
今はやりの蟹工船ではないが、いくら虐げられても、おおんぼろ船から逃げ出すわけにはいかない。
今の若者は、この部分で、極めつけの極楽トンボを決め込んでいるので、派遣切りだとか、仕事が無いとか、仕事が気に入らないから辞めるなどという贅沢が許されているのだと思う。
如何なる社会でも同じだと思うが、報われる人というのは、それだけの努力をしているわけで、この本の主人公も、ごくごく小さい時から自分の才覚で金を稼ぐということをしているわけで、今の日本の若者は、その部分が全く未成熟だと思う。
これは今の若者だけが悪いのではなく、彼らの親、彼らの祖父母までが、代々自分の子供を甘えさせて育ててきたわけで、言い換えれば民族の潜在意識として、自分の才覚で稼ぐということを忌避してきた結果だと思う。
日本でも昭和の初期までは、家族の中の子供は小さいながらも労働力であった。
ところが日本の近代化が進むに従い、子供の扱い方が変わってきて、子供には学歴を付けて立身出世をしてもらうことが親としての喜びとなった。
いわゆる親離れ子離れが未成熟で、自分の子供が可愛いから自分と同じ苦労をさせたくない、良い学校に行って、良い大学に入って、良い会社に就職することが、本人を含めた家族の願いとなったわけである。
だから子供が日銭稼ぎの仕事に精を出すよりも、机に向かって勉強してもらった方が親としては喜ばしいという思考に至った。
この思考が3代続いた結果として今の若者は働くということを安易に考え、働かなくても食うだけはできるので、飢えを知らないが故に甘えているのである。
そこに以ってきて、物わかりの良い知識人というというな人達が、「そういう若者を救済しなければならない」などと綺麗事のご都合主義の言辞を並べるから、彼らはますますハングリー精神を喪失してしまうのである。