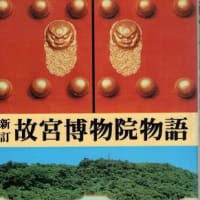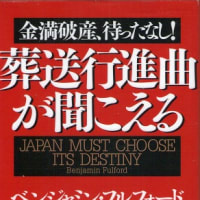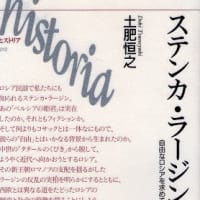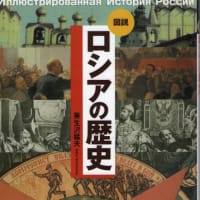例によって図書館から借りてきた本で「敵国日本」という本を読んだ。
ヒュー・バイアスという人が1942年、つまり昭和17年に書いた本である。
まさしく日米戦争の最中に書かれた本だ。
この著者は何年も日本で取材をしていて、それを外国人向けの記事にしていた人ということで、彼は当時の日本というものを実に的確に捉えている。
あの時代の日本の姿というものをかなり正確に捉えていたという点では、例のスパイ、リヒアルト・ゾルゲなどもかなり正確に当時の日本を捉えていたことから考えると、当時の日本というのは、外国人の目から見ると容易にその不自然さというものが目に映っていたのであろう。
外国人が正確に日本を掌握していたことから考えると、我々日本人にどうしてものの本質が見えていなかったのであろう。
但し、この本を読んでいて恐ろしいと思ったことは、当時のメデイアが戦意高揚のために誇張して報道したことが真実と捉えられていることである。
この中に出てくる大逆事件の甘糟大尉の話、南京陥落の虐殺事件、百人切りの話、こういったものは今日では真相が明らかになっているが、当時は真相の隠蔽と同時にその裏返しの心理として戦意高揚のために誇張して報道されていた。
ところがそれを外国人記者は真に受けて受け止めているわけで、それを逆にまた世界に向けて発信していたわけである。
ゲニ、報道というものの影響は恐ろしいもので、日本人以外の民族では、この扱いが実に巧妙である。
プロパガンダと情報を織り交ぜて、真実に蓋をし、それと同時に相手を誹謗する方向に作用させる。その手練手管は我々日本人のお呼びも付かないテクニックである。
メデイア、この場合は新聞であるが、新聞が戦意高揚のためとはいえ、真実とかけ離れた誇張した報道をしたことによって、相手は「新聞の報道によると日本人はこれほど非道、残虐なことをした」と逆に利用されてしまったわけで、これは書いた本人が自分で「誇張して書きました」と訂正をしていないので、日本人の全体の信用問題に関わってしまっているではないか。
現に、今日、これが既成事実として相手側の公式見解として定着してしまっているではないか。
我々はこの事実、つまり日本人がしたと言われている残虐行為が真実とかけ離れた、誇張された報道で、この報道によって相手側から糾弾を受けている中で、その新聞報道記事を書いた人間に、何故、ことの真相を述べ、ねつ造した記事を書いた責任を追及し、その罪を問おうとしないのであろう。
明らかに、この報道によって日本の国益が損なわれているにもかかわらず、その張本人を処罰することに何故躊躇しているのであろう。
相手の報道を逆手に取る外交手腕こそが、いわゆる戦略的な思考というもので、我々はこういう駆け引きに実に疎い。
ある意味でお人好し、お人好しを通り越して馬鹿に限りなく近いということである。
この本に限っていえば、著者の日本を見る目というのは実に正確で、日本は彼の思い描いたとおりの軌跡を歩んでしまった。
彼は最初から日本は負けるといい、日本の中国進出は強盗以外の何ものでもない、という決めつけ方である。
ただ不思議なことに、我々の歩んだ道は彼の指摘したとおりであったが、何故我々はそういう道を選択したのか、という部分の考察が抜け落ちている。
つまり、当時の日本人の考え方というものは正確に掌握されているが、そこに至るまでの先方の考え方に関しては、考察が完全に抜け落ちている。
無理もない話かも知れない。
この本の題名も「敵国日本」なわけで、敵国としての日本を考察しているわけで、日米という二つの国の外交を語るものではなく、明らかに題名が示しているように敵国としての日本に関する考察なわけで、日米関係の考察ではないわけだから、それも致し方ないのかも知れない。
アメリカ人が、敵国としての日本をこれだけ深く考察しているとしたら、当然、日本側にも「敵国アメリカ」を考察した書物があっても良さそうに思うが、果たしてどうなのであろう。
ここでも我々は「敵を知り己を知れば百戦危うからずや」という太古の戒めを無視し続けていたのではなかろうか。
同胞を弁護する意味で、当時の知識人の立場を擁護すれば、あの時点で日本の知識人が「敵国アメリカ」という本を執筆したとしても、結論は日本の敗北ということになるものと思うが、だとすれば、そういう内容の本は当時の日本では発禁になることは請け合いだったろうと想像する。
我々が歴史から教訓を得るとすれば、そういう真実を述べるものに封印をしてはならないということであるが、問題は、それこそ、この真実に問題があるわけで、如何なる扇動的な文書でも、それが真実かどうかは分からないから困るのである。
真実も、その寄って立つ持ち場立場で変わってしまうわけで、その見極めはことのほか困難だと思う。
この著者は、昭和初期の日本の政治状況がまことに不可解だといっているが、まさしく言われるとおりで、あの時期、日本は民主的な議会制度が生きていたにもかかわらず、何故軍部に主導権を握らせてしまったのか、彼ならずとも不可解なことである。
戦後、日本を占領したマッカァサー元帥がいみじくも言ったように、「日本人の政治感覚は12才の子供だ」ということはまことに的を得た発言で、我々の民主政治というのは明らかにこのレベルであろうと思う。
その最大の原因は言葉にあると思う。
日本語の中に、民主政治というものとソリの合わない要因が隠れているのではないかと思う。
言葉の中というよりも、言葉そのものの使い方の中と言わなければならないかも知れない。
明治憲法の欠陥はこの著者も指摘しているが、憲法自体が完璧でないところにもってきて、その運用面において解釈でことを済ますという点の不具合を、この時点で指摘している点には大いに驚かされる。
言葉の解釈で、正反対の結論に結びつけるという点が、日本語の曖昧さの最たるもので、これを議会審議の場で持ち出すから、物事の本質が迷路に紛れ込んでしまうのである。
一つの言葉が、解釈によって幾通りにも受け取れるというところに政治が混迷する原因があるわけで、そこに健全な政党政治が成り立たない理由の一つにもなっていると思う。
そのことは同時に、物事の本質が政争の道具になってしまっていて、自分の属する政党にとって有利か不利かという党利党略に左右されて事が運ぶので、真の解決に至らない。
物事を審議して何らかの結論を出さなければならないというときは、誰にもこれがベストだという結論に自信がないから審議をしているわけで、にもかかわらず、それを党利党略で自分の党に有利に導こうという意志が働くから、本当の答えから遠のいてしまうのである。
その過程で言葉のアヤが微妙に解釈されて、それが本来の意図と全く違う結論に導かれてしまう。
戦前では統帥権について、戦後では憲法9条についてこのことが言えていると思う。
ヒュー・バイアスという人が1942年、つまり昭和17年に書いた本である。
まさしく日米戦争の最中に書かれた本だ。
この著者は何年も日本で取材をしていて、それを外国人向けの記事にしていた人ということで、彼は当時の日本というものを実に的確に捉えている。
あの時代の日本の姿というものをかなり正確に捉えていたという点では、例のスパイ、リヒアルト・ゾルゲなどもかなり正確に当時の日本を捉えていたことから考えると、当時の日本というのは、外国人の目から見ると容易にその不自然さというものが目に映っていたのであろう。
外国人が正確に日本を掌握していたことから考えると、我々日本人にどうしてものの本質が見えていなかったのであろう。
但し、この本を読んでいて恐ろしいと思ったことは、当時のメデイアが戦意高揚のために誇張して報道したことが真実と捉えられていることである。
この中に出てくる大逆事件の甘糟大尉の話、南京陥落の虐殺事件、百人切りの話、こういったものは今日では真相が明らかになっているが、当時は真相の隠蔽と同時にその裏返しの心理として戦意高揚のために誇張して報道されていた。
ところがそれを外国人記者は真に受けて受け止めているわけで、それを逆にまた世界に向けて発信していたわけである。
ゲニ、報道というものの影響は恐ろしいもので、日本人以外の民族では、この扱いが実に巧妙である。
プロパガンダと情報を織り交ぜて、真実に蓋をし、それと同時に相手を誹謗する方向に作用させる。その手練手管は我々日本人のお呼びも付かないテクニックである。
メデイア、この場合は新聞であるが、新聞が戦意高揚のためとはいえ、真実とかけ離れた誇張した報道をしたことによって、相手は「新聞の報道によると日本人はこれほど非道、残虐なことをした」と逆に利用されてしまったわけで、これは書いた本人が自分で「誇張して書きました」と訂正をしていないので、日本人の全体の信用問題に関わってしまっているではないか。
現に、今日、これが既成事実として相手側の公式見解として定着してしまっているではないか。
我々はこの事実、つまり日本人がしたと言われている残虐行為が真実とかけ離れた、誇張された報道で、この報道によって相手側から糾弾を受けている中で、その新聞報道記事を書いた人間に、何故、ことの真相を述べ、ねつ造した記事を書いた責任を追及し、その罪を問おうとしないのであろう。
明らかに、この報道によって日本の国益が損なわれているにもかかわらず、その張本人を処罰することに何故躊躇しているのであろう。
相手の報道を逆手に取る外交手腕こそが、いわゆる戦略的な思考というもので、我々はこういう駆け引きに実に疎い。
ある意味でお人好し、お人好しを通り越して馬鹿に限りなく近いということである。
この本に限っていえば、著者の日本を見る目というのは実に正確で、日本は彼の思い描いたとおりの軌跡を歩んでしまった。
彼は最初から日本は負けるといい、日本の中国進出は強盗以外の何ものでもない、という決めつけ方である。
ただ不思議なことに、我々の歩んだ道は彼の指摘したとおりであったが、何故我々はそういう道を選択したのか、という部分の考察が抜け落ちている。
つまり、当時の日本人の考え方というものは正確に掌握されているが、そこに至るまでの先方の考え方に関しては、考察が完全に抜け落ちている。
無理もない話かも知れない。
この本の題名も「敵国日本」なわけで、敵国としての日本を考察しているわけで、日米という二つの国の外交を語るものではなく、明らかに題名が示しているように敵国としての日本に関する考察なわけで、日米関係の考察ではないわけだから、それも致し方ないのかも知れない。
アメリカ人が、敵国としての日本をこれだけ深く考察しているとしたら、当然、日本側にも「敵国アメリカ」を考察した書物があっても良さそうに思うが、果たしてどうなのであろう。
ここでも我々は「敵を知り己を知れば百戦危うからずや」という太古の戒めを無視し続けていたのではなかろうか。
同胞を弁護する意味で、当時の知識人の立場を擁護すれば、あの時点で日本の知識人が「敵国アメリカ」という本を執筆したとしても、結論は日本の敗北ということになるものと思うが、だとすれば、そういう内容の本は当時の日本では発禁になることは請け合いだったろうと想像する。
我々が歴史から教訓を得るとすれば、そういう真実を述べるものに封印をしてはならないということであるが、問題は、それこそ、この真実に問題があるわけで、如何なる扇動的な文書でも、それが真実かどうかは分からないから困るのである。
真実も、その寄って立つ持ち場立場で変わってしまうわけで、その見極めはことのほか困難だと思う。
この著者は、昭和初期の日本の政治状況がまことに不可解だといっているが、まさしく言われるとおりで、あの時期、日本は民主的な議会制度が生きていたにもかかわらず、何故軍部に主導権を握らせてしまったのか、彼ならずとも不可解なことである。
戦後、日本を占領したマッカァサー元帥がいみじくも言ったように、「日本人の政治感覚は12才の子供だ」ということはまことに的を得た発言で、我々の民主政治というのは明らかにこのレベルであろうと思う。
その最大の原因は言葉にあると思う。
日本語の中に、民主政治というものとソリの合わない要因が隠れているのではないかと思う。
言葉の中というよりも、言葉そのものの使い方の中と言わなければならないかも知れない。
明治憲法の欠陥はこの著者も指摘しているが、憲法自体が完璧でないところにもってきて、その運用面において解釈でことを済ますという点の不具合を、この時点で指摘している点には大いに驚かされる。
言葉の解釈で、正反対の結論に結びつけるという点が、日本語の曖昧さの最たるもので、これを議会審議の場で持ち出すから、物事の本質が迷路に紛れ込んでしまうのである。
一つの言葉が、解釈によって幾通りにも受け取れるというところに政治が混迷する原因があるわけで、そこに健全な政党政治が成り立たない理由の一つにもなっていると思う。
そのことは同時に、物事の本質が政争の道具になってしまっていて、自分の属する政党にとって有利か不利かという党利党略に左右されて事が運ぶので、真の解決に至らない。
物事を審議して何らかの結論を出さなければならないというときは、誰にもこれがベストだという結論に自信がないから審議をしているわけで、にもかかわらず、それを党利党略で自分の党に有利に導こうという意志が働くから、本当の答えから遠のいてしまうのである。
その過程で言葉のアヤが微妙に解釈されて、それが本来の意図と全く違う結論に導かれてしまう。
戦前では統帥権について、戦後では憲法9条についてこのことが言えていると思う。