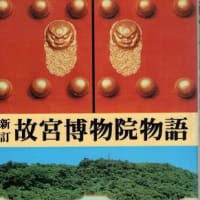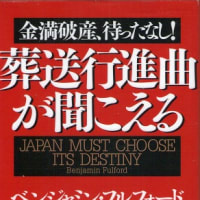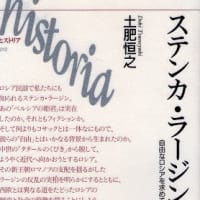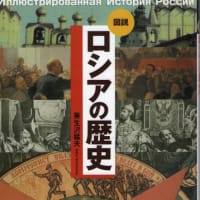例によって図書館から借りてきた本で「昭和の子」という本を読んだ。
前に2度も読んだ「昭和ッ子」とも題名は酷似しているが内容は全く別物である。
代田健慈という人物の目を通した昭和史というようなものだ。
自分史なのかフィクションなのか極めて曖昧な書き方がなされていた。
代田健慈とその姉・亜貴子という子どもの視線から、両親とその両親の周りの大人を描き、そのもう一つ外側に当時の世相を織り交ぜた昭和史になっている。
料理の仕方によっては極めて膨大な著作にもなりうる素材だと思う。
昭和史ともなれば同世代を生きてきた私にとっても共感する部分が多々あって、非常に興味深く読んだ。
中でも、私が不思議でならないのは、あの昭和20年の廃墟の中で、尚も徹底抗戦を唱えた人たちの心情である。
この本の中でも、姉・亜貴子というのは完璧な軍国少女であって、わずか国民学校の6年生でありながら、徹底抗戦を信じているあたりは不思議でならない。
この本の中では、厚木の事例が詳細に記されている。
海軍厚木基地302航空隊司令小園安名大佐として実名で登場しているが、その前には、皇居で天皇の録音盤を略取しようとしてクーデターを起した陸軍の人たちの例もあるわけで、こういう人たちはあの戦争をどういう風に理解していたのであろう。
小学生が「聖戦遂行」と言うのは、あの時代背景を考えればまだ理解できる。
しかし、戦争のプロとしての軍人、特にこの例のように海軍大佐というほどの戦争のプロフェショナルであるべき人が、あの昭和20年の状況下においても尚「聖戦完遂」を言うということは一体どういうことなのであろう。
これを私流の言い方で表現すれば、戦争の私物化である。
口では天皇のため、国民のため、銃後のため、祖国のためと言いながら、何のことはない自己陶酔に酔いしれて、自分自身の大義にのみ忠実であるだけで、周囲の人のことが全く眼中にないということではないか。
海軍大佐ともなって、昭和20年8月の東京の現況を目の当たりにして、それでもなお交戦能力があると思うのはよほどどうかしている。
この物語の中では、主人公の姉・亜貴子は国民学校の6年生にもかかわらず、玉音放送を聞いても尚健気に聖戦完遂を信じていたが、あの戦争を通じて軍人の大部分、軍部の全部が、この少女のような心境であった、ということは一体どういうことなのであろう。
まさしく司馬遼太郎のいう「鬼胎の時代」という以外、表現のしようがないように思える。
戦後の我々は、この部分を深く掘り下げて考えたことがないのではなかろうか。
何でもかんでも軍人の悪行、軍部の独断専行、軍国主義の圧政、言論統制、等々の理由をつけて、軍人と軍部に責任を押し付け、極東国際軍事法廷でけりをつけた形にして、我々が如何にして一億火の玉と化して西洋列強と戦ったのか、という真の根源を追求する努力を怠っているのではなかろうか。
この物語に登場する姉・亜貴子は、戦後しばらくして進学を果たすと、今度は左翼運動に走ることになったが、100%完璧な軍国少女が状況が変わると今度はその対極に走ったわけで、作者はこの少女を介して、当時の日本のインテリ―層の思考を代弁させようと意図したものと考える。
右から左へと、あまりにも極端な思考の遍歴は、日本の真面目な青年の典型的な精神の移行過程ではないかと思う。
この場合、若者の真面目さ、若者の気真面目というものが最大の障害ではなかろうか。
軍国主義の中で、真面目であればある程、猪突猛進的に傾倒してしまうわけで、ところが時代が変わってそのベクトルが逆向きになると、やはりその真面目さなるが故に、新しい方針に前にもまして猪突猛進になってしまうのではなかろうか。
この物語の中で、彼らの父親は経営者として満州の実情視察に出かける場面があって、そのなかで満映社長の甘粕正彦の講演を聞くところがあるが、この父親は満州の視察を経験して、当時の風潮に疑問を感じ、自分の事業の満州進出を断念する。
政府が笛太鼓を鳴らして大宣伝する事業に何かしら不安を感じ、それに便乗することを自重したわけだが、こういう冷静さが昭和初期の日本人には全くなかったわけで、我々の大部分は、自らの政府が大宣伝する事業にいとも安易に便乗しようとしたのである。
当時の日本政府といえども、最初から同胞を騙す気がなかったことは当然であろうが、金太鼓を打ち鳴らして宣伝した計画そのものが極めて杜撰であったわけだ。
この杜撰さがどこから来たのかと問えば、それは我々自身の奢りであったわけで、奢り高ぶっていたので、物事の真の姿が見えず、表層の事象に目を奪われて、それに幻惑されたものと考えざるを得ない。
この兄弟の父親が、満州進出を断念したその根拠は、現地の人々の目の輝き見て悟ったと記されているが、昭和初期の日本人はこういう視点が国民全体として抜け落ちていたに違いない。
第1次世界大戦が終わって、日本は世界の5大強国となったものと勘違いしていたわけで、こういう勘違いに陥ることからして、限りなく増長していたことになるが、われわれはそれを爪の垢ほども認識していなかったのである。
ある面ではいた仕方ないところもあるわけで、われわれは島国の住人で、他民族との接触ということには極めて不慣れであった。
こちらが良かれと思ったことは先方もそのまま受け入れると思い込んでいた節がある。
これが大陸国家ならば、歴史上で何度も犯し侵された経験があるので、外交巧者に成りうるが、われわれは島国なるがゆえに、そういう経験を経ずして名目的な大国になってしまった。
しかし、われわれは近代国家をつくる過程で、優秀な人材を全国各地から集め、陸軍士官学校、海軍兵学校、あるいは各地のナンバースクール、帝国大学で養成して、国家の機関要員として学識経験を積ませた。
ところがその結果として、あるいはその集大成として、昭和20年、わが祖国が恢塵と化した。
日本の都市そのものが灰となってしまったということをどう説明したらいいのであろう。
その根本のところには政治の延長としての戦争という事態が横たわっていたが、そういう過酷な事態を回避あるいは潜り抜けるために、われわれは優秀な人材を育成してきたつもりなのに、それが全く効果を現さなかったということは一体どういうことなのであろう。
明治維新以降、営々と築き上げてきた近代日本、若い優秀な若者を集中的に教育した結果として、彼らの先輩諸氏が築き上げた近代日本というものが灰となってしまったということをどう説明するのであろう。
我が国の優秀な若者が集合した、陸軍士官学校、海軍兵学校、あるいは各地のナンバースクール、帝国大学の教育は一体何であったのか、と問い直さなければならないではないか。
昭和20年の東京の現状を目の当たりしても、なお戦争を継続しようとした軍人を我々はどう考えたらいいのであろう。
明治以降の優秀な若者を集めた教育の効果が、こういう形で現れたことに対して、どういう説明が出来るのであろう。
この本の中で描かれている主人公の父親は、学は無いけれども、満州に渡って、その地に生きている現地の人々の目を見て、彼らは日本を、われわれを恨んでいるということを直感的に悟ったが、高等教育を受けた優秀な若者は、そういう自覚が全くなかったわけで、これは一体どういうことなのであろう。
昭和20年、1945年8月に、われわれがポツダム宣言を受諾して戦争を終結させたのは、昭和天皇の意志であって、優秀とされていた日本の高等教育を受けた人たちの成果は全く反映されていなかったことになる。
だとすれば、その高等教育は一体何であったのかと言いたい。
市井の無名の人が、海を渡って満州の地に立ってみると、現地の人々は日本に対して実に恨めしい眼差しでわが同胞を見ていることを肌で感じたにもかかわらず、高級軍人や高級官僚はそれに全く気がついていなかったというのは一体どういうことなのであろう。
私が思うに、日本の近代化の過程で、四民平等で、日本全国津々浦々から優秀な若者を集めて、国家が枠を嵌めた教育をしたところにその原因があると思う。
この四民平等というのがいわば曲者で、このフレーズはきわめて民主的に聞こえ、好ましい印象を受けがちであるが、ぶっちゃけて言えば味噌も糞も一緒くたにするということでもある。
人間の能力を測るのに、記憶力や洞察力はペーパーチェックで測れるが、その人の持つ潜在的なモラル、精神の気高さ、ノブレス・オブリージというのは測るすべがない。
東北の貧乏な百姓の子忰が、立身出世を夢見て、軍人養成機関に入ってくる。そこで一生懸命、切磋琢磨して、恩賜の短剣を得て卒業、高位高官の地位に就く。故郷に錦を飾って帰る。本人も周囲の人間も彼は優秀な人間と一目置く。
ところが、この人の仕事あるいは任務は、その職権の維持ないしは拡大で、軍の仕事とはいうものの、軍のための軍の仕事であって、それは国民のため、あるいは銃後の人々のためではないわけで、軍による軍のための仕事に過ぎなかったのである。
本人は軍のための仕事を通じて、それが天皇のため、あるいは国民のためになっていると思い込んでいるかもしれないが、この思い込みが大間違いであったわけである。
問題は、貧乏な百姓の子忰が、立身出世のために、学費のいらない高等教育に群らがるという点が、既にその発想からして下賤であって、そういう人が努力の甲斐あって高位高官に就くと、自分の生い立ちを忘れ得て、尊大に振舞い、奢り高ぶって、下々のことを眼中に置かなくなるということである。
貧乏な百姓の子忰が立身出世をして高位高官に就いて、その地位にふさわしい立ち居振る舞いをすれば、その人のモラルも地位に応じて向上し、人としてはそうでなければならないが、普通はこういう場合、地位におぼれ、自分の生い立ちを忘れがちでなところが下賤な百姓根性というものである。
これは現在でも立派に通用しているわけで、若い美空で官僚、公務員になろうと思っている人間は、明らかに百姓根性の持ち主である。
覇気のある若者ならば、ぬるま湯ということが解り切った官僚や公務員の世界など目指すわけがない。
民間の企業で、とことん自分を試す試練に立ち向かうものと思う。
考えてみれば我々大和民族というのは実に不思議な集団だと思う。
われわれは、戦前、アジア大陸に夢と希望を託して進出して、手痛いしっぺ返しを受けた。
にもかかわらず再び高度経済成長で日本が豊かになりかけ、日本の人件費が高騰してくると、再び安い人件費を求めてアジアに進出した。
今度は武力を背景にしていないので、先方はしたい放題嫌がらせをしてくるが、それに対しては我々の側は徹底的に隠忍自重して、完全にエコノミックアニマルに徹しきっている。
あの戦争を通じて、手痛いしっぺ返しを食ったので、なにがなんでもアジアには足を踏み入れない、という信念にはなっていない。
「喉元過ぎれば暑さを忘れる」で、目前の人件費の高騰という問題をいとも安易に中国進出という方法で解決しようとする。
日本の製造業のノウハウは、その一つ一つが戦略的に極めて有効な外交カードだ、という認識が全く存在せず、ただただ自分の会社がいかに儲けるかという下賤な狭い了見でしかない。
つまり表層の流れしか目に入っていないということである。
われわれはアジアの人たちとも仲良くしてかなければならないことは当然であるが、その為には相手の本質をとことん研究して、その傾向と対策を十分に考えてから掛からねばならない。
中国では人件費が安いから工場を移すなどという安直な思考で出るのではなく、常に何かの担保を取り、何か確実な保証を築いてからでなければ相手の土俵に上がらないことである。
われわれの歴史を見れば、明らかに大陸の影響を受けているわけで、それがため我々にとって中国の民は、何となく親近感を持ちがちであるが、そんな甘い感覚でいると「庇を貸して母屋を取られる」ということになりかねない。
だいたいあの戦争だとて、元は中国問題のこじれなのであって、中国におけるトラブルの処理がまずかったので対米戦にまで発展して、最後は廃墟と化してしまったではないか。
日本全土が灰となった原因が中国問題であったことを決して忘れてはならない。
戦後の我々は日中戦争と大東亜戦争を分けて考えがちであるが、あれは一続きの一連の連続した流れであって、分けて考えるべきではない。
ところが我々は戦後に至っても、中国となるとついつい情に絆されて、甘い甘い思考になってしまうのである。
相手は五千年の歴史の国である。
われわれは皇紀で勘定しても2668年でしかないわけで、大雑把に比べても倍の年月の違いがある。
この年月の違いは、そのまましたたかさの違いとなっているわけで、今回の北京オリンピックも上海万博も大きなチャンスなので、これを機に対中国政策を根本的に見直すようにすべきだと思う。
前に2度も読んだ「昭和ッ子」とも題名は酷似しているが内容は全く別物である。
代田健慈という人物の目を通した昭和史というようなものだ。
自分史なのかフィクションなのか極めて曖昧な書き方がなされていた。
代田健慈とその姉・亜貴子という子どもの視線から、両親とその両親の周りの大人を描き、そのもう一つ外側に当時の世相を織り交ぜた昭和史になっている。
料理の仕方によっては極めて膨大な著作にもなりうる素材だと思う。
昭和史ともなれば同世代を生きてきた私にとっても共感する部分が多々あって、非常に興味深く読んだ。
中でも、私が不思議でならないのは、あの昭和20年の廃墟の中で、尚も徹底抗戦を唱えた人たちの心情である。
この本の中でも、姉・亜貴子というのは完璧な軍国少女であって、わずか国民学校の6年生でありながら、徹底抗戦を信じているあたりは不思議でならない。
この本の中では、厚木の事例が詳細に記されている。
海軍厚木基地302航空隊司令小園安名大佐として実名で登場しているが、その前には、皇居で天皇の録音盤を略取しようとしてクーデターを起した陸軍の人たちの例もあるわけで、こういう人たちはあの戦争をどういう風に理解していたのであろう。
小学生が「聖戦遂行」と言うのは、あの時代背景を考えればまだ理解できる。
しかし、戦争のプロとしての軍人、特にこの例のように海軍大佐というほどの戦争のプロフェショナルであるべき人が、あの昭和20年の状況下においても尚「聖戦完遂」を言うということは一体どういうことなのであろう。
これを私流の言い方で表現すれば、戦争の私物化である。
口では天皇のため、国民のため、銃後のため、祖国のためと言いながら、何のことはない自己陶酔に酔いしれて、自分自身の大義にのみ忠実であるだけで、周囲の人のことが全く眼中にないということではないか。
海軍大佐ともなって、昭和20年8月の東京の現況を目の当たりにして、それでもなお交戦能力があると思うのはよほどどうかしている。
この物語の中では、主人公の姉・亜貴子は国民学校の6年生にもかかわらず、玉音放送を聞いても尚健気に聖戦完遂を信じていたが、あの戦争を通じて軍人の大部分、軍部の全部が、この少女のような心境であった、ということは一体どういうことなのであろう。
まさしく司馬遼太郎のいう「鬼胎の時代」という以外、表現のしようがないように思える。
戦後の我々は、この部分を深く掘り下げて考えたことがないのではなかろうか。
何でもかんでも軍人の悪行、軍部の独断専行、軍国主義の圧政、言論統制、等々の理由をつけて、軍人と軍部に責任を押し付け、極東国際軍事法廷でけりをつけた形にして、我々が如何にして一億火の玉と化して西洋列強と戦ったのか、という真の根源を追求する努力を怠っているのではなかろうか。
この物語に登場する姉・亜貴子は、戦後しばらくして進学を果たすと、今度は左翼運動に走ることになったが、100%完璧な軍国少女が状況が変わると今度はその対極に走ったわけで、作者はこの少女を介して、当時の日本のインテリ―層の思考を代弁させようと意図したものと考える。
右から左へと、あまりにも極端な思考の遍歴は、日本の真面目な青年の典型的な精神の移行過程ではないかと思う。
この場合、若者の真面目さ、若者の気真面目というものが最大の障害ではなかろうか。
軍国主義の中で、真面目であればある程、猪突猛進的に傾倒してしまうわけで、ところが時代が変わってそのベクトルが逆向きになると、やはりその真面目さなるが故に、新しい方針に前にもまして猪突猛進になってしまうのではなかろうか。
この物語の中で、彼らの父親は経営者として満州の実情視察に出かける場面があって、そのなかで満映社長の甘粕正彦の講演を聞くところがあるが、この父親は満州の視察を経験して、当時の風潮に疑問を感じ、自分の事業の満州進出を断念する。
政府が笛太鼓を鳴らして大宣伝する事業に何かしら不安を感じ、それに便乗することを自重したわけだが、こういう冷静さが昭和初期の日本人には全くなかったわけで、我々の大部分は、自らの政府が大宣伝する事業にいとも安易に便乗しようとしたのである。
当時の日本政府といえども、最初から同胞を騙す気がなかったことは当然であろうが、金太鼓を打ち鳴らして宣伝した計画そのものが極めて杜撰であったわけだ。
この杜撰さがどこから来たのかと問えば、それは我々自身の奢りであったわけで、奢り高ぶっていたので、物事の真の姿が見えず、表層の事象に目を奪われて、それに幻惑されたものと考えざるを得ない。
この兄弟の父親が、満州進出を断念したその根拠は、現地の人々の目の輝き見て悟ったと記されているが、昭和初期の日本人はこういう視点が国民全体として抜け落ちていたに違いない。
第1次世界大戦が終わって、日本は世界の5大強国となったものと勘違いしていたわけで、こういう勘違いに陥ることからして、限りなく増長していたことになるが、われわれはそれを爪の垢ほども認識していなかったのである。
ある面ではいた仕方ないところもあるわけで、われわれは島国の住人で、他民族との接触ということには極めて不慣れであった。
こちらが良かれと思ったことは先方もそのまま受け入れると思い込んでいた節がある。
これが大陸国家ならば、歴史上で何度も犯し侵された経験があるので、外交巧者に成りうるが、われわれは島国なるがゆえに、そういう経験を経ずして名目的な大国になってしまった。
しかし、われわれは近代国家をつくる過程で、優秀な人材を全国各地から集め、陸軍士官学校、海軍兵学校、あるいは各地のナンバースクール、帝国大学で養成して、国家の機関要員として学識経験を積ませた。
ところがその結果として、あるいはその集大成として、昭和20年、わが祖国が恢塵と化した。
日本の都市そのものが灰となってしまったということをどう説明したらいいのであろう。
その根本のところには政治の延長としての戦争という事態が横たわっていたが、そういう過酷な事態を回避あるいは潜り抜けるために、われわれは優秀な人材を育成してきたつもりなのに、それが全く効果を現さなかったということは一体どういうことなのであろう。
明治維新以降、営々と築き上げてきた近代日本、若い優秀な若者を集中的に教育した結果として、彼らの先輩諸氏が築き上げた近代日本というものが灰となってしまったということをどう説明するのであろう。
我が国の優秀な若者が集合した、陸軍士官学校、海軍兵学校、あるいは各地のナンバースクール、帝国大学の教育は一体何であったのか、と問い直さなければならないではないか。
昭和20年の東京の現状を目の当たりしても、なお戦争を継続しようとした軍人を我々はどう考えたらいいのであろう。
明治以降の優秀な若者を集めた教育の効果が、こういう形で現れたことに対して、どういう説明が出来るのであろう。
この本の中で描かれている主人公の父親は、学は無いけれども、満州に渡って、その地に生きている現地の人々の目を見て、彼らは日本を、われわれを恨んでいるということを直感的に悟ったが、高等教育を受けた優秀な若者は、そういう自覚が全くなかったわけで、これは一体どういうことなのであろう。
昭和20年、1945年8月に、われわれがポツダム宣言を受諾して戦争を終結させたのは、昭和天皇の意志であって、優秀とされていた日本の高等教育を受けた人たちの成果は全く反映されていなかったことになる。
だとすれば、その高等教育は一体何であったのかと言いたい。
市井の無名の人が、海を渡って満州の地に立ってみると、現地の人々は日本に対して実に恨めしい眼差しでわが同胞を見ていることを肌で感じたにもかかわらず、高級軍人や高級官僚はそれに全く気がついていなかったというのは一体どういうことなのであろう。
私が思うに、日本の近代化の過程で、四民平等で、日本全国津々浦々から優秀な若者を集めて、国家が枠を嵌めた教育をしたところにその原因があると思う。
この四民平等というのがいわば曲者で、このフレーズはきわめて民主的に聞こえ、好ましい印象を受けがちであるが、ぶっちゃけて言えば味噌も糞も一緒くたにするということでもある。
人間の能力を測るのに、記憶力や洞察力はペーパーチェックで測れるが、その人の持つ潜在的なモラル、精神の気高さ、ノブレス・オブリージというのは測るすべがない。
東北の貧乏な百姓の子忰が、立身出世を夢見て、軍人養成機関に入ってくる。そこで一生懸命、切磋琢磨して、恩賜の短剣を得て卒業、高位高官の地位に就く。故郷に錦を飾って帰る。本人も周囲の人間も彼は優秀な人間と一目置く。
ところが、この人の仕事あるいは任務は、その職権の維持ないしは拡大で、軍の仕事とはいうものの、軍のための軍の仕事であって、それは国民のため、あるいは銃後の人々のためではないわけで、軍による軍のための仕事に過ぎなかったのである。
本人は軍のための仕事を通じて、それが天皇のため、あるいは国民のためになっていると思い込んでいるかもしれないが、この思い込みが大間違いであったわけである。
問題は、貧乏な百姓の子忰が、立身出世のために、学費のいらない高等教育に群らがるという点が、既にその発想からして下賤であって、そういう人が努力の甲斐あって高位高官に就くと、自分の生い立ちを忘れ得て、尊大に振舞い、奢り高ぶって、下々のことを眼中に置かなくなるということである。
貧乏な百姓の子忰が立身出世をして高位高官に就いて、その地位にふさわしい立ち居振る舞いをすれば、その人のモラルも地位に応じて向上し、人としてはそうでなければならないが、普通はこういう場合、地位におぼれ、自分の生い立ちを忘れがちでなところが下賤な百姓根性というものである。
これは現在でも立派に通用しているわけで、若い美空で官僚、公務員になろうと思っている人間は、明らかに百姓根性の持ち主である。
覇気のある若者ならば、ぬるま湯ということが解り切った官僚や公務員の世界など目指すわけがない。
民間の企業で、とことん自分を試す試練に立ち向かうものと思う。
考えてみれば我々大和民族というのは実に不思議な集団だと思う。
われわれは、戦前、アジア大陸に夢と希望を託して進出して、手痛いしっぺ返しを受けた。
にもかかわらず再び高度経済成長で日本が豊かになりかけ、日本の人件費が高騰してくると、再び安い人件費を求めてアジアに進出した。
今度は武力を背景にしていないので、先方はしたい放題嫌がらせをしてくるが、それに対しては我々の側は徹底的に隠忍自重して、完全にエコノミックアニマルに徹しきっている。
あの戦争を通じて、手痛いしっぺ返しを食ったので、なにがなんでもアジアには足を踏み入れない、という信念にはなっていない。
「喉元過ぎれば暑さを忘れる」で、目前の人件費の高騰という問題をいとも安易に中国進出という方法で解決しようとする。
日本の製造業のノウハウは、その一つ一つが戦略的に極めて有効な外交カードだ、という認識が全く存在せず、ただただ自分の会社がいかに儲けるかという下賤な狭い了見でしかない。
つまり表層の流れしか目に入っていないということである。
われわれはアジアの人たちとも仲良くしてかなければならないことは当然であるが、その為には相手の本質をとことん研究して、その傾向と対策を十分に考えてから掛からねばならない。
中国では人件費が安いから工場を移すなどという安直な思考で出るのではなく、常に何かの担保を取り、何か確実な保証を築いてからでなければ相手の土俵に上がらないことである。
われわれの歴史を見れば、明らかに大陸の影響を受けているわけで、それがため我々にとって中国の民は、何となく親近感を持ちがちであるが、そんな甘い感覚でいると「庇を貸して母屋を取られる」ということになりかねない。
だいたいあの戦争だとて、元は中国問題のこじれなのであって、中国におけるトラブルの処理がまずかったので対米戦にまで発展して、最後は廃墟と化してしまったではないか。
日本全土が灰となった原因が中国問題であったことを決して忘れてはならない。
戦後の我々は日中戦争と大東亜戦争を分けて考えがちであるが、あれは一続きの一連の連続した流れであって、分けて考えるべきではない。
ところが我々は戦後に至っても、中国となるとついつい情に絆されて、甘い甘い思考になってしまうのである。
相手は五千年の歴史の国である。
われわれは皇紀で勘定しても2668年でしかないわけで、大雑把に比べても倍の年月の違いがある。
この年月の違いは、そのまましたたかさの違いとなっているわけで、今回の北京オリンピックも上海万博も大きなチャンスなので、これを機に対中国政策を根本的に見直すようにすべきだと思う。