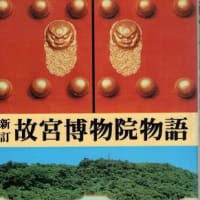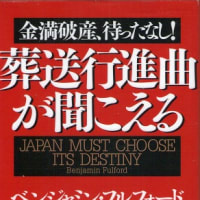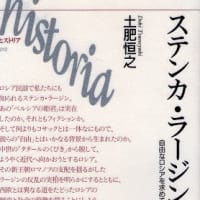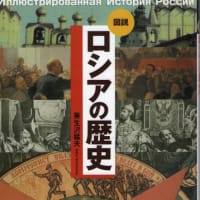例によって図書館から借りてきた本で「大正時代を訪ねてみた」という本を読んだ。
サブタイトルには「平成日本の原風景」となっている。
著者は皿木喜久と言う人だ。
昭和15年生まれの私は今72歳であって、当然のこと大正時代については知る由もない。
しかし、あの狂気の昭和の時代を掘り下げて行くと、その前の大正時代についても、それなりに掘り下げなければならないと思う。
だが、この時代については案外等閑視されているような気がしてならない。
それと言うのも、戦後の歴史教育が西暦で語られるので、大正時代という言葉が俎上に上りにくい、という面があるのかもしれない。
大正時代を西暦でいえば、1912年から1926年までの間であるが、この間はある意味で日本の戦間期であって、平和を謳歌した時代でもある。
大正デモクラシーという言葉は巷にあふれたが、この戦争の無い平和な時代に、ある意味で民主主義が熟成されればよかったが、そうならなかったところが歴史の現実であった。
この本のサブタイトルにもある様に、平成の政治的混乱の萌芽が、既にこの時代に芽生えていたのではないかと思う。
そもそも、人間の生存ということを考えた時、基本的には民主主義が統治の原点ではないかと思う。
人間の集まりが国家という概念に至る前の時代においては、人々は今でいう集団合議制で、自分たちの在り方を決めていたのではないかと思う。
そういう時代を、今の概念で示せば、山賊や野武士の集団と考えればいいと思うが、こういう人達でも、自分たちの先行きを考える場合、リーダーの取り巻き、いわゆるスタッフの意見を聞いて、それを参考にしながらボスがある決定を下していると思う。
自分たちの集団の回りに起きるさまざまな事象、現象、具象に対して、如何に対応するかが統治であったに違いない。
統治の副産物として、金銀財宝を身の回りに集める、という行為もあったに違いなかろうが、それはあくまでも与録であって、統治の主眼がそこにあったわけではないと思う。
山賊の親分でも野武士の頭目でも、自分のスタッフの意見は尊重したに違いないと思うが、そういうスタッフの意見を聞いて決定し、決断を下したことを実践するについても、やはり同じようにスタッフが要るわけで、その部分を今風の言い方をすれば行政・官僚ということになる。
しかし、こういう山賊や夜盗及び海賊の様な集団を一つのマスと捉えた時、そこには必ずリーダーが自然発生的に産まれるわけだが、一つのマスの中ではリーダーの数は限りなく少なく、大抵の場合一人である。
リーダーが2人も3人も居れば、その中での意見の集約ということはあり得ないので、群れ全体が右往左往することになってしまう。
だから、リーダーは一人であるが、リーダーを補佐するスタッフは、それぞれの群れの統治の仕方によって千差万別である。
こういう人間の集団が近代国家をなすようになると、リーダーを補佐するシステムも複雑化してきて、統治のシステム化が顕著になってきた。
統治する側とされる側では、その中の人間の数が極端に違うわけで、統治のシステムとして行政を司る人は、ある程度の人数ではあるが、それでも統治される側の人から比べれば数はうんと少ない。
人間の集団としての社会は、統治する人とされる人の2種類に分類される。
リーダーがたった一人で、そのリーダーが統治すべき人から私利私欲を収奪するような思考であったならば、大勢の人々が困るわけで、そういう統治であってはならないというわけで、様々な政治システムが考案されたが、その中でももっとも人々の共感を得られるに違いないと思われるものが、民主主義という手法であった。
これは統治されるものが、自分たちの総意で、自分たちのリーダーを選出するというシステムであって、そうであるとするならば、人々は自分たちの選んだリーダーに黙ってついていくに違いない、という狙いがあった。
ところが人間の考えというのは、それこそ十人十色で、その考える事というのは文字通り千差万別であるわけで、リーダーが「あっち行こう」と言っても、様々な意見が出て、意見の集約が出来ず、行先は一向に決まらないということになる。
この地球上にある数ある人間集団の中には、リーダーの世襲制のところもあって、そういうところでは大体が独裁政治なので、リーダーは統治される側の人々の意向など考える必要はなく、リーダーの思い通りの施策が可能である。
問題は、そういう施策が、統治されている側の人々の共感を得、そういう人々の幸福感に寄与しているかどうかという点である。
我々日本民族の生い立ちも、基本的には農耕民族で、山から流れでる川の水が得られやすい場所で稲を栽培して、米を作って生計を立てていたに違いない。
そういう集団の中に、山賊か夜盗のような暴力集団が押し入って、今の暴力団のみかじめ料の様な搾取が恒常化して、それがおいおい地方豪族に成長して、最終的にはそれぞれに覇を競うようになった、と私は考えている。
問題は、元々稲を作って平和に暮らしていた人達の意思決定方法であって、こういう人たちは、リーダーをお互いの回り持ちでこなしていた。
だから自分がリーダーの時、余りはりきり過ぎて過去に前例がない特異な行為をすると、自分がリーダーを降りた時にしっぺ返しがあるわけで、好むと好まざると前例踏襲に徹しなければならなかった。
言い方を変えると、封建主義を踏襲せざるを得ず、過去の前例からの脱却できずにいたということである。
農作業の手順に関しては既にルーチン化しているので、誰が号令をかけてもつつがなくこなせるが、想定外の事態に直面した時の対応において、どうしても前例主義に陥ってしまって、新しい発想を試す事が出来なかった。
そういう殻を打ち破ったのが明治維新であったが、この大革命を経ても、日本民族のすべてがすべて意識改革に成功したわけではなく、それに乗り遅れた者も大勢いた。
我々の民族の歴史を振り返ってみると、我々は稲作農民であったが、この過程においてリーダーの回り持ちを経験しているので、大勢の人がある意味で政治的な物の考え方になじんでいたということが言える。
自分たちの考えを政治に反映させることの意義を知っていたとも言える。
ところが、これも我々の仲間の数が少ないうちはそれで治まっていたが、我々の同胞の人口が多くなると従来の方法では行き詰ってしまうことになった。
人口が増えるという意味は、物理的な人間の数のみではなく、従来政治に参与していなかった階層が、人権意識の高揚によって新たに政治参加の権利を持つようになった、という意味も含まれている。
これは、普通は民主化の成熟という言い方で語られているが、古代ギリシャの市民階層でも奴隷の階層の者は政治参加できなかったわけで、我々も同じような軌跡を歩んでいるということだ。
現に普通選挙法の施行も、新たな階層に政治参加の機会を与えたわけで、政治というものがお互いの顔の判りあえる範囲内のものではなくなって、不特定多数の顔の見えない大衆を相手にしなければならなくなったということだ。
従来ならば、自分の顔の見える範囲の利害得失を追い求めておればよかったが、顔の見ないどこの馬の骨とも判らない人間の利害得失を代弁するについては、どうしてもある程度無責任に成らざるを得ない。
そのことは、口を開けば国民大衆の利便を代弁する大言壮語を吠えまくらねばならないが、心の中ではあくまでも自己の利便のための方便であって、口先だけのリップサービスに過ぎないということになる。
だから、現代の先進国の民主主義体制というのは、統治する側のリップサービスと、そのリップサービスの実行を何処まで追求できるかのせめぎ合いだと考えてもいい。
統治する側に立とうと考えている人達の立候補の立会演説は、その内容の全てが「当選した暁にはこうします」という公約であるが、公約はあくまでもリップサービスに過ぎず、自己PRの場でしかない。
被選挙民、つまり選ぶ側が顔見知りの範囲ならば、候補者も本音で語れるが、選んでくれる相手が何処の馬の骨とも判らない大衆では、綺麗ごとを並べたリップサービスでしか、自己の特質を知らしめる方法がない。
よって、出来もしない理想論を振りかざすということになるのであるが、選ぶ側の見識に政治に対する期待が薄い場合は、その選択に瑕疵が生じ、結果はブーメランのように選んだ側に振りかかって来る。
我々の先祖は農耕民族としてルーチン化した祀り事はリーダーを廻り持ちで行ってきたので、ある意味で誰でもその長(おさ)が務まる。
これはいわゆる究極の民主主義体制であったわけだが、このDNAが今日までも引き継がれて、長という立場に固執する日本人は極めて少ない。
いとも安易に長という椅子を放り出してしまう。
リーダーの座に全く未練を持たないということは、その地位が廻り持ちで、誰がやってもある程度は全うできる、ということがわかっているからであるが、政治の場ではその間の政治的空白は免れない。
この政治的空白が問題になるケースは、喫緊の課題を抱え込んだ時であって、そういう時にこそリーダーの存在が問われるのに、その緊急課題を政争の具にするところが我々の悪弊である。
この本の中にも述べられているが、大正14年には治安維持法と普通選挙法は抱き合わせで成立している。
治安維持法は世紀の悪法のように言われているが、政友会、憲政会、革新倶楽部という政党の議論を経て成立しており、スターリンや毛沢東のような独裁者が自分の政敵を潰すために作ったわけではない。
「そういう法律が必要だ」、という国民の側の欲求があった、という当時の我々の置かれた状況をよくよく注視する必要がある。
普通選挙法だとて、当然のこと、国民の欲求があったればこそできたわけで、何も求めるものがないのに為政者の都合で法案ができるわけではない。
そういう意味では我々同胞の政治感覚は素晴らしいものがあるが、皆が皆、この素晴らしい特質を兼ね備えているが故に、結果として「船頭多くして船山を登る」ということになってしまっている。
一人一人が、それぞれに立派な意見を持っているので、百家争鳴となってしまい、意見の集約が出来ず、結果として物事は一歩も前に進まないということになっている。
大正時代の船成り金という言葉はよく聞いたものだが、この成り金という言葉には、成り金になり損ねた庶民の怨嗟の気持が含まれていることは容易に想像できるが、成り金といわれ、暫くして没落する人達のことはどう考えたらいいのであろう。
「自分が一代で稼いだ金なんだから、自分の代で使い切る」という考え方を、我々はどう考えるべきなのであろう。
私の考えで言えば、やはりこういう考え方は下衆っぽい思考であって、堅実な考え方の対極をなすものだと思う。
この考え方は、自分一人のことしか眼中になく、周りの人たちのことが思考から抜け落ちてしまっていて、今で言うところの究極のジコチュウ(自己中心主義)でしかない。
「自分で儲けた金を自分で使って何が悪い」という論法であるが、自分が儲けたということは、相手の犠牲の上に成り立っているわけで、そこの心配りが行き届いていないということが、その後の日本の先行きに大きく影響を及ぼした。
大正3年に日本が第1次世界大戦に参戦するということは、イギリスとの条約がある以上、いた仕方ない面があるが、中国に対して対支21カ条の要求というのは、余りにも我々の側の驕り高ぶった振る舞いだといわざるを得ない。
時の総理大隈重信は、あまりにもシナを舐め切っていたわけで、こういうことが判らない、事の善悪が判断できない、ということはその案件について無知だったとしか言いようがない。
昭和の軍人、特に高級将校、高級参謀といわれるような人々が、現代の戦争に無知だったのと同じように、大隈重信も我が隣国の人々のことに思いが至らず、相手に対して無知だったという事だと思う。
船成り金と同じで、たまたま時の巡り合わせで金持ちになれたものを、自分の実力で儲けれた、と思違いをしたようなもので、身の程知らずということだ。
その一方で、この時代は軍にとってはまことに不運な時期で、ある種の軍縮ムードに押されて、軍人が肩身の狭い思いをさせられた時期でもあった。
その反動で昭和初期の軍人は威張り散らしたわけでもなかろうが、軍人に対する扱い方に、余りにも幅が広いというのも大いに考えざるを得ない。
地球規模で眺めれば、軍人の中でも将校と下士官では扱いが違いうのが世界標準であって、将校というのは何処の国でもある程度社会的地位が確立していて、基本的には貴族であって、食うに困ることのない人々がなっている。
ところが日本の場合は、将校の出自は士農工商のあらゆる階層にあるわけで、一言でいえば官僚化されたサラリーマンである。
軍籍を離れたらその日から食うに困ったわけだ。
そういう階層の者にとって、軍縮は自分の首を絞めるようなもので、そういう状況下で軍人が軍服で街を歩けない、私服でなければ街を歩けない、という状況はまさしく受難の時期であって、その反動が昭和初期の軍人の態度に反映されたものと考えざるを得ない。
先に述べたように、近世以降の統治ということは、山賊や海賊の親玉ではあり得ないわけで、リーダーも下々の下世話にも大いに通じなければならなくなったわけで、下の者のご機嫌伺いをしながら、自己の目的を推し進めなければならないので、上からの「オイ、コラッ」式で行けなくなった。
上は上なりに気苦労が多くなった。
その意味で、大正時代に軍人が軍服で街を歩けないということは、市民の存在感が大きくなったということでもあって、市民の軍部に対する風当たりが強くなったことを指し示しているが、これはこれでまた大きな反省材料でもあった。
つまり、日露戦争では軍人や軍部の活躍を手放しで喜びながら、時代が下がって大正時代になると、彼らの存在を冷ややかな目で見ているわけで、軍人サイドに立って見れば、「何を小癪な平民メ」という思考に自然になると思う。
ということは、国民というものは常に時流に迎合するのがその本質であって、国民大衆には理念も理想も最初から存在していないわけで、それをあたかもある様に吹聴して回るのがメデイアというヤクザな存在であった。
もっとも国民とか市民というのは、目先の自己の利益だけが感心ごとなわけで、そう先のことまで考えてはおらず、目の前の利得だけに関心を示すので、統治者としてはそれに応えてさえおれば安心できる。
つまり馬の鼻さきにニンジンをぶら下げておけば安泰だと思われている。
これを今実践しているのが平成の民主党政権であって、民主党政権というのは国民に金をばら撒くことのみに専念しているわけで、そんなことをしておれば当面の人気は衰えないが、その先はどうなるか判ったものではない。
国民に対して耳障りの良い事ばかりを並べたてて、人気取りには熱心であるが、真の国益については何のビジョンも示し得ない。
国民の嫌がることは先送りして、国民のアメだけをばら撒けば、当座の人気は上がるけれど、そんな事が長続きするわけがない。
私自身の研究不足かもしれないが、昭和初期の時代に軍人が跋扈する背景が大正時代にあるのではないかと思って注視しているが、この時代の事柄を書いた書物は、全てが戦争の話になってしまって、肝心の政治から離れてしまっている。
例えば、美濃部達吉博士の『天皇機関説』の論議もまことに不思議な話で、最初は大勢の国会議員も違和感を持っていなかったにもかかわらず、最終的には議会を追い出されてしまった。
これは一体どういうことなのであろう。
斎藤隆夫の演説も、当初は彼の演説に好意的だった者が、時の経過とともに彼を糾弾する側に傾いてしまう、ということは一体どういうことなのであろう。
この時代には、いわゆる風見鶏のように時流を探り当てる才覚を持ち合わせていないと生き残れないということだったに違いない。
それは俗に言う「寄らば大樹の陰」というもので、大勢のグループに身を寄せるということで、身を寄せるべき大樹の正当性は何ら問題にされず、ただ数さえ多ければそれが正義だったというわけだ。
多数意見の具現といえば究極の民主主義で、その意味からすれば美濃部達吉も斎藤隆夫も自己にこだわり過ぎて冷や飯を食わされたということになる。
それと同時にある意味でイジメの構図でもあった。
彼らを糾弾する声が大きくなると、一人去り二人去りと、彼らの身の回りから身を引いたわけで、火の子が我が身に降りかかる事を避けたということだ。
自分がそういう状況から身を引くだけならまだ許せるが、この後に及んで「虎の威を借りる狐」よろしく、時流に呼応したスローガンを叫び、アジテーター乃至は自己顕示欲の塊のようなさもしい人間の存在である。
ここでいう時流というのが軍国主義であったわけで、この軍国主義に迎合しない気骨のある人間を、異端者としてイジメ抜く構図が一世を風靡していたのが昭和の初期という時代だった。
サブタイトルには「平成日本の原風景」となっている。
著者は皿木喜久と言う人だ。
昭和15年生まれの私は今72歳であって、当然のこと大正時代については知る由もない。
しかし、あの狂気の昭和の時代を掘り下げて行くと、その前の大正時代についても、それなりに掘り下げなければならないと思う。
だが、この時代については案外等閑視されているような気がしてならない。
それと言うのも、戦後の歴史教育が西暦で語られるので、大正時代という言葉が俎上に上りにくい、という面があるのかもしれない。
大正時代を西暦でいえば、1912年から1926年までの間であるが、この間はある意味で日本の戦間期であって、平和を謳歌した時代でもある。
大正デモクラシーという言葉は巷にあふれたが、この戦争の無い平和な時代に、ある意味で民主主義が熟成されればよかったが、そうならなかったところが歴史の現実であった。
この本のサブタイトルにもある様に、平成の政治的混乱の萌芽が、既にこの時代に芽生えていたのではないかと思う。
そもそも、人間の生存ということを考えた時、基本的には民主主義が統治の原点ではないかと思う。
人間の集まりが国家という概念に至る前の時代においては、人々は今でいう集団合議制で、自分たちの在り方を決めていたのではないかと思う。
そういう時代を、今の概念で示せば、山賊や野武士の集団と考えればいいと思うが、こういう人達でも、自分たちの先行きを考える場合、リーダーの取り巻き、いわゆるスタッフの意見を聞いて、それを参考にしながらボスがある決定を下していると思う。
自分たちの集団の回りに起きるさまざまな事象、現象、具象に対して、如何に対応するかが統治であったに違いない。
統治の副産物として、金銀財宝を身の回りに集める、という行為もあったに違いなかろうが、それはあくまでも与録であって、統治の主眼がそこにあったわけではないと思う。
山賊の親分でも野武士の頭目でも、自分のスタッフの意見は尊重したに違いないと思うが、そういうスタッフの意見を聞いて決定し、決断を下したことを実践するについても、やはり同じようにスタッフが要るわけで、その部分を今風の言い方をすれば行政・官僚ということになる。
しかし、こういう山賊や夜盗及び海賊の様な集団を一つのマスと捉えた時、そこには必ずリーダーが自然発生的に産まれるわけだが、一つのマスの中ではリーダーの数は限りなく少なく、大抵の場合一人である。
リーダーが2人も3人も居れば、その中での意見の集約ということはあり得ないので、群れ全体が右往左往することになってしまう。
だから、リーダーは一人であるが、リーダーを補佐するスタッフは、それぞれの群れの統治の仕方によって千差万別である。
こういう人間の集団が近代国家をなすようになると、リーダーを補佐するシステムも複雑化してきて、統治のシステム化が顕著になってきた。
統治する側とされる側では、その中の人間の数が極端に違うわけで、統治のシステムとして行政を司る人は、ある程度の人数ではあるが、それでも統治される側の人から比べれば数はうんと少ない。
人間の集団としての社会は、統治する人とされる人の2種類に分類される。
リーダーがたった一人で、そのリーダーが統治すべき人から私利私欲を収奪するような思考であったならば、大勢の人々が困るわけで、そういう統治であってはならないというわけで、様々な政治システムが考案されたが、その中でももっとも人々の共感を得られるに違いないと思われるものが、民主主義という手法であった。
これは統治されるものが、自分たちの総意で、自分たちのリーダーを選出するというシステムであって、そうであるとするならば、人々は自分たちの選んだリーダーに黙ってついていくに違いない、という狙いがあった。
ところが人間の考えというのは、それこそ十人十色で、その考える事というのは文字通り千差万別であるわけで、リーダーが「あっち行こう」と言っても、様々な意見が出て、意見の集約が出来ず、行先は一向に決まらないということになる。
この地球上にある数ある人間集団の中には、リーダーの世襲制のところもあって、そういうところでは大体が独裁政治なので、リーダーは統治される側の人々の意向など考える必要はなく、リーダーの思い通りの施策が可能である。
問題は、そういう施策が、統治されている側の人々の共感を得、そういう人々の幸福感に寄与しているかどうかという点である。
我々日本民族の生い立ちも、基本的には農耕民族で、山から流れでる川の水が得られやすい場所で稲を栽培して、米を作って生計を立てていたに違いない。
そういう集団の中に、山賊か夜盗のような暴力集団が押し入って、今の暴力団のみかじめ料の様な搾取が恒常化して、それがおいおい地方豪族に成長して、最終的にはそれぞれに覇を競うようになった、と私は考えている。
問題は、元々稲を作って平和に暮らしていた人達の意思決定方法であって、こういう人たちは、リーダーをお互いの回り持ちでこなしていた。
だから自分がリーダーの時、余りはりきり過ぎて過去に前例がない特異な行為をすると、自分がリーダーを降りた時にしっぺ返しがあるわけで、好むと好まざると前例踏襲に徹しなければならなかった。
言い方を変えると、封建主義を踏襲せざるを得ず、過去の前例からの脱却できずにいたということである。
農作業の手順に関しては既にルーチン化しているので、誰が号令をかけてもつつがなくこなせるが、想定外の事態に直面した時の対応において、どうしても前例主義に陥ってしまって、新しい発想を試す事が出来なかった。
そういう殻を打ち破ったのが明治維新であったが、この大革命を経ても、日本民族のすべてがすべて意識改革に成功したわけではなく、それに乗り遅れた者も大勢いた。
我々の民族の歴史を振り返ってみると、我々は稲作農民であったが、この過程においてリーダーの回り持ちを経験しているので、大勢の人がある意味で政治的な物の考え方になじんでいたということが言える。
自分たちの考えを政治に反映させることの意義を知っていたとも言える。
ところが、これも我々の仲間の数が少ないうちはそれで治まっていたが、我々の同胞の人口が多くなると従来の方法では行き詰ってしまうことになった。
人口が増えるという意味は、物理的な人間の数のみではなく、従来政治に参与していなかった階層が、人権意識の高揚によって新たに政治参加の権利を持つようになった、という意味も含まれている。
これは、普通は民主化の成熟という言い方で語られているが、古代ギリシャの市民階層でも奴隷の階層の者は政治参加できなかったわけで、我々も同じような軌跡を歩んでいるということだ。
現に普通選挙法の施行も、新たな階層に政治参加の機会を与えたわけで、政治というものがお互いの顔の判りあえる範囲内のものではなくなって、不特定多数の顔の見えない大衆を相手にしなければならなくなったということだ。
従来ならば、自分の顔の見える範囲の利害得失を追い求めておればよかったが、顔の見ないどこの馬の骨とも判らない人間の利害得失を代弁するについては、どうしてもある程度無責任に成らざるを得ない。
そのことは、口を開けば国民大衆の利便を代弁する大言壮語を吠えまくらねばならないが、心の中ではあくまでも自己の利便のための方便であって、口先だけのリップサービスに過ぎないということになる。
だから、現代の先進国の民主主義体制というのは、統治する側のリップサービスと、そのリップサービスの実行を何処まで追求できるかのせめぎ合いだと考えてもいい。
統治する側に立とうと考えている人達の立候補の立会演説は、その内容の全てが「当選した暁にはこうします」という公約であるが、公約はあくまでもリップサービスに過ぎず、自己PRの場でしかない。
被選挙民、つまり選ぶ側が顔見知りの範囲ならば、候補者も本音で語れるが、選んでくれる相手が何処の馬の骨とも判らない大衆では、綺麗ごとを並べたリップサービスでしか、自己の特質を知らしめる方法がない。
よって、出来もしない理想論を振りかざすということになるのであるが、選ぶ側の見識に政治に対する期待が薄い場合は、その選択に瑕疵が生じ、結果はブーメランのように選んだ側に振りかかって来る。
我々の先祖は農耕民族としてルーチン化した祀り事はリーダーを廻り持ちで行ってきたので、ある意味で誰でもその長(おさ)が務まる。
これはいわゆる究極の民主主義体制であったわけだが、このDNAが今日までも引き継がれて、長という立場に固執する日本人は極めて少ない。
いとも安易に長という椅子を放り出してしまう。
リーダーの座に全く未練を持たないということは、その地位が廻り持ちで、誰がやってもある程度は全うできる、ということがわかっているからであるが、政治の場ではその間の政治的空白は免れない。
この政治的空白が問題になるケースは、喫緊の課題を抱え込んだ時であって、そういう時にこそリーダーの存在が問われるのに、その緊急課題を政争の具にするところが我々の悪弊である。
この本の中にも述べられているが、大正14年には治安維持法と普通選挙法は抱き合わせで成立している。
治安維持法は世紀の悪法のように言われているが、政友会、憲政会、革新倶楽部という政党の議論を経て成立しており、スターリンや毛沢東のような独裁者が自分の政敵を潰すために作ったわけではない。
「そういう法律が必要だ」、という国民の側の欲求があった、という当時の我々の置かれた状況をよくよく注視する必要がある。
普通選挙法だとて、当然のこと、国民の欲求があったればこそできたわけで、何も求めるものがないのに為政者の都合で法案ができるわけではない。
そういう意味では我々同胞の政治感覚は素晴らしいものがあるが、皆が皆、この素晴らしい特質を兼ね備えているが故に、結果として「船頭多くして船山を登る」ということになってしまっている。
一人一人が、それぞれに立派な意見を持っているので、百家争鳴となってしまい、意見の集約が出来ず、結果として物事は一歩も前に進まないということになっている。
大正時代の船成り金という言葉はよく聞いたものだが、この成り金という言葉には、成り金になり損ねた庶民の怨嗟の気持が含まれていることは容易に想像できるが、成り金といわれ、暫くして没落する人達のことはどう考えたらいいのであろう。
「自分が一代で稼いだ金なんだから、自分の代で使い切る」という考え方を、我々はどう考えるべきなのであろう。
私の考えで言えば、やはりこういう考え方は下衆っぽい思考であって、堅実な考え方の対極をなすものだと思う。
この考え方は、自分一人のことしか眼中になく、周りの人たちのことが思考から抜け落ちてしまっていて、今で言うところの究極のジコチュウ(自己中心主義)でしかない。
「自分で儲けた金を自分で使って何が悪い」という論法であるが、自分が儲けたということは、相手の犠牲の上に成り立っているわけで、そこの心配りが行き届いていないということが、その後の日本の先行きに大きく影響を及ぼした。
大正3年に日本が第1次世界大戦に参戦するということは、イギリスとの条約がある以上、いた仕方ない面があるが、中国に対して対支21カ条の要求というのは、余りにも我々の側の驕り高ぶった振る舞いだといわざるを得ない。
時の総理大隈重信は、あまりにもシナを舐め切っていたわけで、こういうことが判らない、事の善悪が判断できない、ということはその案件について無知だったとしか言いようがない。
昭和の軍人、特に高級将校、高級参謀といわれるような人々が、現代の戦争に無知だったのと同じように、大隈重信も我が隣国の人々のことに思いが至らず、相手に対して無知だったという事だと思う。
船成り金と同じで、たまたま時の巡り合わせで金持ちになれたものを、自分の実力で儲けれた、と思違いをしたようなもので、身の程知らずということだ。
その一方で、この時代は軍にとってはまことに不運な時期で、ある種の軍縮ムードに押されて、軍人が肩身の狭い思いをさせられた時期でもあった。
その反動で昭和初期の軍人は威張り散らしたわけでもなかろうが、軍人に対する扱い方に、余りにも幅が広いというのも大いに考えざるを得ない。
地球規模で眺めれば、軍人の中でも将校と下士官では扱いが違いうのが世界標準であって、将校というのは何処の国でもある程度社会的地位が確立していて、基本的には貴族であって、食うに困ることのない人々がなっている。
ところが日本の場合は、将校の出自は士農工商のあらゆる階層にあるわけで、一言でいえば官僚化されたサラリーマンである。
軍籍を離れたらその日から食うに困ったわけだ。
そういう階層の者にとって、軍縮は自分の首を絞めるようなもので、そういう状況下で軍人が軍服で街を歩けない、私服でなければ街を歩けない、という状況はまさしく受難の時期であって、その反動が昭和初期の軍人の態度に反映されたものと考えざるを得ない。
先に述べたように、近世以降の統治ということは、山賊や海賊の親玉ではあり得ないわけで、リーダーも下々の下世話にも大いに通じなければならなくなったわけで、下の者のご機嫌伺いをしながら、自己の目的を推し進めなければならないので、上からの「オイ、コラッ」式で行けなくなった。
上は上なりに気苦労が多くなった。
その意味で、大正時代に軍人が軍服で街を歩けないということは、市民の存在感が大きくなったということでもあって、市民の軍部に対する風当たりが強くなったことを指し示しているが、これはこれでまた大きな反省材料でもあった。
つまり、日露戦争では軍人や軍部の活躍を手放しで喜びながら、時代が下がって大正時代になると、彼らの存在を冷ややかな目で見ているわけで、軍人サイドに立って見れば、「何を小癪な平民メ」という思考に自然になると思う。
ということは、国民というものは常に時流に迎合するのがその本質であって、国民大衆には理念も理想も最初から存在していないわけで、それをあたかもある様に吹聴して回るのがメデイアというヤクザな存在であった。
もっとも国民とか市民というのは、目先の自己の利益だけが感心ごとなわけで、そう先のことまで考えてはおらず、目の前の利得だけに関心を示すので、統治者としてはそれに応えてさえおれば安心できる。
つまり馬の鼻さきにニンジンをぶら下げておけば安泰だと思われている。
これを今実践しているのが平成の民主党政権であって、民主党政権というのは国民に金をばら撒くことのみに専念しているわけで、そんなことをしておれば当面の人気は衰えないが、その先はどうなるか判ったものではない。
国民に対して耳障りの良い事ばかりを並べたてて、人気取りには熱心であるが、真の国益については何のビジョンも示し得ない。
国民の嫌がることは先送りして、国民のアメだけをばら撒けば、当座の人気は上がるけれど、そんな事が長続きするわけがない。
私自身の研究不足かもしれないが、昭和初期の時代に軍人が跋扈する背景が大正時代にあるのではないかと思って注視しているが、この時代の事柄を書いた書物は、全てが戦争の話になってしまって、肝心の政治から離れてしまっている。
例えば、美濃部達吉博士の『天皇機関説』の論議もまことに不思議な話で、最初は大勢の国会議員も違和感を持っていなかったにもかかわらず、最終的には議会を追い出されてしまった。
これは一体どういうことなのであろう。
斎藤隆夫の演説も、当初は彼の演説に好意的だった者が、時の経過とともに彼を糾弾する側に傾いてしまう、ということは一体どういうことなのであろう。
この時代には、いわゆる風見鶏のように時流を探り当てる才覚を持ち合わせていないと生き残れないということだったに違いない。
それは俗に言う「寄らば大樹の陰」というもので、大勢のグループに身を寄せるということで、身を寄せるべき大樹の正当性は何ら問題にされず、ただ数さえ多ければそれが正義だったというわけだ。
多数意見の具現といえば究極の民主主義で、その意味からすれば美濃部達吉も斎藤隆夫も自己にこだわり過ぎて冷や飯を食わされたということになる。
それと同時にある意味でイジメの構図でもあった。
彼らを糾弾する声が大きくなると、一人去り二人去りと、彼らの身の回りから身を引いたわけで、火の子が我が身に降りかかる事を避けたということだ。
自分がそういう状況から身を引くだけならまだ許せるが、この後に及んで「虎の威を借りる狐」よろしく、時流に呼応したスローガンを叫び、アジテーター乃至は自己顕示欲の塊のようなさもしい人間の存在である。
ここでいう時流というのが軍国主義であったわけで、この軍国主義に迎合しない気骨のある人間を、異端者としてイジメ抜く構図が一世を風靡していたのが昭和の初期という時代だった。