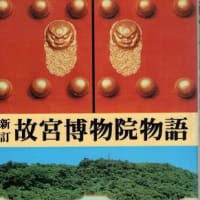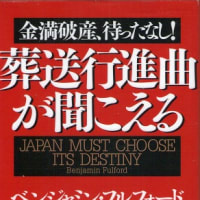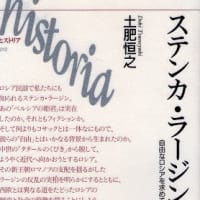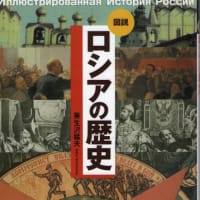例によって図書館から借りてきた本で、「ナツコ」という本を読んだ。
サブタイトルでは「沖縄密貿易の女王」となっているが、そんなにおどおどしい物語ではなかった。
終戦直後の沖縄を生き抜いた金城夏子(旧姓、宮城)という女性の自叙伝という類の物語である。
この女性が戦後の混乱、これは沖縄だけの問題ではないが、を生きんがために法の網を掻い潜らざるを得ず、その苦難は筆舌に尽くしがたい、ということが強調されているが、それは私に言わしめれば沖縄だけの問題ではなかったと思う。
戦後の混乱というのは日本内地でも沖縄となんら変わるものではなく、ただ沖縄というのは海の国であって、海が主体という意味で船に頼らざるを得ず、その意味から密貿易という表現になるのも致し方ない。
沖縄の地勢的な位置というのは太古から変わらないわけで、如何なる時代においても主権国家の辺境という位置は変わりようがない。
中国に属しても、台湾に属しても、日本に属しても、如何なる国に属しても辺境であることに変わりはなく、今日、極東の要石としてアメリカ軍の基地が広大な土地を占めているとしても、その置かれた地勢的な条件からの宿命だと思う。
沖縄を語るとき必ず出てくるキーワードが「鉄の暴風」という言葉であるが、この言葉を出すことによって沖縄は特別に悲劇的な場所だという印象を強調するが、それは沖縄人の思い上がり以外の何物でもない。
内地の東京大空襲をはじめとする各都市の空襲や、広島、長崎の原爆のことを思えば、沖縄だけが特別に悲劇的であったなどとはいえないはずだ。
その意味からしても、戦後という時代は日本の全土が廃墟であったわけで、その中で生き抜く、生き残るということはまさしく原始人並の生き様であった。
経済の原則などというものは存在し得ず、身の回りのものを物々交換で生きなければならなかった。
法を遵守していればまさしく餓死あるのみで、現実にその通りのことが起きているわけで、その意味でその時代の生き様を密貿易と表現することは酷な言い方ではないかと思う。
内地でも買い出し、あるいはかつぎ屋、ブローカーなどという表現は日常的に使われていたわけで、それを違法なことだから糾弾するなどというイメージはほとんど認識されていなかったはずだ。
そういう行為が違法という認識は持っていただろうが、それをしなければ生きておれなかったわけで、背に腹は変えられず、心の隅で罪の意識にさいなまれつつしていたに違いない。
戦後のある時期、乗り物という乗り物にはあらゆる場面でかつぎ屋という風情の人たちが乗っていた。
年の頃は50代から60代の田舎のオバサンという風情で、背中に大きな篭を背負い、おそらく重さは50キロ以上あったのではなかろうか。
そういうものを持ち込んでは列車に乗っていた。
沖縄ではこれと同じことが船でなされていたわけで、海が介在しているので海に依拠する限り、国境というのもあるようでないも同然なことは言うまでもない。
ただただ官憲にさえ捕まらなければ何処までいっても自由が保障されていたわけである。
ただし命の保証はないわけで、そのリスクを問わなければ後は勇気だけが後ろ盾だったに違いない。
そういう意味で、日本内地ではかつぎ屋と言われたことと同じことが船によってなされたわけである。
このかつぎ屋はある意味で実働部隊であるが、当然そういうものが暗躍すれば、それを束ねる組織、あるいは采配する組織が必然的に生まれるわけで、その元締めとして手腕を振るったのが宮城夏子、結婚後は金城夏子ということであった。
戦後の混乱の時期にこういう商売で資金を得、それをその後の発展につなげた事業家は大勢いると思う。
今の大企業も元をたどればこういう闇商売に行き着くケースも多いと思う。
戦後立ち上がった企業で、今成功している企業は、その大部分がこうしたことに手を染めていたに違いない。闇商売、ブローカーというものに対して我々はあまり好感を持って口にすべきことではないと思われているが、ビジネスというものはもともとこういうことだと思う。
世界史で習う大航海時代というのは、一言でいえば国家主体のブローカー時代であったわけで、それこそがビジネスの本質であるものと考える。
問題は、そういう行為で資金を得ながら、それが途中で頓挫して、それ以上の発展が止まってしまって、しばらくすると零落してしまったという現実である。
この本の場合は、ナツコ自身がわづか38歳という若さで死んでしまったので、必然的にそれが適わなかったということも言えるが、企業というのは個人の持ち物ではないはずで、創業者が死んだとしても、企業そのものは生き残ってしかるべきものだと思う。
理屈はそうであろうとも、そうならないのが人の世の常で、今、大企業といわれる会社はそこを上手に生き残ったということであろう。
後継者の養成に成功したということであろう。
私自身は事業の才覚がからっきし無いことを自分でも自覚しているから、今までにおいて金儲けをしようなどと考えたことは一度もない。
然し、日々の生活の中で私の周囲の中小企業の事業者を見ていると、明らかに「あれでは事業が伸びない」と思われるケースがあまりにも多い。
儲かったときは大判振る舞いをして、そうでないときはすぐさま借金に駆け回るでは、事業そのものが最初から綱渡りしているわけで、まるで競輪・競馬をしているのとなんら変わるものではない。
この本の主人公も、ある意味で自叙伝という体をなしているので、本人に好意的に描かれており、人にむやみやたらと資金援助し、政治家にも入れあげているが、この辺りにナツコ自身の善意と理念が垣間見れると言えば表現はやわらかいが、ビジネスが善意や好意で左右されてはビジネス足りえないと思う。
その意味で私の周りの中小企業の面々と大して変わるものではない。
沖縄でトップのブローカーに上り詰めても、事業を継続できなかったという点では、栄華盛衰を地で行ったようなものであるが、それは人を見る目が無かったということに尽きると思う。
それと自分の実績の上に胡坐をかいた独りよがりの思考であったのではないかと思う。
戦後の混乱も落ち着いて正業に事業転換をしようとしたときに、子飼いの人間をトップに据えず、外部から人を引っ張ってきた点に内紛を誘発する要因があったと思うが、これは事業者としてはなはだ難しい問題であろうと思う。
事業が発展的に規模拡大するときに、子飼いの部下の中からそれに対応するだけの能力があるかないかの見極めは、事業者、経営者としては極めて難しい選択眼を要求される。
このナツコは昭和29年に38歳で没しているが、私の母もこの2年前、昭和27年に没している。
母の生まれた年が大正元年だからこのナツコとほぼ同世代を生き、重ねた年もほぼ同じだったが、やはり母の死因は結核であった。
ナツコの場合は皮膚がんということであるが、この時代の病気は死に直結していたことに変わりはない。
今、私の年でこの時代を考えてみると、実に大変な時代であったと思う。
その意味では沖縄でも内地でも全く変わりはないと思う。
内地だから恵まれていたなどということはなかったと思う。
こういう原始時代に等しいような環境を生き抜くには、人間の知恵だけが頼りだったのではなかろうか。
沖縄でも内地でも明らかに無の状態であったわけで、原始時代となんら変わることがなく、そこで生き抜くためには人間の知恵以外に頼るものがなかったものと想像する。
生きんがために体以外に資本はなく、そういう状況下で病に倒れるということは、即、死に直結していたわけだ。
この中で、ナツコがペニシリンやストレプトマイシンを闇で流していたという記述を読んで、結核で母をなくした私としては複雑な気持ちにならざるを得ない。
然し、人が病で死ぬということは、ある意味で天命でもあったわけで、そのときに死ぬべき運命であったものと思う。
あまりにも達観しすぎだろうか。
ナツコにしろ、私の母にしろ、死んだ年が38歳と40歳という短い人生であった。
本人たちはもっともっと生きたかったろうとその無念さは十分にわかる。
子供たちの成長を見届けてから逝きたかったのではなかろうかと、その無念さを思うとなんとも言葉に言い表せないものを感じる。
サブタイトルでは「沖縄密貿易の女王」となっているが、そんなにおどおどしい物語ではなかった。
終戦直後の沖縄を生き抜いた金城夏子(旧姓、宮城)という女性の自叙伝という類の物語である。
この女性が戦後の混乱、これは沖縄だけの問題ではないが、を生きんがために法の網を掻い潜らざるを得ず、その苦難は筆舌に尽くしがたい、ということが強調されているが、それは私に言わしめれば沖縄だけの問題ではなかったと思う。
戦後の混乱というのは日本内地でも沖縄となんら変わるものではなく、ただ沖縄というのは海の国であって、海が主体という意味で船に頼らざるを得ず、その意味から密貿易という表現になるのも致し方ない。
沖縄の地勢的な位置というのは太古から変わらないわけで、如何なる時代においても主権国家の辺境という位置は変わりようがない。
中国に属しても、台湾に属しても、日本に属しても、如何なる国に属しても辺境であることに変わりはなく、今日、極東の要石としてアメリカ軍の基地が広大な土地を占めているとしても、その置かれた地勢的な条件からの宿命だと思う。
沖縄を語るとき必ず出てくるキーワードが「鉄の暴風」という言葉であるが、この言葉を出すことによって沖縄は特別に悲劇的な場所だという印象を強調するが、それは沖縄人の思い上がり以外の何物でもない。
内地の東京大空襲をはじめとする各都市の空襲や、広島、長崎の原爆のことを思えば、沖縄だけが特別に悲劇的であったなどとはいえないはずだ。
その意味からしても、戦後という時代は日本の全土が廃墟であったわけで、その中で生き抜く、生き残るということはまさしく原始人並の生き様であった。
経済の原則などというものは存在し得ず、身の回りのものを物々交換で生きなければならなかった。
法を遵守していればまさしく餓死あるのみで、現実にその通りのことが起きているわけで、その意味でその時代の生き様を密貿易と表現することは酷な言い方ではないかと思う。
内地でも買い出し、あるいはかつぎ屋、ブローカーなどという表現は日常的に使われていたわけで、それを違法なことだから糾弾するなどというイメージはほとんど認識されていなかったはずだ。
そういう行為が違法という認識は持っていただろうが、それをしなければ生きておれなかったわけで、背に腹は変えられず、心の隅で罪の意識にさいなまれつつしていたに違いない。
戦後のある時期、乗り物という乗り物にはあらゆる場面でかつぎ屋という風情の人たちが乗っていた。
年の頃は50代から60代の田舎のオバサンという風情で、背中に大きな篭を背負い、おそらく重さは50キロ以上あったのではなかろうか。
そういうものを持ち込んでは列車に乗っていた。
沖縄ではこれと同じことが船でなされていたわけで、海が介在しているので海に依拠する限り、国境というのもあるようでないも同然なことは言うまでもない。
ただただ官憲にさえ捕まらなければ何処までいっても自由が保障されていたわけである。
ただし命の保証はないわけで、そのリスクを問わなければ後は勇気だけが後ろ盾だったに違いない。
そういう意味で、日本内地ではかつぎ屋と言われたことと同じことが船によってなされたわけである。
このかつぎ屋はある意味で実働部隊であるが、当然そういうものが暗躍すれば、それを束ねる組織、あるいは采配する組織が必然的に生まれるわけで、その元締めとして手腕を振るったのが宮城夏子、結婚後は金城夏子ということであった。
戦後の混乱の時期にこういう商売で資金を得、それをその後の発展につなげた事業家は大勢いると思う。
今の大企業も元をたどればこういう闇商売に行き着くケースも多いと思う。
戦後立ち上がった企業で、今成功している企業は、その大部分がこうしたことに手を染めていたに違いない。闇商売、ブローカーというものに対して我々はあまり好感を持って口にすべきことではないと思われているが、ビジネスというものはもともとこういうことだと思う。
世界史で習う大航海時代というのは、一言でいえば国家主体のブローカー時代であったわけで、それこそがビジネスの本質であるものと考える。
問題は、そういう行為で資金を得ながら、それが途中で頓挫して、それ以上の発展が止まってしまって、しばらくすると零落してしまったという現実である。
この本の場合は、ナツコ自身がわづか38歳という若さで死んでしまったので、必然的にそれが適わなかったということも言えるが、企業というのは個人の持ち物ではないはずで、創業者が死んだとしても、企業そのものは生き残ってしかるべきものだと思う。
理屈はそうであろうとも、そうならないのが人の世の常で、今、大企業といわれる会社はそこを上手に生き残ったということであろう。
後継者の養成に成功したということであろう。
私自身は事業の才覚がからっきし無いことを自分でも自覚しているから、今までにおいて金儲けをしようなどと考えたことは一度もない。
然し、日々の生活の中で私の周囲の中小企業の事業者を見ていると、明らかに「あれでは事業が伸びない」と思われるケースがあまりにも多い。
儲かったときは大判振る舞いをして、そうでないときはすぐさま借金に駆け回るでは、事業そのものが最初から綱渡りしているわけで、まるで競輪・競馬をしているのとなんら変わるものではない。
この本の主人公も、ある意味で自叙伝という体をなしているので、本人に好意的に描かれており、人にむやみやたらと資金援助し、政治家にも入れあげているが、この辺りにナツコ自身の善意と理念が垣間見れると言えば表現はやわらかいが、ビジネスが善意や好意で左右されてはビジネス足りえないと思う。
その意味で私の周りの中小企業の面々と大して変わるものではない。
沖縄でトップのブローカーに上り詰めても、事業を継続できなかったという点では、栄華盛衰を地で行ったようなものであるが、それは人を見る目が無かったということに尽きると思う。
それと自分の実績の上に胡坐をかいた独りよがりの思考であったのではないかと思う。
戦後の混乱も落ち着いて正業に事業転換をしようとしたときに、子飼いの人間をトップに据えず、外部から人を引っ張ってきた点に内紛を誘発する要因があったと思うが、これは事業者としてはなはだ難しい問題であろうと思う。
事業が発展的に規模拡大するときに、子飼いの部下の中からそれに対応するだけの能力があるかないかの見極めは、事業者、経営者としては極めて難しい選択眼を要求される。
このナツコは昭和29年に38歳で没しているが、私の母もこの2年前、昭和27年に没している。
母の生まれた年が大正元年だからこのナツコとほぼ同世代を生き、重ねた年もほぼ同じだったが、やはり母の死因は結核であった。
ナツコの場合は皮膚がんということであるが、この時代の病気は死に直結していたことに変わりはない。
今、私の年でこの時代を考えてみると、実に大変な時代であったと思う。
その意味では沖縄でも内地でも全く変わりはないと思う。
内地だから恵まれていたなどということはなかったと思う。
こういう原始時代に等しいような環境を生き抜くには、人間の知恵だけが頼りだったのではなかろうか。
沖縄でも内地でも明らかに無の状態であったわけで、原始時代となんら変わることがなく、そこで生き抜くためには人間の知恵以外に頼るものがなかったものと想像する。
生きんがために体以外に資本はなく、そういう状況下で病に倒れるということは、即、死に直結していたわけだ。
この中で、ナツコがペニシリンやストレプトマイシンを闇で流していたという記述を読んで、結核で母をなくした私としては複雑な気持ちにならざるを得ない。
然し、人が病で死ぬということは、ある意味で天命でもあったわけで、そのときに死ぬべき運命であったものと思う。
あまりにも達観しすぎだろうか。
ナツコにしろ、私の母にしろ、死んだ年が38歳と40歳という短い人生であった。
本人たちはもっともっと生きたかったろうとその無念さは十分にわかる。
子供たちの成長を見届けてから逝きたかったのではなかろうかと、その無念さを思うとなんとも言葉に言い表せないものを感じる。