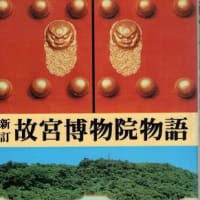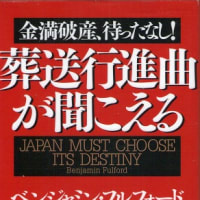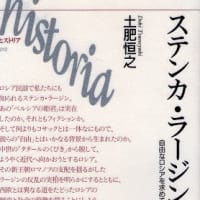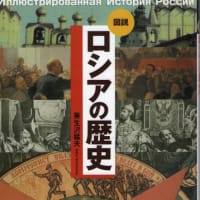例によって図書館から借りてきた本で、「国家の正体」という本を読んだ。
著者は日下公人氏。東京大学を出て日本長期信用銀行に勤めた人で、言うならば国を憂う憂国の士といった感じがする。
しかし、このことは主権国家の国民ならば誰しも当然のことであって、自分の国を憂うことのない国民というのはありえないはずである。
ただ、その憂い方が各人各様に違っているわけで、そのことから考えれば、この人の論旨は私にとっては当然のことだと思う。
この著者は司馬遼太郎の「この国のかたち」というアプローチから攻めているが、確かに「この国」といった場合、第三者的な印象を受ける。
自分が当事者であるということを脇においておいて、第3者が外から眺めている印象がある。
この著者の場合、銀行という業務を通じて国益というものを常に考え続けてきたので、こういう発想に至ったのかもしれない。
国益ということは、基本的には国民の幸福ということにつながるに違いない。
国が豊になるということは、一部の金持ちが跋扈することではなくて、底辺レベルの底上げが豊かな国ということだと思う。
19世紀初頭には、この目的達成のために共産主義という思考のもとで、そういう理想の実現を追い求めた人間の集団があったことも歴史的な事実ではある。
そして今でも、その理想を信じている人たちのいることも歴然たる事実ではある。
一部の金持ちが跋扈する状況を否定して、全体の底上げを目指そうという思考は、非常に説得力があることも厳然たる事実でもある。
過去にそれを実現して、結果的に80年足らずして、その矛盾に押しつぶされて元の黙阿弥に戻った国もあるわけで、だとすると統治される側の国民としては、如何に処すべきかというのがこの著者の抱えている大命題なわけだ。
日本の統治者というのは金銭的には極めて淡白だと思う。
政治家となり、ある程度は金儲けとしての利権あさりというよう行動に出る人もいないでもないが、自民党総裁、総理大臣になったからといって、私利私欲に走る人はいないわけで、大臣の椅子などいとも安易に放り出してしまうし、総理の椅子でも全く固執しないくてあっさり放り出してしまう。
あまりにもあっさり放り出してしまうので、逆の意味で無責任とそしられているが、他の民族では一度手にしたトップの座は、そう安易に放り出す人はいない。
統治のトップがあまり金にこだわらないというのは、やはりそれだけ民度が高いといってもいいと思う。
民度が高いということは、自分のことよりも国民全体のことを優先している、と考えたいところであるが、ことはそう単純ではない。
ここが極めて難しいところで、国民のことを考えて、国民に対して良かれと思ってしたことが、国民から批判を浴びることになる。
統治者が国民のためといくら思っていたとしても、国民の側には様々な考え方があるわけで、必ずしも統治者が良かれと思ったことがそのまま受け入れられないということである。
こういう考え方の相違を突く論戦が行われている内は、政治はノーマル状態であるが、この論戦が論戦のための論戦になってしまって、すべき施策の本質を突く論戦を放り出して、政権交代だけを責める論議に陥るから、政治が低迷するわけである。
もともと我々日本民族というのは、独裁政治を基本的に忌み嫌う民族である。
我々の社会は、一人のリーダーが全てを決するという方策には極めて臆病で、自信がなく、何かを決めなければならない時は、集議に図って皆の意見を聞きながらことを決する。
これは一種の責任逃れでもあるわけで、後から「あいつがやったことだから!」という後ろ指さされないようにという予防線でもあったわけだ。
だから何事においても、ものごとを決するときには、人の意見を聴いたうえで実行に移すのが、この話し合いの場で主導権争いを演じてしまうのである。
独裁で、「俺の言うことを聞け!!」と、はっきりと正面から言うことは厭だが、「俺が言ったから実現した」という風に持っていきたいわけである。
だから、すべきことの本質よりも、その手順とか、手続きとか、主導権とか、どうでもいいことに血道をあげて、名のみを欲しがるのである。
議論すべきことの本質を捨ておいて、相手のスキャンダルを暴き、手順手続きの不備を突き、議論のための議論を繰り返して、相手の失敗に歓喜する、という人間として非常に卑しい行為に走ってしまうのである。
統治する場、国会の場がこういう状況では、今日の流動化した地球規模の国際環境には適応しないことは誰の目にも明らかである。
国内の対応でも、意味もない議論に終始していれば、そのチャンスを逃がすことは当然のことで、対策が後手にまわることは自明である。
そのことは当然国益の損失という形で回り回ってくるのであるが、この著者は、その部分に大きな憂いを感じているようだ。
主権国家の国民としては当然のことだと思う。
我々は先の大戦で、自分達の政府に騙されていた部分は多大にあると思う。
当時の大日本帝国は、自国民に対して、「勝つ!勝つ!」と、大言壮語をしておきながら、結果的には完膚なきまでの敗北であったわけで、その為自国民のみならず、アジアの諸国民に対しても多大な迷惑を掛けたことは紛れもなく我々の側の政治の失敗であったことは素直に認めなければならない。
政治、あるいは統治というのも、人の為す行為なわけで、人の為す行為である以上、失敗も大いにあるわけで、失敗は失敗と素直に認め、今後は同じ失敗を繰り返さないように、細心の注意を払ってしかるべきである。
そこで、過去の反省となるわけであるが、その反省をする時に、「我々は悪いことをしました」という論点に立つと、反省が反省足りえないことになる。
我々の父や、兄弟や、おじさんという親族が、「アジアで、フイリッピンで、朝鮮で悪いことをしてきた」では、後に続く日本の若者に対して顔を上げられないではないか。
事実、そういう認識が戦後の日本の中で一般化しているから、この著者の憂いが浸透しているわけで、相手からそう言われるのはいた仕方ない部分があるが、自らの内側からの声としては、そう言うべきではないと思う。
むしろ相手からそう言われたら、当時の我々の置かれた状況を懇切丁寧に説明すべきだと思う。
相手とこちらでは立場が違うわけで、当然、その立場の違いは利害の違いとなっているのであって、異なる民族が隣り合って存在する限り、利害得失はついて回るわけで、それは昔も今も全く変わることはない。
「悪いことをした」という認識は、あくまでも戦後の認識であって、大戦前の世界的な価値観では、そういう認識は生まれていなかったはずである。
人を抑圧したり、むやみやたらと人を殺していいというわけではないが、価値基準としては非常にあいまいな部分があったわけで、それを今の厳しい基準に照らして、70年近く前のことを今日の基準にてらして評価してはならないと思う。
今の日本の知識階層が、自分達の先輩諸氏、自分達の父や、兄弟や、おじさんたちのしたことを犯罪者よばりするということは、自分たちの祖先を冒涜する行為である。
臭いものに蓋をして口を拭えというわけではない、
当時は、そうしなければ我々自身が生きてこれなかった、ということを考えるべきだ。
我々が生き残るために、昭和初期の日本の政治家たちのとった施策は、結果的には大失敗であったわけで、そのためにアジアの人々も我々同胞も、大いに困惑をしたことになる。
だがそれは生きんがための方便、方策であったわけで、「ならば人殺してもいいか!」という論議まで飛躍すべきではないはずで、善悪、正義不正義という価値観で測るべきではない。
アジアの民と、日本の人々を、二つの異なった人間の集団として運動場に入れたとしら、平和的に共存することもあれば、双方でいきり立って抗争になることも当然あるわけで、如何なる場合でも双方の自己愛に基づいているのであって、ある時は平和的に、ある時は戦争状態になるのも、自己愛のバランスによっているのであるから、それは自然の摂理というべきである。
この著者が祖国を思うとき、日本の大衆があまりにも祖国という概念を喪失している点を憂いているわけで、自分の国の概念を失うということは、あまりにも恵まれすぎているということではなかろうか。
日本が戦争の渦に巻き込まれていった昭和の初期の頃、当時の日本は、今から思えば実に貧相な社会であったわけで、貧乏からの脱出はそれこそ国民的なコンセンサスであった。
社会の上層部分というのは、どこの国でもそう大した違いはなく、貧困層の存在もどこの国でもあったわけで、問題は、それぞれの国の中で金持ちと貧困層の間にある経済力の格差よりも、知識・考え方の格差ではないかと思う。
この頃、どこの国の知識階層にも人気のあったマルクス主義、共産主義というのは、知識階層の考え方であって、知識人が金持ちの富の独占を否定していたわけで、貧乏人はそういう思考の存在そのものも知らずにゴミ箱をあさっていたわけである。
結局、金持ちのボンボンが、金持ち、資本家、不労所得者、成り金を否定し、人は皆平等であるべきだと言っていたわけである。
ところが金持ちのボンボンは、金持ちのボンボンなるがゆえに、貧乏人に金を無償で与えれば働かなくなる、ということを知らなかったわけである。
ところが理念は立派で、慈悲心に富み、博愛精神に富み、人を魅了する言葉であったので、その綺麗事の文言に騙されて、無邪気にそれに惹かれたのである。
これは昭和初期の日本人が、貧乏からの脱出のためには、軍国主義によらなければ日本は滅亡すると思い込んだ構図と軌を一にしていたのである。
ことほど左様に、理念・理想を立派な言葉でまぶし、人の善意をかきたて、魅力的で万人に受け入れされそうな美しい言辞に変えて喧伝すると、正常な感覚まで麻痺してしまう、ということを如実に表していることである。
そういう視点で、今の我々の周りを見てみると、朝鮮や中国に対して、我々の先輩諸氏がひどいことをしてきたと声高に叫ぶと、先方も大いにそれを認めてくれ、自分達も禊をした気になって、世間に対して胸を張って良いことをしてきた気でおれるのである。
ところが、それは相手を利し自分の国を陥ていることに全く気がついていない。
こういう人に限れば、相手が得をすれば、こちらにもそれがブーメランのように回ってくると思い違いをしているようであるが、この考えは無知に等しい。
戦後の日本は、それこそ何を言っても牢屋に放り込まれるということはない。だからものを言う人も、節度ということを考えたこともない。
全くの野放図というのは、こういう状態を指すのであるが、自由というのはどこまで行っても完全に自由だと思っている。
成熟した人間社会には倫理や、道徳や、慣習や、法律で、して良いことと悪いことというものは暗黙の了解の中に存在しているはずであるが、日本の知識人はそういうものを一切無視しようとする。
そういうものを無視してこそ知識人であり、教養人だと、間違った自覚を持って嬉々としている。
知識人や教養人が、自分達の統治者を信用しないというのは、先の大戦の失敗経験から、ある程度はいた仕方ない面もあるが、そこを修復するのが本来ならば知識人や教養人の使命なのではなかろうか。
ただただ反政府を煽るだけならば、誰でもどこでも安易にできる。
統治ということを考えた場合、基本的には官僚の問題にいきつくと思う。
日本の総理大臣も各省庁の大臣も、本来ならば官僚の上に君臨して、官僚を手足のごとく使ってこそ本当の行政機関であろうが、日本の大臣は私欲のために金儲けに血道をあげる人もいない代わりに、国民のために官僚をこき使う人も極めて少ない。
ぶっちゃけて言えば、官庁の烏帽子のようなものだ。
この本の著者の憂いは、この官僚に国のためという意識が微塵もないことを言いたかったに違いない。
官僚の仕事が、官僚のための仕事に終始してしまって、国民の側に視点が向いていないことに非常に怒っている。
そんなことは当然といえば当然の話である。
学校を出て23、4歳で国家公務員になる。一度なったら少々のことでは首にならないわけで、余程の刑事事件でも起こさない限り、生涯安定した生活が保障されているのである。
旧ソビエットのノーメンクラートや、中国共産党員と同じで、そういう安定した組織の中で、誰が一生県命額に汗して働く気になるかと言いたい。
何もしないことが一番身の安全を保障しているわけで、余分なことをすれば、成功すればしたで妬まれ、失敗すればそれ見たことかと評価を下げるだけである。
何もしなくてもそれなりに年功序列で収入は上がるわけで、こういう組織に国益を期待する方が間違っている。
ならば誰が祖国を支えるのかとなれば、それは物作りである。
この物作りも、今では周辺諸国の安い人件費で、海外にその拠点が移ってしまっているが、国益を考えるという場合、そこが物事の根本である。
この本の著者は、日本長期信用という民間の銀行に身を置いていたので、この部分で政府、官僚とも相当に交渉の場をもったらしいが、その経験からこの本が書かれている。
しかし、今までの概念では、国家というものが個人を庇護し、個人の身の安全を支える具体的な機関であったが、こういう考え方も20世紀までのもので、これからは国家という概念そのものが消滅するのではないかと思う。
倫理感とか、正義感とか、善し悪しの判断基準というものが世界標準として定まれば、人は国家の枠組みの中にとどまることなしに、生きていけるのではなかろうか。
ただ親類縁者が固まって住んでいるというぐらいの意味合いで、国家が一人一人の国民に対して忠誠を誓わせたり、援助や支援を差し伸べることはなくなるのではなかろうか。
人は、経済の活発な場所を求めて自分から移動していくわけで、この人間の移動は国境を超えて自由に行き来すると思う。
現にヨーロッパではそういう時代になっているわけで、20世紀における国境の意味が限りなく低くなっているではないか。
著者は日下公人氏。東京大学を出て日本長期信用銀行に勤めた人で、言うならば国を憂う憂国の士といった感じがする。
しかし、このことは主権国家の国民ならば誰しも当然のことであって、自分の国を憂うことのない国民というのはありえないはずである。
ただ、その憂い方が各人各様に違っているわけで、そのことから考えれば、この人の論旨は私にとっては当然のことだと思う。
この著者は司馬遼太郎の「この国のかたち」というアプローチから攻めているが、確かに「この国」といった場合、第三者的な印象を受ける。
自分が当事者であるということを脇においておいて、第3者が外から眺めている印象がある。
この著者の場合、銀行という業務を通じて国益というものを常に考え続けてきたので、こういう発想に至ったのかもしれない。
国益ということは、基本的には国民の幸福ということにつながるに違いない。
国が豊になるということは、一部の金持ちが跋扈することではなくて、底辺レベルの底上げが豊かな国ということだと思う。
19世紀初頭には、この目的達成のために共産主義という思考のもとで、そういう理想の実現を追い求めた人間の集団があったことも歴史的な事実ではある。
そして今でも、その理想を信じている人たちのいることも歴然たる事実ではある。
一部の金持ちが跋扈する状況を否定して、全体の底上げを目指そうという思考は、非常に説得力があることも厳然たる事実でもある。
過去にそれを実現して、結果的に80年足らずして、その矛盾に押しつぶされて元の黙阿弥に戻った国もあるわけで、だとすると統治される側の国民としては、如何に処すべきかというのがこの著者の抱えている大命題なわけだ。
日本の統治者というのは金銭的には極めて淡白だと思う。
政治家となり、ある程度は金儲けとしての利権あさりというよう行動に出る人もいないでもないが、自民党総裁、総理大臣になったからといって、私利私欲に走る人はいないわけで、大臣の椅子などいとも安易に放り出してしまうし、総理の椅子でも全く固執しないくてあっさり放り出してしまう。
あまりにもあっさり放り出してしまうので、逆の意味で無責任とそしられているが、他の民族では一度手にしたトップの座は、そう安易に放り出す人はいない。
統治のトップがあまり金にこだわらないというのは、やはりそれだけ民度が高いといってもいいと思う。
民度が高いということは、自分のことよりも国民全体のことを優先している、と考えたいところであるが、ことはそう単純ではない。
ここが極めて難しいところで、国民のことを考えて、国民に対して良かれと思ってしたことが、国民から批判を浴びることになる。
統治者が国民のためといくら思っていたとしても、国民の側には様々な考え方があるわけで、必ずしも統治者が良かれと思ったことがそのまま受け入れられないということである。
こういう考え方の相違を突く論戦が行われている内は、政治はノーマル状態であるが、この論戦が論戦のための論戦になってしまって、すべき施策の本質を突く論戦を放り出して、政権交代だけを責める論議に陥るから、政治が低迷するわけである。
もともと我々日本民族というのは、独裁政治を基本的に忌み嫌う民族である。
我々の社会は、一人のリーダーが全てを決するという方策には極めて臆病で、自信がなく、何かを決めなければならない時は、集議に図って皆の意見を聞きながらことを決する。
これは一種の責任逃れでもあるわけで、後から「あいつがやったことだから!」という後ろ指さされないようにという予防線でもあったわけだ。
だから何事においても、ものごとを決するときには、人の意見を聴いたうえで実行に移すのが、この話し合いの場で主導権争いを演じてしまうのである。
独裁で、「俺の言うことを聞け!!」と、はっきりと正面から言うことは厭だが、「俺が言ったから実現した」という風に持っていきたいわけである。
だから、すべきことの本質よりも、その手順とか、手続きとか、主導権とか、どうでもいいことに血道をあげて、名のみを欲しがるのである。
議論すべきことの本質を捨ておいて、相手のスキャンダルを暴き、手順手続きの不備を突き、議論のための議論を繰り返して、相手の失敗に歓喜する、という人間として非常に卑しい行為に走ってしまうのである。
統治する場、国会の場がこういう状況では、今日の流動化した地球規模の国際環境には適応しないことは誰の目にも明らかである。
国内の対応でも、意味もない議論に終始していれば、そのチャンスを逃がすことは当然のことで、対策が後手にまわることは自明である。
そのことは当然国益の損失という形で回り回ってくるのであるが、この著者は、その部分に大きな憂いを感じているようだ。
主権国家の国民としては当然のことだと思う。
我々は先の大戦で、自分達の政府に騙されていた部分は多大にあると思う。
当時の大日本帝国は、自国民に対して、「勝つ!勝つ!」と、大言壮語をしておきながら、結果的には完膚なきまでの敗北であったわけで、その為自国民のみならず、アジアの諸国民に対しても多大な迷惑を掛けたことは紛れもなく我々の側の政治の失敗であったことは素直に認めなければならない。
政治、あるいは統治というのも、人の為す行為なわけで、人の為す行為である以上、失敗も大いにあるわけで、失敗は失敗と素直に認め、今後は同じ失敗を繰り返さないように、細心の注意を払ってしかるべきである。
そこで、過去の反省となるわけであるが、その反省をする時に、「我々は悪いことをしました」という論点に立つと、反省が反省足りえないことになる。
我々の父や、兄弟や、おじさんという親族が、「アジアで、フイリッピンで、朝鮮で悪いことをしてきた」では、後に続く日本の若者に対して顔を上げられないではないか。
事実、そういう認識が戦後の日本の中で一般化しているから、この著者の憂いが浸透しているわけで、相手からそう言われるのはいた仕方ない部分があるが、自らの内側からの声としては、そう言うべきではないと思う。
むしろ相手からそう言われたら、当時の我々の置かれた状況を懇切丁寧に説明すべきだと思う。
相手とこちらでは立場が違うわけで、当然、その立場の違いは利害の違いとなっているのであって、異なる民族が隣り合って存在する限り、利害得失はついて回るわけで、それは昔も今も全く変わることはない。
「悪いことをした」という認識は、あくまでも戦後の認識であって、大戦前の世界的な価値観では、そういう認識は生まれていなかったはずである。
人を抑圧したり、むやみやたらと人を殺していいというわけではないが、価値基準としては非常にあいまいな部分があったわけで、それを今の厳しい基準に照らして、70年近く前のことを今日の基準にてらして評価してはならないと思う。
今の日本の知識階層が、自分達の先輩諸氏、自分達の父や、兄弟や、おじさんたちのしたことを犯罪者よばりするということは、自分たちの祖先を冒涜する行為である。
臭いものに蓋をして口を拭えというわけではない、
当時は、そうしなければ我々自身が生きてこれなかった、ということを考えるべきだ。
我々が生き残るために、昭和初期の日本の政治家たちのとった施策は、結果的には大失敗であったわけで、そのためにアジアの人々も我々同胞も、大いに困惑をしたことになる。
だがそれは生きんがための方便、方策であったわけで、「ならば人殺してもいいか!」という論議まで飛躍すべきではないはずで、善悪、正義不正義という価値観で測るべきではない。
アジアの民と、日本の人々を、二つの異なった人間の集団として運動場に入れたとしら、平和的に共存することもあれば、双方でいきり立って抗争になることも当然あるわけで、如何なる場合でも双方の自己愛に基づいているのであって、ある時は平和的に、ある時は戦争状態になるのも、自己愛のバランスによっているのであるから、それは自然の摂理というべきである。
この著者が祖国を思うとき、日本の大衆があまりにも祖国という概念を喪失している点を憂いているわけで、自分の国の概念を失うということは、あまりにも恵まれすぎているということではなかろうか。
日本が戦争の渦に巻き込まれていった昭和の初期の頃、当時の日本は、今から思えば実に貧相な社会であったわけで、貧乏からの脱出はそれこそ国民的なコンセンサスであった。
社会の上層部分というのは、どこの国でもそう大した違いはなく、貧困層の存在もどこの国でもあったわけで、問題は、それぞれの国の中で金持ちと貧困層の間にある経済力の格差よりも、知識・考え方の格差ではないかと思う。
この頃、どこの国の知識階層にも人気のあったマルクス主義、共産主義というのは、知識階層の考え方であって、知識人が金持ちの富の独占を否定していたわけで、貧乏人はそういう思考の存在そのものも知らずにゴミ箱をあさっていたわけである。
結局、金持ちのボンボンが、金持ち、資本家、不労所得者、成り金を否定し、人は皆平等であるべきだと言っていたわけである。
ところが金持ちのボンボンは、金持ちのボンボンなるがゆえに、貧乏人に金を無償で与えれば働かなくなる、ということを知らなかったわけである。
ところが理念は立派で、慈悲心に富み、博愛精神に富み、人を魅了する言葉であったので、その綺麗事の文言に騙されて、無邪気にそれに惹かれたのである。
これは昭和初期の日本人が、貧乏からの脱出のためには、軍国主義によらなければ日本は滅亡すると思い込んだ構図と軌を一にしていたのである。
ことほど左様に、理念・理想を立派な言葉でまぶし、人の善意をかきたて、魅力的で万人に受け入れされそうな美しい言辞に変えて喧伝すると、正常な感覚まで麻痺してしまう、ということを如実に表していることである。
そういう視点で、今の我々の周りを見てみると、朝鮮や中国に対して、我々の先輩諸氏がひどいことをしてきたと声高に叫ぶと、先方も大いにそれを認めてくれ、自分達も禊をした気になって、世間に対して胸を張って良いことをしてきた気でおれるのである。
ところが、それは相手を利し自分の国を陥ていることに全く気がついていない。
こういう人に限れば、相手が得をすれば、こちらにもそれがブーメランのように回ってくると思い違いをしているようであるが、この考えは無知に等しい。
戦後の日本は、それこそ何を言っても牢屋に放り込まれるということはない。だからものを言う人も、節度ということを考えたこともない。
全くの野放図というのは、こういう状態を指すのであるが、自由というのはどこまで行っても完全に自由だと思っている。
成熟した人間社会には倫理や、道徳や、慣習や、法律で、して良いことと悪いことというものは暗黙の了解の中に存在しているはずであるが、日本の知識人はそういうものを一切無視しようとする。
そういうものを無視してこそ知識人であり、教養人だと、間違った自覚を持って嬉々としている。
知識人や教養人が、自分達の統治者を信用しないというのは、先の大戦の失敗経験から、ある程度はいた仕方ない面もあるが、そこを修復するのが本来ならば知識人や教養人の使命なのではなかろうか。
ただただ反政府を煽るだけならば、誰でもどこでも安易にできる。
統治ということを考えた場合、基本的には官僚の問題にいきつくと思う。
日本の総理大臣も各省庁の大臣も、本来ならば官僚の上に君臨して、官僚を手足のごとく使ってこそ本当の行政機関であろうが、日本の大臣は私欲のために金儲けに血道をあげる人もいない代わりに、国民のために官僚をこき使う人も極めて少ない。
ぶっちゃけて言えば、官庁の烏帽子のようなものだ。
この本の著者の憂いは、この官僚に国のためという意識が微塵もないことを言いたかったに違いない。
官僚の仕事が、官僚のための仕事に終始してしまって、国民の側に視点が向いていないことに非常に怒っている。
そんなことは当然といえば当然の話である。
学校を出て23、4歳で国家公務員になる。一度なったら少々のことでは首にならないわけで、余程の刑事事件でも起こさない限り、生涯安定した生活が保障されているのである。
旧ソビエットのノーメンクラートや、中国共産党員と同じで、そういう安定した組織の中で、誰が一生県命額に汗して働く気になるかと言いたい。
何もしないことが一番身の安全を保障しているわけで、余分なことをすれば、成功すればしたで妬まれ、失敗すればそれ見たことかと評価を下げるだけである。
何もしなくてもそれなりに年功序列で収入は上がるわけで、こういう組織に国益を期待する方が間違っている。
ならば誰が祖国を支えるのかとなれば、それは物作りである。
この物作りも、今では周辺諸国の安い人件費で、海外にその拠点が移ってしまっているが、国益を考えるという場合、そこが物事の根本である。
この本の著者は、日本長期信用という民間の銀行に身を置いていたので、この部分で政府、官僚とも相当に交渉の場をもったらしいが、その経験からこの本が書かれている。
しかし、今までの概念では、国家というものが個人を庇護し、個人の身の安全を支える具体的な機関であったが、こういう考え方も20世紀までのもので、これからは国家という概念そのものが消滅するのではないかと思う。
倫理感とか、正義感とか、善し悪しの判断基準というものが世界標準として定まれば、人は国家の枠組みの中にとどまることなしに、生きていけるのではなかろうか。
ただ親類縁者が固まって住んでいるというぐらいの意味合いで、国家が一人一人の国民に対して忠誠を誓わせたり、援助や支援を差し伸べることはなくなるのではなかろうか。
人は、経済の活発な場所を求めて自分から移動していくわけで、この人間の移動は国境を超えて自由に行き来すると思う。
現にヨーロッパではそういう時代になっているわけで、20世紀における国境の意味が限りなく低くなっているではないか。