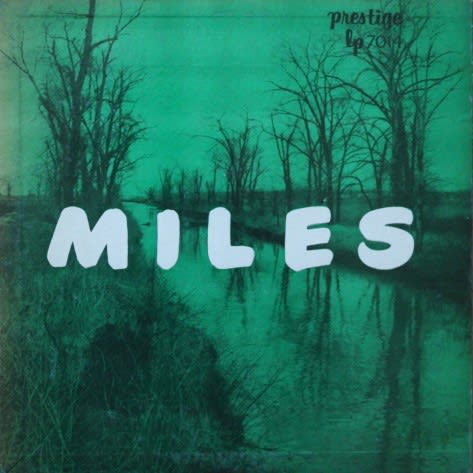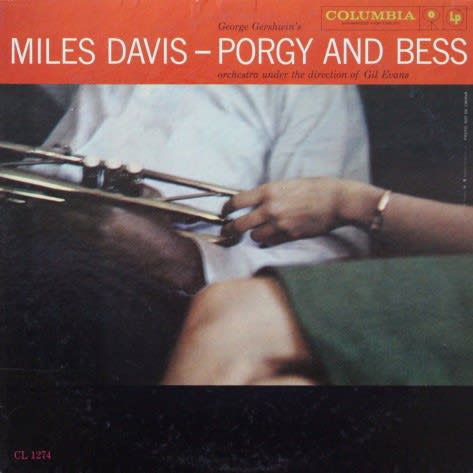Phineas Newborn Jr. / Here Is Phineas ( 米 Atlantic SD 1235 )
いつ、どの店舗に行っても、在庫が転がっているこのレコードのモノラルオリジナル。買ったはいいが、音の貧弱さにがっかりして大半の人がすぐに
手放すせいだ。アトランティックは内容の優れたタイトルが揃っている優良レーベルであるにも関わらず、マニアから褒められることがない。
モノラル盤信仰が蔓延るコレクターの世界でこのレーベルのモノラル盤の音の鮮度の無さやこもったサウンドの評価は極めて悪く、それがそのまま
作品の評価にすり替わってしまっている。まあ、これは致し方ない部分はある。
そこで以前シモキタで拾ったステレオの安レコを聴いてみると、これがモノラル盤よりも音の鮮度が高いことがわかる。ダイナミックレンジは明らかに
拡がり、ピアノの残響感も時代相応ながらもしっかりと再生される。そのおかげでフィニアスのピアノの際立ったタッチがリアルにわかるようになり、
彼がここでやりたかったことがヴィヴィッドに伝わってくる。
このアルバムは、おそらく元がステレオ録音だったのだと思う。ステレオの音場として不自然なところはなく、明らかにモノラル盤のサウンドのほうが
不自然であることがすぐにわかる。ということで、このアルバムに関してはステレオプレスで聴くのがいいと思う。
ただし、冴えない音のアトランテック・モノラル盤のすべてがステレオの方がいい、という結論ではない。それはあまりに短絡的で、正しくない。
こればかりは1枚1枚聴き比べてみて判断するしかない話なのだ。そして、仮にこのアルバムのようにステレオ盤の方に軍配が上がったとしても、
決して「高音質」ということではないことに注意が必要である。あくまでそれはモノラルと比べた場合の相対的な意味合いなのであって、それ自身が
客観的に見て「高音質」という意味では決してない。だから、レコードを買う時にはそういう文言に踊らされて高いものを掴まされることのないよう
気を付ける必要があると思う。
フィニアスのピアノの腕前は鉄の剛腕という感じで素晴らしいが、同時にここが好き嫌いの評価の分かれ目になる。このアルバムも安定感抜群の見事な
弾きっぷりだが、もっとタメてフレーズを歌わせてもよかったんじゃないかと思う。これだけ上手ければ如何ようにも弾けたはずで、そこがちょっと
もったいなかったなと思う。バド・パウエルの "Celia" を入れているあたりにパウエルへの憧憬の強さが感じられるが、あと1歩踏み込んでもよかった
んじゃないかと思う。