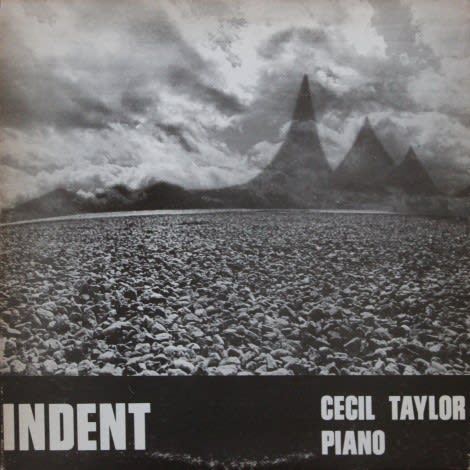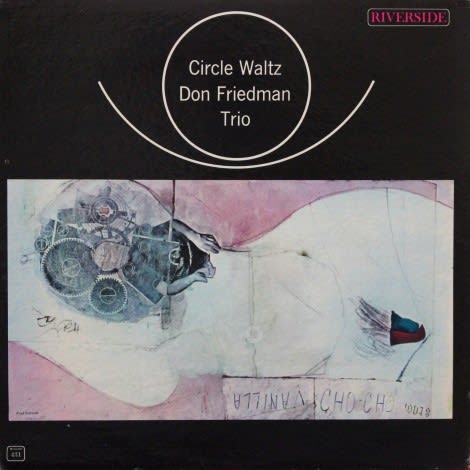Red Garland Quintet / Red's Good Groove ( 米 Jazzland AM 87 )
"レッド・ガーランド五重奏団" という大きな表記が珍しくて目を引いたので手に取った。 ガーランドのアルバムとしてはまったく意識したことがなかった。
メンバーも一流で固められているのに、人口に膾炙されることのないアルバムだ。 ジャズランドというレーベルのせいかもしれない。
管楽器が演奏する "Take Me In Your Arms" は初めて聴いたが、単調なアレンジのせいかさほど印象には残らない。 アレンジが単調なのはこの曲に限らず
全体に共通するところで、メリハリや工夫の跡が見られない。 どの曲も同じような中庸なリズムなので、曲が変わっても違いがわからない印象が残る。
ブルー・ミッチェルはいつものひとクセある音色でなめらかに吹いていくが、元々音色に陰影感がないので、こういう重奏系には向かないなあと思う。
ワンホーンで突っ走る演奏のほうが合っている。 アダムスもいつものドラマチックさに欠ける演奏で、彼の良さが出ていない。 このアルバムは
総じて管楽器の良さが感じられない。
それに比べて、ピアノ・トリオの3人はとてもいい。 1番いいのはやはりフィリー・ジョーで、この人が叩くとハード・バップがよりハード・バップらしくなるのを
改めて実感する。 この人のおかげで、このアルバムは駄作にならずに済んでいる。 サム・ジョーンズのベースの音も非常にクリアに録れていて、ギシギシと
軋む音が生々しい。 リヴァーサイドのレコードは、この人のベースのアコースティック感を上手く録ったものが多い。
そしてガーランドのピアノの音がプレスティッジとは全然違う。 ピアノの音がよりピアノの音らしく、クリアに鳴っている。 グランド・ピアノの音がする。
いつものガーランドとは違う表情が新鮮だ。
良くも悪くも、リヴァーサイドらしいアルバムだと言える。 管楽器にフォーカスして聴くと面白味に欠け、ピアノ・トリオを軸にするととてもいい。
これがプレスティッジ録音だときっと逆になっていたはずで、あちらを立てればこちらが立たず、なかなか難しい。