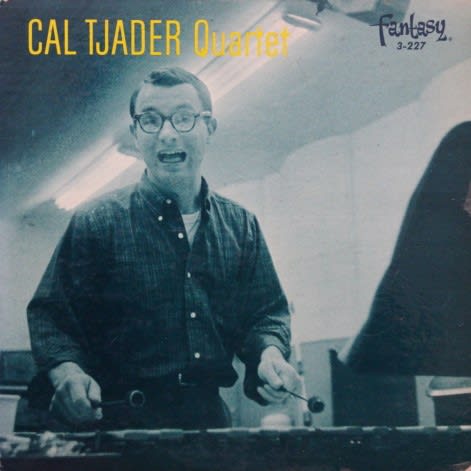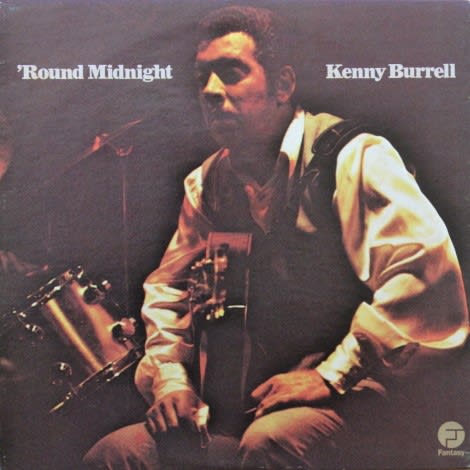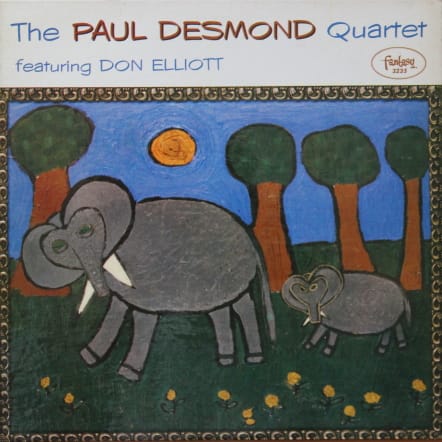Bill Evans / I Will Say Goodbye ( 米 Fantasy F-9593 )
昔(30年ほど前)は、マニアの間でビル・エヴァンスの晩年の作品は今ほどは評価されていなかった。エヴァンスと言えばリヴァーサイド時代で、
それ以外は聴く必要がないという雰囲気があった。イージーリスニングに堕した、という認識があったように思う。それを思うと、今は多くの
人が晩年のエヴァンスをしっかりと聴いて評価するようになっていて、とてもいいことだと思う。そういう面ではリスナーは昔より健全になって
いるように感じる。
"You Must Believe In Spring" へと繋がるこのアルバムの素晴らしさは今更議論の余地などあるわけがないけれど、年季の入った硬派な愛好家にとって、
こういうアルバムを素直に受け入れることができるかどうかは意外とハードルが高く、一種の試金石になっているんじゃないだろうか。こんな軟弱な
音楽に果たして肩入れしていいのだろうか、という疑問が湧いてくる人は少なからずいるだろう。
ここで聴けるエヴァンスのピアノについて分析的な聴き方をするのは、さすがにナンセンスだと思う。彼の生涯の詳細な軌跡を知り、作品の多くを
長年聴いてきた我々にとって、この時点でこういう作品が出てきたというのは当然の成り行きだということが既によくわかっている。だから、この
アルバムを前にすると、ある種の無力感に襲われる。この美しさに身を任せる以外、できることは他に何もないと感じるからだ。
如何にもミシェル・ルグランらしい表題曲の美しさに陶酔しながらも、私はジョニー・マンデルの "Seascape" に心奪われる。マンデルにしか書けない
独特の美しい旋律を、エヴァンスは豊かなハーモニーを付けながら情感を込めて弾いていく。そのメロディーは、ただひたすら美しい。