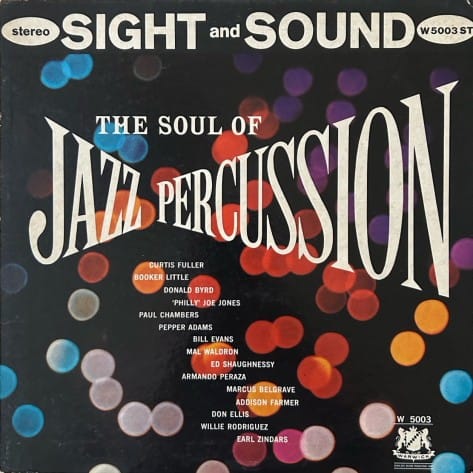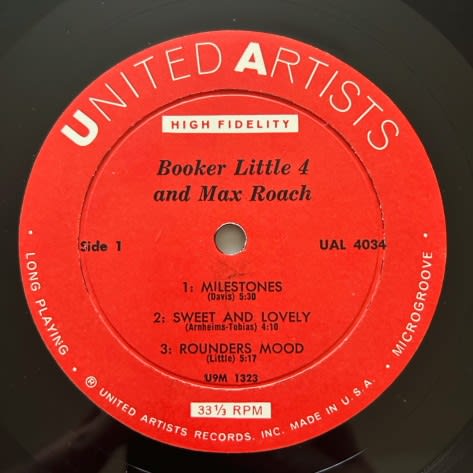Randy Weston / Trio And Solo ( 米 Riverside RLP 12-227 )
お洒落なスーツにオレンジ色のシャツ、背後にはクラシック・カー、とわざわざこのアルバムジャケット用に写真を撮っている。リヴァーサイドは
カタログの初期にランディー・ウェストンのアルバムを立て続けに出していて、異例とも言える好待遇をしている。彼のレコード・デビューは
このリヴァーサイドだったようなので、キープニューズの新人発掘力の賜物だったのかもしれない。他のレーベルがまだ手を付けていない才能を
紹介するというのはレーベルにとっては大事なパブリシティーになるだろうし、当時三顧の礼をもって迎えたセロニアス・モンクとよく似た個性を
持つこのピアニストは、キープニューズの眼には大きな逸材として映ったのかもしれない。
ただ、このリヴァーサイドとの契約が終わった後はあまりパッとはしなかった。彼は長生きして、生涯ジャズ・ピアニストとして活動して
たくさんの作品を残したけれど、ジャズ・ファンからの評価とは無縁だった。モンクとよく似た間の取り方やフレーズを弾くが、あそこまで
徹底はしておらず、個性としては弱かったことは否めない。モンクが古いラグタイムやブギウギを基盤にしていたのに対して、この人の場合は
そういうリズム感の面が弱く、ジャズっぽくない。だからモンクはどんなにねじれていても常にジャズの核心に触れた音楽になっていたけど、
この人はそういう中心からは大きく離れた外縁部付近にいて、そういうところが一般的なファンには届かなかったのだろうと思う。
このアルバムはA面がブレイキーらとのトリオ、B面はソロ演奏で彼のピアノがよく堪能できる内容となっているが、流麗・闊達とは言えない
ピアニストとして弱さが浮き彫りになっている。ただ、そうは言いながらもレコード自体はこうして手元に残っているのだから、私自身は
嫌いではないということなんだろう。頻繁に聴くというわけではないにしても、たまに聴いてみるかと取り出すことがあるのだから。
録音はハッケンサックのヴァン・ゲルダー・スタジオだが、モンクのレコードと同様にRVG刻印がない。当時のリヴァーサイドのレコードは
これが標準だったのかもしれない。